<金曜は本の紹介>
 「ダントツ経営(坂根正弘)」の購入はコチラ
「ダントツ経営(坂根正弘)」の購入はコチラ
この「ダントツ経営」という本は、現在コマツの取締役会長の坂根正弘氏が書いた本です。
彼は2001年の代表取締役社長就任直後に創業以来初の赤字に直面しますが、構造改革を断行し、翌期にはV字回復を達成し、中国や東南アジア、アフリカなど新興国にグローバル展開を進めました。
この本では、その構造改革や中国市場や新興国への挑戦、日本企業の強みや弱み、ダントツ商品、コマツウェイ、日本への提言についてとても興味深く書かれています。
特に、以下についてはなるほどと思いました。
・建設機械は経済全体の先行指標
・新興国の売り上げは7割で日本国内の売り上げは15%程度
・海外では現地の人に任せることが大事
・販売店の実機はメーカーが準備し、在庫ゼロを目指す
・コムトラックスで見える化を成功
・事業多角化などの固定費にメスを入れる
・ハイブリッド建機を開発しその需要に応える
・リストラの大手術は1回限りにすること
・世界1位、2位のポジションなら勝ち抜いていける
・日本人は計画を変更することに対して抵抗感が少ない
・コストは変動コストのみでの比較が大事
・日本は自前主義で高コスト体質につながる
・トラックの無人運行システムの成功
・ダントツ商品は競合メーカーが数年かかっても追いつけないもので、これまでの製品に比べて原価を10%引き下げそのコスト余力をダントツの実現に向ける
・売れ続けるための仕組みをつくることが大事
・日本の強みは成長するアジアに近いこと
・日本は構造的な問題を乗り越えたドイツを参考にすべき
この本はとてもオススメです!
以下はこの本のポイントなどです。
・2000年ごろには日米欧市場の建設・鉱山機械の需要が全体の約8割を占めていましたが、現時点では3割程度にまで縮んでしまいました。また、2010年度のコマツの日本国内での売り上げは、全体の15%程度にまで縮小する見通しです。コマツ社内では、日米欧のことを「伝統市場」と呼んでいますが、主戦場はもはやこうした伝統市場ではありません。中国を筆頭とした新興市場であり、これらを「戦略市場」と呼んでいます。戦略市場での売り上げは7割近くまで達しています。
・いま振り返ると「現地の人に任せる」という方針は正しかったと思います。現地に密着した人が代理店を経営することで、その土地その土地の情報が集まってきます。「次に、ここでダム建設が始まる」という情報があれば、その地域で建設機械の需要が盛り上がります。ちなみに中国では、建設機械の買い手の9割が個人です。日本でも高度成長期には、トラックを個人で買って輸送の請負で稼ぐ「トラック野郎」といわれた人たちがたくさんいましたが、中国には「ブルドーザー野郎」や「油圧ショベル野郎」がたくさんいます。自分で買った建設機械を自ら操作して、建設現場や工事現場で働き、成功しようと夢見る人たちです。こうした個人のお客様の動向をキャッチし、彼らのハートをつかむには、現地の事情に精通し、経済感覚が肌身でわかる人材が欠かせません。
・「在庫ゼロ」といっても、代理店のヤードに実際の機械を置かないわけではありません。中国で建設機械を買う人は、必ず一度は試乗して、そのうえで「これを買う」と決めるのが普通だそうです。実機なしの商売はそもそも成り立ちません。しかし、代理店のヤードに置かれる実機が、その店の所有物である必要はありません。コマツが所有する機械を代理店の軒先に並べて、お客様に見てもらったり、試乗してもらったりする。代理店にとっては、建設機械をメーカーから買い取る必要がなく、販売業務に徹すればいい、という仕組みです。実は、中国ではこの取り組みが非常にうまくいっており、いま「流通在庫」は存在していません。完成品の在庫はすべてコマツの所有物で、無駄のない効率的な販売体制ができあがっています。
・コマツが中国でうまくいった理由として、市場の「見える化」に成功したことも大きかったと思います。コマツの建設機械には、「コムトラックス」と呼ぶシステムが標準装備されています。このシステムにはGPS機能があるほか、エンジンコントローラーやポンプコントローラーなどから集めた情報を通信機能を使ってコマツのデータセンターに送ってくる仕組みになっています。コムトラックスを装備することで、建設機械をお客様に納品した後も、それがいまどこにあり、何時間ぐらい稼働しているか、燃料の残りはどのくらいかといった情報を、お客様や代理店と共有することができるようになります。
・実は中国市場というのは、建設機械にとって非常に過酷な場所なのです。日本では建設機械の稼働時間が年間1000時間に満たず1日あたりに換算すると平均3時間弱といわれています。工事の規模が小さいことに加え、労働法規や騒音などといったさまざまな規制があり、建設機械を動かせる時間が限られているからです。ところが、中国では稼働時間が年間3000時間、日本の3倍に達しています。中国の建設機械は個人オーナーが持っている場合が多く、彼らは自らが投資した機械を少しでも多く動かして、早く元をとろうとするからです。3年前に日本で初めて「ハイブリッド建機」を市販しました。ハイブリッド建機は燃費のいい分、価格も高いのですが、これからは中国のほうが多く売れるのではないかと見ています。稼働時間が3倍もある中国では燃料代がかさみますから、オーナーにとっては、少々価格が高くてもハイブリッド建機のほうが儲かるのです。
・高すぎる固定費の本質は、成長とコストを分けて考えてこなかったツケともいえう、社内に蓄積されてきた「無駄な事業や業務」にありました。たとえば、コマツは、ほかの日本企業と同様、事業の多角化を進め、たくさんの子会社をつくってきました。しかし、その後、景気が落ちこんで不採算になっても、雇用を維持するために、そうした事業を続けてきたのです。慢性的に赤字の子会社群や、それを許す体制、体質こそが、高い固定費を生み出す原因だったのです。
・私は、いくつか改革の原則を決めました。ひとつは「大手術は1回限り」という原則です。世の中の経営不振企業を見ていると、何度も何度も小出しのリストラを繰り返すところがありますが、それは、小手術を繰り返して、患者(会社)の体力をじわじわ奪うようなものです。それでは、再起の可能性を小さくするだけです。1990年代初頭にIBMのリストラを主導し、見事に復活に導いたルイス・ガースナー元CEOも、「だらだら続くリストラは、社員や取引先にとって苦痛以外の何ものでもない。経営者はこれを絶対に避けるべきだ」と述べています。
・事業の整理統合を思い切って進めてきましたが、その基本スタンスは「どんな事業でも、世界1、2位のポジションなら勝ち抜いていける」というものです。「わが社独自の技術を有し、そのシナジー効果を発揮できる事業で世界1、2位を目指そう」と、事業や商品の選択と集中を続けてきまsた。結果として現在、コマツの売り上げの約50%は、世界1位の商品で構成されています。世界2位の商品まで含めると、全売上高の約85%にい達します。
・日本の工場では、日進月歩といいますか、日々「カイゼン」を重ね、5年も経つと、機械設備から現場の工員が使うひとつひとつの工具に至るまで、その様相が一変しているのです。ところが、アメリカの工場はほとんど変わっていませんでした。それが、大きな差となって出てくるのです。
・日本とアメリカを比較すると、これは技術者だけに限りませんが、日本人は「計画を変更すること」「変更されること」に対して抵抗感が少なく、それを柔軟に受け止め、対応することが得意です。一方、アメリカ人は、物事が計画通りに進むときに無頼の強さを発揮するように思います。
・日本では、コストというと「総原価方式」が一般的ですが、コマツではアメリカで学んだ変動コストのみでの比較をしています。さらに、日本の組織の特徴はミドルが強いことです。課長などの中間管理職が優秀で、しっかりと組織を回します。政治のリーダーシップが欠如していても、中央官庁がこれまで日本を引っ張ってこられたのは、官僚というミドルの強さがあったからです。コマツでも、とりわけ生産部門で、ミドルが強かったのです。
・一方で、アメリカで仕事をするうちに日本企業のおかしなところも、はっきりわかるようになりました。そのひとつが、行きすぎた「自前主義」です。何でもかんでも自分で1からつくらないと気が済まないのです。しかし、それは、必然的に高コスト体質につながります。このことを痛感したのは、ICTシステムについてでした。アメリカの企業は、業務用のICTシステムに汎用ソフトを入れて、多少カスタマイズしているだけですから、新入社員でもすぐに使えるようになります。また、一度覚えると、転職しても転職した先の会社で使えるので、システムを習熟するインセンティブが働きます。ところが、当時のコマツでもそうでしたが、日本企業は、給料計算にしても生産管理にしても、すべて自社専用のソフトやシステムを使いたがります。要するに、仕事のやり方を変えずに、そのままシステムに乗せようとするのです。ですから、開発コストがかかるうえ、新しい社員が入ったときにはその都度、システム部門の社員がやってきて、手取り足取り教えなければなりません。アメリカのように労働市場の流動性が高い国では、致命的です。
・その後、コマツでは、「定型的な仕事は外部の汎用システムを使い、競争力に密接にかかわる部分だけは独自のシステムを開発する」という仕分けをすることに決めました。
・「お客様が第一」のトヨタでさえ、ありとあらゆる仕様をそろえているわけではない。高級な革張りシートを選択できるのは、一定のサイズ以上の大型車のみと決めていたのです。その会議で私は、この話をして、営業部門の抵抗を押し切りました。モデル数の圧縮という方針が決まれば、あとはICTがやってくれます。「このパターンの建設機械しか生産しない」「販売しない」とICTシステムに登録しておけば、その翌日から、それ以外の仕様パターンはなくなります。ところで、仕様を減らしたことで、お客様はライバル社に流れたのでしょうか。おそらく、そんな事例はあったとしてもほんのわずかでしょう。それよりも、仕様パターン削減による固定費圧縮効果のほうがはるかに大きかったと思います。
・コムトラックスと真っ先に評価してくれたのは、福島県の建設機械のレンタル会社です。コムトラックスは建設機械にかかわるさまざまな情報を集約しているので、レンタル会社の側でもパソコン画面を見ていれば、「この機械はそろそろ部品の交換が必要だな」といった情報が一目でわかります。レンタル会社が燃料補給に向かう際にも、それぞれの建設機械の燃料の残量をコムトラックスで把握できるので、補給の順番や経路を効率的に選ぶことができます。
・最も反響が大きかった市場のひとつが、中国です。中国では、建設機械のオーナーが携帯電話で、自分が所有する車両の稼働状況や燃料の残量などの情報を見ることができます。あるお客様が20台の建設機械を所有していて、そのうち10台でそういうことができれば、残りの10台もコマツ製に切り替えたいという話になります。顧客を囲い込むうえで、コムトラックスは強力な武器になりました。
・コマツが手がけるダンプトラックは、一般道を走っているものではなく、最も大きいものでは積載量300トンというような巨大なダンプです。タイやだけでも直径4mくらいで、運転席には階段を上らないといけない代物です。もちろん一般道を走るためではなく、鉱山の採掘現場で掘り出した石炭や鉄鉱石を運び出すために使われています。このダンプトラックは、決められたルートを繰り返し行ったり来たりするので自立運転による無人走行に適しています。コマツは、チリとオーストラリアの2つの鉱山で、ダンプトラックの無人運行を実現しました。最初に導入したチリでは、2008年から実稼働に入り、オーストラリアでも2009年1月から動かしています。24時間体制でダンプトラックを動かそうとすると、以前は1台あたり4~5人が必要でした。しかし、コマツの無人運行システムを使えば、こうした人件費をゼロにできます。
・私は社長になると、営業と開発の責任者を呼んで、「いままでのような開発の仕組みでは、これまでの常識をくつがえすような突き抜けた商品は出てこない。新商品の開発にあたって、営業と開発は、まず何を犠牲にするかで合意しろ」と指示を出しました。ライバルに負けてもいいところ、あるいはライバルと同じくらいでいいところをあらかじめ決めておき、その分、強みに磨きをかけるわけです。
・この方針をかけ声倒れに終わらせないようにするために導入したのが、「ダントツ・プロジェクト」という手法です。「ダントツ」という名前の名付け親は、ほかでもない私です。この言葉に奮い立ってくれたのが、開発技術陣でした。そして、その意気込みはすぐさま製造部門や協力企業にも伝わり、「こんな商品をつくってみたい」という要望や提案がどんどん上がってくるようになったのです。
・「ダントツ・プロジェクト」に認定されるには複数の条件があります。まずは、「いくつかの重要な性能やスペックで、競合メーカーが数年かかっても追いつけないような際だった特徴を持つ」ということです。これが、そもそも「ダントツ商品」の定義でもあります。もうひとつの条件は、「これまでの製品に比べて、原価を10%以上引き下げ、そのコスト余力をダントツの実現に振り向ける」ということです。さらにキーワードとして、「環境」「安全性」「ICT」を挙げています。こうした部分で大きくライバルと差をつける商品を世に出していこう、と全社に号令をかけたのです。
・早い段階から生産部門も設計作業に参画することで、「コストを切り下げたいなら、こんな設計ではダメで、こういうふうに改めるべきだ」といった具体的な提案ができるようになります。こうしたコラボレーションがうまくいった背景には、開発部門と生産部門が大阪工場という同じ敷地内にあり、年中、顔を合わせて議論できたことを見逃すわけにはいきません。
・ダントツ・プロジェクトを始めた背景には、私が社長になって早々に取り組んだ「構造改革」もありました。このときは、人員や子会社だけでなく、「機種のリストラ」にも踏み込みました。それまで、建設機械のベースマシンは160機種もあり、細かな要望にあわせた付随モデルを合計すると750機種を超えていました。惰性的に多くの機種を市場投入し続けるのは経営にとっていかにも効率が悪いと考え、機種数をかなり絞り込んだのです。
・建設機械の動力源は、ディーゼルエンジンです。軽油を燃やして、そのエネルギーでモノを持ち上げたり、自走したりしています。しかし、二酸化炭素による地球温暖化問題がクローズアップされ、あるいいは21世紀に入ってからの原油価格高騰もあり、いつまでも化石資源だけに頼るわけにはいかない、と実感するようになりました。そこで、着目したのがハイブリッド技術です。コマツは2008年6月にハイブリッド油圧ショベルを発売しました。ハイブリッド自動車はバッテリー(蓄電池)を搭載し、エンジンと電池でクルマを動かすのですが、ハイブリッド建機はそれとhっや構造が違い、バッテリーは積んでいません。その代わりに、回収した電気を効率よくためこむためにキャパシターという蓄電装置を搭載しています。では、キャパシターにためこむ電気は、どうやってつくりだすのか。油圧ショベルは、運転席やアームなどで構成する「上部旋回体」が、足回りの上に乗っかっている構造です。工事のときは、この旋回体がくるくると回ってショベルを動かすのですが、この旋回が減速するときの運動エネルギーでモーターを回転させることで、電力を回収する新機構を開発しました。自動車に使うバッテリーは化学反応を伴い、充放電に時間がかかりますが、キャパシターは、回収したばかりの電気を瞬時に放電することが可能です。旋回体の減速時に電気エネルギーを取り出し、次に旋回体が起動するときにその電力をエンジンの補助エネルギーとして使うことで、軽油の消費量を抑える仕組みです。これによる燃費向上効果はかなり大きく、試算では燃料消費量が平均25%低減します。ユーザーテストによる実測データでは、最大41%の燃料消費が低減できたという結果も出ました。旋回する頻度が高い現場では、それだけ燃費向上効果が大きくなるのです。
・中国といえば、売れるのは廉価品ばかりというイメージがありますが、なぜそこでハイブリッドなのか。中国の建設機械の稼働時間が長いことは前に書きましたが、その結果たくさんの軽油を消費します。しかも、意外なことに、中国の軽油価格は安くありません。日本より若干安い程度の値段です。その結果、建設機械1台あたりの年間の燃料費は、日本円で300万円ぐらいかかるのです。一方、機会のオペレーターに支払う人件費は年間わずか50万円ほどで、燃料費の約6分の1にすぎません。日本などでは人件費が最大の費用ですが、中国ではまったく逆で、建設機械オーナーにとって、燃料費を節約したいというニーズは私たちの想像以上に大きいのです。
・いまコマツが目指しているのはブランディングで、「売れ続けるための仕組み、お客様から選ばれ続けるための仕組みをつくる」というところです。そのためには、いい商品を売るだけでなく、いいサービスも提供して、「また、コマツ製品を買ってやろう」と思ってもらうことが大切です。
・日本は、ものづくり業界にとって、つくづく住みにくい国になってしまいました。低成長であるにもかかわらず、円高が輸出産業の業績を圧迫しています。しかも、国内の需要が減るなか、「過保護」によって淘汰されなkった多くのプレーヤーによる供給過剰がデフレを生み出しています。金融危機によって、安全資産であるといわれている円が実力以上に買われ、さらには諸外国の通貨安戦争もあり、円が独歩高となっているわけですが、円高対策といっても、ゼロ金利政策のなかでは、短期的な市場介入しか打つ手はなく、効果も限られます。また、諸外国と比べて高い法人税率は、海外からの直接投資機会を抑制します。さらに、「2020年までに温室効果ガスを1990年比25%削減する」というきわめて困難な環境対策目標も、日本をベースにして企業が国際市場で戦うにはたいへん高いハードルとなっています。
・では、私たちの強みとは何か。それは、何といっても、成長するアジアに近いことです。物理的な意味もありますが、アジアが発展するうえでも日本の協力(ビジネスと支援)は欠かせません。また、アジアとともに栄えていくうえでは、安全保障問題が最重要です。多くのアジアの国々にとっては、日米基軸が安心の源ではないでしょうか。そして、私たち日本人の強みは、農耕民族的な強み、すなわち「チームワーク」と「きめ細かさ」です。「チームワーク」は、機械や電気、油圧、制御といったさまざまな技術分野の人たちが汗と知恵を結集したロボットや建設機械などで国際競争力が突出していることに表れています。「きめ細やかさ」は、どこにエネルギー・ロスがあるかを調べ尽くして開発する省エネ絵医術や、機械の安全性を高める技術、ICTの開発で大いに発揮されます。
・閉塞感が漂う日本は、戦後ドラスティックな変化を2度も体験し、日本よりも先に構造的な問題に直面、そしてこの問題を乗り越えたドイツを手本にしてはどうでしょうか。1990年の東西統一で失業率の悪化など、経済格差というハンディキャップを背負い、2002年にはマルクを捨ててユーロを導入したドイツは、危機的状況でも門を閉ざさず、反対に門を開くことで変化を受け入れ、試練を克服しつつあります。日本と同じく工業製品輸出国であり技術立国である一方、食料自給率は90%です。30年前まで疲弊していた林業も、生産性を向上させたことで、木製品自給率は60%を誇っています。また、東西統一後に首都移転を成し遂げ、伝統的な連邦制による強固な地方主権を行うなど、日本の改革のためのヒントを多く有しています。
<目次>
序章 世界市場の大転換
一足早く大転換にさらされた建設機械業界
建設機械が売れると経済が大きく伸びる
危機感をテコに進めてきた品質改善
日本の建設機械メーカーの強さ
国内で売られている建設機械がいかに安いか
過当競争が生み出した中古車人気
大転換と格闘してきたコマツ
第1章 中国市場での挑戦
世界一の激戦区
現地の人たちに任せる
コマツのやり方をどう理解してもらうか
中国で生まれた「流通在庫ゼロ」の仕組み
中国発の仕組みを先進国市場へ
コムトラックスで市場を「見える化」する
機械の稼働状況から先行きを予測する
工場移転に伴う、市からの提案
部品メーカーとともに成長
稼働時間は日本の3倍
経営の舵取りも現地に任せる
かなりのところまで現地で意思決定できる体制に
取り組みへの本気度が試される
第2章 構造改革への取り組み-危機が会社を強くする①
構造改革宣言
成長とコストを分けて考える
なぜ赤字になったのか
原因は「固定費」にあった
見える化できれば、打つべき手もはっきりする
大手術は1回限り
子会社の整理統合
なぜ子会社でなければならないかを問う
事業を持ち続ける理由
すべての商品で世界1、2位を目指す
痛みを伴う改革を実行するのが、リーダーの役目
間接部門の生産性をいかに上げるか
決算集計の迅速化
第3章 ポスト・リーマンショック-危機が会社を強くする②
真っ暗闇のトンネルに飛び込む
「リセッション」ではなく「パニック」
在庫が適正な水準に戻るまで生産を止める
生産ラインの合理化
生産拠点の統合
協力企業とともに栄える
大幅な減産を強いる事態を放置しない
設備や部品を買い取り、支援する
協力企業同士の切磋琢磨も促す
なぜライバルより早く増産できたのか
基幹部品は国内で集中生産する
マザー工場とチャイルド工場
日々新たに生まれる投資機会
第4章 日本企業の強みと弱み-アメリカで学んだこと
アメリカ駐在で見えてきた日本企業の強みと弱み
説明することの大切さ
アメリカ企業の弱点
生産技術者だけは現地化できない
日米比較では1ドル70円でも負けない
仕事のやり方を標準化する
ICTで無駄をなくす
コムトラックス-建設機械へのICT活用
標準装備への決断
データというかたちで「見える化」する。
新しいサービスを可能にするICT
苦労したのはクルマの運転と英語
説明能力を高める
第5章 ダントツ商品で強みを磨く
まずは何を犠牲にするか
ライバルが追いつけない「ダントツ商品」の開発
開発と生産の距離の近さ
開発・生産一体の原則
機種のリストラ
ハイブリッド建機
ハイブリッド建機が中国で売れる理由
環境、安全性、ICT-今後の方向性
為替には一喜一憂しない
「コマツでないと困る」度合いを高める
第6章 代を重ねるごとに強くなる
なぜ「コマツウェイ」なのか
マネジメント編
取締役会の活性化
報告、討議、そして決議へ
会社の状況、方向性を自らの言葉で語る
バッドニュースを最初に報告する
リスクの処理を先送りしない
後継者育成は社長にしかできない仕事
全社共通編
強みを磨き、代を重ねるごとに強くなる
終章 傍観者ではなく当事者になろう
トップは何を示すべきか
これからはアジアの時代
都市化率が低い社会
過保護から抜け出せない産業
低成長こそ根本課題
チームワークときめ細かさ-日本の強み
部分最適が横行しやすい-日本の弱み
できることはたくさんある
業界再編と雇用の柔軟化
業務の合理化と固定費の削減が最優先課題
批判するばかりの傍観者ではなく当事者になろう
あとがきに代えて
面白かった本まとめ(2011年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「ダントツ経営(坂根正弘)」の購入はコチラ
「ダントツ経営(坂根正弘)」の購入はコチラ この「ダントツ経営」という本は、現在コマツの取締役会長の坂根正弘氏が書いた本です。
彼は2001年の代表取締役社長就任直後に創業以来初の赤字に直面しますが、構造改革を断行し、翌期にはV字回復を達成し、中国や東南アジア、アフリカなど新興国にグローバル展開を進めました。
この本では、その構造改革や中国市場や新興国への挑戦、日本企業の強みや弱み、ダントツ商品、コマツウェイ、日本への提言についてとても興味深く書かれています。
特に、以下についてはなるほどと思いました。
・建設機械は経済全体の先行指標
・新興国の売り上げは7割で日本国内の売り上げは15%程度
・海外では現地の人に任せることが大事
・販売店の実機はメーカーが準備し、在庫ゼロを目指す
・コムトラックスで見える化を成功
・事業多角化などの固定費にメスを入れる
・ハイブリッド建機を開発しその需要に応える
・リストラの大手術は1回限りにすること
・世界1位、2位のポジションなら勝ち抜いていける
・日本人は計画を変更することに対して抵抗感が少ない
・コストは変動コストのみでの比較が大事
・日本は自前主義で高コスト体質につながる
・トラックの無人運行システムの成功
・ダントツ商品は競合メーカーが数年かかっても追いつけないもので、これまでの製品に比べて原価を10%引き下げそのコスト余力をダントツの実現に向ける
・売れ続けるための仕組みをつくることが大事
・日本の強みは成長するアジアに近いこと
・日本は構造的な問題を乗り越えたドイツを参考にすべき
この本はとてもオススメです!
以下はこの本のポイントなどです。
・2000年ごろには日米欧市場の建設・鉱山機械の需要が全体の約8割を占めていましたが、現時点では3割程度にまで縮んでしまいました。また、2010年度のコマツの日本国内での売り上げは、全体の15%程度にまで縮小する見通しです。コマツ社内では、日米欧のことを「伝統市場」と呼んでいますが、主戦場はもはやこうした伝統市場ではありません。中国を筆頭とした新興市場であり、これらを「戦略市場」と呼んでいます。戦略市場での売り上げは7割近くまで達しています。
・いま振り返ると「現地の人に任せる」という方針は正しかったと思います。現地に密着した人が代理店を経営することで、その土地その土地の情報が集まってきます。「次に、ここでダム建設が始まる」という情報があれば、その地域で建設機械の需要が盛り上がります。ちなみに中国では、建設機械の買い手の9割が個人です。日本でも高度成長期には、トラックを個人で買って輸送の請負で稼ぐ「トラック野郎」といわれた人たちがたくさんいましたが、中国には「ブルドーザー野郎」や「油圧ショベル野郎」がたくさんいます。自分で買った建設機械を自ら操作して、建設現場や工事現場で働き、成功しようと夢見る人たちです。こうした個人のお客様の動向をキャッチし、彼らのハートをつかむには、現地の事情に精通し、経済感覚が肌身でわかる人材が欠かせません。
・「在庫ゼロ」といっても、代理店のヤードに実際の機械を置かないわけではありません。中国で建設機械を買う人は、必ず一度は試乗して、そのうえで「これを買う」と決めるのが普通だそうです。実機なしの商売はそもそも成り立ちません。しかし、代理店のヤードに置かれる実機が、その店の所有物である必要はありません。コマツが所有する機械を代理店の軒先に並べて、お客様に見てもらったり、試乗してもらったりする。代理店にとっては、建設機械をメーカーから買い取る必要がなく、販売業務に徹すればいい、という仕組みです。実は、中国ではこの取り組みが非常にうまくいっており、いま「流通在庫」は存在していません。完成品の在庫はすべてコマツの所有物で、無駄のない効率的な販売体制ができあがっています。
・コマツが中国でうまくいった理由として、市場の「見える化」に成功したことも大きかったと思います。コマツの建設機械には、「コムトラックス」と呼ぶシステムが標準装備されています。このシステムにはGPS機能があるほか、エンジンコントローラーやポンプコントローラーなどから集めた情報を通信機能を使ってコマツのデータセンターに送ってくる仕組みになっています。コムトラックスを装備することで、建設機械をお客様に納品した後も、それがいまどこにあり、何時間ぐらい稼働しているか、燃料の残りはどのくらいかといった情報を、お客様や代理店と共有することができるようになります。
・実は中国市場というのは、建設機械にとって非常に過酷な場所なのです。日本では建設機械の稼働時間が年間1000時間に満たず1日あたりに換算すると平均3時間弱といわれています。工事の規模が小さいことに加え、労働法規や騒音などといったさまざまな規制があり、建設機械を動かせる時間が限られているからです。ところが、中国では稼働時間が年間3000時間、日本の3倍に達しています。中国の建設機械は個人オーナーが持っている場合が多く、彼らは自らが投資した機械を少しでも多く動かして、早く元をとろうとするからです。3年前に日本で初めて「ハイブリッド建機」を市販しました。ハイブリッド建機は燃費のいい分、価格も高いのですが、これからは中国のほうが多く売れるのではないかと見ています。稼働時間が3倍もある中国では燃料代がかさみますから、オーナーにとっては、少々価格が高くてもハイブリッド建機のほうが儲かるのです。
・高すぎる固定費の本質は、成長とコストを分けて考えてこなかったツケともいえう、社内に蓄積されてきた「無駄な事業や業務」にありました。たとえば、コマツは、ほかの日本企業と同様、事業の多角化を進め、たくさんの子会社をつくってきました。しかし、その後、景気が落ちこんで不採算になっても、雇用を維持するために、そうした事業を続けてきたのです。慢性的に赤字の子会社群や、それを許す体制、体質こそが、高い固定費を生み出す原因だったのです。
・私は、いくつか改革の原則を決めました。ひとつは「大手術は1回限り」という原則です。世の中の経営不振企業を見ていると、何度も何度も小出しのリストラを繰り返すところがありますが、それは、小手術を繰り返して、患者(会社)の体力をじわじわ奪うようなものです。それでは、再起の可能性を小さくするだけです。1990年代初頭にIBMのリストラを主導し、見事に復活に導いたルイス・ガースナー元CEOも、「だらだら続くリストラは、社員や取引先にとって苦痛以外の何ものでもない。経営者はこれを絶対に避けるべきだ」と述べています。
・事業の整理統合を思い切って進めてきましたが、その基本スタンスは「どんな事業でも、世界1、2位のポジションなら勝ち抜いていける」というものです。「わが社独自の技術を有し、そのシナジー効果を発揮できる事業で世界1、2位を目指そう」と、事業や商品の選択と集中を続けてきまsた。結果として現在、コマツの売り上げの約50%は、世界1位の商品で構成されています。世界2位の商品まで含めると、全売上高の約85%にい達します。
・日本の工場では、日進月歩といいますか、日々「カイゼン」を重ね、5年も経つと、機械設備から現場の工員が使うひとつひとつの工具に至るまで、その様相が一変しているのです。ところが、アメリカの工場はほとんど変わっていませんでした。それが、大きな差となって出てくるのです。
・日本とアメリカを比較すると、これは技術者だけに限りませんが、日本人は「計画を変更すること」「変更されること」に対して抵抗感が少なく、それを柔軟に受け止め、対応することが得意です。一方、アメリカ人は、物事が計画通りに進むときに無頼の強さを発揮するように思います。
・日本では、コストというと「総原価方式」が一般的ですが、コマツではアメリカで学んだ変動コストのみでの比較をしています。さらに、日本の組織の特徴はミドルが強いことです。課長などの中間管理職が優秀で、しっかりと組織を回します。政治のリーダーシップが欠如していても、中央官庁がこれまで日本を引っ張ってこられたのは、官僚というミドルの強さがあったからです。コマツでも、とりわけ生産部門で、ミドルが強かったのです。
・一方で、アメリカで仕事をするうちに日本企業のおかしなところも、はっきりわかるようになりました。そのひとつが、行きすぎた「自前主義」です。何でもかんでも自分で1からつくらないと気が済まないのです。しかし、それは、必然的に高コスト体質につながります。このことを痛感したのは、ICTシステムについてでした。アメリカの企業は、業務用のICTシステムに汎用ソフトを入れて、多少カスタマイズしているだけですから、新入社員でもすぐに使えるようになります。また、一度覚えると、転職しても転職した先の会社で使えるので、システムを習熟するインセンティブが働きます。ところが、当時のコマツでもそうでしたが、日本企業は、給料計算にしても生産管理にしても、すべて自社専用のソフトやシステムを使いたがります。要するに、仕事のやり方を変えずに、そのままシステムに乗せようとするのです。ですから、開発コストがかかるうえ、新しい社員が入ったときにはその都度、システム部門の社員がやってきて、手取り足取り教えなければなりません。アメリカのように労働市場の流動性が高い国では、致命的です。
・その後、コマツでは、「定型的な仕事は外部の汎用システムを使い、競争力に密接にかかわる部分だけは独自のシステムを開発する」という仕分けをすることに決めました。
・「お客様が第一」のトヨタでさえ、ありとあらゆる仕様をそろえているわけではない。高級な革張りシートを選択できるのは、一定のサイズ以上の大型車のみと決めていたのです。その会議で私は、この話をして、営業部門の抵抗を押し切りました。モデル数の圧縮という方針が決まれば、あとはICTがやってくれます。「このパターンの建設機械しか生産しない」「販売しない」とICTシステムに登録しておけば、その翌日から、それ以外の仕様パターンはなくなります。ところで、仕様を減らしたことで、お客様はライバル社に流れたのでしょうか。おそらく、そんな事例はあったとしてもほんのわずかでしょう。それよりも、仕様パターン削減による固定費圧縮効果のほうがはるかに大きかったと思います。
・コムトラックスと真っ先に評価してくれたのは、福島県の建設機械のレンタル会社です。コムトラックスは建設機械にかかわるさまざまな情報を集約しているので、レンタル会社の側でもパソコン画面を見ていれば、「この機械はそろそろ部品の交換が必要だな」といった情報が一目でわかります。レンタル会社が燃料補給に向かう際にも、それぞれの建設機械の燃料の残量をコムトラックスで把握できるので、補給の順番や経路を効率的に選ぶことができます。
・最も反響が大きかった市場のひとつが、中国です。中国では、建設機械のオーナーが携帯電話で、自分が所有する車両の稼働状況や燃料の残量などの情報を見ることができます。あるお客様が20台の建設機械を所有していて、そのうち10台でそういうことができれば、残りの10台もコマツ製に切り替えたいという話になります。顧客を囲い込むうえで、コムトラックスは強力な武器になりました。
・コマツが手がけるダンプトラックは、一般道を走っているものではなく、最も大きいものでは積載量300トンというような巨大なダンプです。タイやだけでも直径4mくらいで、運転席には階段を上らないといけない代物です。もちろん一般道を走るためではなく、鉱山の採掘現場で掘り出した石炭や鉄鉱石を運び出すために使われています。このダンプトラックは、決められたルートを繰り返し行ったり来たりするので自立運転による無人走行に適しています。コマツは、チリとオーストラリアの2つの鉱山で、ダンプトラックの無人運行を実現しました。最初に導入したチリでは、2008年から実稼働に入り、オーストラリアでも2009年1月から動かしています。24時間体制でダンプトラックを動かそうとすると、以前は1台あたり4~5人が必要でした。しかし、コマツの無人運行システムを使えば、こうした人件費をゼロにできます。
・私は社長になると、営業と開発の責任者を呼んで、「いままでのような開発の仕組みでは、これまでの常識をくつがえすような突き抜けた商品は出てこない。新商品の開発にあたって、営業と開発は、まず何を犠牲にするかで合意しろ」と指示を出しました。ライバルに負けてもいいところ、あるいはライバルと同じくらいでいいところをあらかじめ決めておき、その分、強みに磨きをかけるわけです。
・この方針をかけ声倒れに終わらせないようにするために導入したのが、「ダントツ・プロジェクト」という手法です。「ダントツ」という名前の名付け親は、ほかでもない私です。この言葉に奮い立ってくれたのが、開発技術陣でした。そして、その意気込みはすぐさま製造部門や協力企業にも伝わり、「こんな商品をつくってみたい」という要望や提案がどんどん上がってくるようになったのです。
・「ダントツ・プロジェクト」に認定されるには複数の条件があります。まずは、「いくつかの重要な性能やスペックで、競合メーカーが数年かかっても追いつけないような際だった特徴を持つ」ということです。これが、そもそも「ダントツ商品」の定義でもあります。もうひとつの条件は、「これまでの製品に比べて、原価を10%以上引き下げ、そのコスト余力をダントツの実現に振り向ける」ということです。さらにキーワードとして、「環境」「安全性」「ICT」を挙げています。こうした部分で大きくライバルと差をつける商品を世に出していこう、と全社に号令をかけたのです。
・早い段階から生産部門も設計作業に参画することで、「コストを切り下げたいなら、こんな設計ではダメで、こういうふうに改めるべきだ」といった具体的な提案ができるようになります。こうしたコラボレーションがうまくいった背景には、開発部門と生産部門が大阪工場という同じ敷地内にあり、年中、顔を合わせて議論できたことを見逃すわけにはいきません。
・ダントツ・プロジェクトを始めた背景には、私が社長になって早々に取り組んだ「構造改革」もありました。このときは、人員や子会社だけでなく、「機種のリストラ」にも踏み込みました。それまで、建設機械のベースマシンは160機種もあり、細かな要望にあわせた付随モデルを合計すると750機種を超えていました。惰性的に多くの機種を市場投入し続けるのは経営にとっていかにも効率が悪いと考え、機種数をかなり絞り込んだのです。
・建設機械の動力源は、ディーゼルエンジンです。軽油を燃やして、そのエネルギーでモノを持ち上げたり、自走したりしています。しかし、二酸化炭素による地球温暖化問題がクローズアップされ、あるいいは21世紀に入ってからの原油価格高騰もあり、いつまでも化石資源だけに頼るわけにはいかない、と実感するようになりました。そこで、着目したのがハイブリッド技術です。コマツは2008年6月にハイブリッド油圧ショベルを発売しました。ハイブリッド自動車はバッテリー(蓄電池)を搭載し、エンジンと電池でクルマを動かすのですが、ハイブリッド建機はそれとhっや構造が違い、バッテリーは積んでいません。その代わりに、回収した電気を効率よくためこむためにキャパシターという蓄電装置を搭載しています。では、キャパシターにためこむ電気は、どうやってつくりだすのか。油圧ショベルは、運転席やアームなどで構成する「上部旋回体」が、足回りの上に乗っかっている構造です。工事のときは、この旋回体がくるくると回ってショベルを動かすのですが、この旋回が減速するときの運動エネルギーでモーターを回転させることで、電力を回収する新機構を開発しました。自動車に使うバッテリーは化学反応を伴い、充放電に時間がかかりますが、キャパシターは、回収したばかりの電気を瞬時に放電することが可能です。旋回体の減速時に電気エネルギーを取り出し、次に旋回体が起動するときにその電力をエンジンの補助エネルギーとして使うことで、軽油の消費量を抑える仕組みです。これによる燃費向上効果はかなり大きく、試算では燃料消費量が平均25%低減します。ユーザーテストによる実測データでは、最大41%の燃料消費が低減できたという結果も出ました。旋回する頻度が高い現場では、それだけ燃費向上効果が大きくなるのです。
・中国といえば、売れるのは廉価品ばかりというイメージがありますが、なぜそこでハイブリッドなのか。中国の建設機械の稼働時間が長いことは前に書きましたが、その結果たくさんの軽油を消費します。しかも、意外なことに、中国の軽油価格は安くありません。日本より若干安い程度の値段です。その結果、建設機械1台あたりの年間の燃料費は、日本円で300万円ぐらいかかるのです。一方、機会のオペレーターに支払う人件費は年間わずか50万円ほどで、燃料費の約6分の1にすぎません。日本などでは人件費が最大の費用ですが、中国ではまったく逆で、建設機械オーナーにとって、燃料費を節約したいというニーズは私たちの想像以上に大きいのです。
・いまコマツが目指しているのはブランディングで、「売れ続けるための仕組み、お客様から選ばれ続けるための仕組みをつくる」というところです。そのためには、いい商品を売るだけでなく、いいサービスも提供して、「また、コマツ製品を買ってやろう」と思ってもらうことが大切です。
・日本は、ものづくり業界にとって、つくづく住みにくい国になってしまいました。低成長であるにもかかわらず、円高が輸出産業の業績を圧迫しています。しかも、国内の需要が減るなか、「過保護」によって淘汰されなkった多くのプレーヤーによる供給過剰がデフレを生み出しています。金融危機によって、安全資産であるといわれている円が実力以上に買われ、さらには諸外国の通貨安戦争もあり、円が独歩高となっているわけですが、円高対策といっても、ゼロ金利政策のなかでは、短期的な市場介入しか打つ手はなく、効果も限られます。また、諸外国と比べて高い法人税率は、海外からの直接投資機会を抑制します。さらに、「2020年までに温室効果ガスを1990年比25%削減する」というきわめて困難な環境対策目標も、日本をベースにして企業が国際市場で戦うにはたいへん高いハードルとなっています。
・では、私たちの強みとは何か。それは、何といっても、成長するアジアに近いことです。物理的な意味もありますが、アジアが発展するうえでも日本の協力(ビジネスと支援)は欠かせません。また、アジアとともに栄えていくうえでは、安全保障問題が最重要です。多くのアジアの国々にとっては、日米基軸が安心の源ではないでしょうか。そして、私たち日本人の強みは、農耕民族的な強み、すなわち「チームワーク」と「きめ細かさ」です。「チームワーク」は、機械や電気、油圧、制御といったさまざまな技術分野の人たちが汗と知恵を結集したロボットや建設機械などで国際競争力が突出していることに表れています。「きめ細やかさ」は、どこにエネルギー・ロスがあるかを調べ尽くして開発する省エネ絵医術や、機械の安全性を高める技術、ICTの開発で大いに発揮されます。
・閉塞感が漂う日本は、戦後ドラスティックな変化を2度も体験し、日本よりも先に構造的な問題に直面、そしてこの問題を乗り越えたドイツを手本にしてはどうでしょうか。1990年の東西統一で失業率の悪化など、経済格差というハンディキャップを背負い、2002年にはマルクを捨ててユーロを導入したドイツは、危機的状況でも門を閉ざさず、反対に門を開くことで変化を受け入れ、試練を克服しつつあります。日本と同じく工業製品輸出国であり技術立国である一方、食料自給率は90%です。30年前まで疲弊していた林業も、生産性を向上させたことで、木製品自給率は60%を誇っています。また、東西統一後に首都移転を成し遂げ、伝統的な連邦制による強固な地方主権を行うなど、日本の改革のためのヒントを多く有しています。
<目次>
序章 世界市場の大転換
一足早く大転換にさらされた建設機械業界
建設機械が売れると経済が大きく伸びる
危機感をテコに進めてきた品質改善
日本の建設機械メーカーの強さ
国内で売られている建設機械がいかに安いか
過当競争が生み出した中古車人気
大転換と格闘してきたコマツ
第1章 中国市場での挑戦
世界一の激戦区
現地の人たちに任せる
コマツのやり方をどう理解してもらうか
中国で生まれた「流通在庫ゼロ」の仕組み
中国発の仕組みを先進国市場へ
コムトラックスで市場を「見える化」する
機械の稼働状況から先行きを予測する
工場移転に伴う、市からの提案
部品メーカーとともに成長
稼働時間は日本の3倍
経営の舵取りも現地に任せる
かなりのところまで現地で意思決定できる体制に
取り組みへの本気度が試される
第2章 構造改革への取り組み-危機が会社を強くする①
構造改革宣言
成長とコストを分けて考える
なぜ赤字になったのか
原因は「固定費」にあった
見える化できれば、打つべき手もはっきりする
大手術は1回限り
子会社の整理統合
なぜ子会社でなければならないかを問う
事業を持ち続ける理由
すべての商品で世界1、2位を目指す
痛みを伴う改革を実行するのが、リーダーの役目
間接部門の生産性をいかに上げるか
決算集計の迅速化
第3章 ポスト・リーマンショック-危機が会社を強くする②
真っ暗闇のトンネルに飛び込む
「リセッション」ではなく「パニック」
在庫が適正な水準に戻るまで生産を止める
生産ラインの合理化
生産拠点の統合
協力企業とともに栄える
大幅な減産を強いる事態を放置しない
設備や部品を買い取り、支援する
協力企業同士の切磋琢磨も促す
なぜライバルより早く増産できたのか
基幹部品は国内で集中生産する
マザー工場とチャイルド工場
日々新たに生まれる投資機会
第4章 日本企業の強みと弱み-アメリカで学んだこと
アメリカ駐在で見えてきた日本企業の強みと弱み
説明することの大切さ
アメリカ企業の弱点
生産技術者だけは現地化できない
日米比較では1ドル70円でも負けない
仕事のやり方を標準化する
ICTで無駄をなくす
コムトラックス-建設機械へのICT活用
標準装備への決断
データというかたちで「見える化」する。
新しいサービスを可能にするICT
苦労したのはクルマの運転と英語
説明能力を高める
第5章 ダントツ商品で強みを磨く
まずは何を犠牲にするか
ライバルが追いつけない「ダントツ商品」の開発
開発と生産の距離の近さ
開発・生産一体の原則
機種のリストラ
ハイブリッド建機
ハイブリッド建機が中国で売れる理由
環境、安全性、ICT-今後の方向性
為替には一喜一憂しない
「コマツでないと困る」度合いを高める
第6章 代を重ねるごとに強くなる
なぜ「コマツウェイ」なのか
マネジメント編
取締役会の活性化
報告、討議、そして決議へ
会社の状況、方向性を自らの言葉で語る
バッドニュースを最初に報告する
リスクの処理を先送りしない
後継者育成は社長にしかできない仕事
全社共通編
強みを磨き、代を重ねるごとに強くなる
終章 傍観者ではなく当事者になろう
トップは何を示すべきか
これからはアジアの時代
都市化率が低い社会
過保護から抜け出せない産業
低成長こそ根本課題
チームワークときめ細かさ-日本の強み
部分最適が横行しやすい-日本の弱み
できることはたくさんある
業界再編と雇用の柔軟化
業務の合理化と固定費の削減が最優先課題
批判するばかりの傍観者ではなく当事者になろう
あとがきに代えて
面白かった本まとめ(2011年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。































 「にいいことだけをやりなさい(マーシー・シャイモフ(著)、茂木健一郎(訳)」の購入はコチラ
「にいいことだけをやりなさい(マーシー・シャイモフ(著)、茂木健一郎(訳)」の購入はコチラ 


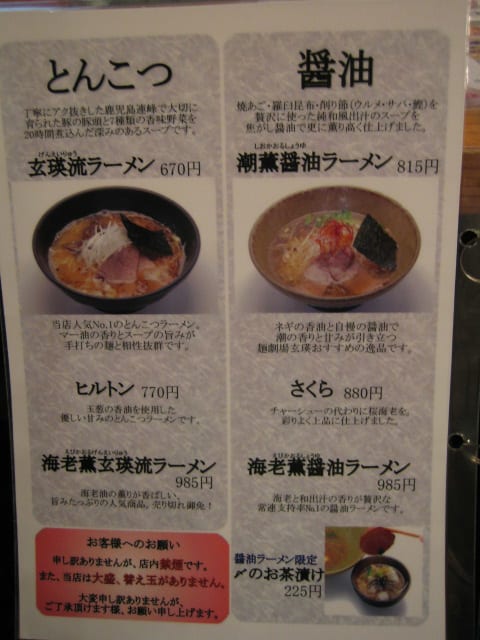
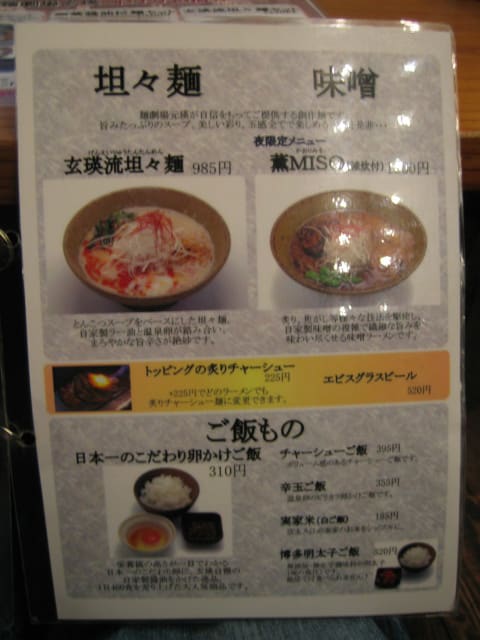
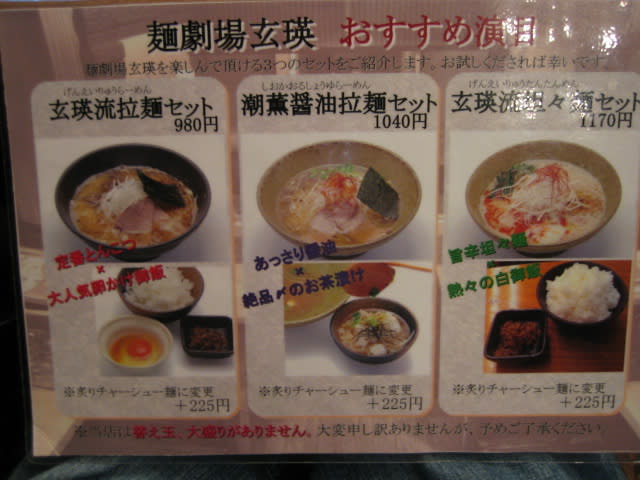






 「野村の「監督ミーティング」(橋上秀樹)」の購入はコチラ
「野村の「監督ミーティング」(橋上秀樹)」の購入はコチラ 



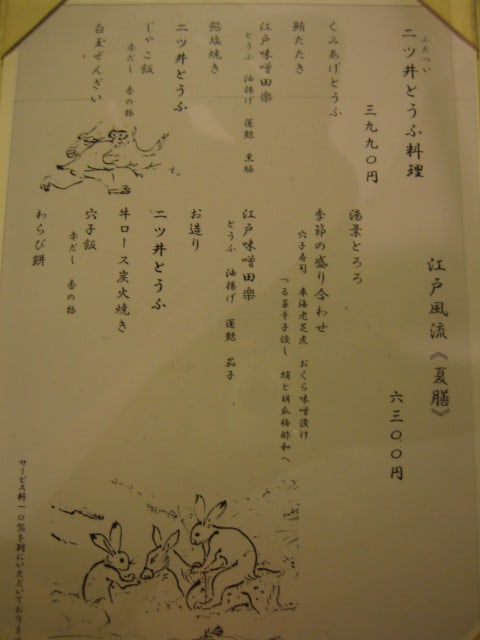









 「ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣(美月あきこ)」の購入はコチラ
「ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣(美月あきこ)」の購入はコチラ 

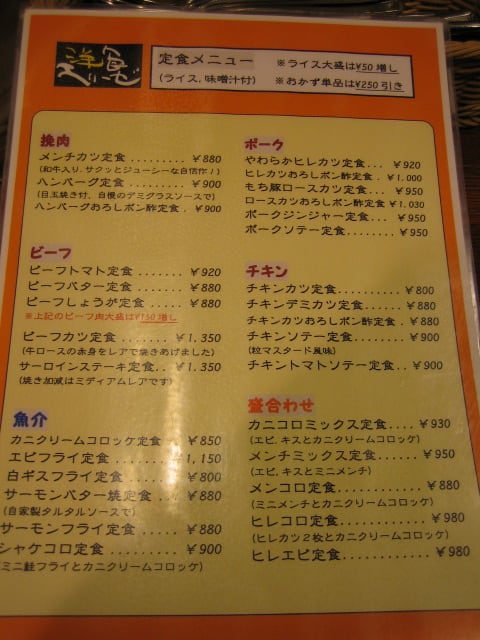






 「うらおもて人生録(色川武大)」の購入はコチラ
「うらおもて人生録(色川武大)」の購入はコチラ 




