<金曜は本の紹介>
 「きみまろ流(綾小路きみまろ)」の購入はコチラ
「きみまろ流(綾小路きみまろ)」の購入はコチラ
この「きみまろ流(綾小路きみまろ)」という本は、漫談家の「綾小路きみまろ」の自伝や心情を綴ったものです。
潜伏期間30年のあいだに学んだ「人間の価値」「人情の機微」「人生の無常」を活字にしたとのことです。
本の最後にはライブもあり、全体的にも漫談口調で楽しく読める本です。
2003年に出版されたものですが、とてもオススメです!!
以下はこの本のポイントなどです。
・私は小さいころから、ちょっと変わった子どもでした。どこが変わっていたかというと、人間って何だろうとか、人生って何だろうということを、いつも頭の片隅で考えながら生きてきたのです。口では人を笑わせることをいっているのですが、頭のなかは冷静になっている自分を発見したのもかなり若いときでした。私は鹿児島の田舎の生まれですから、周りは自然だらけです。自然のなかで育ったというか、自然が私にいろいろ教えてくれたといってもよいでしょう。たとえば、一日中、野原に寝っころがって、雲を見ていたこともありました。あの雲どこへ行くんだろう、と不思議でしかたがなかったのです。あるいは、タンポポの白い冠毛が風に揺られてあたり一面に飛んでいる風景に出くわすと、ジッと何時間もそれを見ているのです。あの白い冠毛風に吹かれてどこへ行くんだろう、土の上に落ちて、またタンポポになるのだろうか、なんてことを考えだすと止まらなくなってしまうんです。そんな青春を過ごすなかで、だんだん人間って何だろうと考えはじめたわけです。大人になってからも、常に「俺って何だろう」とか「何のために生きているんだろう」といった、禅問答のようなことを繰り返してきました。それはキャバレーの司会をやっているときも、毎日のように全国を講演で飛び回っているいまも、変わりません。
・芸人にとって年齢は大きな要素だと思います。私もこの年齢になったから、中高年が聞いてくれる話ができるわけで、十年前に同じことをやっても受けませんでした。
・種つけ師だったオヤジは、選挙の応援演説もウマかった。私の話し好きも、たぶんオヤジのDNAを受け継いでいるのでしょう。口達者の血筋なら話もウマイはずです。ドキドキ感と緊張感を味方につけ、物おじせずに高校時代、3年連続弁論大会に出たこともあります。「俺、将来、司会者になる」私が家族にそう宣言したのは、まだ白黒テレビが主流の中学2年生のころでした。私が住んでいた鹿児島ではテレビのチャンネルはNHKと民放1社のたった2つでした。その民放で大好きだったのが、当時から名司会者として有名だった玉置宏さんでした。まさに私の憧れだったのです。あのころはテープレコーダーなどなかったので、テレビから流れる玉置さんの言葉をすべて紙に書き、丸暗記しました。
・芸人は有名になってナンボの世界ですから、人のモノを盗んでも、上に上がっていけばいいんです。売れたほうが勝ちなんです。でも、私はそういう人たちを見ていて、人を押し退けてまで生きることはやめようと決心したんです。というか、私にはそれほどのバイタリティーがなかったといったほうが正解かもしれません。そりゃあ、陰では悩みましたよ。キャバレーの世界でおもしろいやつがいるとはいわれていたんです。一方で、「なぜ世に出ないんだ」とか、「何か足りないんじゃないか」とか、「人間がおかしいんじゃないか」という声も聞こえていました。人間がおかしいというのは変な表現ですが、結局みんな世に出るチャンスをうかがっているわけで、自分から売り込まなければチャンスをつかめないんです。でも、私はダメなんです。誰かにスリ寄っていって「仕事をください」といえないんです。また、そこまでして仕事をしたくないんです。
・実は、ホリプロに1年間所属していたこともあります。山口百恵さんが全盛のころです。なぜ所属していたかというと、キャバレーの司会におもしろいやつがいるといううわさをホリプロが嗅ぎつけて、私を1年間預かってくれたんです。でも、私は大きな事務所に所属したことがないし、ずっと一人でやってきたものだから、どうしてもなじめませんでした。いただいた仕事を器用にこなせない。人ともうまく交われない。ホリプロにも迷惑をかけると思い、1年で辞めました。この前、堀会長から電話がかかってきたときは懐かしかったですね。「きみまろ、元気か」「あのときはお世話になりました」って。ホリプロが紹介してくれたのはテレビの仕事が中心でしたが、ダメでした。私はこう見えても上がり性なんです。しかも、テレビはお客様がいないから、どうもうまくいかない。いつもは客席のお客様と呼吸を取りながら話すんですが、カメラとは呼吸が取れないんです。ディレクターは、「カメラの向こうに、お客様が寝転がって見ていますから」というんですが、そういわれても、私にはわかりませんでした。だから、よけいにカメラの前で緊張して、かしこまってしまう。
・自分でテープをつくって売ろうと考えたのは、こういう芸人がいたんだ、売れなかったけれど、という、形に残しておきたい気持ちがあったからです。ここで、改めて私の経歴を簡単に紹介させていただきます。1950年鹿児島県生まれ。地元の高校を卒業後、玉置宏さんに憧れて司会になるんだと上京。しかし、司会になるには大学を出ていないと難しいことがわかり、産経新聞を配りながら拓殖大学商学部に進学。その後、たまたま出会ったキャバレーの営業部長の口利きでキャバレーで働きだし、運良く司会に抜擢されます。それから大学卒業後もキャバレーの司会一筋で生きてきました。転機は29歳のとき。たまたま日劇ミュージックホールで漫談をやったところ、それを聞いていた森進一さんが認めてくれて、約8年、森進一さんの専属司会をつとめました。それから小林幸子さんの専属司会を約4年つとめたあと、伍代夏子さんからは専属ゲストで呼んでいただけることになりました。それが1995年のことです。伍代さんのショーでは20分のコーナーをいただき、お客さまの反応や「間」の取り方を学びながら、いまの中高年漫談が完成しました。その漫談が好評で、地方の営業に一人で呼ばれるようになるにつれ、自信がついてきました。それで、自分の芸を記録に残したいという気持ちが強くなってきたんです。「売れなかったけれど、こんな芸人もいたんだ」と。テープは自分で録音しました。何本も試し録りしたんです。まず、A面とB面で話がダブらないようにするのがいちばん大切です。それで、地方に営業にいったとき、今日は調子がいいぞと思ったら、片面23分、ぴっちり話して録音しました。
・私が世に出たのは、すべてバスガイドさんと運転手さんの力です。バスガイドさんからも「きみまろさんのテープをかけたら、お客様がよろこんでくれました」といった感謝の電話がきたり、お客様からも「きみまろさんのテープを聴きました。今回の旅行でいろいろ観光名所を回ったけれども、きみまろさんのテープがいちばんの収穫でした」といったファックスがくるようになりました。それでだんだん手応えを感じ始めたんです。それは、テープを配り始めてから1年ぐらい経ったころでしょうか。タダで配ったテープは3千本を超えました。
・はじめて富士山を間近で見たのは、大学生のとき富士急ハイランドにスケートをしに行ったときです。雄姿を見て心が震えました。そのときの感動はいまでも忘れません。それから毎年、冬になると富士山を見るのが楽しみになって、いつかは富士山の見えるところに住みたいなと漠然と思っていました。その後、司会時代にけっこう河口湖方面に仕事で行っていましたので、富士山の見えるところで土地を探していたんです。たまたま、ある人の紹介でいまの場所を手に入れたのですが、そこから見る富士山が、いろんな場所から見たなかでいちばんきれいだったので、借金して土地を買ったわkです。偶然というか、不思議な縁を感じました。私が好きな富士山の姿はいくつかありますが、一つは赤富士です。めったに見えないから貴重なんです。年に1回とか2回とか。しかも夏の夕暮れにしか出ません。
・私の持論をいわせてもらえば、結婚はカフェオレと同じでございます。男がコーヒー、女が牛乳。これを互いに混ぜるのが結婚です。混ぜてみると、最初は甘くてにおいもいい。ところが、だんだん冷めてきて、次第に脂が浮いてくる。元の牛乳やコーヒーに戻りたくても、もう簡単には戻れない。離婚にはものすごい労力が必要です。だって、ろ過しないといけないですから。互いに幸せを求め、一人では幸せ感が得られないから、ドドドドッと勢いでカップのなかで混じり合ってはみたけれど、時が経つにつれて気がついた。こんなはずではなかった。もっと甘いもんだと思っていた。これが夫婦でございます。そりゃ最初は甘いでしょう。熱くて新鮮なんだから。だけど、みなさらけだしたとき、すべてが冷めちゃうんです。私も、他人のことだからいえるのでございますが。だから、ほどほどがよいのです。
・恋愛しているときは、会って楽しんで、別れ際の一言がすべてなんです。「また会おうね」って。あそこがクライマックス。そのとき、どういう言葉をかけられるか、女性に満足感を与えて別れることができるかどうかが男の評価みたいなもの。
・自分にとって、いい人か悪い人か、見分ける方法は、一つには「時間」があります。時間に遅れてくるやつは、ダメです。年頃の娘さんがいる人は、よくいっておいたほうがいいです。時間にルーズな男はダメです。たとえば、デートの待ち合わせ時間に10分ぐらい早くやってくる男は信用できます。5分でもいい。それだけ相手のことを思っているという気持ちの表れです。この5分間が大事なんです。5分遅れるか、5分早くくるか。この差ってすごく大きいんです。もう一つ、娘さんにいっておいたほうがいいのは、待ち合わせをしているとき、キョロキョロしているような男は、まずダメです。ジーッと一点を見つめて待っているような男のほうがしっかりしています。また、唾をぺっぺっと吐くような男とか、歩きながらガムを食べているような男もダメ。つきあうだけムダです。なぜ、時間にルーズな男がダメかというと、社会人としての基本がなっていないからです。たぶん、そういう男はデートの約束だけじゃなくて、仕事もルーズでしょう。時間を守るのは、人間が社会生活を送るうえでの基本マナーです。時間にピタッとくる、ちょっと早めにくる。そういう心がけをいつもしていない男は、何をやってもルーズなんです。
・そもそも人生は、やることなすこと、初体験じゃないですか。いわば、なにごとも人生は初体験で死んでいくんです。50歳になったら50歳の人生は初体験で、60歳になったら60歳の人生は初体験なんですから。「俺、昔、50歳の人生送ったことやるよ」という人はいないのです。二度と人生は繰り返しません。だから、80歳になってみないとわからないことって、いっぱいあるわけです。ただし、一つだけわかっていることがあります。体力的には下り坂になることはあっても、上り坂になることはありません。
・何か一つ取り柄があるから花が咲いたのであって、一回咲けばいいじゃないですか。ドーンと花火を上げれば、それでいいと思うんです。花火だって、一瞬パーッと咲くからきれいであって、ずーっと咲きっぱなしだったら、誰も見に行かないでしょう。やっぱり消えるところによさがあるんです。女みたいなものです、花火って。「えーっ、あんなきれいだったのに」って、ずいぶん時間が経って会ったとき、驚くことがあるじゃないですか。人生でいちばんきれいなときに、その女を見て、何十年か経って偶然に会ったとき、「ああ、梅干ってこんなふうにできるんだ」みたいな感慨を持つことがあるでしょう。私はとくにキャバレーという華やかな世界にいたから、人より余計にそういう経験があるんです。
・美人の人生は50まで、美人じゃない人の人生は50から、です。そこから美人じゃない人は有利です、身体が丈夫だから。どんな美人も、どんな美人じゃない人も、50歳になったら「おばさん」という一つの単語でくくられちゃうんです。60歳をすぎたら「ババア」という一つの単語しか存在しないんです。なぜか。みんな同じ顔に見えるからです。ファッションも同じにしか見えなくなります。だいたい同じような店で買っているからです。誰が美人か、誰が美人じゃないか、甲乙つけがたくなるのが50歳以降です。勝負はそれからです。あとは身につけるものとスタイルです。美人じゃない人は勝負をかけるしかありません。いままで美人の陰で我慢してきたのですから。エステに通って身を引き締め、クロコダイルとか宝石とか本物で自分を飾ればいいんです。つまり、金力の勝負となるわけです。
<目次>
はじめに~きみまろワールドへようこそ!
第1章 正直に生きるのが私の信条です
カツラを自ら公表した理由
サラリーマン川柳事件の真相
ブレークとブレーキは紙一重
私のお客さまは50代以上の熟年世代
小話や作り話は笑いが薄いのです
なぜ私の漫談が受けるのか
思いやりのある毒舌のつもりです
私の笑いはミックスジュース
第2章 人生、諦めてはいけません
父に教わった人生の真実
オーディションに落ちつづけた80年代
自分を売り込むことが嫌いなんです
自分はテレビに向かない芸人です
マッサージ師の免許を取った理由
売れない時代は警察官が友だちでした
なぜ自作のテープをつくったか
テープを持ってサービスエリアへ
「勝手にものを売るな」と怒られる
すべてバスガイドさんのおかげです
最初は断ったCDの話
客席で受けなかった私の漫談
富士山は自分の姿を映す鏡ですx
余生は富士山を見ながら過ごしたい
テープが売れなければたいへんなことに
第3章 夫婦生活は”止まらない小便”
結婚はカフェオレと同じです
夫婦喧嘩はモグラ叩きと同じ
女房は人生の預かり物です
なぜ女房からしっぺ返しをくらうのか
お互いに太れば幸せになれます
亭主が絶対に捨てられない女房とは
女房も趣味も骨董がいちばん
けっして見つめ合ってはいけません
第4章 人生はないものねだりの80年
みんなお金に振り回されて生きている
人間は死ぬまで欲の塊です
お金持ちはお金を使いません
お金を使う空しさもあrます
「武士は食わねど高楊枝」の生き方
神様は平等に苦しみを与えてくれる
「ほどほど」でいいじゃないか
仕方なく働いている中高年もいます
なぜ満足ができないのか
人間は何かと引き換えに生きている
どんな大金持ちも人生の最後は人任せ
いきなり「心の豊かさ」といわれても
第5章 孤独は人間の必需品です
壁をつくるのは自分自身です
私も30年間「かもしれない人生」でした
人生には目に見えないグラフがあります
目標を達成するだけが人生なのか
たこ八郎さん的生き方に憧れます
嫌なやつはどこに行ってもいます
私もよく騙されました
騙された経験がネタに生きています
時間にルーズな男は信用できません
芸能人の身の滅ぼし方
信じられるのは占い師だけ
人間は人との出会いで変わります
最後まで結果なんて出ないもの
第6章 咲いた花は枯れます
人生は初体験で死んでいく
自分の器以上のことはできません
一度花火を上げればそれでいい
美人じゃない人の人生は50から
追い詰められた夢ばかり見ます
「あの人はいま」で会いましょう
第7章 おまけに最新ライブをどうぞ
あとがき
面白かった本まとめ(2010年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「きみまろ流(綾小路きみまろ)」の購入はコチラ
「きみまろ流(綾小路きみまろ)」の購入はコチラ この「きみまろ流(綾小路きみまろ)」という本は、漫談家の「綾小路きみまろ」の自伝や心情を綴ったものです。
潜伏期間30年のあいだに学んだ「人間の価値」「人情の機微」「人生の無常」を活字にしたとのことです。
本の最後にはライブもあり、全体的にも漫談口調で楽しく読める本です。
2003年に出版されたものですが、とてもオススメです!!
以下はこの本のポイントなどです。
・私は小さいころから、ちょっと変わった子どもでした。どこが変わっていたかというと、人間って何だろうとか、人生って何だろうということを、いつも頭の片隅で考えながら生きてきたのです。口では人を笑わせることをいっているのですが、頭のなかは冷静になっている自分を発見したのもかなり若いときでした。私は鹿児島の田舎の生まれですから、周りは自然だらけです。自然のなかで育ったというか、自然が私にいろいろ教えてくれたといってもよいでしょう。たとえば、一日中、野原に寝っころがって、雲を見ていたこともありました。あの雲どこへ行くんだろう、と不思議でしかたがなかったのです。あるいは、タンポポの白い冠毛が風に揺られてあたり一面に飛んでいる風景に出くわすと、ジッと何時間もそれを見ているのです。あの白い冠毛風に吹かれてどこへ行くんだろう、土の上に落ちて、またタンポポになるのだろうか、なんてことを考えだすと止まらなくなってしまうんです。そんな青春を過ごすなかで、だんだん人間って何だろうと考えはじめたわけです。大人になってからも、常に「俺って何だろう」とか「何のために生きているんだろう」といった、禅問答のようなことを繰り返してきました。それはキャバレーの司会をやっているときも、毎日のように全国を講演で飛び回っているいまも、変わりません。
・芸人にとって年齢は大きな要素だと思います。私もこの年齢になったから、中高年が聞いてくれる話ができるわけで、十年前に同じことをやっても受けませんでした。
・種つけ師だったオヤジは、選挙の応援演説もウマかった。私の話し好きも、たぶんオヤジのDNAを受け継いでいるのでしょう。口達者の血筋なら話もウマイはずです。ドキドキ感と緊張感を味方につけ、物おじせずに高校時代、3年連続弁論大会に出たこともあります。「俺、将来、司会者になる」私が家族にそう宣言したのは、まだ白黒テレビが主流の中学2年生のころでした。私が住んでいた鹿児島ではテレビのチャンネルはNHKと民放1社のたった2つでした。その民放で大好きだったのが、当時から名司会者として有名だった玉置宏さんでした。まさに私の憧れだったのです。あのころはテープレコーダーなどなかったので、テレビから流れる玉置さんの言葉をすべて紙に書き、丸暗記しました。
・芸人は有名になってナンボの世界ですから、人のモノを盗んでも、上に上がっていけばいいんです。売れたほうが勝ちなんです。でも、私はそういう人たちを見ていて、人を押し退けてまで生きることはやめようと決心したんです。というか、私にはそれほどのバイタリティーがなかったといったほうが正解かもしれません。そりゃあ、陰では悩みましたよ。キャバレーの世界でおもしろいやつがいるとはいわれていたんです。一方で、「なぜ世に出ないんだ」とか、「何か足りないんじゃないか」とか、「人間がおかしいんじゃないか」という声も聞こえていました。人間がおかしいというのは変な表現ですが、結局みんな世に出るチャンスをうかがっているわけで、自分から売り込まなければチャンスをつかめないんです。でも、私はダメなんです。誰かにスリ寄っていって「仕事をください」といえないんです。また、そこまでして仕事をしたくないんです。
・実は、ホリプロに1年間所属していたこともあります。山口百恵さんが全盛のころです。なぜ所属していたかというと、キャバレーの司会におもしろいやつがいるといううわさをホリプロが嗅ぎつけて、私を1年間預かってくれたんです。でも、私は大きな事務所に所属したことがないし、ずっと一人でやってきたものだから、どうしてもなじめませんでした。いただいた仕事を器用にこなせない。人ともうまく交われない。ホリプロにも迷惑をかけると思い、1年で辞めました。この前、堀会長から電話がかかってきたときは懐かしかったですね。「きみまろ、元気か」「あのときはお世話になりました」って。ホリプロが紹介してくれたのはテレビの仕事が中心でしたが、ダメでした。私はこう見えても上がり性なんです。しかも、テレビはお客様がいないから、どうもうまくいかない。いつもは客席のお客様と呼吸を取りながら話すんですが、カメラとは呼吸が取れないんです。ディレクターは、「カメラの向こうに、お客様が寝転がって見ていますから」というんですが、そういわれても、私にはわかりませんでした。だから、よけいにカメラの前で緊張して、かしこまってしまう。
・自分でテープをつくって売ろうと考えたのは、こういう芸人がいたんだ、売れなかったけれど、という、形に残しておきたい気持ちがあったからです。ここで、改めて私の経歴を簡単に紹介させていただきます。1950年鹿児島県生まれ。地元の高校を卒業後、玉置宏さんに憧れて司会になるんだと上京。しかし、司会になるには大学を出ていないと難しいことがわかり、産経新聞を配りながら拓殖大学商学部に進学。その後、たまたま出会ったキャバレーの営業部長の口利きでキャバレーで働きだし、運良く司会に抜擢されます。それから大学卒業後もキャバレーの司会一筋で生きてきました。転機は29歳のとき。たまたま日劇ミュージックホールで漫談をやったところ、それを聞いていた森進一さんが認めてくれて、約8年、森進一さんの専属司会をつとめました。それから小林幸子さんの専属司会を約4年つとめたあと、伍代夏子さんからは専属ゲストで呼んでいただけることになりました。それが1995年のことです。伍代さんのショーでは20分のコーナーをいただき、お客さまの反応や「間」の取り方を学びながら、いまの中高年漫談が完成しました。その漫談が好評で、地方の営業に一人で呼ばれるようになるにつれ、自信がついてきました。それで、自分の芸を記録に残したいという気持ちが強くなってきたんです。「売れなかったけれど、こんな芸人もいたんだ」と。テープは自分で録音しました。何本も試し録りしたんです。まず、A面とB面で話がダブらないようにするのがいちばん大切です。それで、地方に営業にいったとき、今日は調子がいいぞと思ったら、片面23分、ぴっちり話して録音しました。
・私が世に出たのは、すべてバスガイドさんと運転手さんの力です。バスガイドさんからも「きみまろさんのテープをかけたら、お客様がよろこんでくれました」といった感謝の電話がきたり、お客様からも「きみまろさんのテープを聴きました。今回の旅行でいろいろ観光名所を回ったけれども、きみまろさんのテープがいちばんの収穫でした」といったファックスがくるようになりました。それでだんだん手応えを感じ始めたんです。それは、テープを配り始めてから1年ぐらい経ったころでしょうか。タダで配ったテープは3千本を超えました。
・はじめて富士山を間近で見たのは、大学生のとき富士急ハイランドにスケートをしに行ったときです。雄姿を見て心が震えました。そのときの感動はいまでも忘れません。それから毎年、冬になると富士山を見るのが楽しみになって、いつかは富士山の見えるところに住みたいなと漠然と思っていました。その後、司会時代にけっこう河口湖方面に仕事で行っていましたので、富士山の見えるところで土地を探していたんです。たまたま、ある人の紹介でいまの場所を手に入れたのですが、そこから見る富士山が、いろんな場所から見たなかでいちばんきれいだったので、借金して土地を買ったわkです。偶然というか、不思議な縁を感じました。私が好きな富士山の姿はいくつかありますが、一つは赤富士です。めったに見えないから貴重なんです。年に1回とか2回とか。しかも夏の夕暮れにしか出ません。
・私の持論をいわせてもらえば、結婚はカフェオレと同じでございます。男がコーヒー、女が牛乳。これを互いに混ぜるのが結婚です。混ぜてみると、最初は甘くてにおいもいい。ところが、だんだん冷めてきて、次第に脂が浮いてくる。元の牛乳やコーヒーに戻りたくても、もう簡単には戻れない。離婚にはものすごい労力が必要です。だって、ろ過しないといけないですから。互いに幸せを求め、一人では幸せ感が得られないから、ドドドドッと勢いでカップのなかで混じり合ってはみたけれど、時が経つにつれて気がついた。こんなはずではなかった。もっと甘いもんだと思っていた。これが夫婦でございます。そりゃ最初は甘いでしょう。熱くて新鮮なんだから。だけど、みなさらけだしたとき、すべてが冷めちゃうんです。私も、他人のことだからいえるのでございますが。だから、ほどほどがよいのです。
・恋愛しているときは、会って楽しんで、別れ際の一言がすべてなんです。「また会おうね」って。あそこがクライマックス。そのとき、どういう言葉をかけられるか、女性に満足感を与えて別れることができるかどうかが男の評価みたいなもの。
・自分にとって、いい人か悪い人か、見分ける方法は、一つには「時間」があります。時間に遅れてくるやつは、ダメです。年頃の娘さんがいる人は、よくいっておいたほうがいいです。時間にルーズな男はダメです。たとえば、デートの待ち合わせ時間に10分ぐらい早くやってくる男は信用できます。5分でもいい。それだけ相手のことを思っているという気持ちの表れです。この5分間が大事なんです。5分遅れるか、5分早くくるか。この差ってすごく大きいんです。もう一つ、娘さんにいっておいたほうがいいのは、待ち合わせをしているとき、キョロキョロしているような男は、まずダメです。ジーッと一点を見つめて待っているような男のほうがしっかりしています。また、唾をぺっぺっと吐くような男とか、歩きながらガムを食べているような男もダメ。つきあうだけムダです。なぜ、時間にルーズな男がダメかというと、社会人としての基本がなっていないからです。たぶん、そういう男はデートの約束だけじゃなくて、仕事もルーズでしょう。時間を守るのは、人間が社会生活を送るうえでの基本マナーです。時間にピタッとくる、ちょっと早めにくる。そういう心がけをいつもしていない男は、何をやってもルーズなんです。
・そもそも人生は、やることなすこと、初体験じゃないですか。いわば、なにごとも人生は初体験で死んでいくんです。50歳になったら50歳の人生は初体験で、60歳になったら60歳の人生は初体験なんですから。「俺、昔、50歳の人生送ったことやるよ」という人はいないのです。二度と人生は繰り返しません。だから、80歳になってみないとわからないことって、いっぱいあるわけです。ただし、一つだけわかっていることがあります。体力的には下り坂になることはあっても、上り坂になることはありません。
・何か一つ取り柄があるから花が咲いたのであって、一回咲けばいいじゃないですか。ドーンと花火を上げれば、それでいいと思うんです。花火だって、一瞬パーッと咲くからきれいであって、ずーっと咲きっぱなしだったら、誰も見に行かないでしょう。やっぱり消えるところによさがあるんです。女みたいなものです、花火って。「えーっ、あんなきれいだったのに」って、ずいぶん時間が経って会ったとき、驚くことがあるじゃないですか。人生でいちばんきれいなときに、その女を見て、何十年か経って偶然に会ったとき、「ああ、梅干ってこんなふうにできるんだ」みたいな感慨を持つことがあるでしょう。私はとくにキャバレーという華やかな世界にいたから、人より余計にそういう経験があるんです。
・美人の人生は50まで、美人じゃない人の人生は50から、です。そこから美人じゃない人は有利です、身体が丈夫だから。どんな美人も、どんな美人じゃない人も、50歳になったら「おばさん」という一つの単語でくくられちゃうんです。60歳をすぎたら「ババア」という一つの単語しか存在しないんです。なぜか。みんな同じ顔に見えるからです。ファッションも同じにしか見えなくなります。だいたい同じような店で買っているからです。誰が美人か、誰が美人じゃないか、甲乙つけがたくなるのが50歳以降です。勝負はそれからです。あとは身につけるものとスタイルです。美人じゃない人は勝負をかけるしかありません。いままで美人の陰で我慢してきたのですから。エステに通って身を引き締め、クロコダイルとか宝石とか本物で自分を飾ればいいんです。つまり、金力の勝負となるわけです。
<目次>
はじめに~きみまろワールドへようこそ!
第1章 正直に生きるのが私の信条です
カツラを自ら公表した理由
サラリーマン川柳事件の真相
ブレークとブレーキは紙一重
私のお客さまは50代以上の熟年世代
小話や作り話は笑いが薄いのです
なぜ私の漫談が受けるのか
思いやりのある毒舌のつもりです
私の笑いはミックスジュース
第2章 人生、諦めてはいけません
父に教わった人生の真実
オーディションに落ちつづけた80年代
自分を売り込むことが嫌いなんです
自分はテレビに向かない芸人です
マッサージ師の免許を取った理由
売れない時代は警察官が友だちでした
なぜ自作のテープをつくったか
テープを持ってサービスエリアへ
「勝手にものを売るな」と怒られる
すべてバスガイドさんのおかげです
最初は断ったCDの話
客席で受けなかった私の漫談
富士山は自分の姿を映す鏡ですx
余生は富士山を見ながら過ごしたい
テープが売れなければたいへんなことに
第3章 夫婦生活は”止まらない小便”
結婚はカフェオレと同じです
夫婦喧嘩はモグラ叩きと同じ
女房は人生の預かり物です
なぜ女房からしっぺ返しをくらうのか
お互いに太れば幸せになれます
亭主が絶対に捨てられない女房とは
女房も趣味も骨董がいちばん
けっして見つめ合ってはいけません
第4章 人生はないものねだりの80年
みんなお金に振り回されて生きている
人間は死ぬまで欲の塊です
お金持ちはお金を使いません
お金を使う空しさもあrます
「武士は食わねど高楊枝」の生き方
神様は平等に苦しみを与えてくれる
「ほどほど」でいいじゃないか
仕方なく働いている中高年もいます
なぜ満足ができないのか
人間は何かと引き換えに生きている
どんな大金持ちも人生の最後は人任せ
いきなり「心の豊かさ」といわれても
第5章 孤独は人間の必需品です
壁をつくるのは自分自身です
私も30年間「かもしれない人生」でした
人生には目に見えないグラフがあります
目標を達成するだけが人生なのか
たこ八郎さん的生き方に憧れます
嫌なやつはどこに行ってもいます
私もよく騙されました
騙された経験がネタに生きています
時間にルーズな男は信用できません
芸能人の身の滅ぼし方
信じられるのは占い師だけ
人間は人との出会いで変わります
最後まで結果なんて出ないもの
第6章 咲いた花は枯れます
人生は初体験で死んでいく
自分の器以上のことはできません
一度花火を上げればそれでいい
美人じゃない人の人生は50から
追い詰められた夢ばかり見ます
「あの人はいま」で会いましょう
第7章 おまけに最新ライブをどうぞ
あとがき
面白かった本まとめ(2010年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。












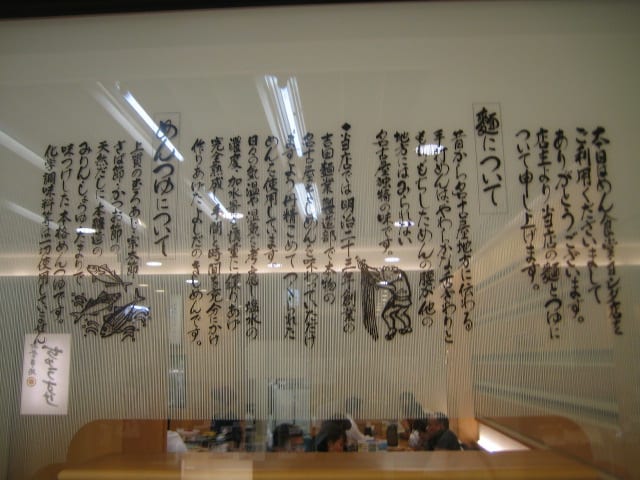
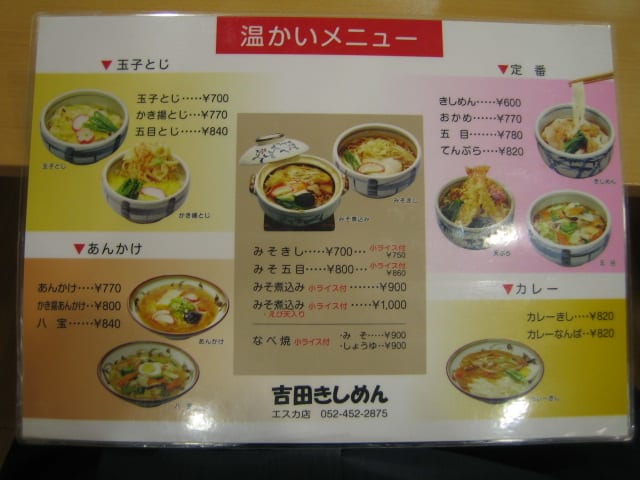














 「臓器は若返る-メタボリックドミノの真実(伊藤裕)」の購入はコチラ
「臓器は若返る-メタボリックドミノの真実(伊藤裕)」の購入はコチラ 

 「幸福立国ブータン(大橋照枝)」の購入はコチラ
「幸福立国ブータン(大橋照枝)」の購入はコチラ 










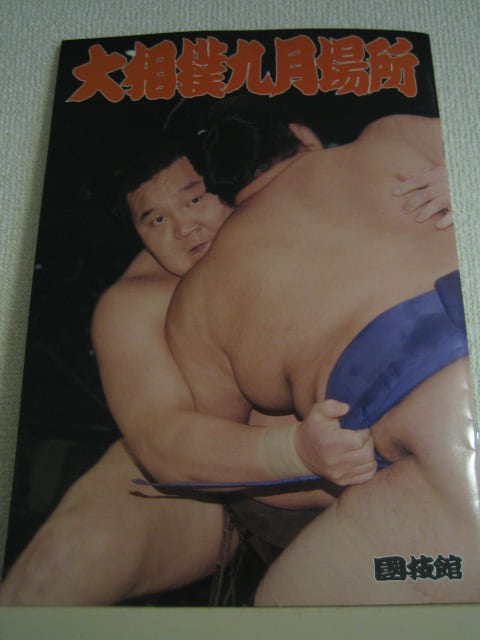

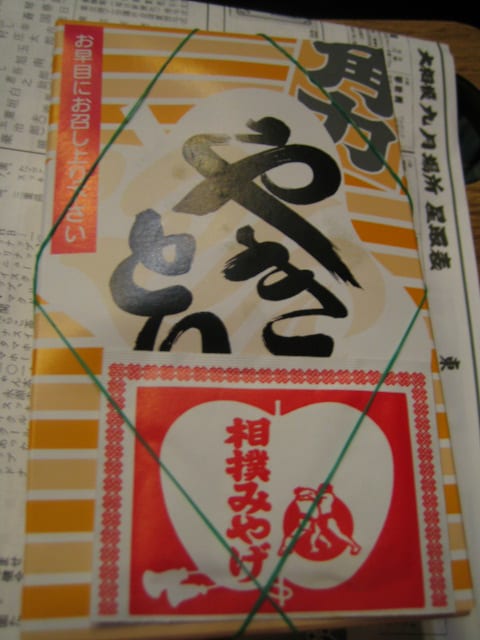


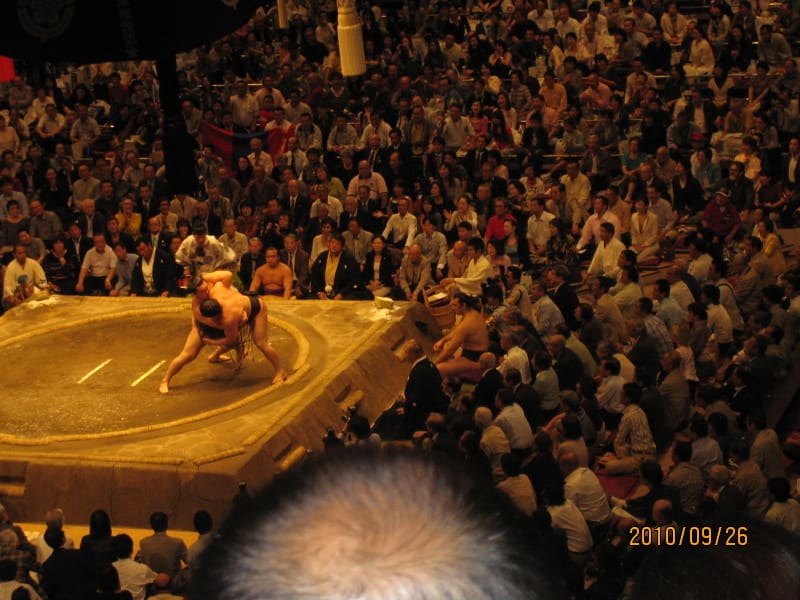
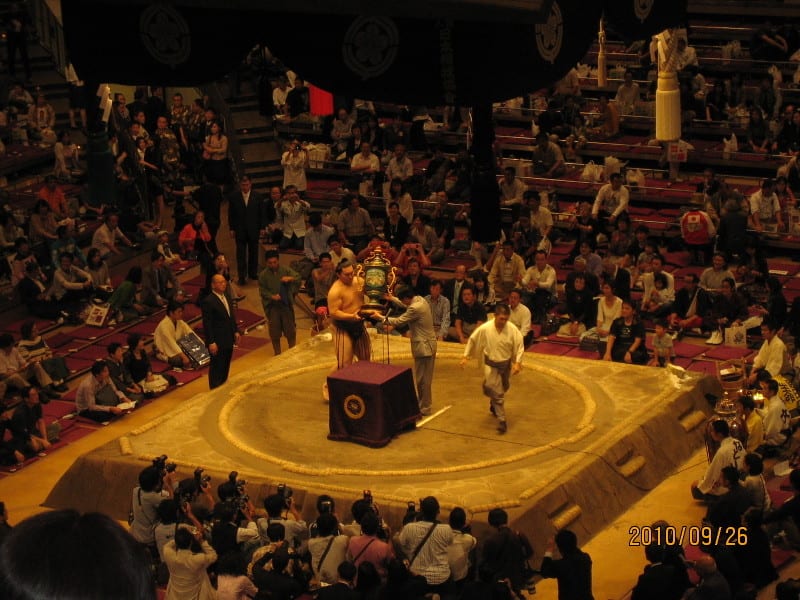
 「一生モノの勉強法(鎌田浩毅)」の購入はコチラ
「一生モノの勉強法(鎌田浩毅)」の購入はコチラ 














 「一生モノの人脈術(鎌田浩毅)」の購入はコチラ
「一生モノの人脈術(鎌田浩毅)」の購入はコチラ 



