都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「虎屋文庫のお菓子な展示77」 虎屋ギャラリー
虎屋ギャラリー
「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」
5/20-6/16
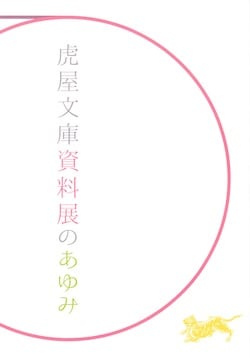
虎屋ギャラリーで開催中の「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」を見てきました。
創業は室町時代に遡るという老舗和菓子メーカーのとらや。赤坂の現本店は1973年に建てられたそうです。(ちなみに赤坂に店を構えたのは1879年です。)
ビル老朽化ということでしょうか。このほど建て替えが決定。よって本店内のギャラリーも一時、休館することになりました。

まさしく休館前の最後の展示です。タイトルは「虎屋文庫のお菓子な展示77」。ラストの77とは本展が77回目であることを示します。これまで虎屋ギャラリーにて数多く行われてきた展示を振り返っていました。
記念すべき第1回展はビルの竣工した1973年。「富岡鉄斎と虎屋展」です。何故に鉄斎と思ってしまいましたが、実は彼、虎屋と深い縁を持っていたとか。何でも生前、京都の虎屋の支配人と親しかったそうです。
続くのは同年の「虎屋の古文書展」。最近でこそ和菓子の展示も目立つ虎屋ギャラリーですが、初めは必ずしもそうではありませんでした。かつてはこうした古文書なり、歴代の店主を今も務める黒川家にまつわる資料展が多かったそうです。
和菓子文化に目が向けられるようになったのは1980年代に入ってからのこと。1983年の「和菓子の歴史展」に始まります。翌年には「虎屋と菓銘と由来展」を開催。江戸以降、近代に至る和菓子の名の由来についての展示を行いました。
1987年には「和菓子と甘み展」が開催されます。それまでの展示では集客に苦労し、少ない日では来場者が1桁の時もあったそうですが、この回は新聞にも取り上げられ、結果的に1000名を超える人で賑わいました。
さらに翌年の「慶びと寿ぎの和菓子展」からは限定菓子の発売もスタート。同年の「源氏物語と和菓子展」では源氏物語の世界を料紙とともに和菓子で再現する試みもなされたそうです。
和菓子を入れるための容器、お通箱こと井籠が大変に立派なのには驚きました。井籠を取り上げたのは1989年の「お通箱と和菓子展」です。江戸時代に制作された井籠を並べて展示しました。
「竹虎青貝井籠」は螺鈿です。生前は1698年、5段の重箱でしょうか。実に艶やかです。蓋にも側面にも虎が螺鈿で描かれています。サイズはかなり大きい。重さはどのくらいあるのでしょうか。また持ち運びの方法にも興味が湧きます。
光琳も登場しました。第45回展、1995年の「歴史上の人物と和菓子展(その2)」でのことです。光琳が友人の中村内蔵助に贈ったのは10種類の和菓子。注文の内容が「緒方御用留書」に記録されています。
清長の「名代干菓子山殿」に目を引かれました。いわゆる黄表紙の読み物、何でも茶碗を探しにいくという物語だそうですが、中には擬人化されたお菓子がたくさん描かれています。それを2000年の「江戸おもしろお菓子展」で紹介したそうです。また2006年の「和菓子アート展」では文字通り現代アートとコラボレーション。かの森村泰昌が参加しては作り文字のモチーフを手がけました。
本店2階の小さな小さな展示スペースこと、虎屋ギャラリー。しかしながらそこには和菓子に関する文化を伝えてきた虎屋の長きに渡る伝統があります。

キャプションやパネルの随所に記載されていたスタッフの方の苦労話なども興味深いのではないでしょうか。また職人さんによる和菓子制作についての展示もあります。単に歴史だけでなく、虎屋の和菓子にかける熱意のようなものも伝わる内容でした。
 「虎屋ー和菓子と歩んだ五百年/新潮新書/新潮社」
「虎屋ー和菓子と歩んだ五百年/新潮新書/新潮社」
「虎屋文庫資料展のあゆみ」と題した小冊子もいただきました。次回、ビル建て替えを経て、3年後に予定されている第78回展にも期待したいと思います。
 「和菓子 (NHK美の壺)/日本放送出版協会」
「和菓子 (NHK美の壺)/日本放送出版協会」
会期中無休、入場は無料です。6月16日まで開催されています。
「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」 虎屋ギャラリー
会期:5月20日(水)~6月16日(火)
休館:会期中無休。
時間:10:00~17:30。
料金:無料。
住所:港区赤坂4-9-22
交通:東京メトロ銀座線・丸の内線赤坂見附駅A出口より徒歩7分。
「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」
5/20-6/16
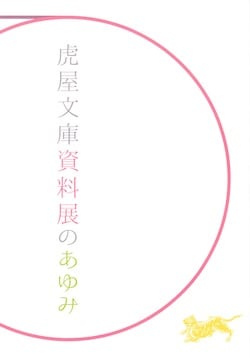
虎屋ギャラリーで開催中の「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」を見てきました。
創業は室町時代に遡るという老舗和菓子メーカーのとらや。赤坂の現本店は1973年に建てられたそうです。(ちなみに赤坂に店を構えたのは1879年です。)
ビル老朽化ということでしょうか。このほど建て替えが決定。よって本店内のギャラリーも一時、休館することになりました。

まさしく休館前の最後の展示です。タイトルは「虎屋文庫のお菓子な展示77」。ラストの77とは本展が77回目であることを示します。これまで虎屋ギャラリーにて数多く行われてきた展示を振り返っていました。
記念すべき第1回展はビルの竣工した1973年。「富岡鉄斎と虎屋展」です。何故に鉄斎と思ってしまいましたが、実は彼、虎屋と深い縁を持っていたとか。何でも生前、京都の虎屋の支配人と親しかったそうです。
続くのは同年の「虎屋の古文書展」。最近でこそ和菓子の展示も目立つ虎屋ギャラリーですが、初めは必ずしもそうではありませんでした。かつてはこうした古文書なり、歴代の店主を今も務める黒川家にまつわる資料展が多かったそうです。
和菓子文化に目が向けられるようになったのは1980年代に入ってからのこと。1983年の「和菓子の歴史展」に始まります。翌年には「虎屋と菓銘と由来展」を開催。江戸以降、近代に至る和菓子の名の由来についての展示を行いました。
1987年には「和菓子と甘み展」が開催されます。それまでの展示では集客に苦労し、少ない日では来場者が1桁の時もあったそうですが、この回は新聞にも取り上げられ、結果的に1000名を超える人で賑わいました。
さらに翌年の「慶びと寿ぎの和菓子展」からは限定菓子の発売もスタート。同年の「源氏物語と和菓子展」では源氏物語の世界を料紙とともに和菓子で再現する試みもなされたそうです。
和菓子を入れるための容器、お通箱こと井籠が大変に立派なのには驚きました。井籠を取り上げたのは1989年の「お通箱と和菓子展」です。江戸時代に制作された井籠を並べて展示しました。
「竹虎青貝井籠」は螺鈿です。生前は1698年、5段の重箱でしょうか。実に艶やかです。蓋にも側面にも虎が螺鈿で描かれています。サイズはかなり大きい。重さはどのくらいあるのでしょうか。また持ち運びの方法にも興味が湧きます。
光琳も登場しました。第45回展、1995年の「歴史上の人物と和菓子展(その2)」でのことです。光琳が友人の中村内蔵助に贈ったのは10種類の和菓子。注文の内容が「緒方御用留書」に記録されています。
清長の「名代干菓子山殿」に目を引かれました。いわゆる黄表紙の読み物、何でも茶碗を探しにいくという物語だそうですが、中には擬人化されたお菓子がたくさん描かれています。それを2000年の「江戸おもしろお菓子展」で紹介したそうです。また2006年の「和菓子アート展」では文字通り現代アートとコラボレーション。かの森村泰昌が参加しては作り文字のモチーフを手がけました。
本店2階の小さな小さな展示スペースこと、虎屋ギャラリー。しかしながらそこには和菓子に関する文化を伝えてきた虎屋の長きに渡る伝統があります。

キャプションやパネルの随所に記載されていたスタッフの方の苦労話なども興味深いのではないでしょうか。また職人さんによる和菓子制作についての展示もあります。単に歴史だけでなく、虎屋の和菓子にかける熱意のようなものも伝わる内容でした。
 「虎屋ー和菓子と歩んだ五百年/新潮新書/新潮社」
「虎屋ー和菓子と歩んだ五百年/新潮新書/新潮社」「虎屋文庫資料展のあゆみ」と題した小冊子もいただきました。次回、ビル建て替えを経て、3年後に予定されている第78回展にも期待したいと思います。
 「和菓子 (NHK美の壺)/日本放送出版協会」
「和菓子 (NHK美の壺)/日本放送出版協会」会期中無休、入場は無料です。6月16日まで開催されています。
「休館前の特別企画 虎屋文庫のお菓子な展示77」 虎屋ギャラリー
会期:5月20日(水)~6月16日(火)
休館:会期中無休。
時間:10:00~17:30。
料金:無料。
住所:港区赤坂4-9-22
交通:東京メトロ銀座線・丸の内線赤坂見附駅A出口より徒歩7分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










