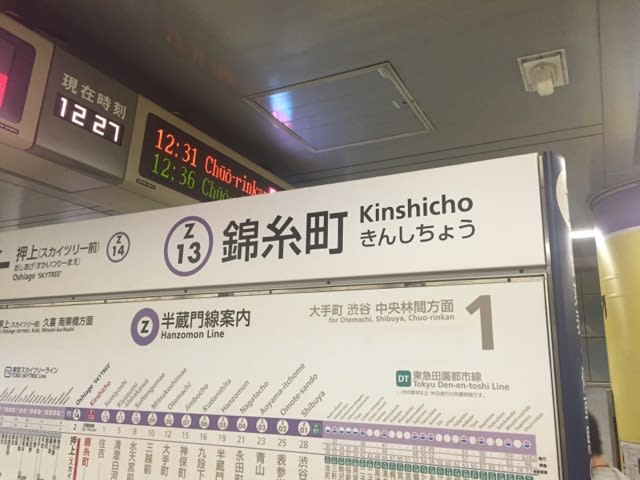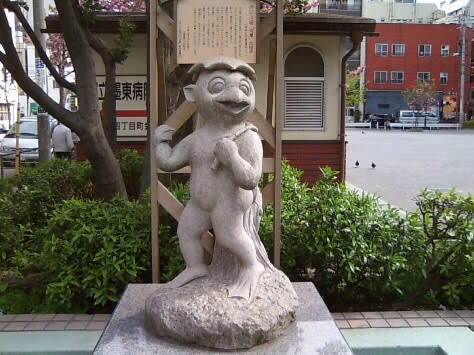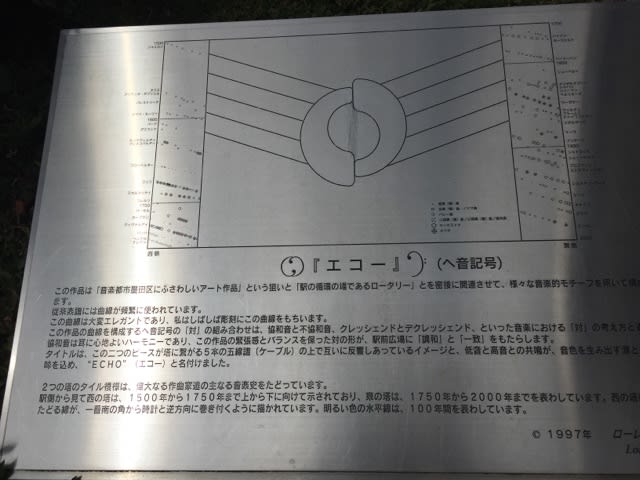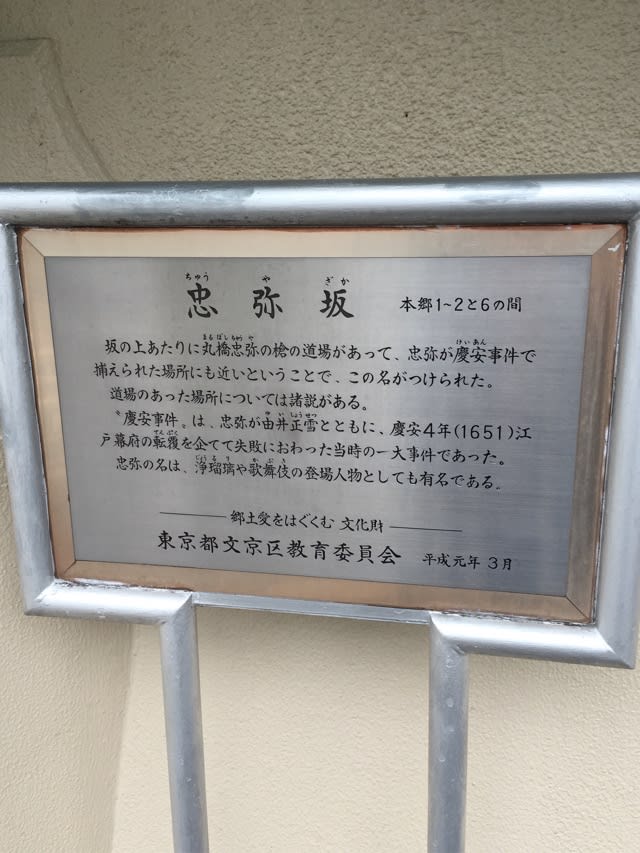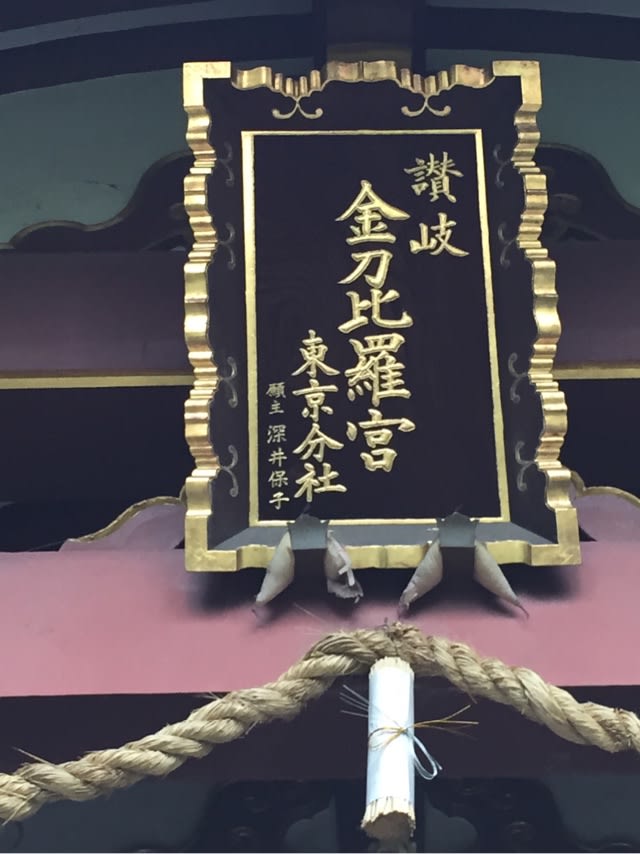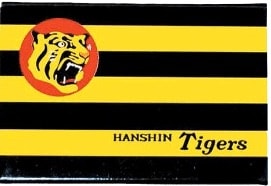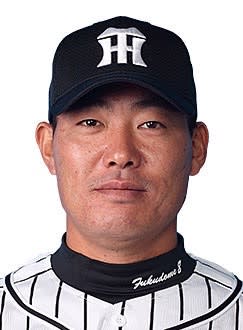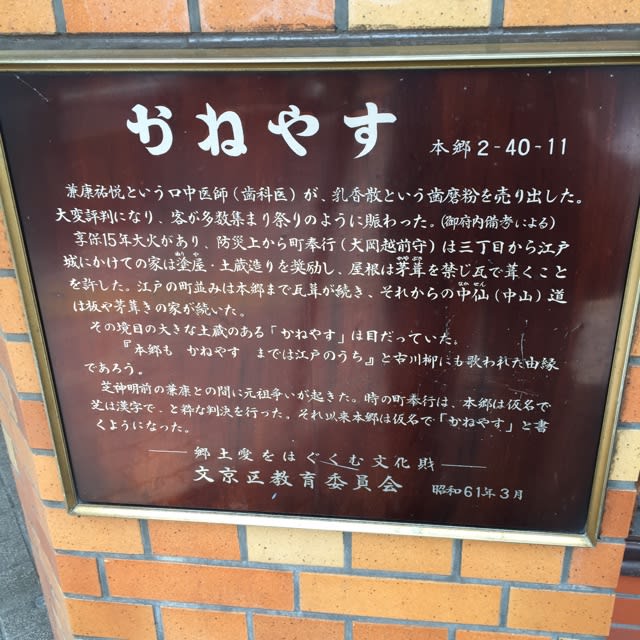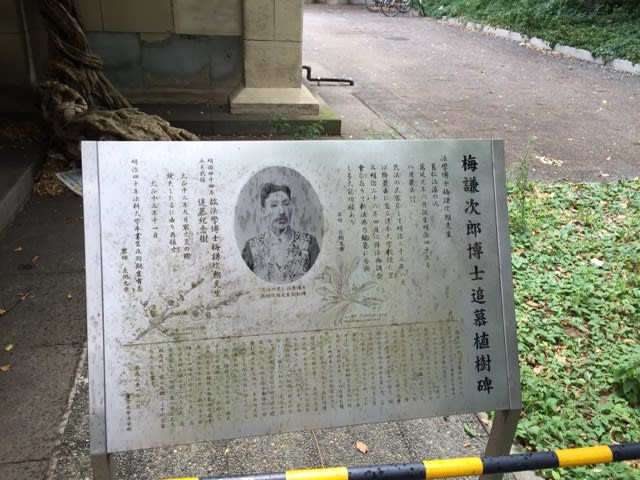Villa D'est Gardenfarm and Wineryは文筆家の玉村豊男氏が2003年に開設したワイナリー。ワイナリーや庭園の散策ができ、カフェではランチやディナーを楽しむことができる。場所は長野県東御市(旧 東部町)の小高い丘の上にあり、町を一望でき、また、周りはブドウ畑と庭園に囲まれている。

以前から訪れてみたい場所であったが、念願叶い、8月某日1時半にランチを予約した。店はそれほど広くないが、中に入ると玉村氏がデザインをした食器やポストカード、ワインを販売しており、その奥にカフェがある。

席に通されて右側を見ると遠くに上田の街並みが広がり、サンセットが素晴らしいと聞いたが、そのロケーションに納得。予約したコースに飲み物とメインを決めてランチスタート。

アミューズに信州サーモンのマリネに生食用のカボチャを刺したピンチョス。サーモンは脂が乗っている。

前菜は夏野菜づくし、『夏のヴィラデスト』。夏野菜入りのガスパチョ、レタスサラダ、焼いたナスにモッツァレラとミニトマトを乗せたもの。サラダのドレッシングもトマトも美味く、信州の夏野菜に感動。

次に別料金で追加した小さなスープ、トウモロコシの冷製スープ。自然の甘さが際立つ。

メインは小生は『信州牛と丸ナスのムサカ』、簡単にいうとナスと牛肉のつなぎなしハンバーグにトマトとチーズ入りホワイトソースをかけたもの。敷いてある焼いた玉ねぎと共に食べるとその味のバランスが良く、ボリュームもある。

相方は『信州ハーブ鶏と自家製ソーセージ、じゃがいものローズマリー風味』鶏のムネ肉をローズマリーとともにローストし、塩レモンのソースをかけたもの。

デサートはヨーグルトのアイスクリームとペパーミントのムース。特にムースの控えめなペパーミントの香りが素晴らしい。

全てを通し、器やランチョンマットなどの調和も良く、特に最後のコーヒーカップなど欲しくなるほど。残念ながら、車のため、ワインは相方のみであったが、十分堪能した。味もいいが、雰囲気が良く、ご婦人を招待すると必ず株が上がることはうけあいである。(因みに某氏がノンアルコールシャンパンを飲んだらサイダーと変わらないくせにしっかりした値段だったとの話もあり、やめた方が賢明らしい。)

ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー
長野県東御市和6027
0268637373