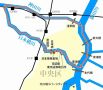2020年12月は前月と比べて著名人の訃報が内外ともに多かった。遅れて発表される訃報があるかもしれないが、そろそろ書いておきたい。12月は広義の「芸能界」の訃報が多かった。
12月23日に、作詞家、作家のなかにし礼が死去。82歳。がん闘病を告白し多くの本も書いているが、死因は心筋梗塞だった。阿久悠などと並んで、戦後歌謡曲の代表的な作詞家だった。シャンソンの訳詞を書いていたが、たまたま石原裕次郎の知遇を得て、歌謡曲の作詞を始めた。60年代にもう多くの傑作がある。1965年の「知りたくないの」(菅原洋一)、1966年の「天使の誘惑」(黛ジュン、レコード大賞)、1969年の「恋の奴隷」(奥村チヨ)、「人形の家」(弘田美枝子)、「今日でお別れ」(菅原洋一、レコード大賞)、「港町ブルース」(森進一)などである。
 (なかにし礼)
(なかにし礼)
その後も70年代に「手紙」(由紀さおり)、「グッドバイ・マイ・ラブ」(アン・ルイス)、「石狩挽歌」(北原ミレイ)、「時には娼婦のように」(黒沢年雄)など、80年代に「北酒場」(細川たかし、レコード大賞)、「まつり」(北島三郎)、「風の盆恋歌」(石川さゆり)などがある。60年代のシャンソン的、ポップス的な世界が次第に演歌が多くなっている。先に亡くなった筒美京平作曲のレコードは3枚持っていたが、なかにし礼作詞の曲は持っているのだろうか。調べたらキャンディーズの「哀愁のシンフォニー」と小柳ルミ子の「京のにわか雨」があった。そんな曲も買っていたのか。
 (哀愁のシンフォニー)
(哀愁のシンフォニー) (京のにわか雨)
(京のにわか雨)
これらの歌の世界には知らず知らずのうちに大きな影響を受けていたのかも知れない。上で挙げなかったが,一番好きなのはペドロ&カプリシャス「別れの朝」だ。その後小説家になって、「長崎ぶらぶら節」(1999)で直木賞を受けた。他に特攻隊員だった兄との関係を書いた「兄弟」、満州からの引き上げ体験を書いた「赤い月」などが話題を呼んだ。近年はがんと闘病しながら、自身の体験をもとに反戦・平和の訴えを続けていた。明治大学に「阿久悠記念館」があるので、ぜひ出身の立教大学に「なかにし礼記念館」を作って欲しいと思う。
今挙げたなかにし礼作詞の細川たかし「北酒場」の作曲家だった中村泰士(たいじ)が12月20日死去、81歳。「スター誕生!」の審査員だったから、僕も昔から名前を知っている。最高傑作は紛れもなく「喝采」(ちあきなおみ)だろう。1972年の紅白歌合戦で聞いたときの感動は忘れがたい。他にも桜田淳子「わたしの青い鳥」、細川たかし「心のこり」、松崎しげる「黄色い麦わら帽子」などがある。多くの曲を書いているが,今ひとつ大ヒットが少ない印象だ。
 (中村泰士)
(中村泰士)
コメディアンの小松政夫が12月7日に死去、78歳。クレージーキャッツの付き人をしながら、次第に人気を得ていった経過は2018年に東京新聞夕刊に掲載された「この道」(聞き書きの自伝)に詳しい。その前年にNHKで植木等と小松との関わりを描くドラマが放送された。それらで僕は小松政夫という人を初めて知った気がした。小松政夫が伊東四朗と組んで「しらけ鳥音頭」「電線音頭」で大ブレークした頃は、ほとんどテレビを見なくなっていたのでよく知らなかったのである。本名は「松崎雅臣」だが、「しゃぼん玉ホリデー」に大男の松崎真が出ていて、「小さい方の松崎」で「小松」となった。忘れていたけど、ウィキペディアを見たら「麻雀放浪記2020」で「出目徳」を演じ、予告編で淀川長治のマネをしていた。それがおかしかったのを思い出した。
 (小松政夫)
(小松政夫)
人間国宝の講談師、一竜斎貞水が12月3日に死去、81歳。「立体講談」と呼ぶ照明や音響を使った怪談噺で知られた。僕も「牡丹灯籠」を聞いている。2002年に講談界初の人間国宝に認定された。僕は実はこの訃報に一番驚いた。それは正月の国立演芸場の公演に出場予定だったからである。行ったかどうかは判らないけど、まだ元気なんだなと思っていた。最近は神田伯山の人気がブレークしたが、神田派は「日本講談協会」、「一竜斎」の講談師は「講談協会」である。
 (一竜斎貞水)
(一竜斎貞水)
落語家の林家こん平が死去、12月17日死去、77歳。「笑点」メンバーの人気者だったが、2004年以来多発性硬化症や糖尿病などの闘病のため降板し高座にも復帰できなかった。しかし、死因は誤嚥性肺炎だった。いつも「笑点」でネタにしていたように、新潟県千谷沢村(現・長岡市)に生まれ、1958年に初代林家三平に入門した。師匠が1980年に急死した後は、事実上の一番弟子(一番弟子の林家珍平は俳優に転業、昔の映画で時々見られる)として、一門をまとめる役目を果たした。「笑点」を引き継いだ林家たい平や二代目林家三平は弟子に当たる。最初の呼びかけ「チャラーン」は有名だった。闘病後も都電荒川線を借り切って都電落語会などをやっていた。あれほど有名だった人も、テレビから消えて10数年たつと知名度がグッと落ちるもんだ。
 (林家こん平)
(林家こん平)
「女剣劇」で活躍した浅香光代が12月13日に死去、92歳。1950年代に大人気だったというから、時代的には全然知るわけがない。浅草の最後の輝きを代表したスターだったのだろう。その後、映画やテレビドラマに出るようになり,晩年はテレビのバラエティ番組の出演で知られた。晩年まで浅草で大衆芸能発展に尽力していた。
 (浅香光代)
(浅香光代)
・横山アキラ、9日没、88歳、横山ホットブラザーズのリーダー。
・西川右近、12日没、81歳。日本舞踊西川流総帥。
・小谷承靖(つぐのぶ)、13日没、84歳。映画監督。「ゴキブリ刑事」「はつ恋」「ホワイト・ラブ」「潮騒」など。草刈正雄が主演した「頑張れ!若大将」も小谷監督だった。
・出口典雄、16日没、80歳。演出家。文学座、劇団四季を経て、「シェイクスピア・シアター」を旗揚げした。シェイクスピア前作上演が高く評価された。小田島雄志の翻訳を現代風に演出したことで大きな影響力を持った。佐野史郎や吉田剛太郎が所属していたが、僕は見ていない。
・堅田喜三久(かただ・きさく)、17日没、85歳。歌舞伎長唄囃子の家元。人間国宝。
12月23日に、作詞家、作家のなかにし礼が死去。82歳。がん闘病を告白し多くの本も書いているが、死因は心筋梗塞だった。阿久悠などと並んで、戦後歌謡曲の代表的な作詞家だった。シャンソンの訳詞を書いていたが、たまたま石原裕次郎の知遇を得て、歌謡曲の作詞を始めた。60年代にもう多くの傑作がある。1965年の「知りたくないの」(菅原洋一)、1966年の「天使の誘惑」(黛ジュン、レコード大賞)、1969年の「恋の奴隷」(奥村チヨ)、「人形の家」(弘田美枝子)、「今日でお別れ」(菅原洋一、レコード大賞)、「港町ブルース」(森進一)などである。
 (なかにし礼)
(なかにし礼)その後も70年代に「手紙」(由紀さおり)、「グッドバイ・マイ・ラブ」(アン・ルイス)、「石狩挽歌」(北原ミレイ)、「時には娼婦のように」(黒沢年雄)など、80年代に「北酒場」(細川たかし、レコード大賞)、「まつり」(北島三郎)、「風の盆恋歌」(石川さゆり)などがある。60年代のシャンソン的、ポップス的な世界が次第に演歌が多くなっている。先に亡くなった筒美京平作曲のレコードは3枚持っていたが、なかにし礼作詞の曲は持っているのだろうか。調べたらキャンディーズの「哀愁のシンフォニー」と小柳ルミ子の「京のにわか雨」があった。そんな曲も買っていたのか。
 (哀愁のシンフォニー)
(哀愁のシンフォニー) (京のにわか雨)
(京のにわか雨)これらの歌の世界には知らず知らずのうちに大きな影響を受けていたのかも知れない。上で挙げなかったが,一番好きなのはペドロ&カプリシャス「別れの朝」だ。その後小説家になって、「長崎ぶらぶら節」(1999)で直木賞を受けた。他に特攻隊員だった兄との関係を書いた「兄弟」、満州からの引き上げ体験を書いた「赤い月」などが話題を呼んだ。近年はがんと闘病しながら、自身の体験をもとに反戦・平和の訴えを続けていた。明治大学に「阿久悠記念館」があるので、ぜひ出身の立教大学に「なかにし礼記念館」を作って欲しいと思う。
今挙げたなかにし礼作詞の細川たかし「北酒場」の作曲家だった中村泰士(たいじ)が12月20日死去、81歳。「スター誕生!」の審査員だったから、僕も昔から名前を知っている。最高傑作は紛れもなく「喝采」(ちあきなおみ)だろう。1972年の紅白歌合戦で聞いたときの感動は忘れがたい。他にも桜田淳子「わたしの青い鳥」、細川たかし「心のこり」、松崎しげる「黄色い麦わら帽子」などがある。多くの曲を書いているが,今ひとつ大ヒットが少ない印象だ。
 (中村泰士)
(中村泰士)コメディアンの小松政夫が12月7日に死去、78歳。クレージーキャッツの付き人をしながら、次第に人気を得ていった経過は2018年に東京新聞夕刊に掲載された「この道」(聞き書きの自伝)に詳しい。その前年にNHKで植木等と小松との関わりを描くドラマが放送された。それらで僕は小松政夫という人を初めて知った気がした。小松政夫が伊東四朗と組んで「しらけ鳥音頭」「電線音頭」で大ブレークした頃は、ほとんどテレビを見なくなっていたのでよく知らなかったのである。本名は「松崎雅臣」だが、「しゃぼん玉ホリデー」に大男の松崎真が出ていて、「小さい方の松崎」で「小松」となった。忘れていたけど、ウィキペディアを見たら「麻雀放浪記2020」で「出目徳」を演じ、予告編で淀川長治のマネをしていた。それがおかしかったのを思い出した。
 (小松政夫)
(小松政夫)人間国宝の講談師、一竜斎貞水が12月3日に死去、81歳。「立体講談」と呼ぶ照明や音響を使った怪談噺で知られた。僕も「牡丹灯籠」を聞いている。2002年に講談界初の人間国宝に認定された。僕は実はこの訃報に一番驚いた。それは正月の国立演芸場の公演に出場予定だったからである。行ったかどうかは判らないけど、まだ元気なんだなと思っていた。最近は神田伯山の人気がブレークしたが、神田派は「日本講談協会」、「一竜斎」の講談師は「講談協会」である。
 (一竜斎貞水)
(一竜斎貞水)落語家の林家こん平が死去、12月17日死去、77歳。「笑点」メンバーの人気者だったが、2004年以来多発性硬化症や糖尿病などの闘病のため降板し高座にも復帰できなかった。しかし、死因は誤嚥性肺炎だった。いつも「笑点」でネタにしていたように、新潟県千谷沢村(現・長岡市)に生まれ、1958年に初代林家三平に入門した。師匠が1980年に急死した後は、事実上の一番弟子(一番弟子の林家珍平は俳優に転業、昔の映画で時々見られる)として、一門をまとめる役目を果たした。「笑点」を引き継いだ林家たい平や二代目林家三平は弟子に当たる。最初の呼びかけ「チャラーン」は有名だった。闘病後も都電荒川線を借り切って都電落語会などをやっていた。あれほど有名だった人も、テレビから消えて10数年たつと知名度がグッと落ちるもんだ。
 (林家こん平)
(林家こん平) 「女剣劇」で活躍した浅香光代が12月13日に死去、92歳。1950年代に大人気だったというから、時代的には全然知るわけがない。浅草の最後の輝きを代表したスターだったのだろう。その後、映画やテレビドラマに出るようになり,晩年はテレビのバラエティ番組の出演で知られた。晩年まで浅草で大衆芸能発展に尽力していた。
 (浅香光代)
(浅香光代)・横山アキラ、9日没、88歳、横山ホットブラザーズのリーダー。
・西川右近、12日没、81歳。日本舞踊西川流総帥。
・小谷承靖(つぐのぶ)、13日没、84歳。映画監督。「ゴキブリ刑事」「はつ恋」「ホワイト・ラブ」「潮騒」など。草刈正雄が主演した「頑張れ!若大将」も小谷監督だった。
・出口典雄、16日没、80歳。演出家。文学座、劇団四季を経て、「シェイクスピア・シアター」を旗揚げした。シェイクスピア前作上演が高く評価された。小田島雄志の翻訳を現代風に演出したことで大きな影響力を持った。佐野史郎や吉田剛太郎が所属していたが、僕は見ていない。
・堅田喜三久(かただ・きさく)、17日没、85歳。歌舞伎長唄囃子の家元。人間国宝。