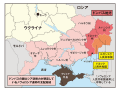6月に入ってからは、ブルース・チャトウィン(Charles Bruce Chatwin、1940~1989)をずっと読んでいる。岩波ホールの最後の作品、ヴェルナー・ヘルツォーク監督『歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡』という映画の上映が始まった。ところで岩波ホールやヘルツォークなら語れるけど、映画の対象のブルース・チャトウィンを知らない。というか、名前は知っていて、本も一冊持っているけど、読んでない。そこで河出文庫から2017年に刊行された『パタゴニア』を読んでみたのである。
 (『パタゴニア』)
(『パタゴニア』)
いや、これが素晴らしく面白かった。ただし、内容についてはちょっと誤解していた。パタゴニアといったら、荒涼たる風景が延々と続く人跡未踏の地みたいなイメージがあって、そういう場所の探検紀行かと思い込んでいた。だからアルプスやヒマラヤの登山記みたいな本だと思っていたのである。しかし、そのイメージがそもそも全然違った。今「パタゴニア」を検索すると、アメリカ発のアウトドア用品がずらっと出て来て、南米のパタゴニアまで行き着くのも大変だ。何とか探し当てると、南アメリカ大陸の南緯40°付近を流れるアルゼンチンのコロラド川以南の土地を呼ぶと出ている。アルゼンチンだけでなく、チリも含まれる。
 (パタゴニアの位置)
(パタゴニアの位置)
そもそもチャトウィンがパタゴニアに憧れたのは、幼い頃の思い出によるのである。祖母のいとこが彼の地に赴いて、太古の恐竜プロントサウルスの皮を送ってきたのである。その皮を見て触って、自慢したくて学校で話したら、先生から恐竜は爬虫類だから、そんな獣のような皮ではないと一蹴されてしまった。今ではその皮はオオナマケモノという絶滅した生物のものだとされているようだ。乾燥した気候で大昔の動物の皮が残された。しかし、恐竜であれオオナマケモノであれ、パタゴニアの未知の大自然の中でまだ生存しているんだと探検に訪れるものが多かった。一族の過去をたどるということではなく、天性の放浪者(ノマド)を自認してチャトウィンは、様々な人生行路を経てパタゴニアに行き着いた。
 (パタゴニア風景)
(パタゴニア風景)
パタゴニアには誰も住んでいないのかと思うと、実はそこにはスコットランドやウェールズからの移住者がたくさん住んでいた。宗教的背景からアルゼンチンに逃れてきた人々がいっぱいいたのである。それらの人々の子孫を訪ね歩き、数多くのドラマを書き記す。20世紀になると、パタゴニアにある羊牧場や食肉工場には、多くの社会主義者やアナーキストがやってきた。大ストライキがあり、大弾圧があった。それらのドラマもまたパタゴニアで起こったことである。チャトウィンの旅は70年代半ばのことで、すでにチリではアジェンデ政権がクーデタで倒れて軍事政権になっていた時代である。
またブッチ・キャシディとサンダンス・キッドもパタゴニアに逃げてきた。アメリカの大盗賊である。僕らの世代にはポール・ニューマン、ロバート・レッドフォードが主演した『明日に向かって撃て!』で名高い。映画では確かボリビアに逃げたことになっているが、その前にパタゴニアにいたらしい。このように多彩な人々が登場するのだが、次第に歴史の中を訪ね歩くようになる。もともとパタゴニアとは、かつてマゼランなどの大航海時代に、ここに「パタゴン」族が住んでいたとことから付けられた。パタゴンとは「巨大な足」という意味らしい。すでに絶滅した先住民は別に特に大きかったわけではないという。
 (フエゴ島最大の都市ウシュアイア)
(フエゴ島最大の都市ウシュアイア)
一番南にあるフエゴ諸島など、寒くて誰も住んでいないような気がしていた。しかし、アルゼンチン側最大都市のウシュアイアを調べると、南緯54°にあるこの町は夏の最高気温は29度に達している。南半球だから、夏とは12月や1月である。もちろん平均気温はずっと低いが、それでも冬でも平均気温は氷点下より高い。北半球で同程度の緯度のカムチャツカ半島などよりずっと暖かいのである。まあ暖かいと言っても、もちろん寒いけれど、それでも人が住むには十分だし産業もある。そこには歴史があり、ドラマがあった。自然誌というより、思ったよりは歴史をめぐる紀行だった。
 (ブルース・チャトウィン)
(ブルース・チャトウィン)
しかし、歴史紀行だから面白いのではない。やはり、これは紀行文学であって、詩的な文体が素晴らしいのである。風、雨、花、大地…チャトウィンの手に掛かると、その場にいるがごとくに感じられる。池澤夏樹が評するように、「冒険から一歩だけ文学の方に歩み寄り」成立した、他の誰にも書けない世界なのである。そこには人がいて、歴史とドラマがあったが、やはり「不毛の地」というに近い。そこで見つめる内面の旅こそが真の紀行というべきか。最初が取っつきにくいが、次第にその世界に入り込んで出られなくなる。そんな本だった。一度頑張って読んでみるに値する20世紀の傑作。
 (『パタゴニアふたたび』)
(『パタゴニアふたたび』)
なお、ブルース・チャトウィン、ポール・セルー共著の『パタゴニアふたたび』(白水社)という本もある。ポール・セルーはアメリカ人には珍しい鉄道マニアで、ヨーロッパからアジアで鉄道で旅して『鉄道大バザール』を書いた人である。その前にボストンから鉄道だけでパタゴニアまで南北アメリカ大陸を縦断しようと思いついて実行した。その後何十年か経って、再びヨーロッパから日本まで旅して、日本では村上春樹にあったりした。その時の旅をもとにした『ゴースト・トレインは東の星へ』という本もある。そのことは「ポール・セローのユーラシア大陸鉄道大冒険」という記事を10年前に書いた。二人の共著だから、さぞ面白いかと思うと、実際に訪れて書いたのではなく、歴史を中心に本の世界を語った本なので、案外面白くなかった。一応紹介しておくけど。
 (『パタゴニア』)
(『パタゴニア』)いや、これが素晴らしく面白かった。ただし、内容についてはちょっと誤解していた。パタゴニアといったら、荒涼たる風景が延々と続く人跡未踏の地みたいなイメージがあって、そういう場所の探検紀行かと思い込んでいた。だからアルプスやヒマラヤの登山記みたいな本だと思っていたのである。しかし、そのイメージがそもそも全然違った。今「パタゴニア」を検索すると、アメリカ発のアウトドア用品がずらっと出て来て、南米のパタゴニアまで行き着くのも大変だ。何とか探し当てると、南アメリカ大陸の南緯40°付近を流れるアルゼンチンのコロラド川以南の土地を呼ぶと出ている。アルゼンチンだけでなく、チリも含まれる。
 (パタゴニアの位置)
(パタゴニアの位置)そもそもチャトウィンがパタゴニアに憧れたのは、幼い頃の思い出によるのである。祖母のいとこが彼の地に赴いて、太古の恐竜プロントサウルスの皮を送ってきたのである。その皮を見て触って、自慢したくて学校で話したら、先生から恐竜は爬虫類だから、そんな獣のような皮ではないと一蹴されてしまった。今ではその皮はオオナマケモノという絶滅した生物のものだとされているようだ。乾燥した気候で大昔の動物の皮が残された。しかし、恐竜であれオオナマケモノであれ、パタゴニアの未知の大自然の中でまだ生存しているんだと探検に訪れるものが多かった。一族の過去をたどるということではなく、天性の放浪者(ノマド)を自認してチャトウィンは、様々な人生行路を経てパタゴニアに行き着いた。
 (パタゴニア風景)
(パタゴニア風景)パタゴニアには誰も住んでいないのかと思うと、実はそこにはスコットランドやウェールズからの移住者がたくさん住んでいた。宗教的背景からアルゼンチンに逃れてきた人々がいっぱいいたのである。それらの人々の子孫を訪ね歩き、数多くのドラマを書き記す。20世紀になると、パタゴニアにある羊牧場や食肉工場には、多くの社会主義者やアナーキストがやってきた。大ストライキがあり、大弾圧があった。それらのドラマもまたパタゴニアで起こったことである。チャトウィンの旅は70年代半ばのことで、すでにチリではアジェンデ政権がクーデタで倒れて軍事政権になっていた時代である。
またブッチ・キャシディとサンダンス・キッドもパタゴニアに逃げてきた。アメリカの大盗賊である。僕らの世代にはポール・ニューマン、ロバート・レッドフォードが主演した『明日に向かって撃て!』で名高い。映画では確かボリビアに逃げたことになっているが、その前にパタゴニアにいたらしい。このように多彩な人々が登場するのだが、次第に歴史の中を訪ね歩くようになる。もともとパタゴニアとは、かつてマゼランなどの大航海時代に、ここに「パタゴン」族が住んでいたとことから付けられた。パタゴンとは「巨大な足」という意味らしい。すでに絶滅した先住民は別に特に大きかったわけではないという。
 (フエゴ島最大の都市ウシュアイア)
(フエゴ島最大の都市ウシュアイア)一番南にあるフエゴ諸島など、寒くて誰も住んでいないような気がしていた。しかし、アルゼンチン側最大都市のウシュアイアを調べると、南緯54°にあるこの町は夏の最高気温は29度に達している。南半球だから、夏とは12月や1月である。もちろん平均気温はずっと低いが、それでも冬でも平均気温は氷点下より高い。北半球で同程度の緯度のカムチャツカ半島などよりずっと暖かいのである。まあ暖かいと言っても、もちろん寒いけれど、それでも人が住むには十分だし産業もある。そこには歴史があり、ドラマがあった。自然誌というより、思ったよりは歴史をめぐる紀行だった。
 (ブルース・チャトウィン)
(ブルース・チャトウィン)しかし、歴史紀行だから面白いのではない。やはり、これは紀行文学であって、詩的な文体が素晴らしいのである。風、雨、花、大地…チャトウィンの手に掛かると、その場にいるがごとくに感じられる。池澤夏樹が評するように、「冒険から一歩だけ文学の方に歩み寄り」成立した、他の誰にも書けない世界なのである。そこには人がいて、歴史とドラマがあったが、やはり「不毛の地」というに近い。そこで見つめる内面の旅こそが真の紀行というべきか。最初が取っつきにくいが、次第にその世界に入り込んで出られなくなる。そんな本だった。一度頑張って読んでみるに値する20世紀の傑作。
 (『パタゴニアふたたび』)
(『パタゴニアふたたび』)なお、ブルース・チャトウィン、ポール・セルー共著の『パタゴニアふたたび』(白水社)という本もある。ポール・セルーはアメリカ人には珍しい鉄道マニアで、ヨーロッパからアジアで鉄道で旅して『鉄道大バザール』を書いた人である。その前にボストンから鉄道だけでパタゴニアまで南北アメリカ大陸を縦断しようと思いついて実行した。その後何十年か経って、再びヨーロッパから日本まで旅して、日本では村上春樹にあったりした。その時の旅をもとにした『ゴースト・トレインは東の星へ』という本もある。そのことは「ポール・セローのユーラシア大陸鉄道大冒険」という記事を10年前に書いた。二人の共著だから、さぞ面白いかと思うと、実際に訪れて書いたのではなく、歴史を中心に本の世界を語った本なので、案外面白くなかった。一応紹介しておくけど。