3度目の正直(今年、すでに2回調査にきた;汗)。浄智寺の白雲木の花が満開だった。去年も5月15日だった。ただ、去年と違うことは、花のつきがすごい。一昨年の5月5日の花のように、白い雲が、木全体に覆いかぶさるように咲いていた。

そして、円覚寺の仏殿裏のなんじゃもんじゃの木(ヒトツバタゴ)。これも、まるで春の雪が積もったように咲いていた。これも、三度目の正直(汗)。満足。松嶺院にもあるが、これだけで十分です。2日前(13日)の大船フラワーセンターのは、7分咲きぐらいだったので、おそらく、今日、満開を迎えているはず。

木の花、シリーズ。14日、つくばの紅花栃の木。有楽町の街路樹も咲いているかな。
13日、大船フラワーセンターの、しょうきうつぎ。まるで枝垂れ桜のようなうつくしさ。空木(うつぎ)の仲間。鍾馗(しょうき)の名は、実の長い褐色の毛が鐘馗さまのあごひげに似ているからだそうだ。いつもより、白っぽい感じがするが、気のせいだろうか。三春の滝桜もそうだった。
5月12日。上野の東博のシンボルツリー、ユリの木。ユリというよりチューリップの花のよう。WIFEは今日15日、東博の裏庭の応挙館で開かれた、ティーセレモニーに行ってきた。花はさらに増えているもよう。茶花はユリの木の花だったとのこと。
omake
今日、明月院でみた、夏蝋梅(ろうばい)の咲き始め
今日、円覚寺・黄梅院でみた、セッコク(石斛)の花。満開。寄生木だけど。
黄梅院でみた、真民さんの詩。
mata omake
円覚寺・方丈の庭の苔
明月院の苔
明月院のリサちゃん




































 おまえ、シンシンか、きのう、みてきたよ、いねむりしてたな。
おまえ、シンシンか、きのう、みてきたよ、いねむりしてたな。 ぼくはリーリーで、動き回っていた方です。
ぼくはリーリーで、動き回っていた方です。












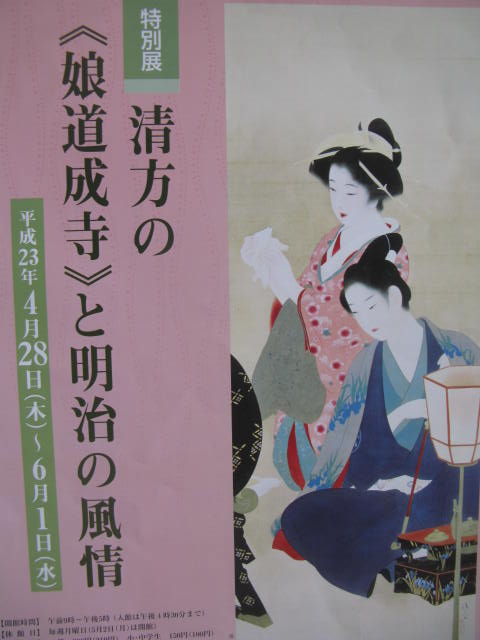










































 いや、まだやすめない。これから世界卓球を観なければ
いや、まだやすめない。これから世界卓球を観なければ 。
。



