出来るのを待つうちに、読みたいと思っていた多田富雄さんの
『わたしのリハビリ闘争 最弱者の生存権は守られたか』を読んでいた。
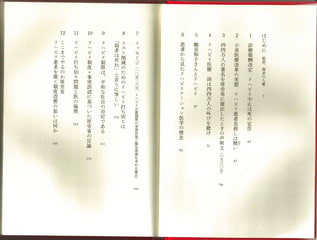

世界的な免疫学者である著者は、脳梗塞を患って以来、リハビリによって障害と闘いながら、かろうじて執筆活動を続けてきた。ところが二〇〇六年四月、厚労省の保険診療報酬改定によってリハビリ打ち切りという思わぬ事態が生じた。現場の実体を無視した医療費削減政策の暴走、弱者切り捨ての失政に怒った著者は、新聞への投書を皮切りに立ち上がった――。本書は一年余にわたる執筆・発言をまとめた闘争の記録であり、病床と車椅子の上から発せられた “命の叫び” である。
『わたしのリハビリ闘争 最弱者の生存権は守られたか』
(多田富雄著/青土社/2007)
いまのわたしの気分にぴったし。
昨日の続きの記事「このまちはどこへ行こうとしているのか」
を書こうと思っていたのだけど、
この本の言葉が心にずしんと響いていた。
「選挙がどうのこうのという前に政治家はみんなこの本を読むべきだ」
などと思いながら、届いた毎日新聞夕刊を開くと、
なんと多田富雄さんの大きな記事。


人気ブログランキングに参加中

応援クリック
 してね
してね 



待っていた方には申し訳ないけれど、きゅうきょこちらの記事に変更。
| 特集ワイド:この国はどこへ行こうとしているのか 多田富雄さん <おちおち死んではいられない> ◇今の政治は病んでいる--免疫学者・74歳・多田富雄さん ◇後期高齢者医療制度は姥捨てです 反乱起こしたいぐらい 「歌占(うたうら)」 死んだと思われて三日目に蘇(よみがえ)った若い男は 白髪の老人になって言った 俺(おれ)は地獄を見てきたのだと そして誰にも分からない言葉で語り始めた 詩集「歌占」(藤原書店)より 非の打ち所のない人生。01年5月2日までの多田富雄さんの人生はそれだった。若くして免疫学で世界的な業績を上げ、東大教授に。世界を駆け回るかたわら鼓を打ち、脳死や相対性理論を主題に能も書いた。 だがその日、脳梗塞(こうそく)で倒れ、半身不随になった。歩くことも、語ることも、水を飲むことさえもできなくなった。詩の中の白髪の老人は、多田さんだ。一時は死を望んだ。 ■ 桜を散らす雨が上がった午後、東京都文京区のご自宅を訪ねた。いかめしい老学者を想像していて、拍子抜けした。さまざまな茶色の糸で編まれたセーターを着て、車椅子に座ってはにかむように笑っていた。 でも言葉は鋭い。政府が「長寿」と言い換えた後期高齢者医療制度について聞くと、キーを打つと音声になる「トーキングマシン」で、「ウバステ(姥捨て)デスネ」。あまりに率直な表現に「ぷっ」と噴き出すと一緒に笑い、そして続けた。 「これは人間の国の政治じゃないね。私には、この国自身が病んでいるように見えます」 話を7年前に戻そう。倒れて2カ月、車椅子で海に沈む夕日を見ていた時、突然ひらめいた。「脳の神経細胞が死んだら再生することなんかありえない。(略)もし機能が回復するとしたら、元通りに神経が再生したからではない。それは新たに創(つく)り出されるものだ。(略)私が一歩を踏み出すとしたら、それは失われた私の足を借りて、何者かが歩き始めるのだ」(「寡黙なる巨人」集英社より)。その何者かを多田さんは巨人と呼び、彼と会いたくてリハビリに励んだ。「歌占」はそのころ書いた。50メートルも歩けるようになった。 だが06年4月、再び打ちのめされる。小泉純一郎内閣の下で診療報酬が改定され、リハビリの保険給付が最大180日で打ち切りになった。それ以上続けても医学的に改善の見込みはない、という理由だ。 「リハビリは、病気から回復するための医科学です。それを制限するのは、治るのをやめろと言うのと同じ」。トーキングマシンを通しても、震えるような怒りが伝わってくる。 多田さんは闘った。左手でパソコンをたたき「リハビリ中止は死の宣告」と新聞に投書した。リハビリをやめたら、歩けなくなる。病状が後戻りし悪化してしまう。投書は署名運動に発展し、44万件も集まった。車椅子で厚生労働省に届けた。でも制度はほとんど変わっていない。 そして今度は後期高齢者医療制度だ。75歳以上が対象で、全体の医療費が増えると高齢者が支払う保険料も上がる。つまり高齢者ができるだけ医者に行かなくなるようにする仕組みだ。保険料は年金から天引きし、払えなければ保険証も取り上げる。 しばらく前から、多田さんとメールのやりとりをしてきた。多田さんは怒っていた。障害者や寝たきりの人、人工透析を受けている人など約100万人が、75歳ではなく65歳から同制度に加入させられる。<これは命の差別です。個人の尊重や、幸福追求権を認めた憲法13条、法の下の平等を定めた同14条に違反している。こんなことが堂々とまかり通っている> 長寿医療制度への呼び換えを指示したのは福田康夫首相だ。 <怒りに身が震えます。体さえ動けば1300万人の後期高齢者と、その予備軍を結集し、『老兵連』を集めて反乱を起こしたいぐらい。力はないが数はあるぞとデモしたい。言い換えで誤魔化されるほど、後期高齢者は落ちぶれてはいない> 行間から「私は生きている」という叫びが、聞こえた。 ■ 「高齢者や障害者は早く死ねというならナチスと同じ。国は、国民が自ら国民皆保険を捨てるのも狙っているのでしょう」 聞き直したのはトーキングマシンの声が小さかったからではない。驚いたのだ。 「このごろ、何歳でも加入できる医療保険の宣伝が目立つでしょう」 小泉政権発足は01年4月。7月には保険業の規制が緩和され、医療保険やがん保険が急速に伸長した。その一方で、小泉政権は、社会保障関係費を毎年度2200億円分も圧縮してきた。06年には、11年度までに社会保障分野で1兆7000億円を削減すると決めた。後期高齢者医療制度も、リハビリの打ち切りも、介護保険料の見直しも、すべてその延長線上にある。 健康保険制度に不安を持つ人々は、保険料を支払って医療保険やがん保険に加入する。得をするのはだれか--。 ■ 多田さんの中で目覚めた巨人は、これから何をしたいのか。そう聞くと、体を揺すって笑った。 「ヨナオシ(世直し)!」 すごい。その瞬間、口元から光がこぼれた。よだれだ。口の右側はまひが強いためだ。 トーキングマシンで話をしながら、この時まで私はすっかり忘れていた。多田さんが物をのみ込むのが困難なほど重い障害を持つことを。多田さんはまるで能役者のように自然に左手で口元をぬぐっていたから。能弁だったから。……違う。なぜだろう、健康で40代の私よりも、病んだこの人の方がずっと強く、生き生きと、生命にあふれているように感じるのだ。 こうして人と会い、姿勢を保つだけでもどれだけの労力を要するか。資料を読み、文章や本を書き、社会に異議申し立てをするのは……。 「言葉は僕に残された最後の力です」 この人の後ろには、老いて病み、物言えぬ多くの人がいる。死者すらいるかもしれない。 「歌占」の終節はこうだ。 死ぬことなんか容易(たやす)い/生きたままこれを見なければならぬ/よく見ておけ/地獄はここだ 詩はあと3行続く。老人は何と語るのか、あえて書かない。【太田阿利佐】 ============== ■人物略歴 ◇ただ・とみお 1934年茨城県生まれ。千葉大医学部卒。71年、免疫反応を抑制するサプレッサーT細胞を発見。国際免疫学会連合会会長も務めた。東大名誉教授。著書に「免疫の意味論」「わたしのリハビリ闘争」「寡黙なる巨人」など多数。 毎日新聞夕刊 2008年4月11日 |
| 『歌占 多田富雄全詩集』(古本屋の殴り書き) 歌占 死んだと思われて三日目に蘇った男は 白髪の老人になって言った 俺は地獄を見てきたのだと そして誰にも分からない言葉で語り始めた それは死人の言葉のように頼りなく 蓮の葉の露を幽(かす)かに動かしただけだが 言っているのはどうやらあの世のことのようで 我らは聞き耳を立てるほかなかった。 真実は空しい 誰が来世など信じようか 何もかも無駄なことだといっているようだった そして一息ついてはさめざめと泣いた 死の世界で見てきたことを 思い出して泣いているようで 誰も同情などしなかったが ふと見ると大粒の涙をぼろぼろとこぼしているので まんざら虚言(そらごと)をいっているのではないことが分かった 彼は本当に悲しかったのだ 無限に悲しいといって老人は泣き叫んだ まるで身も世も無いように身を捩(よじ)り 息も絶え絶えになって 血の混じった涙を流して泣き叫ぶ有様は 到底虚言とは思えなかった それから老人は ようやく海鳥のような思い口を開いて 地獄のことを語り始めた まずそれは無限の暗闇で光も火も無かった でも彼にはよく見えたという 岬のようなものが突き出た海がどこまでも続いた でも海だと思ったのは瀝青(れきせい)のような水で 気味悪く老人の手足にまとわりついた さびしい海獣の声が遠くでした 一本の白い腕が流れてきた それは彼にまとわりついて 離れようとはしなかった。 あれは誰の腕? まさかおれの腕ではあるまい その腕は老人の胸の辺りにまとわりついて どうしても離れようとしなかった ああいやだいやだ だが叫ぼうとしても声は出ず 訴えようとしても言葉にならない 渇きで体は火のように熱く 瀝青のような水は喉を潤さない たとえようも無い無限の孤独感にさいなまれ この果てのない海をいつまでも漂っていたのだ 身動きもできないまま いつの間にか歯は抜け落ち 皮膚はたるみ皺を刻み 白髪の老人になってこの世に戻ってきたのだ 語っているうちにそれを思い出したのか 老人はまたさめざめと泣き始めた が、突然思い出したように目を上げ 思いがけないことを言い始めた そこは死の世界なんかじゃない 生きてそれを見たのだ 死ぬことなんか容易(たやす)い 生きたままこれを見なければならぬ よく見ておけ 地獄はここだ 遠いところにあるわけではない ここなのだ 君だって行けるところなのだ 老人はこういい捨てて呆然として帰っていった |
わたしの心にずしんと響いた『わたしのリハビリ闘争』(青土社)の
「はじめに」の棹尾の詩「君はふん怒佛のように」。
写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大

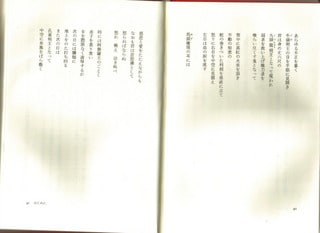
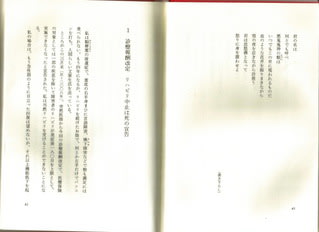
以下の言葉のあとに続く。
勝っても実現できていないものは沢山ある。原爆症認定裁判も、水俣病の被害者認定裁判も、最高裁の判決では勝っていても、いまだに救われない原告が大勢いる。でも、実現しなかったものに残された怒りが、息の長い運動のエネルギーになっているのではないか。
私はそれに期待している。私はこの闘いの間に、一遍の詩を書いた。「君はふん怒佛のように」という詩である。それを棹尾において、私の人権を守る戦いの最後を飾ろう。
(『わたしのリハビリ闘争』はじめに、より)
政治はいままで強者のものだった。
わたしが実現したいのは、「弱者の政治」だ。
人気ブログランキングに参加中

応援クリック
 してね
してね 




















