天気予報は午後から雨。
朝のうちに庭のお花を写そうと思っていたのですが、起きたらしとしと雨が降っています。
この季節は三寒四温で冷え込む日もありぐずついた天気が続いています。
きょう4月1日は、「エイプリルフール(万愚節)」。
罪のない嘘をついて良いとされる日で、「四月馬鹿」とも呼ばれます。
介護保険は2000年4月1日の開始から今日でちょうど10年。
高速道路の休日料金1000円は、今日から廃止されます。
4月1日は、官公庁の年度初めでもあって、いくつかの新制度がはじまります。
ぴかぴかの高校生にうれしいのは、「授業料無償化法」が成立して、
公立高校が4月から無料になること。
もっと前にこの法律が成立していたら、子どもが多いわが家もどんなに助かったことでしょうね。
とはいえ、手放しでは喜べません。
「朝鮮学校」が対象からはずされ、結論が8月弐先送りされるなど、
実施までには課題もたくさん残ってます。
先日のブログでも記事にしましたが、病院の「医療費明細書」も今日から義務化されます。
毎日新聞に続いて、朝日新聞にも詳しい記事が出ていましたので紹介します。
医療費明細書 どう活用
義務化 病院4月・診療所7月から

(2010.3.26 朝日新聞)
いなば通りのしだれ桜、咲き始め。
/病院領収書:治療明細を記載 来月から(2010-03-25)

病院領収書:治療明細を記載 来月から原則、全施設で
毎日新聞 2010年3月24日
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
母子加算の問題では、訴訟を起こしていた原告団と長妻昭厚労相が、
「母子加算を原則的に廃止しないこと」などで今日、合意書を交わす方針とのこと。
医療費については、4月から協会けんぽ保険料値上げの記事も。
アメリカでも、「医療保険制度改革法案」が成立して、医療費制度の改革が一歩すすみそうです。
最後まで読んでくださってありがとう
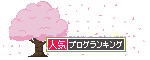
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

朝のうちに庭のお花を写そうと思っていたのですが、起きたらしとしと雨が降っています。
この季節は三寒四温で冷え込む日もありぐずついた天気が続いています。
きょう4月1日は、「エイプリルフール(万愚節)」。
罪のない嘘をついて良いとされる日で、「四月馬鹿」とも呼ばれます。
介護保険は2000年4月1日の開始から今日でちょうど10年。
高速道路の休日料金1000円は、今日から廃止されます。
4月1日は、官公庁の年度初めでもあって、いくつかの新制度がはじまります。
ぴかぴかの高校生にうれしいのは、「授業料無償化法」が成立して、
公立高校が4月から無料になること。
もっと前にこの法律が成立していたら、子どもが多いわが家もどんなに助かったことでしょうね。
とはいえ、手放しでは喜べません。
「朝鮮学校」が対象からはずされ、結論が8月弐先送りされるなど、
実施までには課題もたくさん残ってます。
| 公立高4月から無料に、授業料無償化法が成立 (2010年3月31日20時17分 読売新聞) 高校授業料無償化法が31日の参院本会議で、与党と公明、共産両野党の賛成多数で可決され、成立した。 自民党は反対した。4月1日に施行される。民主党が昨年の衆院選で掲げた政権公約(マニフェスト)の中の「給付型」の施策として、子ども手当とともに実施されることになる。 無償化は、高校のほか高等専門学校や専修学校、一部の各種学校などが対象となる。 このうち、公立高と公立の中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部については、国が生徒1人当たりの授業料相当額(年11万8800円)を基準に地方自治体に授業料収入相当額を交付することで、授業料が徴収されなくなる。 私立高や高等専門学校などについては、国が同じ授業料相当額を就学支援金として学校に支給する。これより授業料が高い場合は差額を払うことになるが、支援金は世帯の年収に応じて増額されるため、世帯ごとに払う額が異なるケースも出てくる。 具体的には、年収250万円未満の世帯には2倍の年23万7600円、年収250万~350万円未満には1・5倍の年17万8200円の支援金が支払われるが、いずれも課税証明書の提出を必要とする。生徒は入学時に、支援金の受給資格認定申請書を提出する。 各種学校である外国人学校については、文部科学省は、〈1〉本国が日本の高校と同等であることを認めている〈2〉国際的な評価機関で認定を受けている――のいずれかを満たせば対象とする方針だ。同省が基準を省令で定める。 外国人学校のうち、朝鮮学校については、閣内から日本人拉致問題を踏まえて対象外とするよう求める声が出た。文科省は「朝鮮学校は両基準に該当しないが、多くの大学が卒業生の入学を認めている」としており、今後、専門家の検討会を設置して検討する予定だ。対象にすることになれば、4月分にさかのぼって支援金を支給する。判断が出るのは8月ごろになる見通しだ。 無償化法案は衆院の審議で修正され、施行3年後に必要な見直しを行うことが付則に盛り込まれた。これにより、公明、共産両党も賛成に回った。 (2010年3月31日20時17分 読売新聞) ------------------------------------------------------- 「公私格差」残る課題…高校授業料無償化法 低所得世帯には利点少なく 31日に成立した高校授業料無償化法は、高校生の教育にかかる経済的負担の軽減が最大の目的だ。親の所得に関係なく国の支援を受けられるよう、所得制限は設けなかった。 しかし、すでに都道府県から授業料減免措置を受けている低所得世帯には利点が少なく、公立と私立の「格差」も残るなど、問題点も指摘されている。 「大きな予算を使って高校の学びの環境を劇的に変化させる」 川端文部科学相は同法の成立後、無償化の意義を記者団にこう強調した。 2008年度には、高校中退者約6万6000人のうち、約2200人(3%)が経済的理由で中退した。政府はこうした理由で中退したり、高校進学をあきらめたりする人に対する支援になることを期待している。ただ、すでに中退したり、進学しなかったりした人には制度の恩恵は届かない。授業料以外の費用は依然として必要な中で、どれほどの効果があるかも不透明だ。 無償化の財源確保を目指し、16~18歳の子どもを持つ家庭の所得税などの特定扶養控除が縮小されるため、こうした子どもが高校に行っていない場合は負担増となる問題もある。 また、私立高の授業料は平均で約35万円にのぼり、大半は就学支援金があっても授業料の負担は残る。全額が無償となる公立との格差は大きい。 成立が施行日の前日となったことで、準備不足の面も少なくない。無償化の対象外となる留年者などへの対応は自治体に委ねられているが、対応する条例の改正はこれからの自治体もある。文科省は私立高については、4月分の授業料から就学支援金の分を減額させたい考えだが、間に合わないケースも出そうだ。 (2010年4月1日 読売新聞) |
先日のブログでも記事にしましたが、病院の「医療費明細書」も今日から義務化されます。
毎日新聞に続いて、朝日新聞にも詳しい記事が出ていましたので紹介します。
医療費明細書 どう活用
義務化 病院4月・診療所7月から

(2010.3.26 朝日新聞)
いなば通りのしだれ桜、咲き始め。
/病院領収書:治療明細を記載 来月から(2010-03-25)

病院領収書:治療明細を記載 来月から原則、全施設で
毎日新聞 2010年3月24日
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
母子加算の問題では、訴訟を起こしていた原告団と長妻昭厚労相が、
「母子加算を原則的に廃止しないこと」などで今日、合意書を交わす方針とのこと。
| 母子加算で4月1日に合意 原告団、訴訟取り下げへ 2010/03/31 22:07 【共同通信】 厚生労働省は31日、昨年11月まで続いた生活保護の母子加算廃止をめぐり、違憲訴訟を起こしている各地の原告と、今後は母子加算を原則的に廃止しないことなどで合意する方針を明らかにした。4月1日、長妻昭厚労相と原告弁護団関係者らが基本合意文書を取り交わす。 昨年12月、厚労省が母子加算を復活させたことを受けた措置。合意を受け、原告側は札幌など各地で係争中の訴訟を取り下げる見通し。 厚労省によると、合意事項は(1)今後、合理的な理由なく母子加算を廃止しない(2)高齢者を含め、貧困世帯の実態を調査する―など。 母子加算は18歳以下の子どもを持つひとり親家庭に支給され、対象は約10万世帯。子ども1人の場合で月約2万円が支給されていたが、専門委員会の見直し提言などを根拠に2005年度から減額を始め、昨年4月に全廃された。 だが、廃止の根拠とされたデータのあいまいさなどに批判が集中。加算復活を掲げた民主党が昨年の衆院選で勝利し、鳩山政権下で支給再開が決まった。10年度以降も継続される。 2010/03/31 22:07 【共同通信】 |
医療費については、4月から協会けんぽ保険料値上げの記事も。
アメリカでも、「医療保険制度改革法案」が成立して、医療費制度の改革が一歩すすみそうです。
| 【暮らし】医療費適正化で地域に差 4月から協会けんぽ保険料値上げ 2010年2月18日 中日新聞 中小企業の従業員やその家族ら約三千五百万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料が、四月から大幅に上がる。平均的な収入(月収二十八万円、年収三百七十四万円)なら、四月以降に納める保険料は、本人負担が一カ月で約千六百円増え、年間では約二万一千円の負担増だ。不況で多くの従業員の給料が減る中、手痛い出費になりそうだ。 (佐橋大) 給与に対する健康保険料率は現在、全国平均で8・2%。これが四月には9・34%に上がる。一割以上も保険料率を上げざるをえないのは、保険の収支が急激に悪化しているためだ=グラフ。 協会けんぽの収入の大半は、被保険者(加入者)と事業者が折半で納める保険料。加入者の給料が安定していれば、保険料も安定して入る。ところが一昨年来の不況で、被保険者の給料は大幅に減少。協会けんぽの収入も減っている。 一方、支出は高齢化による医療費の増加で、年々着実に増えている。 二〇〇九年度は、給付費の13%に当たる約六千八百億円の補助を国から受けているが、減収が響き、単年度の赤字は約六千億円になる見通し。積立金である準備金を取り崩しても、約四千五百億円が不足する。 従来の仕組みでは、9・9%まで保険料率を上げる必要があった。しかし、これでは加入者や加入企業の負担が重くなりすぎると国は判断。一〇年度の国庫補助率を16・4%に引き上げて、保険料率を9・34%に抑えた。 ◇ 保険料率は都道府県で異なり、四月以降は差が広がる=表。 〇八年十月の協会けんぽ発足から一年は、前身の政府管掌健康保険(政管健保)時代と同様に、全国一律の保険料だった。しかし、〇九年十月からは、加入者の年齢構成や所得水準の違いを考慮した上で、加入者にかかった医療費が多い都道府県は保険料が高くなり、少ない地域は保険料が安くなる仕組みに変わった。 保険料に差をつけるのは、医療費を抑える「医療費適正化」の一環。保険料を上げたくないという加入者らの心理に働き掛け、生活習慣病の予防など医療費抑制の努力を地域ごとに促すのが狙いだ。 ただし、医療費の差を、そのまま保険料に反映させると、保険料率の差は1ポイントを超え、地域によっては保険料が高騰する。このため一三年九月までは、保険料の格差を縮める「激変緩和措置」が適用される。 今は、医療費の影響を本来の10%に抑える「緩和措置」により、最も高い北海道(8・26%)と、最も低い長野県(8・15%)の差は0・11ポイント。 四月からは、影響を抑える割合を15%に緩めるため、北海道(9・42%)から長野県(9・26%)までの差は0・16ポイントに広がる。平均的な月収(二十八万円)の人では、保険料の地域差は月百五十円から二百二十円に拡大する。 今回の保険料のアップに続いて、計画通り一三年に緩和措置を打ち切れば、医療費の高い地域では保険料が短期間に急激に上がることになるとして、厚生労働省は緩和措置の延長を検討している。 ◇ 四十歳以上の加入者が払う介護保険料も、健康保険分と同様の理由で、今の1・19%(労使折半)から四月以降は、1・5%(同)に上がる。平均的な収入の従業員では、本人負担が年に五千八百円増える。医療と介護の合計では年二万六千八百円の負担増になる。 |
| 米国:医療保険改革成立へ 国民加入義務付け--下院で可決 毎日新聞 2010年3月23日 東京朝刊 【ワシントン古本陽荘】米下院本会議は21日、オバマ政権の内政上の最重要課題である医療保険制度改革法案の採決を行い、賛成多数で可決した。すでに上院が可決しているためオバマ大統領の署名を経て成立する。国民皆保険制度のない米国で、医療保険加入を国民に義務付ける初めての歴史的な制度導入となり、オバマ大統領は自らの指導力回復につなげたい考えだ。 下院は、保険対象を広げるための同法案の一部修正法案も可決。週内にも上院が同じ修正法案を可決、成立させ、法的枠組みが整う。改革の主要事業は2014年から始まる。 オバマ大統領は同日深夜、ホワイトハウス内で「急進的な改革とは言えないまでも、大改革だ。一党の勝利でなく米国民の勝利だ」と意義を強調した。 採決は賛成219、反対212、一部修正法案も賛成220、反対211といずれも小差だった。共和党は全員が反対に回り、民主党からも30人以上が反対票を投じた。 法案の成立により、今後10年間で9400億ドル(約85兆円)を支出。現在4000万人以上いる無保険者のうち3200万人が保険加入し、保険加入率は83%から95%に上昇する。また、低所得者向け医療扶助(メディケイド)を拡充し、医療保険加入のための連邦政府による補助金制度も導入する。既往症を理由に保険会社が保険加入を拒否することは禁じられる。一方で、公的保険制度の創設は見送られた。 米国では無保険者が多く、医療費の支払いに伴う破産のほか、保険加入者の間でも、保険会社の医療費支払い拒否が社会問題化していた。だが、共和党や民主党の一部保守派は、改革による財政支出の拡大などに反対してきた。 改革法案は、09年に上院と下院が別個の法案を可決した後、一本化が難航。最終的には、上院で12月に可決した法案を下院で可決したうえで、内容を一部修正する法案を上下両院がそれぞれ採決する手続きを採用した。 |
最後まで読んでくださってありがとう

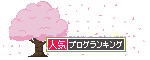
 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね


















