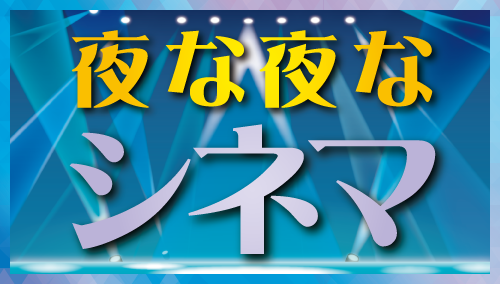シネ・リーブル梅田にて“映画で旅する自然派ワイン”という特集上映をしています。
上映作品はドキュメンタリー2本。
今日までの上映なので、時間休を取って2本とも観てきました。
1本目は『ジョージア、ワインが生まれたところ』(原題:Our Blood Is Wine)。
アメリカ人のエミリー・レイルズバック監督がジョージアへ。
ジョージアってややこしいですよね。
以前はグルジアだったはずなのに、いつからジョージアと呼ぶようになったのか。
グルジアの表記はロシア語起源なのだそうですが、
約10年前にロシア軍の侵攻を受けたことから、
ロシア語は嫌やねんと(言ったかどうかは知らんけど)、
英語表記のジョージアと呼んでくれと(も言ったかどうか知らんけど)なったらしい。
で、そんなややこしい国ではありますが、ワイン発祥の地である。
ワインといえば木製にしろステンレス製にしろ樽を用いるものだと思っていたら、
こんな壺を土の中に埋めてワインを造っているとは。
8千年もの歴史を持つ“クヴェヴリ製法”という製造の方法なのだそうです。
壺を洗うのが大変で、もう無理だと笑う爺ちゃん。
昔ながらの方法を守る現地の人々の様子すべてが私にとっては新しい。
2本目は『ワイン・コーリング』(原題:Wine Calling)。
こちらはフランス人のブリュノ・ソヴァール監督による作品です。
南フランスの生産者たちに密着し、製造過程やライフスタイルを撮っています。
1本目より2本目のほうが圧倒的にポップ。
ノリのよい音楽がBGMとしてふんだんに流され、睡魔に襲われる率も1本目より低い(笑)。
私自身が行きつけのお店で自然派ワインを多く飲ませてもらっているから、
ジョージアワインと聞くよりもビオやナチュラルといわれるほうが馴染みがあるゆえかも。
ほったらかしのイメージもあるけれど、ほったらかしにするって思うよりも難しいこと。
あれこれ手をかけたほうが病気にもなりにくいでしょう。
人の体と同じことで、予防や治療に薬を投与することで、病に罹らない、治る。
でも何もしないで病に罹らないようにするのは大変です。
湿疹を何もしないことで治そうとしたとき、本当に大変だったから。
でも何もしないで大丈夫な体をつくれたら、次に病に罹りかけてもすぐ治るんですよねぇ。
ワインも人も同じだなんてことを思いながら観た2本でした。
ワインを飲まない人生なんて。