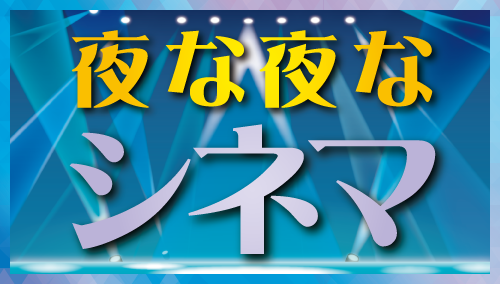『千年医師物語 ペルシアの彼方へ』(原題:The Physician)
監督:フィリップ・シュテルツェル
出演:トム・ペイン,ステラン・スカルスガルド,オリヴィエ・マルティネス,
エマ・リグビー,エリアス・ムバレク,ベン・キングズレー他
数カ月に一度、わが家でどうしても食べたくなるのが
西宮の“淡路島バーガー”のハンバーガーと桃谷の“たわら”のとんかつ弁当。
水曜日に休みを取り、前日の夕方、まずはたわらにお弁当を予約。
その時間に合わせてどこかで映画を観ることに。
いつでも安く観られる劇場に行くのはもったいない。
レディースデーを活用すべく、なんばのシネコンでハシゴする3本を検討。
桃谷から電車でお弁当を持ち帰るのも嫌だから、やっぱり車で。
なんばに行くときは日本橋のタイムズに駐めるのが常だったけど、
平日ならばなんばパークスは最大料金1,000円だと知ってから
なんばパークスの駐車場を愛用しています。
新御堂筋が渋滞していたら何時に着けるかわからないので、
とりあえずこの日観たい2本目と3本目だけオンライン予約。
1本目の候補として数本メモして、どれを観るかは到着時間次第。
結果、最も早い時間からの上映で、いちばん観たかった本作に間に合いました。
なんばパークスシネマにて。
アメリカ人作家ノア・ゴードンの同名小説が原作。
この原作は、アメリカではさほど売れなかったのに、ヨーロッパでベストセラーに。
『アイガー北壁』(2008)のドイツ人監督フィリップ・シュテルツェルによる映画化です。
イスラムが生み出した最高の知識人と言われるイブン・スィーナーが登場しますが、
史実に基づく作品として観るよりもフィクションとして観るべき作品のよう。
大画面で観るのが楽しい、一種の冒険ものとも言えます。
11世紀のイングランド。
キリスト教の世界では医療行為が神への冒涜とみなされ、医者は存在しない。
病に罹った人は旅回りの理髪師に診てもらうよりほかない。
理髪師は妖術使いとして、痛みを伴う歯を抜いたり指を切断したりして銭を稼ぐ。
少年ロブは、脇腹の痛みに悶え苦しむ母親を理髪師に診せようとする。
しかし、理髪師を家に連れ帰ってみると、すでに母親の枕元には神父が。
母親を救えるのは神のみだという神父に逆らえず、そのまま母親は死亡。
翌日、ロブの幼い弟妹は村の別家族に引き取られるが、ロブはひとり取り残される。
神父に相談しても冷たい返事しかなく、ロブは理髪師を頼る。
迷惑顔の理髪師だったが、孤児になったロブを追い返せない。
ロブは理髪師とともに旅をするようになり、やがて青年に。
医術を学んで、母親のように病気に苦しむ人を救いたいと願う。
ロブは理髪師の行為こそが医術だと信じて疑わなかったが、
あるとき理髪師の目が見えなくなる。
ユダヤ人の村には治療してくれる医者がいると聞いて行ってみると、
理髪師の病は白内障だとわかり、手術でみごとに視力を取り戻す。
これこそ自分が求めていた医術。
もっともっと学びたいと、ロブは高名な医師イブン・シーナがいるという
ペルシアのイスファンを目指して旅立つのだが……。
イブン・シーナ役には『ザ・ウォーク』のパパ・ルディ役もよかったベン・キングズレー。
素晴らしい俳優ですね。この人がいなくなったら、とても悲しいかも。
ロブ役にはトム・ペイン。この役に関しては小栗くんよりもタイプ(笑)。
色気もあって、もっといろいろ出演してほしいところ。
理髪師役にはステラン・スカルスガルド。いい加減だけど善人で、涙を誘います。
イケてる暴君、見たことあるけど誰だっけと思ったらオリヴィエ・マルティネスでした。
イランを貶める、史実に反した軽率な作品との評価もありますが、
フィクションの冒険ものとして観る分には私は好きでした。
医術の進歩にはさまざまな人が関わり、想像できないほどの苦労があったはず。
作品中、黒死病(=ペスト)が流行した折りに、逃げ出す政治家が多いなか、
医師たちは最後まで現場に残ってひとりでも多くの患者を救おうとしました。
救命の手段がない患者にも命を賭ける医師たち。
その姿には国境も宗教もないはず、と思うのは甘いですか。
監督:フィリップ・シュテルツェル
出演:トム・ペイン,ステラン・スカルスガルド,オリヴィエ・マルティネス,
エマ・リグビー,エリアス・ムバレク,ベン・キングズレー他
数カ月に一度、わが家でどうしても食べたくなるのが
西宮の“淡路島バーガー”のハンバーガーと桃谷の“たわら”のとんかつ弁当。
水曜日に休みを取り、前日の夕方、まずはたわらにお弁当を予約。
その時間に合わせてどこかで映画を観ることに。
いつでも安く観られる劇場に行くのはもったいない。
レディースデーを活用すべく、なんばのシネコンでハシゴする3本を検討。
桃谷から電車でお弁当を持ち帰るのも嫌だから、やっぱり車で。
なんばに行くときは日本橋のタイムズに駐めるのが常だったけど、
平日ならばなんばパークスは最大料金1,000円だと知ってから
なんばパークスの駐車場を愛用しています。
新御堂筋が渋滞していたら何時に着けるかわからないので、
とりあえずこの日観たい2本目と3本目だけオンライン予約。
1本目の候補として数本メモして、どれを観るかは到着時間次第。
結果、最も早い時間からの上映で、いちばん観たかった本作に間に合いました。
なんばパークスシネマにて。
アメリカ人作家ノア・ゴードンの同名小説が原作。
この原作は、アメリカではさほど売れなかったのに、ヨーロッパでベストセラーに。
『アイガー北壁』(2008)のドイツ人監督フィリップ・シュテルツェルによる映画化です。
イスラムが生み出した最高の知識人と言われるイブン・スィーナーが登場しますが、
史実に基づく作品として観るよりもフィクションとして観るべき作品のよう。
大画面で観るのが楽しい、一種の冒険ものとも言えます。
11世紀のイングランド。
キリスト教の世界では医療行為が神への冒涜とみなされ、医者は存在しない。
病に罹った人は旅回りの理髪師に診てもらうよりほかない。
理髪師は妖術使いとして、痛みを伴う歯を抜いたり指を切断したりして銭を稼ぐ。
少年ロブは、脇腹の痛みに悶え苦しむ母親を理髪師に診せようとする。
しかし、理髪師を家に連れ帰ってみると、すでに母親の枕元には神父が。
母親を救えるのは神のみだという神父に逆らえず、そのまま母親は死亡。
翌日、ロブの幼い弟妹は村の別家族に引き取られるが、ロブはひとり取り残される。
神父に相談しても冷たい返事しかなく、ロブは理髪師を頼る。
迷惑顔の理髪師だったが、孤児になったロブを追い返せない。
ロブは理髪師とともに旅をするようになり、やがて青年に。
医術を学んで、母親のように病気に苦しむ人を救いたいと願う。
ロブは理髪師の行為こそが医術だと信じて疑わなかったが、
あるとき理髪師の目が見えなくなる。
ユダヤ人の村には治療してくれる医者がいると聞いて行ってみると、
理髪師の病は白内障だとわかり、手術でみごとに視力を取り戻す。
これこそ自分が求めていた医術。
もっともっと学びたいと、ロブは高名な医師イブン・シーナがいるという
ペルシアのイスファンを目指して旅立つのだが……。
イブン・シーナ役には『ザ・ウォーク』のパパ・ルディ役もよかったベン・キングズレー。
素晴らしい俳優ですね。この人がいなくなったら、とても悲しいかも。
ロブ役にはトム・ペイン。この役に関しては小栗くんよりもタイプ(笑)。
色気もあって、もっといろいろ出演してほしいところ。
理髪師役にはステラン・スカルスガルド。いい加減だけど善人で、涙を誘います。
イケてる暴君、見たことあるけど誰だっけと思ったらオリヴィエ・マルティネスでした。
イランを貶める、史実に反した軽率な作品との評価もありますが、
フィクションの冒険ものとして観る分には私は好きでした。
医術の進歩にはさまざまな人が関わり、想像できないほどの苦労があったはず。
作品中、黒死病(=ペスト)が流行した折りに、逃げ出す政治家が多いなか、
医師たちは最後まで現場に残ってひとりでも多くの患者を救おうとしました。
救命の手段がない患者にも命を賭ける医師たち。
その姿には国境も宗教もないはず、と思うのは甘いですか。