
■「妻と私・幼年時代」江藤淳(文春文庫 2001年刊)
■「悲しいだけ」藤枝静男(恋愛小説アンソロジー 「感じて。息づかいを。」川上弘美選 光文社文庫)

(こちらが「感じて。息づかいを。」の表紙)
「感じて。息づかいを。」(光文社)は100円の棚にあったので、たまたま手に取って眺めたら藤枝静男の「悲しいだけ」が掲載されていたため、この恋愛小説アンソロジーと称する文庫本を買うことになった。
「藤枝文学の極北と称賛された感動の名作、野間文芸賞受賞の『悲しいだけ』を併録」と謳ってある。ただし、講談社文芸文庫の新刊で買うと税込み1,353円とお高い(゚ω、゚) ナハハ
「感じて。息づかいを。」には、本編のほか、「桜の森の満開の下」坂口安吾、「武蔵丸」車谷長吉をふくめ、8篇が収められている。
病苦の涯に身罷った妻のことが、容赦のない残酷な筆致で描かれ、途中で気分が重積して仕方なかった。私小説だから90%は、“本当のこと”が書いてあるはず。
この3~4日「悲しいだけ」が、脳裡にわだかまっていたのだ。
《正味三十五日間、毎日二、三枚ずつ書いて百三枚に及んだ》と、江藤淳さんはあとがきで述べておられる。
伴侶を失う悲しみを手記のようなかたちで公表した有名人は、大勢いる。
死に至るさまざまな出来事を、記念に残しておきたいとかんがえる人は多いだろうし、編集者もそれをすすめる。物書きの業のようなものかもしれない。ファンもおやおや、そうかいといって手にする。
江藤さんがここで述べておられるのは“妻の死”と、その前後の数か月間の日常的な出来事で看取りの記事が中心に据えられてある。
このとき、江藤さんは大学の講師・日本文芸家協会理事長をし、「漱石とその時代 第五部」その他の原稿を書いておられた。
しかし、これは非常事態である。41年半にわたって自分を陰でささえてくれた“妻の死”は、心身に重くのしかかってくる。
《慶子は、無言で語っていた。あらゆることにかかわらず、自分が幸せだったということを。告知せずにいたことを含めて、私のすべてを赦すということを。四十一年半に及ぼうとしている二人の結婚生活は、決して無意味ではなかった、いや、素晴らしいものだったということを。
私は、それに対して、やはり無言で繰り返していた。有難う、ということを。君の生命が絶えても、自分に意識がある限り、君は私の記憶のなかで生きつづけていくのだ、ということを。》(80ページより引用)
《死の時間は、家内が去っても私に取り憑いたままで、離れようとしないのであった。
家内とはやがて別れなければならない、そのときは自分が日常的な実務の時間に帰るときだ、と思っていたのは、どうやら軽薄極まる早計であったらしい。何故なら、死の時間と日常的な実務の時間とは、そう簡単に往復できるような構造にはできていないらしいからである。
いったん死の時間に深く浸り、そこに独り取り残されてまだ生きている人間ほど、絶望的なものはない。家内の生命が尽きていない限りは、生命の尽きるそのときまで一緒にいる、決して家内を一人ぽっちにはしない、という明瞭な目標があったのに、家内が逝ってしまった今となっては、そんな目標などありはしない。ただ私だけの死の時間が、わたしの心身を捕らえ、意味のない死に向かって刻一刻と私を追い込んで行くのである。》(89ページ)
もっと引用したいがやめておく。
読みすすめるにつれ目頭が自然と熱くなり、昨夜は涙が滲んで仕方なかった。
江藤さんは妻を看取る前後に、脳梗塞後遺症と排尿障害に苦しんでいたようだ。
《心身の不自由が進み、病苦が堪え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は、形骸に過ぎず、自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。平成十一年七月二十一日 江藤淳》
自ら処決して形骸を断ずる所以なり・・・とはカッコつけで、じっさいには愛しぬいた妻慶子の元へ行きたかったのだ。

(「成熟と喪失 “母の崩壊”」は「夏目漱石論」とならぶ江藤さんの代表作)
わたしの感想など、書いても書かなくてもいいものに類する。少しでも多く引用してあればそれでいいとしよう。正攻法で伴侶の最期を書いたものをこれまで読んだことがないので、そういう意味ではわたしには評価する資格はない。
本書には3者の追悼文がおさめてある。
・江藤淳を悼む 福田和也
・江藤淳記 吉本隆明
・さらば、友よ、江藤よ! 石原慎太郎
さらに絶筆となった「幼年時代」、付録として武藤康史編の江藤淳年表がそえられてある。
妻慶子死去。1998年(平成10)11月7日 享年64。
江藤淳、1999年(平成11)自殺。7月21日 享年66。


(手許にある、若かりしころの著作)
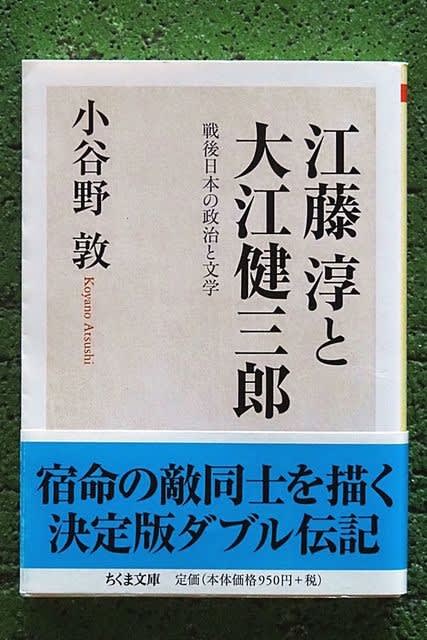
(最近購入した小谷野敦「江藤淳と大江健三郎」 ちくま文庫)

(お元気だったころのご夫妻♬ 画像検索よりお借りしました)
■「悲しいだけ」藤枝静男(恋愛小説アンソロジー 「感じて。息づかいを。」川上弘美選 光文社文庫)

(こちらが「感じて。息づかいを。」の表紙)
「感じて。息づかいを。」(光文社)は100円の棚にあったので、たまたま手に取って眺めたら藤枝静男の「悲しいだけ」が掲載されていたため、この恋愛小説アンソロジーと称する文庫本を買うことになった。
「藤枝文学の極北と称賛された感動の名作、野間文芸賞受賞の『悲しいだけ』を併録」と謳ってある。ただし、講談社文芸文庫の新刊で買うと税込み1,353円とお高い(゚ω、゚) ナハハ
「感じて。息づかいを。」には、本編のほか、「桜の森の満開の下」坂口安吾、「武蔵丸」車谷長吉をふくめ、8篇が収められている。
病苦の涯に身罷った妻のことが、容赦のない残酷な筆致で描かれ、途中で気分が重積して仕方なかった。私小説だから90%は、“本当のこと”が書いてあるはず。
この3~4日「悲しいだけ」が、脳裡にわだかまっていたのだ。
《正味三十五日間、毎日二、三枚ずつ書いて百三枚に及んだ》と、江藤淳さんはあとがきで述べておられる。
伴侶を失う悲しみを手記のようなかたちで公表した有名人は、大勢いる。
死に至るさまざまな出来事を、記念に残しておきたいとかんがえる人は多いだろうし、編集者もそれをすすめる。物書きの業のようなものかもしれない。ファンもおやおや、そうかいといって手にする。
江藤さんがここで述べておられるのは“妻の死”と、その前後の数か月間の日常的な出来事で看取りの記事が中心に据えられてある。
このとき、江藤さんは大学の講師・日本文芸家協会理事長をし、「漱石とその時代 第五部」その他の原稿を書いておられた。
しかし、これは非常事態である。41年半にわたって自分を陰でささえてくれた“妻の死”は、心身に重くのしかかってくる。
《慶子は、無言で語っていた。あらゆることにかかわらず、自分が幸せだったということを。告知せずにいたことを含めて、私のすべてを赦すということを。四十一年半に及ぼうとしている二人の結婚生活は、決して無意味ではなかった、いや、素晴らしいものだったということを。
私は、それに対して、やはり無言で繰り返していた。有難う、ということを。君の生命が絶えても、自分に意識がある限り、君は私の記憶のなかで生きつづけていくのだ、ということを。》(80ページより引用)
《死の時間は、家内が去っても私に取り憑いたままで、離れようとしないのであった。
家内とはやがて別れなければならない、そのときは自分が日常的な実務の時間に帰るときだ、と思っていたのは、どうやら軽薄極まる早計であったらしい。何故なら、死の時間と日常的な実務の時間とは、そう簡単に往復できるような構造にはできていないらしいからである。
いったん死の時間に深く浸り、そこに独り取り残されてまだ生きている人間ほど、絶望的なものはない。家内の生命が尽きていない限りは、生命の尽きるそのときまで一緒にいる、決して家内を一人ぽっちにはしない、という明瞭な目標があったのに、家内が逝ってしまった今となっては、そんな目標などありはしない。ただ私だけの死の時間が、わたしの心身を捕らえ、意味のない死に向かって刻一刻と私を追い込んで行くのである。》(89ページ)
もっと引用したいがやめておく。
読みすすめるにつれ目頭が自然と熱くなり、昨夜は涙が滲んで仕方なかった。
江藤さんは妻を看取る前後に、脳梗塞後遺症と排尿障害に苦しんでいたようだ。
《心身の不自由が進み、病苦が堪え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は、形骸に過ぎず、自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。平成十一年七月二十一日 江藤淳》
自ら処決して形骸を断ずる所以なり・・・とはカッコつけで、じっさいには愛しぬいた妻慶子の元へ行きたかったのだ。

(「成熟と喪失 “母の崩壊”」は「夏目漱石論」とならぶ江藤さんの代表作)
わたしの感想など、書いても書かなくてもいいものに類する。少しでも多く引用してあればそれでいいとしよう。正攻法で伴侶の最期を書いたものをこれまで読んだことがないので、そういう意味ではわたしには評価する資格はない。
本書には3者の追悼文がおさめてある。
・江藤淳を悼む 福田和也
・江藤淳記 吉本隆明
・さらば、友よ、江藤よ! 石原慎太郎
さらに絶筆となった「幼年時代」、付録として武藤康史編の江藤淳年表がそえられてある。
妻慶子死去。1998年(平成10)11月7日 享年64。
江藤淳、1999年(平成11)自殺。7月21日 享年66。


(手許にある、若かりしころの著作)
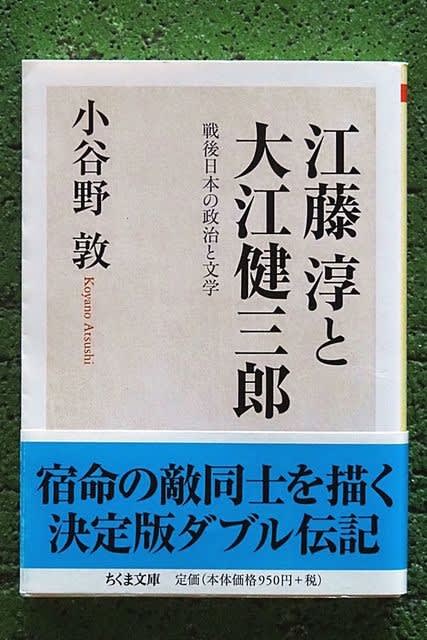
(最近購入した小谷野敦「江藤淳と大江健三郎」 ちくま文庫)

(お元気だったころのご夫妻♬ 画像検索よりお借りしました)


























