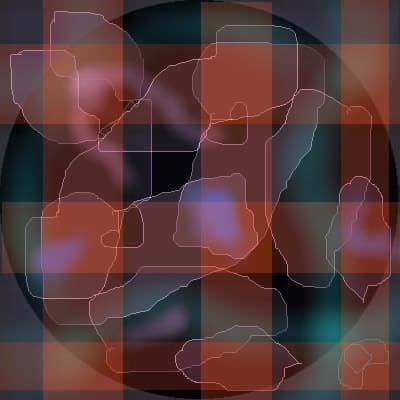その橋は『烏柵舞橋』という名が付いており、同じ名前のバスストップもその橋のたもとにあった。
私はそれをどう読むのか分からなかった。誰か人が通りかかったら訊ねてみようと一瞬思ったが、口をきくのが疎ましく、会話が辛い事のように思えて結局その呼び名を知らぬまま佇んでいた。
私は橋の中央の欄干にもたれて川の流れを上から眺めた。その流れをさらに上流へと追って行けば、その視野に尽きる彼方の山並に今太 . . . 本文を読む
太陽はいつしか西端に傾き、弱々しい日差しに変わっていた。潤んだ太陽の下には頭を平坦に切り落とされたような林がどこまでも続いていて、灰色に煙っていた。そして私の背後には千歳川が流れている。
私はとにかく日が暮れるまで歩いて行こうと決心していた。千歳川を遡りながら支笏湖に向かう国道には民家が思い出したように点在するだけで、夕暮れがふと心ぼそさを持ってきた。
もう民家も尽きるかと思われる頃にま . . . 本文を読む
私の心は少しずつ和んで行った。千歳の自然はたわいない激情には取り合わず、逆に心を和らげて体を開かせてくれるようだ。
私は自分がこのように自然の中に抱かれてしか生きてゆけないような、甘えん坊のように思えた。社会の中で私のようなものは弱者に違いなかったが、しかし私の本心はここにしかありようがなかった。私は自分を惨めな人間と認めたくはなかったが、しかしだからと云って心を欺いて、苦痛を与える生き方 . . . 本文を読む
流れる水は冷たく澄みきっていて、人を寄せ付けないような厳しさが感じられた。その水の中に一切の無駄を取り除いた魚たちが黒々と身を引き締めて泳いでると思うと胸が熱くなってくる。夕陽に映えて白く輝くさざ波のその水底にまで感覚が及んで、私は涙ぐむほどに心を動かした。そして同時にこの千歳川が、今しがた別れて来た里依子に似ていると思うのだった。
その時川の中央に黒いものが見えた。私はそれをクマだと思っ . . . 本文を読む
アヒルが数匹人なれた様子で遊んでいた。その水底にはたくさんの魚が泳いでいた。ウグイや鱒だろうか、その姿は鋭く、無駄のない動きが若々しく思えるのだった。
雪解けの冷水の中で魚たちは溌剌とその体躯をしならせ、素早い動きを見せている。なんだか私まで自分の体が引きしめられて行くように思われ、私はしばらくこの魚たちの泳ぎに見とれていた。
庭園を一巡するとすぐそばに千歳川が柵越しに見えた。その流れを . . . 本文を読む
やがてこの道が支笏湖に続いている国道だと分かった。支笏湖まで25キロという道路標識を見たとき、私は真っ先に里依子のことを思った。
支笏湖は紅葉の深い秋晴れの日に、里依子が同僚達と一緒に闊歩したところであった。そのどこかに発電所の高台があって、胸に可愛らしい動物のイラストが入った白いセーターを着た里依子が支笏湖を背にして立っている。一枚のスナップ写真が届いたのはいつのことだったか。以来私は毎日 . . . 本文を読む
私は歩いた。どこに行こうなど頭には何もなかった。ただ私の前に真っ直ぐに伸びて行く道があった。私は降りかかってくる重苦しく悲しい思いを振り切るように必死で歩いた。
もしや里依子が追いかけて来はしまいかと、そんな思いもあったが、私はもう振り向くまいと決心した。そしてただ歩くのだと思った。こうして必死で歩いているうちは、自分に歩くという目的を持たせておくことができるのだ。歩くために歩けばいい。
. . . 本文を読む
もう私たちはだめなのかも知れない。そういう思いを打ち消すことが出来ずに私は自分の心を苦しめた。それでもこの列車がいつまでも千歳に着かなければいいと思うのだった。私には何より彼女の傍にいることが重要な事のように思われ、どんなに胸を焦がしてもこのままいつまでも立っていたかった。
しかし列車は千歳の駅に止まった。私たちは重苦しい気持ちで列車から降り、駅舎から出た。
「寮まで送りませんよ。」
. . . 本文を読む
満員の列車の中で、私たちは通路に並んで立っていて、わずかに肩が触れ合うことがあった。すると里依子の温かさがそっと私に届いた。そのたびに彼女は静かに身を離した。私もまた、それを追おうとはしなかった。身を固くして吊皮を持った手を握りしめるばかりで、ただそんな里依子を淋しくあるいはいじらしく感じるのだ。そして今度は私が深いため息をついて本から目を離すのだった。
車窓からは相変わらずの雪原が私を . . . 本文を読む
しばらく私たちはそれぞれの本に見入っていた。
私は詩集の文字面を辿ってはいたが、読むことなどとても出来なかった。心を本の上に留めておくことが出来ずに、もうこれで里依子と会えないのかという思いばかりが繰り返す浪のようにやって来る。
里依子が私と一緒に帰るのを拒んだのは、あるいは私が彼女の寮まで未練たらしく付いて行くことを嫌がったのかも知れない。
いろいろに考えあぐんだ末に私はそう思いいた . . . 本文を読む