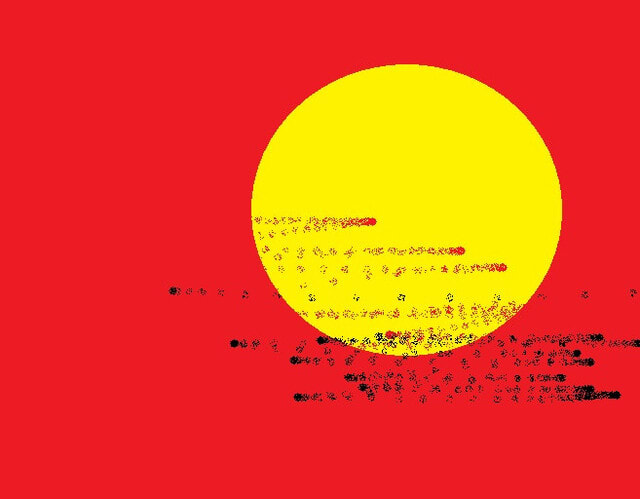
子曰、學而不思則罔。思而不學則殆。
これは、情報と思考の関係みたいに解されることもあり、そりゃまあ、そんな風にとってもかまわないのかもしれない。しかし、これは教えというより、実践的な意識と離れたある種の感慨であるような気がする。上のことはテキストを解する学問をやってみるとさしあたりよく分かるからである。調べたことや学んだことを繋げて繋げてある全体を形成させると、それは何かグロテスクにみえる何かになっており、そんなときには翻って再考することこそが必要である。しかしだからといって、最初から全体を把握しようとしてももっと駄目で、いや、駄目でない場合もあるが、それと調査したり学んだりする「学」の段階との関係は一様ではない。この対になっているものは実際は両立しているのではなく、入りくんだ低回である。そもそも、どうやっても失敗する場合もありうるのだし。。。人は大概、志向を逆にすれば、最初の失敗が上書きされて消されると思いたいのだが、そんなことはない。
思うに、我々は、実際に積み重ねていることの単純な重層にたいして、勝手にそこでの不可思議な発酵を信じている場合がある。例えば、――いろんな人をみてきて思うんだが、褒められすぎて育つと、人にやさしくなるより、大概はむしろ褒められることを人に要求するようになってるのではないだろうか。経験されてきたものの重層の結果として考えるとそうなり、実際そうなっていると思う。褒められることの反復が、自己の肯定から転じて他者への肯定になるという想定は、そこに何かの発酵があり得ると考えた結果なのだがちょっと甘い気がする。他者の肯定は、自己の肯定と簡単に並び立たないのじゃないか。敬意を持った態度を学ぶというのは、あらゆる場合に偉ぶらない練習である。対して、むりに上下関係を教育したら自分より下だと思った相手に威張り散らすようになったというのは、威張り散らし方を学んだためであろう。これも重層の結果である。
現実にどうだったかはともかく、――必要な仕事して食って寝て、だれかにそれ以外をやってもらっているのは『昭和のオヤジ』そのものであって、むしろ、いまはそういうエラそうなやつが大半を占める社会が到来している。自分のケツをちゃんと自分でフケとしかいいようがないが、『昭和のオヤジ』みたいなものが一種の不可思議な意味(偉ぶり?)を発酵させていて、本当は、偉ぶりによって何が犠牲になっていたのかを忘れたためである。文化的イメージによって差別は生じもするが、問題はそれが明らかで分かりやすすぎる点にある。逆に「必要な仕事して食って寝て、だれかにそれ以外をやってもらっている」というものの実態は案外、苦労している労働者のイメージによって見えなくなっている。昨今のなんちゃって改革ブームで忘れられがちなのは、改革によって破壊された部分もそうだが、むしろ症状がひどくなっている部分であって、乗り越えたみたいな自意識がいろんなことを見えなくしてしまっている。いまさら協働とか言うとるけれども、これはいろんな人が言っているように戦時下の脅し文句でもあって、主婦の過剰労働みたいなものはそれ以来リニューアルされて強化された部分もあったわけだ。戦時下から現在に至るまでずっと起こっている現象――すなわち、みんなで協力し合ってみたいなかけ声によってその都度新たな「小間使いとしての主婦的な存在」が生産されるということだ。最近は、ジェンダーの差別が禁じられたので、男女関係ないほんとに弱いもんにその存在を押しつけるやり方がはびこってて、ちょっとひどいことになっとんなという感じだ。「支援」みたいな便利な言葉でよく気がつくやつが自主的に働かされている。女性も男も発達障害者も健常者もこの点からみると、その多くが抑圧者の方である。
労働をただ積み重ねればうまくいくものではない。ただし考えて働いてもうまくいくものではない。――我々は、やっと労働時間を守ろうという方便を用いて、二番目の段階に突入したにすぎず、当然うまくいかない。労働が苦行である限り、苦行は苦行のまま積み重なる。時間的な休憩でその積み重なりがなくなったりしないことぐらい、我々は小学校のころのテスト勉強で分かっているはずではないか。そして、そのときに母や父にお前は何をやらせていたのだ?









