■落語でブッダ
昔、一度寄席に行って、最近もサケ友ちゃんのススメで何度か行って、
ちょっとだけ落語が身近な娯楽になってきたところで、
落語と仏教が関係しているって番宣を見て興味をもって、
予録していたのをやっと見てみたら、
こないだF氏に言いたかったこととリンクしていて感動した/驚
難しい仏教の教えを、分かりやすく、飽きさせないために
「小噺」も入れて大衆に話した「お説法」が落語のルーツ/驚
落語家がはなす時に上がる講壇は、お説教をする時のスタイルだったとか。
▼「維摩経(ゆいまぎょう)」
聖徳太子も大好きだったという読んで面白いお経なんだって!
維摩居士(釈迦の在家弟子でありながら、誰より深い悟りの境地にあったという)が病にふせった時、
ブッダが弟子に「お見舞いに行ってくれ」とゆっても、
日頃から彼にやりこめられていた弟子たちは行きたがらない(第1幕)という様子は、
まさに古典落語「寝床」に通じるw
「寝床」は、長屋の主人が浄瑠璃をみんなに聞かせようとするが、
あまりにヘタっぴで耐えられないから、バレバレの言い訳で逃れようとする様子が面白い落語
そこには、「人はみな自分の都合で物事を考えてしまう」などの教えが含まれている。

 「自分にとらわれると、周りが見えなくなる」
「自分にとらわれると、周りが見えなくなる」
 「自分の考えにとらわれていると、苦しみを招く」
「自分の考えにとらわれていると、苦しみを招く」
 因果関係、つまり「自分の都合(因)」を小さくすれば、
因果関係、つまり「自分の都合(因)」を小さくすれば、
おのずと「苦悩(果)」も小さくなるという根本的な仕組みを理解することが大事。
▼「三毒(さんどく)」

節分の青鬼(貪欲/とんよく)、赤鬼(瞋恚/しんい)、黒鬼(愚癡/ぐち))。
 貪欲:自分ではコントロール出来ないような、坂道を転がるような欲望。
貪欲:自分ではコントロール出来ないような、坂道を転がるような欲望。
「どうしても欲しい」というココロが苦しみを生み出している。
自分を強くすると、苦しみも強くなる。
 瞋恚:抑えのきかない怒り。仏教は怒りに警戒が強い宗教。
瞋恚:抑えのきかない怒り。仏教は怒りに警戒が強い宗教。
 愚癡:ブッダの教えが分からない愚かさの意味。
愚癡:ブッダの教えが分からない愚かさの意味。
第2幕では、維摩居士の病気見舞いのため文殊菩薩がやってきて、問答対決 がおこる様子。
がおこる様子。
維摩居士は、大乗仏教の根本原理「空(くう)」を表すために、何もない部屋 で菩薩を迎えた。
で菩薩を迎えた。
その様子は、興福寺の仏像に復元されている。
これは、落語での「書割盗人(かきわりぬすっと)」によく似ているという。
極貧の男が長屋に引っ越してきて、家財道具が一切ないから、
絵描きにタンスから、へっつい(竈)など全部描いてもらい、酒 を飲んで寝ていたところ、
を飲んで寝ていたところ、
何も知らない泥棒が入り、モノを盗もうとするが、絵に騙される
絵に騙されたことに気づいて悔しく思って、泥棒は「盗んだつもり 」になり、
」になり、
男は「盗まれたつもり」になって追いかけるという落語。
 空とは
空とは
この世のものは、すべて実体がないこと。
 なににもとらわれない(家財道具を絵に描いて満足した男のように
なににもとらわれない(家財道具を絵に描いて満足した男のように
 とらわれないと、苦しみから救われる。
とらわれないと、苦しみから救われる。
▼「止観(しかん)」

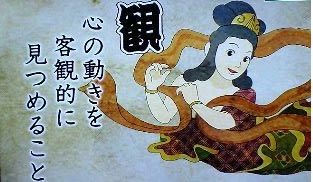
 止:ココロの動きを静めること(なにかに集中している状態も同じ。瞑想・座禅・呼吸法など
止:ココロの動きを静めること(なにかに集中している状態も同じ。瞑想・座禅・呼吸法など
 観:ココロの動きを客観的に見つめること。気づくこと。
観:ココロの動きを客観的に見つめること。気づくこと。
自分がいま、どんな状態か、第三者のような目で自分を見つめること。
「観するとココロが暴れなくなる」
ココロとカラダを静かな状態に保つことで、ココロが暴れるのを整えることが大事。
喜怒哀楽を観することで苦悩が減る。
「止観」は、日常生活で仏道を実践できるという。

実は、「維摩経(ゆいまぎょう)」には第3幕もあって、つづきが知りたかったけど、
「それにはとらわれないように」ってオチw
自分をちゃんともって、自らを知ることで、
“生きる苦しみを受けながら生きる”ことができる
っていい言葉だなって感動した
昔、一度寄席に行って、最近もサケ友ちゃんのススメで何度か行って、
ちょっとだけ落語が身近な娯楽になってきたところで、
落語と仏教が関係しているって番宣を見て興味をもって、
予録していたのをやっと見てみたら、
こないだF氏に言いたかったこととリンクしていて感動した/驚

難しい仏教の教えを、分かりやすく、飽きさせないために
「小噺」も入れて大衆に話した「お説法」が落語のルーツ/驚
落語家がはなす時に上がる講壇は、お説教をする時のスタイルだったとか。
▼「維摩経(ゆいまぎょう)」
聖徳太子も大好きだったという読んで面白いお経なんだって!
維摩居士(釈迦の在家弟子でありながら、誰より深い悟りの境地にあったという)が病にふせった時、
ブッダが弟子に「お見舞いに行ってくれ」とゆっても、
日頃から彼にやりこめられていた弟子たちは行きたがらない(第1幕)という様子は、
まさに古典落語「寝床」に通じるw
「寝床」は、長屋の主人が浄瑠璃をみんなに聞かせようとするが、
あまりにヘタっぴで耐えられないから、バレバレの言い訳で逃れようとする様子が面白い落語

そこには、「人はみな自分の都合で物事を考えてしまう」などの教えが含まれている。

 「自分にとらわれると、周りが見えなくなる」
「自分にとらわれると、周りが見えなくなる」 「自分の考えにとらわれていると、苦しみを招く」
「自分の考えにとらわれていると、苦しみを招く」 因果関係、つまり「自分の都合(因)」を小さくすれば、
因果関係、つまり「自分の都合(因)」を小さくすれば、おのずと「苦悩(果)」も小さくなるという根本的な仕組みを理解することが大事。
▼「三毒(さんどく)」

節分の青鬼(貪欲/とんよく)、赤鬼(瞋恚/しんい)、黒鬼(愚癡/ぐち))。
 貪欲:自分ではコントロール出来ないような、坂道を転がるような欲望。
貪欲:自分ではコントロール出来ないような、坂道を転がるような欲望。「どうしても欲しい」というココロが苦しみを生み出している。
自分を強くすると、苦しみも強くなる。
 瞋恚:抑えのきかない怒り。仏教は怒りに警戒が強い宗教。
瞋恚:抑えのきかない怒り。仏教は怒りに警戒が強い宗教。 愚癡:ブッダの教えが分からない愚かさの意味。
愚癡:ブッダの教えが分からない愚かさの意味。第2幕では、維摩居士の病気見舞いのため文殊菩薩がやってきて、問答対決
 がおこる様子。
がおこる様子。維摩居士は、大乗仏教の根本原理「空(くう)」を表すために、何もない部屋
 で菩薩を迎えた。
で菩薩を迎えた。その様子は、興福寺の仏像に復元されている。
これは、落語での「書割盗人(かきわりぬすっと)」によく似ているという。
極貧の男が長屋に引っ越してきて、家財道具が一切ないから、
絵描きにタンスから、へっつい(竈)など全部描いてもらい、酒
 を飲んで寝ていたところ、
を飲んで寝ていたところ、何も知らない泥棒が入り、モノを盗もうとするが、絵に騙される

絵に騙されたことに気づいて悔しく思って、泥棒は「盗んだつもり
 」になり、
」になり、男は「盗まれたつもり」になって追いかけるという落語。
 空とは
空とはこの世のものは、すべて実体がないこと。
 なににもとらわれない(家財道具を絵に描いて満足した男のように
なににもとらわれない(家財道具を絵に描いて満足した男のように とらわれないと、苦しみから救われる。
とらわれないと、苦しみから救われる。▼「止観(しかん)」

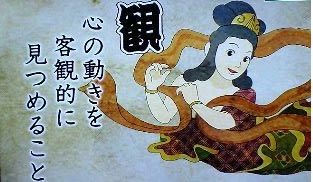
 止:ココロの動きを静めること(なにかに集中している状態も同じ。瞑想・座禅・呼吸法など
止:ココロの動きを静めること(なにかに集中している状態も同じ。瞑想・座禅・呼吸法など 観:ココロの動きを客観的に見つめること。気づくこと。
観:ココロの動きを客観的に見つめること。気づくこと。自分がいま、どんな状態か、第三者のような目で自分を見つめること。
「観するとココロが暴れなくなる」
ココロとカラダを静かな状態に保つことで、ココロが暴れるのを整えることが大事。
喜怒哀楽を観することで苦悩が減る。
「止観」は、日常生活で仏道を実践できるという。

実は、「維摩経(ゆいまぎょう)」には第3幕もあって、つづきが知りたかったけど、
「それにはとらわれないように」ってオチw
自分をちゃんともって、自らを知ることで、
“生きる苦しみを受けながら生きる”ことができる
っていい言葉だなって感動した













 しかもらえず、
しかもらえず、 」
」
 、兄を頼ると断られ、娘を吉原に売り、その金もスラれてしまう夢を見るという人情話/涙
、兄を頼ると断られ、娘を吉原に売り、その金もスラれてしまう夢を見るという人情話/涙 は大事故で全員死亡。
は大事故で全員死亡。
 )をもらった3人の男。
)をもらった3人の男。

 にとうとう傘もないから笠をかぶって店先まで見に行くw
にとうとう傘もないから笠をかぶって店先まで見に行くw 」と番頭は頭を抱える。
」と番頭は頭を抱える。



