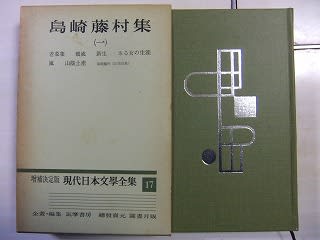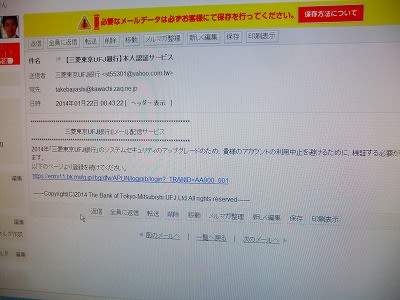ケロリンは語ります。
「明日からまた雪が降るという。雪はもう勘弁だよー。」

居酒屋のタヌキもつぶやきます。
「雪に埋もれて死んじゃうんじゃないかと怖かったー。」とね。

畑のキジバトは首を振り振り怒鳴ります。
「雪ばっかりで虫やミミズを探すのが容易でねえー。」


雪の重みでビワの枝が折れてしまい、後始末に二日かかる。
昨年は強剪定してあまり収穫できなかったけど、今年はビワの豊作を期待していたんだけどなー。
「明日からまた雪が降るという。雪はもう勘弁だよー。」

居酒屋のタヌキもつぶやきます。
「雪に埋もれて死んじゃうんじゃないかと怖かったー。」とね。

畑のキジバトは首を振り振り怒鳴ります。
「雪ばっかりで虫やミミズを探すのが容易でねえー。」


雪の重みでビワの枝が折れてしまい、後始末に二日かかる。
昨年は強剪定してあまり収穫できなかったけど、今年はビワの豊作を期待していたんだけどなー。