本日、 のち
のち の予報。
の予報。

昨日は久々に暑い日でした。外で、薪小屋を作っていると、宅急便が届きました!
開けてみると9/1新発売の拙著『『1㎡からはじめる自然菜園~草を活かして、無農薬で野菜がぐんぐん育つ!』(学研パブリックス)でした。
編集者さんと一緒に、今も連載を続ける菜園雑誌「野菜だより」(学研)の連載をレイアウトからすべて見直し、新たな情報も盛り込んで体系的にまとめました。
私もはじめて手に取る実物の拙著見本誌です。
それまでは、PCのPDFでのメールでの編集校正作業でしたし、印刷されたものは最終校正で見開き状態のもだったので、紙の質感・本にした時の厚みや重み開いた感じなどが今日やっと感じることができました。
みなさんのもとには、9/1以降に書店やネット上に並びますので、是非手にとって見てみてください。
柔らかい質感の表紙に対して、畑などで見開きで見たい場合にも観やすいような硬めのオールカラーになっております。
大きさは、農文協さん、家の光協会さんの拙著と同じ大きさでB5サイズになります。

発売前にいち早く、ちょっと中身をご紹介していきます。
今回も3部構成で、

第1章は「自然菜園入門」がテーマで、
自然菜園を始めたい方、無農薬で家庭菜園を始めたい方、自然菜園の基本が写真でわかりやすく載っております。

特にこの本では、菜園プランの大切さ、相性のよい野菜の混植に焦点を合わせ、
初めての方でも、ベテランさんでも知って得するぐるぐるリレープランで野菜の栽培方法をご紹介しております。

第2章は、「1㎡からはじめる自然菜園 実践編」
1㎡の区画をぐるぐるリレー栽培することで、どんどん野菜が次の野菜の土づくりをしてくれるそんな夢のような組み合わせが、

なぜ、どんどん良くなっていくのか、その秘密や仕組みを解説し、
実際に、いつどのように配置すればいいのか、草マルチ強化月間もご紹介。

1㎡のプランが、2つ℃のようにぐるぐるリレーされていくのか栽培ポイントを解説!
初めての方は、詳しすぎてわかりにくかった点を、改善し、ぱっと見てポイントを抑えることができます。
ベテランさんは、自然菜園ならではのテクニックや切り替えのタイミングや草マルチ、補いをいつやるのかがイメージできるページです。

第3章は、「1㎡を組み合わせて無限大のカスタマイズ菜園へ」
1㎡は、お庭の空いたスペースでもはじめることができますし、
100㎡以上でも、組み合わたり、することでぐるぐるリレー栽培が自分の菜園ライフに合わせて実践できるヒントがまとめてあります。
写真にあるように、7㎡位のお庭など空いた近くのスペースは、キッチンガーデンとして、ちょっとした野菜が食卓に彩りを与えてくれます。
1カ月に2~3回位は通える方は、15㎡位がお奨めだったり、
週一菜園30㎡、自給菜園100㎡で栽培する時のポイントをまとめてあります。
自分が自然体で取り組める菜園は、広さや菜園への距離だけでなく、育てる野菜の特性を知った上で、自分と野菜がちょうどいいところにあります。
例えば、たまにしか行けない場所で、、毎日収穫が必要なキュウリは合っていませんし、ある程度放っておいても育つカボチャやジャガイモ合っています。
ミニトマトやネギは、庭やプランターなど身近にあると食卓の彩りに助かります。
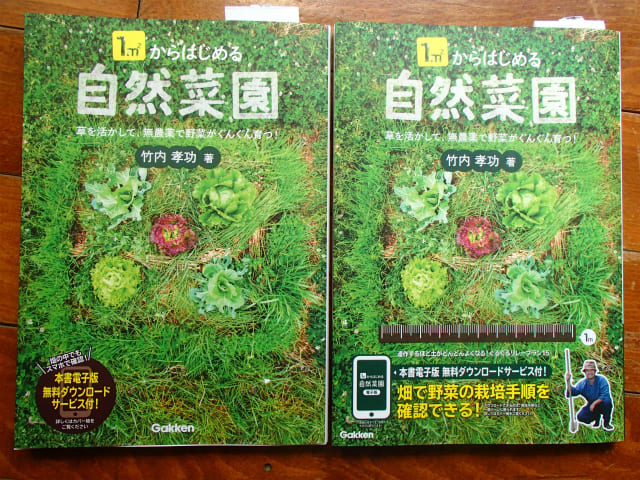
2冊の違いは?

帯がついているかどうかでした。
今回表紙は、1㎡で育てたレタスとキャベツの組み合わせ、緑肥mixを畝ふちに播いてあります。
今回の本は、新しい試みをしてみました。
私は一応携帯をもっておりますが、いわゆる折り畳み式の旧式なので、活用できませんが、
購入者特典で、スマートフォンやタブレット端末でも栽培に関する、畑で確認したいページのみ無料ダウンロードできる特典がついております。
実は、私の菜園教室の生徒さんの多くは、スマートフォンやタブレット端末で、写真を撮ったり、動画で記録したりととてもハイテクで、
本も畑に持参してくれボロボロになる位見ながら野菜を育ててくれております。
そこで、編集部の方々に無理をいって、本としても楽しめ、最新のタブレット端末でも確認できる画期的な試みをさせていただきました。
もちろん、全部のページダウンロードできる電子版書籍も同時発売となりました。
今回で4冊目の拙著ですが、初の電子書籍対応の本です。
私は対応できておりませんが、このサービスによりより菜園が身近なものになっていただければ嬉しいです。
もし、本屋さんや図書館などでお手を取ってみていただけた場合には、是非、感想やご質問をこのブログのコメント欄にお寄せください。
次の本づくりに参考にさせていただき、より良い本、より分かりやすいように勉強させていただきたいと思います。
自然農法をはじめて19年目、自然菜園をお伝えし始めて9年目。
さまざまな学びや体験がありました。特に菜園教室をはじめてからは、多くの生徒さんからのご質問や生徒さんの菜園区画からいろいろ学ばせていただき鍛えられて、
3年前に、『これならできる!自然菜園』(農文協)として、まとまり、去年家の光さんから『自然菜園で野菜づくり』も出版させていただき、
現在、雑誌「やさい畑」(家の光協会)、「野菜だより」(学研)、「田舎暮らしの本」(宝島社)で自然菜園を連載中です。
日々の菜園でも多くを学ばせていただいておりますが、実際の菜園教室や雑誌の取材などから意外な発見や収穫があり、勉強になります。
下手ながらどんどんわかりやすくお伝えできるようになってこれたのも体系的に、説明させていただく機会が多くなったお蔭かと思います。
今後どのような本や雑誌の企画があったら嬉しいなどご希望をコメント欄にお寄せください。
より分かりやすく、よろ面白い、ここが知りたかったなど今後に生かさせていただき、一緒に本や雑誌を作っていけたらいいなーと思っております。
今後もよろしくお願いいたします。
 のち
のち の予報。
の予報。
昨日は久々に暑い日でした。外で、薪小屋を作っていると、宅急便が届きました!
開けてみると9/1新発売の拙著『『1㎡からはじめる自然菜園~草を活かして、無農薬で野菜がぐんぐん育つ!』(学研パブリックス)でした。
編集者さんと一緒に、今も連載を続ける菜園雑誌「野菜だより」(学研)の連載をレイアウトからすべて見直し、新たな情報も盛り込んで体系的にまとめました。
私もはじめて手に取る実物の拙著見本誌です。
それまでは、PCのPDFでのメールでの編集校正作業でしたし、印刷されたものは最終校正で見開き状態のもだったので、紙の質感・本にした時の厚みや重み開いた感じなどが今日やっと感じることができました。
みなさんのもとには、9/1以降に書店やネット上に並びますので、是非手にとって見てみてください。
柔らかい質感の表紙に対して、畑などで見開きで見たい場合にも観やすいような硬めのオールカラーになっております。
大きさは、農文協さん、家の光協会さんの拙著と同じ大きさでB5サイズになります。

発売前にいち早く、ちょっと中身をご紹介していきます。
今回も3部構成で、

第1章は「自然菜園入門」がテーマで、
自然菜園を始めたい方、無農薬で家庭菜園を始めたい方、自然菜園の基本が写真でわかりやすく載っております。

特にこの本では、菜園プランの大切さ、相性のよい野菜の混植に焦点を合わせ、
初めての方でも、ベテランさんでも知って得するぐるぐるリレープランで野菜の栽培方法をご紹介しております。

第2章は、「1㎡からはじめる自然菜園 実践編」
1㎡の区画をぐるぐるリレー栽培することで、どんどん野菜が次の野菜の土づくりをしてくれるそんな夢のような組み合わせが、

なぜ、どんどん良くなっていくのか、その秘密や仕組みを解説し、
実際に、いつどのように配置すればいいのか、草マルチ強化月間もご紹介。

1㎡のプランが、2つ℃のようにぐるぐるリレーされていくのか栽培ポイントを解説!
初めての方は、詳しすぎてわかりにくかった点を、改善し、ぱっと見てポイントを抑えることができます。
ベテランさんは、自然菜園ならではのテクニックや切り替えのタイミングや草マルチ、補いをいつやるのかがイメージできるページです。

第3章は、「1㎡を組み合わせて無限大のカスタマイズ菜園へ」
1㎡は、お庭の空いたスペースでもはじめることができますし、
100㎡以上でも、組み合わたり、することでぐるぐるリレー栽培が自分の菜園ライフに合わせて実践できるヒントがまとめてあります。
写真にあるように、7㎡位のお庭など空いた近くのスペースは、キッチンガーデンとして、ちょっとした野菜が食卓に彩りを与えてくれます。
1カ月に2~3回位は通える方は、15㎡位がお奨めだったり、
週一菜園30㎡、自給菜園100㎡で栽培する時のポイントをまとめてあります。
自分が自然体で取り組める菜園は、広さや菜園への距離だけでなく、育てる野菜の特性を知った上で、自分と野菜がちょうどいいところにあります。
例えば、たまにしか行けない場所で、、毎日収穫が必要なキュウリは合っていませんし、ある程度放っておいても育つカボチャやジャガイモ合っています。
ミニトマトやネギは、庭やプランターなど身近にあると食卓の彩りに助かります。
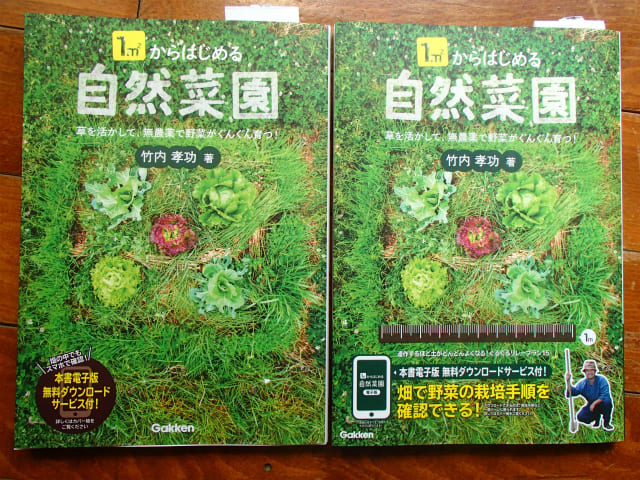
2冊の違いは?

帯がついているかどうかでした。
今回表紙は、1㎡で育てたレタスとキャベツの組み合わせ、緑肥mixを畝ふちに播いてあります。
今回の本は、新しい試みをしてみました。
私は一応携帯をもっておりますが、いわゆる折り畳み式の旧式なので、活用できませんが、
購入者特典で、スマートフォンやタブレット端末でも栽培に関する、畑で確認したいページのみ無料ダウンロードできる特典がついております。
実は、私の菜園教室の生徒さんの多くは、スマートフォンやタブレット端末で、写真を撮ったり、動画で記録したりととてもハイテクで、
本も畑に持参してくれボロボロになる位見ながら野菜を育ててくれております。
そこで、編集部の方々に無理をいって、本としても楽しめ、最新のタブレット端末でも確認できる画期的な試みをさせていただきました。
もちろん、全部のページダウンロードできる電子版書籍も同時発売となりました。
今回で4冊目の拙著ですが、初の電子書籍対応の本です。
私は対応できておりませんが、このサービスによりより菜園が身近なものになっていただければ嬉しいです。
もし、本屋さんや図書館などでお手を取ってみていただけた場合には、是非、感想やご質問をこのブログのコメント欄にお寄せください。
次の本づくりに参考にさせていただき、より良い本、より分かりやすいように勉強させていただきたいと思います。
自然農法をはじめて19年目、自然菜園をお伝えし始めて9年目。
さまざまな学びや体験がありました。特に菜園教室をはじめてからは、多くの生徒さんからのご質問や生徒さんの菜園区画からいろいろ学ばせていただき鍛えられて、
3年前に、『これならできる!自然菜園』(農文協)として、まとまり、去年家の光さんから『自然菜園で野菜づくり』も出版させていただき、
現在、雑誌「やさい畑」(家の光協会)、「野菜だより」(学研)、「田舎暮らしの本」(宝島社)で自然菜園を連載中です。
日々の菜園でも多くを学ばせていただいておりますが、実際の菜園教室や雑誌の取材などから意外な発見や収穫があり、勉強になります。
下手ながらどんどんわかりやすくお伝えできるようになってこれたのも体系的に、説明させていただく機会が多くなったお蔭かと思います。
今後どのような本や雑誌の企画があったら嬉しいなどご希望をコメント欄にお寄せください。
より分かりやすく、よろ面白い、ここが知りたかったなど今後に生かさせていただき、一緒に本や雑誌を作っていけたらいいなーと思っております。
今後もよろしくお願いいたします。





















