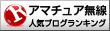ゲルマニュームラジオの同調回路
よくみるとアンテナが、コイルとコンデンサー(バリコン)の並列回路を通ってアースに落ちてます。
なんでこれで目的の電波を選ぶことが出来るのか考えてみましょう。
コイルとコンデンサーの並列回路は共振回路の基本ですね。
コイルもコンデンサーもその素子には特定のタイミングというかリズムというか、時定数というか、時間と関係のある反応を示します。
ある組み合わせで、あるタイミング(周波数)の交流が、コイルとコンデンサーで行ったりきたりする、キャッチボール、トランポリン、そんな感じで往復します。
このリズムにハマらない電流は、影響を受けずにアンテナからアースに抜けていきます。低い周波数はコイルを通って、高い周波数はコンデンサーを通って(かどうかは知らないけど好きな道で)抜けていきます。
ところが、コイルとコンデンサーがキャッチボールしている周波数だけは、キャッチボールが邪魔して通れません。つまりここで通せんぼを食らいます。
通せんぼでいじめられた電波は仕方ないので検波回路へ迂回し、そこで電波から音声成分(変調)を取り出してイヤホンを鳴らす。こんな仕掛けです。
同調回路はいじめっこの巻 でした。 (あってるかな?)
(私たちが日頃使っているラジオはスーパーヘテロダイン方式。上記のような入り口で目的の電波を選別する同調回路は使いません。特定の周波数(455KHz)に固定したラジオが入っていて、目的の電波と自ら発生させた微弱な電波を混ぜて、特定の周波数(455KHz)に変換する仕組みになっています。これにはこれのメリットがたくさんあるので、こんな複雑な仕組みを採用しているわけです。)
よくみるとアンテナが、コイルとコンデンサー(バリコン)の並列回路を通ってアースに落ちてます。
なんでこれで目的の電波を選ぶことが出来るのか考えてみましょう。
コイルとコンデンサーの並列回路は共振回路の基本ですね。
コイルもコンデンサーもその素子には特定のタイミングというかリズムというか、時定数というか、時間と関係のある反応を示します。
ある組み合わせで、あるタイミング(周波数)の交流が、コイルとコンデンサーで行ったりきたりする、キャッチボール、トランポリン、そんな感じで往復します。
このリズムにハマらない電流は、影響を受けずにアンテナからアースに抜けていきます。低い周波数はコイルを通って、高い周波数はコンデンサーを通って(かどうかは知らないけど好きな道で)抜けていきます。
ところが、コイルとコンデンサーがキャッチボールしている周波数だけは、キャッチボールが邪魔して通れません。つまりここで通せんぼを食らいます。
通せんぼでいじめられた電波は仕方ないので検波回路へ迂回し、そこで電波から音声成分(変調)を取り出してイヤホンを鳴らす。こんな仕掛けです。
同調回路はいじめっこの巻 でした。 (あってるかな?)
(私たちが日頃使っているラジオはスーパーヘテロダイン方式。上記のような入り口で目的の電波を選別する同調回路は使いません。特定の周波数(455KHz)に固定したラジオが入っていて、目的の電波と自ら発生させた微弱な電波を混ぜて、特定の周波数(455KHz)に変換する仕組みになっています。これにはこれのメリットがたくさんあるので、こんな複雑な仕組みを採用しているわけです。)