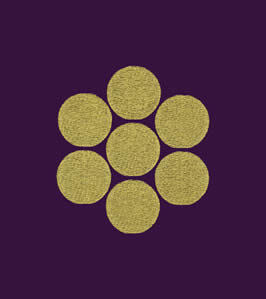◇ショーシャンクの空に(1994年 アメリカ 143分)
原題 The Shawshank Redemption
原作/スティーヴン・キング『刑務所のリタ・ヘイワース』
監督・脚本/フランク・ダラボン
撮影/ロジャー・ディーキンス 美術/テレンス・マーシュ
衣装/エリザベス・マクブライド 音楽/トーマス・ニューマン
挿入曲/ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト
『歌劇・フィガロの結婚』第3幕「手紙の二重唱」やさしいそよ風が(1786年)
出演/ティム・ロビンス モーガン・フリーマン ウィリアム・サドラー ボブ・ガントン
◇希望とはいいものだ
作品の中で映画が上映される。それが、リタ・ヘイワース主演の『ギルダ』だ。彼女は赤毛がトレードマークだったんだけど、もともとは濃い茶色で、映画デビューの際に染めたものだ。マリリン・モンローの前にセックス・シンボルとして爆発的な評判をとった。
作品中、モーガン・フリーマンがあだ名を聞かれて「Red」と答えるところがある。アイルランド系だからさと付け加えるんだけど、姓が「Redding」だから当然そうなる。とはいえ、原作でも重要な鍵になってるリタ・ヘイワースに掛けてるとも考えられないかしら?ま、どうでもいいことなんだけどね。
ちなみに、活字の読めないぼくにしては珍しく、昭和の終わりから平成の初めにかけて、読み耽った作家がいる。それがスティーヴン・キングで『刑務所のリタ・ヘイワース』も読んだ。原作を読んだときはそれほどおもしろいともおもわなかったんだけど、スティーヴン・キングはなんでかわからないけれど、前面にホラーが押し出されてない小説が映画化されたとき珠玉の作品になる。ふしぎだな~っておもうわ。ま、それもどうでもいいことだ。
ただ、ぼくにはよくわからないことがある。
なんで、この作品が大絶賛されるのかってことで、たしかに悪い出来ではないし、こぢんまりとした良質の作品ではあるけれど、人がいうほど凄い出来なんだろうかと思ってしまうのは、ぼくがひねくれているからなんだろうか?極限情況からの脱出という活劇要素は低いけど、人間の我儘と心の裏表を微妙かつ皮肉を込めて紡いでゆく過程は。地味ながら実にうまい。
終身刑にされていた人間が恩赦で放り出されたとき、もはや年を取りすぎてて、外に出ること自体が恐怖になるという皮肉、かつ、外に出て生きていくことそのものが最大の罰という皮肉の積み重ねはあまりにも哀れで、そこに希望はない。希望を得るには資金が必要で、それをどうやって手に入れるかが問題で、それについて爽快感はあるし、ラストだけようやく青空になる解放感もあるけど、そのあたりのことをすべてひっくるめて考えても、ぼくには感動という言葉とはちょっと異なる映画におもえたんだけどな~。
もちろん、人はそれぞれなので、ぼくみたいな風変わりな人間の感想なんか、どうでもいいことなんだけどね。