
漢字の字体の違いや読みの違いを考慮してカウントした場合、日本の姓は27万種あるといわれている。名もその時代々々で流行がありクラスに同じ名の方がいることもままあれど、やはり数多い。その組み合わせの姓名となると想像も付かない数だが、よほど珍しい姓と名でない限り同姓同名の人は全国にいるものだ。
ジャズも100年の歴史となれば同姓同名のプレイヤーも珍しくない。今年の富士通スペシャル 100 GOLD FINGERS は、秋吉敏子を始めジュニア・マンス、ケニー・バロン、ドン・フリードマン等ビッグネイムが並ぶ。そのメンバーの一人に Benny Green がいる。チャーリー・ベンチュラのバンドで脚光をあび、50年代に活躍したトロンボーン奏者は Bennie Green 。スペルも違い多少発音の違いもあるが、カタカナ表記では共にベニー・グリーンである。その名を見聞きすると小生はトロンボーン奏者のグリーンを思い浮かべるが、最近のジャズファンはグリーンというとピアニストらしい。
Benny Green はアート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに参加し、知名度を得たピアニストで、63年生まれの比較的若い世代ながらそのスタイルはオーソドックスなものである。メッセンジャーズの伝統でもあるファンキー・フィーリングに溢れ、スウィング感はグリーンをホール目指して飛び上がるゴルフボールのように鮮やかなラインを持っている。ここ一番聴かせどころの壺を心得たテクニックも申し分なく、オスカー・ピーターソンが自分の後継者に指名したのも頷ける。
「FUNKY!」と題されたアルバムは、ファンキーという姓を持つようなベニーの本領を遺憾なく発揮した快作だ。「マーシー・マーシー」、「ディス・ヒア」、「ワーク・ソング」等、お馴染みのナンバーが並んでいる。思わず足が踊り、体が揺れる同姓同名はファンキーという心地よく響く名であった。
ジャズも100年の歴史となれば同姓同名のプレイヤーも珍しくない。今年の富士通スペシャル 100 GOLD FINGERS は、秋吉敏子を始めジュニア・マンス、ケニー・バロン、ドン・フリードマン等ビッグネイムが並ぶ。そのメンバーの一人に Benny Green がいる。チャーリー・ベンチュラのバンドで脚光をあび、50年代に活躍したトロンボーン奏者は Bennie Green 。スペルも違い多少発音の違いもあるが、カタカナ表記では共にベニー・グリーンである。その名を見聞きすると小生はトロンボーン奏者のグリーンを思い浮かべるが、最近のジャズファンはグリーンというとピアニストらしい。
Benny Green はアート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに参加し、知名度を得たピアニストで、63年生まれの比較的若い世代ながらそのスタイルはオーソドックスなものである。メッセンジャーズの伝統でもあるファンキー・フィーリングに溢れ、スウィング感はグリーンをホール目指して飛び上がるゴルフボールのように鮮やかなラインを持っている。ここ一番聴かせどころの壺を心得たテクニックも申し分なく、オスカー・ピーターソンが自分の後継者に指名したのも頷ける。
「FUNKY!」と題されたアルバムは、ファンキーという姓を持つようなベニーの本領を遺憾なく発揮した快作だ。「マーシー・マーシー」、「ディス・ヒア」、「ワーク・ソング」等、お馴染みのナンバーが並んでいる。思わず足が踊り、体が揺れる同姓同名はファンキーという心地よく響く名であった。












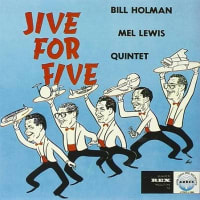













死語になりつつあるファンキーという言葉、忘れられているそのファンキージャズ、歴史を振り返ってほしいものです。そこにはダイヤモンドのような輝きがあるのですから・・・
と、マイスルなら言うでしょうね。(笑)
ティモンズとシルバーのナンバーに人気がありましたが、曲数が多くて絞り込むことができませんでした。皆さんが挙げられた数々の曲は全てファンキーです。ファンキーな曲というは聴いていて楽しいものばかりです。楽しいばかりがジャズではありませんが、楽しくないことには「音楽」ではありません。ふと落ち込んだとき、ちょっと嬉しかったとき、ティモンズやシルバーの曲に耳を傾けはいかがでしょう。ファンキーな1曲が明日への活力につながることもあります。
音楽用語というのは概していい加減なものでして、感覚だけで使ったりしますから、その定義となると説明できないものが多いですね。ファンクという表現では、ブラック・ファンクなる言葉もあります。こうなると余計に分かりません。
我々の時代・・・私の場合70年代ですが、チャールス・ロイドの「ラブ・イン」あたりをスーパー・サイケデリック・ジャズ・サウンドなるよく分からん表現をしていました。
ジャック・ケルアック やウィリアム・バロウズの反社会的小説あたりからでしょうか、ヒップという言葉も流行りました。ヒップホップという音楽表現もありますが本来の感覚とは違いますね。まぁ理論的説明を展開すると今時の若いもんにスクエアと言われそうです。(笑)
トロンボーンのベニー・グリーン登場とは嬉しいですね。記事の内容に即した名前が挙がりました。(笑)
「ファンキー」はフィーリングですから、感じたままでいいと思いますよ。私も上手く説明できませんで、まぁティモンズやシルバーのあれですよ、あれ、と言っております。(笑)
ゴンザレスはファンキーですね。あのアルバムはジーン・アモンズの粘っこいソロもまたファンキーです。
我々の時代・・・というか60年代はファンキーという表現しか無かった。
しかし、ロック系からファンクという表現が出てきた。
これは似て非なる表現かなと、無い頭で考えるのです。
ここでDUKEさんが語源の分析でその違いを述べられており、流石とうなりました。
今時の若いもんに、この感覚的相違をどう説明というか・・・感じてもらえばよいのか・・そう聴いてもらうのが一番ですね。
ここで挙げられた盤を全部聴くと分かると思いますよ。でもここで挙げた盤でも随分と幅がありますから、自分でも笑ってしまいます。
若返りの秘薬・・・ファンキー論争を永遠に続けること!(汗)
イメージするのはトロンボーンのベニー・グリーンの
「ソウル・スターリン」かなぁ
タイトル曲のバブス・ゴンザレスのヴォーカルはファンキーかな?
Cool Struttin' 丸ごとファンキー名盤できましたね。「徹底的な粘り腰」とは上手い表現です。おっしゃるようにあのノリは自然発生的であり、クラークをはじめメンバー全員飾らない美しさがあります。歩くときに飾るのはモデルや他の視線を意識するもので、普通は無意識の自然体です。この自然体を美しく表現するのが実は難しい・・・よってジャケの女性は美しい。(笑)この脚と立ち姿に関しては美脚に詳しい 4438miles さん(笑)が、「Fのブルース」で展開しておりました。
ファンキージャズと呼ばれるようになった曲や時代は分かりませんが、「ファンキー」は黒人の体臭を指すスラングです。一般にファンキーは感覚、ファンクは肉体の意のようです。
黒人の絶望や悲しみ、苦しみを歌うブルースよりも、希望や喜び、楽しさを歌うゴスペルからの影響が強いファンキージャズです。こういった解放感のある明るい背景が音楽性につながっているのでしょう。おっしゃるようにこの解放がファンキーなのだと思います。一方、その明るさが芸術性という点では評価されないわけです。バップ~モード~フリーという大雑把な流れにファンキージャズを加えるべきでしょう。
いやあ・・・KAMIさん、素晴らしい唄い口(言葉)ですね。今回の「ファンキー」・・・いわゆるその路線のジャズ・・・実はちょっと苦手でして(みなさんより少し下の世代のせいかもしれない:笑)だから・・・「ファンキー路線」を端から意識しての路線は(シルヴァーとかキャノンボール)あまり聴いてないのです。
で・・・KAMIさんのこの言葉をもうちょっと拡大解釈すると・・・僕の中で感じる「ファンキーさ」というのは、ソニー・クラークのCool Struttin'です。あのマクリーンのモタレにモタレたノリ、ファーマーのじっくり唄いこむ感じ、そしてクラークのこれまた鍵盤に指が吸い付いているかのような(以前、どなたかのブログでこういう表現をしていた・・・素晴らしい!)あの粘るタッチ~技術的に言えば「テヌート感」がたっぷりということかもしれないが、そんなもんではない、徹底的な粘り腰!~というわけで、僕は「Cool Struttin'1枚全部」を自然発生的ファンク的名盤と呼びたい(笑)
追伸~ハンク・モブレイのQuintet(1550番)に入ってるfunk in deep freeze という曲も、暗さ加減・粘り加減が、実にいいですね。あれ、1957年録音なので・・・ひょっとしたら、あの曲辺りが、「ファンク」(それらしきノリ、という意味で)という言葉の元ネタですかね?
違うんだよな。自分の中にあるファンキーな感覚を解放すること。そうすると自然にファンキーになる・・・。
と思っております。
徘徊痴人の独り言です。
ザビナルがファンキーな曲を書いてもファンキーなアドリブができないのは音楽理論を優先するからでしょうか。「カミン・ホーム・ベイビー」を書いたベン・タッカーも、ソロとなると地味でした。理論的でも、真摯な紳士でも、ファンキーな音は刻めないとういことでしょうね。かといって不良でもできぬ。ファンキーとはそのバランスが程よく保たれているのだと・・・
植草甚一さんのピーターソン論は読んだ記憶があります。「植草甚一ジャズの世界」というアルバムがあります。「Sandu」、「Wabash」等、好きな曲をオムニバスで入れたものですが、鍵谷幸信氏との対談を挿んでおります。語り口はファンキーですね。そういえば植草甚一スクラップ・ブックの1冊に「ファンキー・ジャズの勉強」がありました。
政治、経済、哲学、宗教、芸術に風俗、ジャズに関係なく展開するのがアドリブ帖です。コメント欄は 4438miles さんに場外乱闘の様相だとお褒めの言葉を頂いております。(笑)久保田利伸、大いに歓迎です。また、二言語、多文化主義のカナダからのリポートもお待ちしておりますよ。カナダの作家マリー・クレール・ブレの「エマニュエルの人生における一つの季節」は読みました。カナダ文学を研究しているわけではありませんよ。エマニュエルに惹かれただけです。(笑)
>ホーラスは、面白いタイトルの曲を一杯作ってますよね。ユーモラスな一面がすきです。
「AH! SO」は天皇陛下が毎日言っておられます。
「Too Much SAKE」は私が毎晩言っております。
しかし・・・自分のソロとなるとからきしダメ、譜面上でファンキーがザビナルではと思うしだいです。
要は、こうすれば皆さんお好きなファンキーでしょと、書けてしまうのですね。
でもアドリブではファンキーにできない人なのでしょう。(笑)
あと、ファンキーといえばオルガンがありますが、オルガンは音だけでもファンキーサウンドですから、今回は遠慮します。
あとそうだな、ジーン・ハリスやモンティ・アレキサンダーかな・・タレンタインはR&Bっぽいところと紙一重ですね。
ウエスもファンキー、ブレイキーのドラミングもファンキーでんなあ。
そういえば、高校時代、私がマイルスもファンキーな一面があると言って、4人のバンド仲間で論争になり殴り合いになり、その闘争が3ヶ月続きました。
でも毎日練習と論争は欠かさず、時にはボクシングで決着と・・・若いジャズ熱ってそんなものでした。
やはり殴り合いくらいしないとね・・・最近のジャズファンは軟弱でんなあ。
そもそも、ピーターソンがファンキーの後継者でティモインズだなんて、傍にいたら完全にオスカーと論争です。
そもそも60年代のジャズ雑誌ではピーターソンはスイングしないと定評だったのですから。
植草甚一さん曰く、ピーターソンのアドリブは全部同じですねと書いたくらいでした。
いい世の中になりましたなぁ・・。(笑)
そうですね、久保田でかなり道がはずれてきました(笑)、でも好きなんですよね、ああいう乗りが。
でもあの子はジャズと関係ないですねぇ~(後悔)。
しかしあのチェットいいでしょ、すごく乗ってます。
皆さんに機会があれば聴いて欲しい一枚です。
ベニー。グリーンは、何故か私的に言うとピアノの方になります。オスカー。ピーターソンが結構目を
かけていたから、気になって良く聴くようになりました。ベニー。グリーンはラッセル。マローンとよく競演してますね。
ラッセルのギターとよく合ってるように思います。
ホーラスは、面白いタイトルの曲を一杯作ってますよね。ユーモラスな一面がすきです。
>ネタには困らない方ですから、これからもお使いください(笑)。
昨夜は宴会でしてネタを全部出してきました。あるようで無いのがネタ、ないようで無いのがカネ、無いようであるのがツケ、また増えました。(笑)
モーニンはジャズを聴き始めの頃、シングル盤で買いました。緊張感を失わないためA面からB面に素早くひっくり返す練習をしたものです。今のCD時代には考えられないことでしょうが、当時は真剣でしたね。私はトップに挙げましたが、忘れられないファンキーベストです。
ベニー・グリーンは私もボントロと思ってCD店の棚から抜きました。記事で紹介したアルバムなのですが、曲目を見てビックリ。50年代の作品かと思いましたよ。(笑)スタイル的にはティモンズの後継者という感がありますが、ピーターソンと共演したのがきっかけで、後継者に指名したそうです。naru さんがピーターソンを挙げておられましたが、相通ずるファンキーな薫りが漂います。
>安富祖貴子の「マブイの歌」に「マーシー・・・」が入っていますが
これは知りませんでした。バッキンガムズは聴いておりますよ。「マーシー・・・」がアドリブのやりにくい曲とは・・・どうりでソロが展開しないわけだ、なるほどです。ザビナルの顔からすると哲学的な曲を想起しますが、けっこう顔に似合わずファンキーな曲を書いておりますね。
ファンキーコンボのベスト3は同感です。シルバーといい、ティモンズといい、母親はファンキーかなと。して父親はというとブルースでしょうか。
ベイカーの Love For Sale は言われてみれば確かにファンキーかなと。ブレッカーもいい音出しております。ファンキーと Love For Sale ・・・ハハハ、共通するものが・・・ス、ス、スイマセン、超男的ファンキーな発想で。(笑)
>Ron Carterのベースが這いずり回ってもう
音が聴こえてくる表現ですね。畏れ入りました。
「スイス・ムーブメント」のレス・マッキャンを忘れておりました。マッキャンもファンキーならエディ・ハリスのテナーも超ファンキー、「サニー」同様気分が高揚し、ついでに陽が昇る傑作です。
>久保田利伸
感覚的にはファンキーな要素がありますね。エゴラッピンもそのような匂いを持っております。ジャズのブログとは思えない展開になってまいりました。このファンキーな展開が実は好きなのです(笑)
「ソング・フォー・マイ・ファーザー」はいい選曲です。ジャケットがファンキーじいさんですね。このような年寄りになりたいものです。
ピーターソンの「ナイト・トレイン」とは予想もしませんでした。確かにファンキーなピアノです。
スタンリー・タレンティンは顔がファンキーですね。顔に似合った音は自信を持って、おすすめです。(笑)
ティモンズとシルバーで大きく分かれる思っておりましたが、やはりシルバーが人気のようです。ブルー・ミッチェルはジュニア・クック同様、音そのものがファンキーですね。シルバー・バンド出身者は皆筋金入りです。
>よくご存知で。
中古レコード店によっては 1st,2nd Press を知らずに価格を付けていることもありますので、オリジナル盤を安くゲットできる場合もあります。また 2nd Press とは知らず高値で買うこともあります。よく経験しました。知るためには授業料も必要なようです。(笑)
ネタには困らない方ですから、これからもお使いください(笑)。
>C JAM BLUES エリントンに敬意を表してでしょうか。duke に・・・(笑)
あ、分かっていただけましたか(笑)。
モーニンと言えば、ジャズを聴くきっかけはこれでした。
それにしても、ファンキーとなると、みなさん次から次へと出てきますね。
勿論
1、シスターセディ
2、フィルシー、マクナスティ
3、ダッドデアー
次点、ワークソング
因みにファンキーコンボのベスト3:即ち、やれば全部ファンキーにしてしまうバンドは!
1、ホレス・シルバー5
2、J&M(ティモンズがピアノの編成)
3、キャノンボール・アダレー5
わたしも、ベニー・グリーンは同性同名で間違えていました・・・てきっりボントロと、しかし、双方ともにファンキーであることを認識し、ピアノのベニーにその名を名乗ることを許したのです。(笑)
ピーターソンが後継者・・・私はティモンズの後継者と思うのですが?
デビット・ヘイゼルタイン等という若者もファンキーフレーズで頑張っていますね。
しかし、「マーシー、マーシー、マーシー」がザビナルの曲とは顔に似合わない・・そしてヒットはバッキンガムズというグループサウンズが歌詞をつけて歌いヒットパレードに登場したのが流行の始まり。
しかし、アドリブのやりにくい曲でキャノンボールもテーマをフェイクするのが精一杯、僕もこの曲はよく弾きます。
そうだ、安富祖貴子の「マブイの歌」に「マーシー・・・」が入っていますが、これは良いです、推薦します。
では、ファンキーを話だすと明日になってしまうので失礼します。
ホレスをお忘れなく!
はいっている。
Love For Sale(Chet Baker)
です。アップテンポで初めにベースがボンボン鳴り響いてMichael Brecker のテナーがブオーンと入ってきてRon Carterのベースが這いずり回ってもう。
私にするとファンキーになる一曲!
Sunny(Les McCann)
このサニーはスローヴァージョンとアップテンポの
がサイド バイ サイドで入ってるんですけど。
ファンキーじゃないかもしれないけど、もう楽しくってこれを聴くと気分がアップになります。
こんなところにこれを入れていいもんか。
ちょっと場違いな感じもするけど。いや完全にしてる!けどMichael Breckerが入っているから許して!
Let's get A Groove~Yo! Hips(久保田利伸)
このNeptuneってCDはもうすごくファンキーです。
この子のファンキーな感覚にはまってしまいました。
(ちょっと恥ずかしいけど)
1ソング・フォー・マイ・ファーザー ホレス・シルバー
2ナイト・トレイン オスカー・ピーターソン
3ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド スタンリー・タレンティン
いかかでしょうか?自信を持って、おすすめの3曲です!(笑!)
1)Nicas Dream(by Horace Silver)
2)Funji Mama(by Blue Mitchell)
3)Dat Dere(By Bobby Timmons)
2)は本来のファンキー・ナンバーからはちょっと
外れるかもしれませんが、まあ「ノリのいい曲」ということで
選ばせていただきました。
3)は定番の「This Here Is Bobby Timmons」のものよりも、
「Bobby Timmons In Person」のエンディングで演奏されている
ヴァージョンのほうがスリリングで好きなんですが、
あれってLP両面ともほんの数十秒でフェードアウト
しちゃうんですよねぇ、残念.....
あ、前トピでの話題の遅いレスを。
>25-25 さんがお持ちのワインカラーには Orpheum と入っておりませんか。こちらは2nd Press です。
ああ、そのとおりです、脱帽!
ほんと、よくご存知で。
>フリーがかった PEACE は David Friedman (vib)です。
あ、そうだフリードマンでしたね、ヴァイブ。
なんでカール・ベルガーを連想したんだろ?
ちょっと前に買った、カール・ベルガー&デイブ・ホランドの
Sackville 盤のイメージが強く残っていたのかな?
ブルース・マーチがトップとは嬉しいですね。高揚感があって落ち込んだときに聴くと元気が出る一曲です。ゴルソンは編曲で上手さが光りますが、作曲者としてもこの曲で評価される人でしょう。
ファンキーなピアノと問われて、まず聴こえてくるのはティモンズです。食傷気味とはいえ「モーニン」はファンキーの代名詞であり、私にとってはジャズの聴き始めに強いインパクトを与えたものです。当時は朝から「モーニン」でした。(笑)
今回のファンキー・ネタは miyuki さんの掲示板から拝借しました。ネタなしの貧困さ、憚りなくネタにする貪欲さ、であります。(笑)ネタ提供のあのお方に宜しくお伝えください。
レイ・ブライアントはかつて私も参加している当地のジャズ愛好会で主催したことがあります。GOTTA TRAVEL ON も演奏していましたが、いいノリでファンキーそのものでした。記事で紹介しましたグリーンのアルバムにあの「ゴールデン・イアリングス」も収録されていたのが嬉しかったですね。
シルバー・ナンバーは必ず出てくると思っておりましたが、コメント一番できましたね。DOODLN' サイコーです。次に C JAM BLUES エリントンに敬意を表してでしょうか。duke に・・・(笑)
ファンキー、良い響きですね。
でも最近はあまり使われなくなったように思います。
でもこのサイトのご常連の方は、ご年配(失礼)の方が多そうですから、先週に続き沢山の曲が出てきそうですね。
お気に入りの曲は
ブルース・マーチ(ベニー・ゴルソン)
オパス・デ・ファンク(ホレス・シルバー)
ジス・ヒア(ボビー・ティモンズ)
モーニンも大好きですが、聴きすぎてやや食傷気味なので上記の3曲にしました。
でも他にも良い曲が沢山ありますね。
ファンキーなピアノで思い浮かぶのは、私の場合、ホレス・シルヴァー、レイ・ブライアントでしょうか。
ファンキー・ナンバーも多いですね。
Moanin'もいいですね。あと、GOTTA TRAVEL ONも好きです。まだまだ、色々出てきそうですが、フェイバリットというと、
DOODLN' (Horace Silver)
C JAM BLUES (Duke Ellington)
BAG'S GROOVE (Milt Jacson)
かしら・・・。
いつもご覧頂きありがとうございます。
ファンキー・ナンバーと呼ばれるのは数多くあります。どのような曲でも演奏次第ではファンキーな仕上がりになりますが、誰が演奏してもファンキーの香りが漂う曲もあります。何でもベスト3、お気に入りのファンキー・ナンバーお寄せ頂ければ幸いです。今週もたくさんのコメントお待ちしております。
管理人フェイバリット・ファンキー・ナンバー3
1 Moanin' (Bobby Timmons)
2 Bohemia After Dark (Oscar Pettiford)
3 Blues March (Benny Golson)
括弧内は作曲者で、プレイヤーのヴァージョンではありません。誰が演奏してもファンキーな曲に違いありません。
「一」さん、「十」さん、「四十物」さん等、変った姓の方も是非コメントお寄せください。