
この「アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー」の出だしを聴くとほとんどの方はコルトレーンと思うだろう。しばらく聴く進むとどこか違うことに気付き、コルトレーン・ファンならまず思い付くのは未発表音源か?という疑問だが、ライブ音源ならまだしもスタジオ録音となると「ソウル・トレーン」しかないはずだ。では、別テイクか?と推理を巡らせてみても合い間に入るピアノはガーランドのそれとは違う。
よく歌い、運指もスムーズなのでコルトレーン研究家のアンドリュー・ホワイトではない。では誰か?ファラオ・サンダースである。60年代後半から70年代にかけてのインパルスやストラタ・イーストの諸作を聴き慣れた耳にそれは別人にしか聴こえないが、日本の企画とサンダースの年齢、そしてジャズを取り巻く現状況と重ねると、これも宜なるかなと納得してしまう。この曲はビリー・エクスタインが自らのバリトン・ヴォイスを売りにするため書き下ろした傑作だが、コルトレーンが取り上げたことにより一躍有名になったバラードで、度々ライブで演奏したコルトレーンの変遷を知る上で重要視されている。
サンダースが師であるコルトレーンの重要なレパートリーを取り上げても何ら不思議はないし、その演奏内容が似ていても驚くことではないが、注目すべきはコルトレーンのプレスティッジ時代の演奏手法だろう。アルバムタイトルの「The Creator Has A Master Plan」は、サンダースの傑作と評される「Karma」からの一曲で、こちらは再演とはいえ嘗ての湧き立つリズムとアヴァンギャルドな手法で健在振りをアピールしているので、当然この曲にしてもその展開が自然なのだが、敢えて初期のスタイルに倣ったのはコルトレーンの原点に回帰しようとする試みだったのかもしれない。
コルトレーン初期のバラード・プレイはマイルスが絶賛したほど素晴らしいだけに、手本とするプレイヤーは数多く存在するが、その精神性には誰一人として近づけなかった。唯一人、受け継いだのは後期のコルトレーンと行動を共にしたサンダースである。この曲があまりに似ているのは単なる模倣ではなく、師の精神性までをも表現しているからなのだろう。アルバート・アイラーはトレーンが父なら、ファラオが子だと評した。
よく歌い、運指もスムーズなのでコルトレーン研究家のアンドリュー・ホワイトではない。では誰か?ファラオ・サンダースである。60年代後半から70年代にかけてのインパルスやストラタ・イーストの諸作を聴き慣れた耳にそれは別人にしか聴こえないが、日本の企画とサンダースの年齢、そしてジャズを取り巻く現状況と重ねると、これも宜なるかなと納得してしまう。この曲はビリー・エクスタインが自らのバリトン・ヴォイスを売りにするため書き下ろした傑作だが、コルトレーンが取り上げたことにより一躍有名になったバラードで、度々ライブで演奏したコルトレーンの変遷を知る上で重要視されている。
サンダースが師であるコルトレーンの重要なレパートリーを取り上げても何ら不思議はないし、その演奏内容が似ていても驚くことではないが、注目すべきはコルトレーンのプレスティッジ時代の演奏手法だろう。アルバムタイトルの「The Creator Has A Master Plan」は、サンダースの傑作と評される「Karma」からの一曲で、こちらは再演とはいえ嘗ての湧き立つリズムとアヴァンギャルドな手法で健在振りをアピールしているので、当然この曲にしてもその展開が自然なのだが、敢えて初期のスタイルに倣ったのはコルトレーンの原点に回帰しようとする試みだったのかもしれない。
コルトレーン初期のバラード・プレイはマイルスが絶賛したほど素晴らしいだけに、手本とするプレイヤーは数多く存在するが、その精神性には誰一人として近づけなかった。唯一人、受け継いだのは後期のコルトレーンと行動を共にしたサンダースである。この曲があまりに似ているのは単なる模倣ではなく、師の精神性までをも表現しているからなのだろう。アルバート・アイラーはトレーンが父なら、ファラオが子だと評した。










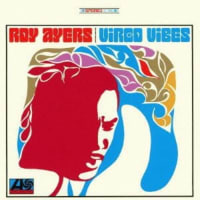

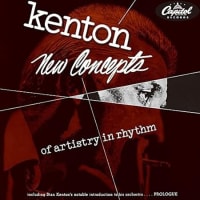


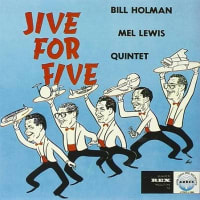










今週はバラードの傑作、アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユーのお気に入りをインストでお寄せください。ヴォーカルとファラオ・サンダースのベストは機を改めて話題にします。
管理人 I Want To Talk About You Best 3
John Coltrane / Live At Birdland (Impulse)
Art Blakey / New Year's Eve at Sweet Basil (Evidence)
Stephane Grappelli & McCoy Tyner / One on One (Milestone)
他にもデビッド・マレイ、チャールズ・トリバー、ピアノ物ではスティーヴ・キューン、ジョン・ヒックス、テテ・モントリュー、シダー・ウォルトン、札幌が誇るピアニスト福居良等々、多くの名演がありますので何が挙がるのか楽しみです。
今週も皆様のコメントをお待ちしております。
Soultrane / John Coltrane
これ一票で!
鉄板すぎるほど鉄板的な演奏です.
後年のライブ演奏も決して悪くはありませんが、やっぱりこのリズムセクションでの演奏が、ボクは一番好きです.
トレーン以外のヴァージョンは、殆ど持っていませんので、
管理人さんが挙げたアイテム、ポチしまくりました(笑)。
トレーンは、バードランドとソウルトレーン、
甲乙つけがたいですね。
唯一、エンディングのピアノは
マッコイ>ガーランドのように感じました。
いつも言うんですが、トレーン配下のマッコイは
本当に素敵です。
これが、自分が頭になると途端に色褪せるのが不思議。
ギターのウルフ・ワケニウスの
「First Step」に収録がありますが、
これはやや期待外れでした。
やはりソウル・トレーンがきましたか。リズムセクションはこの時代の黄金トリオですので申し分ありません。これを起点に発展するトレーンを辿ると私はバードランドになりました。ともに甲乙付け難い名演です。トレーンのトップは間違いないでしょうが、どちらに軍配が上がるのか楽しみです。
トレーンのイメージが強く、他の演奏はほとんど話題になりませんが、管奏者もピアニストも心なしかトレーンの影響を感じます。マイフェヴァ同様、この曲もトレーンが取り上げなければ忘れられた曲になっていたかもしれませんね。
おっしゃるようにトレーンの下でマッコイは素晴らしいソロを残しておりますが、リーダー作になると今一歩という感じがします。サハラ以降の諸作を聴くとピアノよりもグループのサウンドが重要視され本来のピアノの味を出せないで終わっております。それがリーダーとしての役割なのかもしれません。
ウルフ・ワケニウスもありましたね。名前の割りに優しいギターです。ソーホワットのアレンジは凝ったものでした。
ビリー・エクスタインの名曲、 I Want To Talk About You は、トレーンの演奏が強烈で他の演奏が出てきません。
と言うわけで、
Soultrane / John Coltraneを挙げたいと思います。
このアルバムでトレーンは、I Want To Talk About Youを美しく歌い上げていて痺れてしまう!ガーランド、チェンバース、アート・テイラーも最高!
若いころは、バードランドの方が好きだったのですが、最近はこのアルバムが気に入っています。
ジャズ喫茶の人気盤ソウル・トレーンが挙がりましたか。このアルバムはグッド・ベイトやシーツ・オブ・サウンドのロシアの子守唄等、傑作揃いです。
バードランドはバックは違いますがこちらはバラードの新解釈といったところでしょうか。今週はこの2枚でベストが決定しそうですね。
このDukeさんのお題のお陰で、両方とも聴いてみました。両方とも良いのですが、トレーンの最後のエンディングの部分でバードランドを1番にしました。
ソウルトレーンは聞き飽きるほど聞きましたが、最近はご無沙汰で、久々に・・新鮮でした。
3番もこの御題で思い出した新生ブレイキーで、なかなか面白いと3番に挙げました。
John Coltrane / Live At Birdland (Impulse)
Soultrane / John Coltrane
Art Blakey / New Year's Eve at Sweet Basil (Evidence)
ということになりやした。
とおろで、先般、ジャズ専門店「ミムラ」の閉店セールで間違って売ってしまったサキコロのオリジナル盤ロリンズの直筆サイン入りが、見つかったとの情報が入りました。
良かったです!
私も今回久しぶりにコルトレーンの2枚を聴きましたが、甲乙付け難い内容ですね。プレスティッジとインパルス、どの時代に於いてもコルトレーンの先進性を聴けます。
New Year's Eve at Sweet Basil は新生ブレイキーではなかなかの内容と思います。親分のかつての凄みはありませんが、若手の溌溂としたプレイはメッセンジャーズという登竜門の健在ぶりを証明したものでしょう。
サキコロのオリジナル盤が見つかった第一報は、25-25 さんから入りましたが、良かったですね。その場所、その人の手元にあってこそ真の名盤なのだと思います。
御大SHINさん以外は、皆オトナシ過ぎる。
これは、老化現象?ではないように思います。
かなりの数のジャズ・メン及び名曲を取り上げた為、最近のテーマは、上級者レベルになった為だと思います。
このまま進むのも、一つのやり方かもしれませんね。
コメントが無くなるまで続けろ!
頑張れ、ジャズ狂duke!!!
退散!(笑)