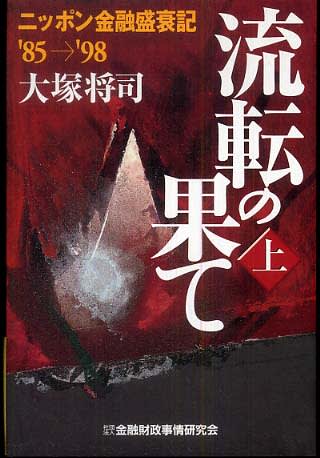の写真を探して、Googleを画像検索したのだが、見つからなかった。たしか、歯ブラシを持ったユダヤ人たちが石畳の通りを磨かされ、それを群集が見物している写真だった。web検索したら、歯ブラシとユダヤ人は関係が深いことがわかった。つまり、眼前のユダヤ人集団を嘲笑するという以上に、ユダヤ民族全体を貶める意図だったわけだ。以下の文章も見つけたので貼り付け。
わたしは常にマジョリティに対する不安と恐怖を抱いている。自分がマイノリティに属しているという自覚があるわけではないのだが、マジョリティがヒステリー状態に陥ったとき、自分は必ず攻撃されるという確信のようなものがあるからだ。その確信は、わたしが大前提的にマジョリティを嫌っていることに原因がある。
わたしがマジョリティを嫌悪するのは、真の多数派など存在しないのに、ある限定された地域での、あるいは限定された価値観の中でのマジョリティというだけで、危機に陥った多数派は少数派を攻撃することがあるからだ。そしてマイノリティといわれる人々も、その少数派の枠内で、細かなランク付けをして、少数派同士で内部の少数派を攻撃することもある。
忘れることのできない写真がある。それは大戦前のドイツでユダヤ人たちがひざまずいて通りを歯ブラシで磨いているという写真だ。その人物がある宗教に属しているというだけ、その人物の人格や法的地位と関係なく差別するというのはもっとも恥ずべき行為だが、わたしたちは立場が危うくなるとそれを恥だと感じなくなる。
わたしはどんなことがあっても、宗教や信条の違いによって、他人をひざまずかせて通りを磨かせたりしたくない。それはわたしがヒューマニストだからというより、そういったことが合理的ではないというコンセンサスを作っておかないと、いつわたしがひざまずいて通りを磨くことになるかわからないからだ。
わたしたちは、状況が変化すればいつでもマイノリティにカテゴライズされてしまう可能性の中に生きている。だから常に想像力を巡らせ、マイノリティの人たちのことを考慮しなければならない。繰り返すがそれはヒューマニズムではない。わたしたち自身を救うための合理性なのである。『恋愛の格差』(村上龍 青春出版社)より。
村上春樹と村上龍は、小説は面白くないけれど(私には)、エッセイや紀行文は読ませる。
(敬称略)
わたしは常にマジョリティに対する不安と恐怖を抱いている。自分がマイノリティに属しているという自覚があるわけではないのだが、マジョリティがヒステリー状態に陥ったとき、自分は必ず攻撃されるという確信のようなものがあるからだ。その確信は、わたしが大前提的にマジョリティを嫌っていることに原因がある。
わたしがマジョリティを嫌悪するのは、真の多数派など存在しないのに、ある限定された地域での、あるいは限定された価値観の中でのマジョリティというだけで、危機に陥った多数派は少数派を攻撃することがあるからだ。そしてマイノリティといわれる人々も、その少数派の枠内で、細かなランク付けをして、少数派同士で内部の少数派を攻撃することもある。
忘れることのできない写真がある。それは大戦前のドイツでユダヤ人たちがひざまずいて通りを歯ブラシで磨いているという写真だ。その人物がある宗教に属しているというだけ、その人物の人格や法的地位と関係なく差別するというのはもっとも恥ずべき行為だが、わたしたちは立場が危うくなるとそれを恥だと感じなくなる。
わたしはどんなことがあっても、宗教や信条の違いによって、他人をひざまずかせて通りを磨かせたりしたくない。それはわたしがヒューマニストだからというより、そういったことが合理的ではないというコンセンサスを作っておかないと、いつわたしがひざまずいて通りを磨くことになるかわからないからだ。
わたしたちは、状況が変化すればいつでもマイノリティにカテゴライズされてしまう可能性の中に生きている。だから常に想像力を巡らせ、マイノリティの人たちのことを考慮しなければならない。繰り返すがそれはヒューマニズムではない。わたしたち自身を救うための合理性なのである。『恋愛の格差』(村上龍 青春出版社)より。
村上春樹と村上龍は、小説は面白くないけれど(私には)、エッセイや紀行文は読ませる。
(敬称略)