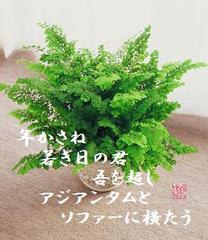年かさね 若き日の君 吾を超し アジアンタムと ソファーに横たう
■
【究極の成長戦略】
植物の表面にある二酸化炭素を吸収する穴「気孔
」の数を増やす方法を、京都大大学院理学研究科
の西村いくこ教授(植物分子細胞生物学)らの研
究チームが世界で初めて発見し、10日付(日本時
間)の英科学誌「ネイチャー」(電子版)に掲載
された。西村教授等は、10月15日にも、細菌が感
染したアブラナ科の植物が、細胞の一部を犠牲に
して病原体と“心中”する防御のメカニズムを世
界で初めて突き止め、研究成果が15日付の米科学
誌「ジーンズ・アンド・ディベロップメント」(
電子版)に掲載している。さらに、1987年には彼
女自身により、動物のアポトーシス(=プログラ
ムされた細胞死のこと)の実行因子と、死に至る
メカニズムを解明している。「液胞プロセシング
酵素(VPE:Vacuolar Processing Enzyme)」と名付け
たタンパク質は、実は過敏感細胞死の実行因子で
あることを突き止めている。
高等植物の液胞は細胞内の不要物質を蓄積、分解
するためのオルガネラであり、液胞は種子形成時
にタンパク質を大量に蓄積するタンパク質となり、
発芽時に蓄積したタンパク質を分解する一方で、
病原菌感染時には液胞は自ら崩壊することで、素
早く感染細胞を死に至らせる役割を果たす。但し、
細胞にアポトーシスを起こさせるシグナル伝達経
路を構成するカスパーゼ(caspase)は未解明。
気孔は、二酸化炭素を吸い込むことによって光合
成を助ける役割を持つ。気孔を増やして二酸化炭
素の吸収率が上がれば、植物内で生産されるデン
プンが多くなり作物の増産につながるほか、地球
温暖化問題の改善にもつながりのではと期待され
ている。西村教授らはシロイヌナズナを使い、気
孔の形成時に働いている遺伝子を網羅的に解析し
遺伝子の一つが作る小さなタンパク質に気孔(ス
トーマ)を増やす働きがあることを確認し「スト
マジェン」と名付け、シロイヌナズナの種子をス
トマジェンの溶液に浸しておくと、発芽した葉の
気孔が最大4倍にまで増えた。ストマジェン遺伝
子を導入しても同様の効果があったという。 ストマジェンの効果(上・無/下・有)
ストマジェンの効果(上・無/下・有)
まぁ、来年度のノーベル化学賞はこのグループが
かっさらった感がする。ちがうか!^^;。なぜか
って?これらの研究が応用展開することで、①地
球温暖化防止に役立つ(→地球に優しい炭素固定
)と②食糧危機の予防に役立つ(→植物の疫病予
防→食糧増産→バイオエタノールへの転換による
バイオ燃料実用化:目標、百円/㍑以下の実現→
超臨界装置や浸透気化装置等のプラント増産→エ
タノールバイオによる水素燃料とした燃料電池プ
ラント増産によるグリーンワークス(『マユミと
破局の回避策』)による地球益貢献度と国内GDP
上昇→新政権の成長戦略への中核化→日本のいや、
世界の景気回復と。いや早、日本人として、還暦
まで生きていてよかった~ぁ!これこそ、究極の
成長戦略だと ^^;。
【もう1つの究極の成長戦略】
エネルギー政策として太陽光発電装置への補助金
制度が導入されてはいるが、これを田中角栄張り
の「新日本列島改造計画」とし格上げし、住宅及
び建造物への設備投資の全額若しくは部分的金額
を、建設債として、国庫負担することの法律を制
定する。余剰電力の買電制は下位の政策におき、
スマートグリッド政策の進捗状態を見ながら調整
していくという戦略だ。こうすることにより、既
存電力供給企業と並存させ、究極的にどうなるか
(→原子力発電所が不要になる?)を見極め、余
剰電力のストック設備の整備を図っていくという
政策だ。これで、半永久的にエネルギー保障でき
るだろと。
残るは、移動体の動力用エネルギーだが、自動車
は電気自動車と燃料電池とバイオ燃料で解決でき
る。船舶はバイオ燃料と燃料電池と水素燃料で対
応。航空機もバイオ燃料と水素燃料で対応すれば
温暖化防止が両立する。当に、オイルショック→
反インフレ闘争→地下化石燃料本位制からの脱却
→先端技術本位制(1984年の『デジタル革命』、
マッキントッシュ→1987年『バイオ革命』、西村
いくこら)→環境リスク本位制へと繋がりという、
このことを明確に意識していたわたし(たち)の
確信が実現しつつある。

【航空機とバイオ燃料】 長谷川達哉
長谷川達哉
バイオ航空燃料の原料としてジャトロファが注目
されている。例えば、2008年初めには英国のヴァ
ージンアトランティック航空が、ココナッツ油な
どを原料とするバイオ燃料を20%混合し、ロンド
ン-アムステルダム間のテスト飛行に成功してい
る。さらに、他の航空会社数社も既存のジェット
燃料に加えてバイオ燃料を使用する計画を発表し
ている。航空燃料に必要な特性を満たす石炭、天
然ガス、バイオマスから航空燃料を製造した場合
の技術や経済性、環境性の評価方法、評価に基づ
いて燃料供給側や需要側がどのような選択するか
の課題がある。
【バイオマスから水素製造技術】 岡田行夫
岡田行夫
サッポロビールでは、食品工場から出る製造廃棄
物のこれまでの活用方法は、飼料や肥料としての
利用に限られ、多くは焼却されたり埋め立てられ
たりしていたが、独自技術の水素・メタン二段発
酵技術は、投入した廃棄パンから燃料電池などに
利用できる水素ガスと、ボイラーなどの燃料とな
るメタンガスを別々に生成。食品製造廃棄物など
のように固形物を含む場合、メタン発酵処理には
長時間かかるが、水素発酵を併用することで効率
的な分解が可能になり、処理時間を大幅な短縮に
成功。バイオメタンを燃料電池の燃料ガスに利用
する技術を国内でも導入している例があるが、こ
の方法ではメタンガスに含まれる硫黄分の除去が
前提だが、このバイオ水素は硫黄分がほとんど含
まれず、燃料電池用に優れるという特徴も備えて
いるという(『白樺と次世代燃料の関係式』)。
※特許:P2005-223777
「バイオガスの製造方法」 マツダ 水素自動車
マツダ 水素自動車
高圧水素貯蔵と水素エネルギ社会
■
門松とは、正月に家の門の前などに立てられる一
対になった松や竹の飾りのこと。松飾りとも。古
くは、木のこずえに神が宿ると考えられていたこ
とから、門松は年神を家に迎え入れるための依代
という意味合いがある。地域の言い伝えにより松
を使わない所もある。新年に松を家に持ち帰る習
慣は平安時代に始まり、室町時代に現在のように
玄関の飾りとする様式が決まったという説がある。
起源は、新年に松を家に持ち帰る習慣は平安時代
に始まり、室町時代に現在のように玄関の飾りと
する様式が決まったという説がある。泣いても、
笑っても後少しすると新年だ。門松を白山神社に
飾るのも任期から最後或いは千秋楽となる。素材
は町内から調達する。一の宮になれなかったこと
を総括し、後任に託しわが道を行こう ^^;。
■
ホウライシダ属(Adiantum)は、シダ植物門ホウライ
シダ科(Parkeriaceae)の一群で、細く硬い軸と、葉
が巻き込んだような包膜が特等である。鑑賞価値
が高いものが多く、一部は観葉植物として栽培さ
れている。学名仮名書でアジアンタムと呼称され
る。観賞価値の高いものが多くあり、観葉植物と
して栽培される。日本産のものではホウライシダ
がよく栽培され、時に栽培逸出のものが自生状態
で発見される。また、クジャクシダはむしろ山野
草として栽培される。ほかに、ハコネシダも観賞
価値の高いものとして有名であるが、栽培はとて
も難しい。シダ植物の「アジアンタム」。花言葉
は「純潔」「若さ」。
■