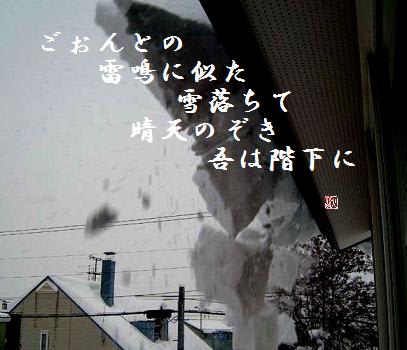ごぉんとの 雷鳴に似た 雪落ち 晴天のぞき 吾は階下に

世界における太陽電池の年間設置量が2020
年頃には100GW を超えると予想され、太陽
電池の大量導入の時代に突入しつつある。
このため、資源量が豊富であり省資源・低
コストを実現できることから薄膜Si太陽電
池が電力用太陽電池の本命と期待されてい
る。この太陽電池の大量導入の成否は、高
効率・低コスト・高歩留まりを実現するこ
とにかかっている。
広いスペクトルを有する太陽光のエネルギ
ーをできるだけ多く電気エネルギーに変換
するために、異なるバンドギャップ材料の
太陽電池を直列接続する多接合太陽電池が
今後主流になる。薄膜Si太陽電池では、単
接合、2接合が産業化されており、3接合
は開発段階にある。高効率・低コスト・高
歩留まりの観点から、最適な接合数があり,
現状では2接合が、将来的には3接合が良
いとされている。何れの接合においても、
高エネルギー側の光子を吸収するトップセ
ルには、バンドギャップが1.6~1.8 eV 程
度の水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)
が用いられている。
これは、プロセスの整合性と性能の観点か
ら a-Si:H が現在でも最も良いトップセル
材料であるためである。しかしながら、a-
Si:H太陽電池では光照射により膜中に未結
合手(欠陥)が発生し、この光誘起欠陥を
介してキャリアの一部が再結合することに
より、使用開始直後に比べて発電効率が低
下する光劣化現象が存在する。この現象が
単接合だけではなく多接合太陽電池におい
ても高効率化の足枷となっている。光劣化
低減には2つの方策がある。1つは、光劣
化が生じにくい膜を作製することであり、
もう1つは、薄膜中への光閉じ込めを用い
て、太陽電池に用いるa-Si:Hの膜厚を薄く
して光劣化を生じにくくすることである。

ここでは、後者の光劣化しないa-Si:H薄膜
の作製について述べる。光誘起欠陥密度が
初期欠陥密度より十分低ければ、光誘起欠
陥により太陽電池の効率は低下しない。こ
のような膜を、ここでは光劣化しないa-Si
:H 薄膜と呼ぶことにする(「白谷正治、
古閑一憲九州大学大学院システム情報科学
研究院「光劣化しない革新的アモルファス
シリコン太陽電池の作製をめざして」)

この様にSi 系薄膜太陽電池の効率向上を
実現する重要な鍵の1つに、a-Si:H の光劣
化の低減が重要で、アモルファスSiクラス
タのa-Si:H 膜への取り込み量の増加ととも
に、膜中のSiH2 結合量が増加する。フーリ
エ変換赤外分光光度(FT-IR)測定から、
アモルファスSiクラスタ中には多数のSiH2
結合が存在し、膜中のSiH2 結合の形成機
構に、表面反応に起因するものと、クラス
タの膜への取り込みに起因するものがある。


さらに、膜中のSiH2 結合量が少ないほど
アモルファスSiクラスタの膜への取り込み
を抑制するほど光安定な膜が得られる(ク
ラスタの取り込みを従来比で2桁程度以上
少なくすることで、図2に示すように欠陥
密度が1015 cm-3台で、光照射しても欠陥
密度の増加が見られないa-Si:H 膜が作製
できる)。現状における光安定なa-Si:H
の特徴は、
1)膜中へのクラスタ取り込み量が従来比
で1/100 以下である。
2)膜中のSiH2 結合量がFT-IRの検出限界
以下に低い。
3)膜中の水素含有量が5%程度と低い。
4)水素含有量が低いとバンドギャップが
1.6 eV 台とa-Si:H にしては狭い。
5)光安定化後の欠陥密度は5×1015 cm-3
程度である。
多接合太陽電池のトップセル材料としては
バンドギャップが狭いが、この点は、成膜
時の基板温度を低くして表面からの水素離
脱を抑制することにより改善できるから、
薄膜シリコン系の高品質ソーラセルの製造
コスト実現技術を獲得できれば、一挙に綿
々として続いてきた太陽信仰はこの地上で
融合し『贈与経済社会』(=社会主義社会)
を迎えることになると期待できる。

とはいえ、ソーラセルには急所がある。積雪と
いう。「無落雪建築」技術で心配ご無用という
ことも現実的な対応が進んでいるので、これが
すべてではないが、従属技術問題として、いろ
いろ進展してきそうだから楽観している。
落雪の轟音で、目を覚まし窓越しに顔をだして
「問題やねぇ~~~」と大きな独り言を呟き階
段を降りる光景を、「雷」と「雪」を対にして歌に
した。