アフリカは 吾が故郷と 言いかけて 指折り数える百万年


電力10社は20日、政府が2009年に導入した太
陽光発電の余剰電力買い取り制度に基づく電
気料金への上乗せ額を公表。家庭の負担増は
月額2~21円程度で、同日、経済産業省に認可
を申請。同省審議会での承認を得て、4月から
全ての電力利用者の料金に付加する。この制
度で国民負担が生じるのは初めて。

買い取り制度は、家庭や工場などに設置さ
れた太陽光発電システムで生じた電気のう
ち、使わなかった分を電力会社が1月から12
月まで買い取り、その費用を翌年度の電気
代に転嫁する仕組みだ。

※ (参考)太陽光発電促進単価表
各社の上乗せ額は、昨年1年間の太陽光発
電の買い取りにかかった費用から、太陽光
買い取りにより不要になった他の発電の燃
料費などを差し引き、来年度の想定電力需
要量で割って計算した。太陽光発電の導入
度合いや需要が各社で違うため、利用者に
求める負担額にもばらつきがあるというの
だが、その調整は残件するが太陽光の普及
が本格化する。

【バイオ燃料@アフリカ】
暗黒大陸のアフリカ大陸。近年、最後に残
された巨大経済市場とし、注目を集めてい
る。世界の陸地の約20%を占めるアフリカ大
陸は、2008年の統計では世界人口の約14%に
当たる9億2T万人に達している。資源価格の
高騰などを追い風に安定成長し、アフリカ
諸国全体の1998~ 2006年の国内総生産(GDP)
は年間成長率が43%に達している。
南アフリカ共和国では、国民1人当たりの
GDPでは中国 インドを上回るほどの経済発
展を遂げているほか、他のアフリカ諸国に
おいて、消費の担い手である中流層が台頭
している。最後の巨大市場であるアフリカ
諸国と先進国との経済交流が進展する中、
これらアフリカ諸国の植物バイオ燃料の開
発に大きな注目が集まっている。
サハラ砂漠以南のアフリカ諸国は、ナイジ
ェリア、カメルーン、コンゴなどで石油が
産出され、南アフリカ共和国などでは石炭
が産出。化石エネルギー資源を産出しない
国も多く、全体としてはエネルギー輸入国
が多い。また、アフリカ53諸国のうち半数
以上が京都議定書(第3回気候変動枠組条約
締結)を批准し、自国における温室効果ガス
の排出削減の義務を負っている。また、バ
イオ燃料を含めた循環型エネルギーに対し
国際的な関心が高まりっている。

植物バイオ燃料の生産性はその土地の気候
風土に依存、その地域に適合した植物種を
選択することが重要。アフリカにおけるバ
イオ燃料植物には、ソルガム、サトウキビ
トウモロコシ、キャッサバや、ヤトロファ
などが挙げられる。ソルガム(モロコシ)
はアフリカの多くの地域で主食として、最
も一般的な穀物であり、世界全体のソルガ
ム年間生産量の約40%に当たる2500万tが、
アフリカ人陸で生産されている。ソルガム
はC4型の光合成代謝を営み、高温や乾燥に
強い性質を持つ。またソルガムは品種間で
の遺伝的多様性が高く、育種研究の発展で
生産性の拡大が見込まれるため、耕作限界
地でのバイオ燃料作物として期待される。
サトウキビもC4作物で、概して高温や乾燥
に耐性が高い。サトウキビは世界百カ国以
上で栽培され、世界の主要作物のうち総収
穫量が最大。サトウキビからのバイオ燃料
生産は、南米ブラジルにおける先駆的な例
が有名だが、アフリカでは大陸南東部のマ
ラウイ共和国の例が知られるい。マラウイ
では1982年より、サトウキビの糖蜜のエタ
ノール生産が開始され、ガソリンと1:9で
混合するいわゆるE10の生産とエタノール
混合燃料に適合したFFV(nexible-fllel vehicle)
車の導入が国家主導で進められている。

【ヤトロファをめぐる動向】
最も注目を集めている植物はヤトロファ(
和名:ナンヨウアブラギリ)。ヤトロファは
中米メキシコ付近が原産地のトウダイグサ
科の樹木で、長さ2cmほどの種子は25~ 40
%程度の脂肪分を含む。単位ヘクタール面
積Jlたり1,300での油脂生産量は、植物の
中ではパームに次いで高い。ヤトロファの
生長は早く、定植して1年目から収穫が可
能である。ヤトロファは乾燥や高温に比較
的強く、食糧生産に適さない荒廃地でも生
育可能だ。アフリカ大陸におけるヤトロフ
ァの栽培総面積は、2008年には7万3千haと
推計され、2010年にはその約9倍の63万ha
2015年には30倍近い200万haに達すると予
測されている。
バイオデイーゼル比率向上を掲げるEUは、
植物の原材料として、ヨーロッパ域内にお
けるナタネ、ヒマワリ等に加え、その植物
原料の供給源の海外依存例が増え、欧米資
本の主体的関与例は多い(タンザニア、ザ
ンビア、モザンビーク)。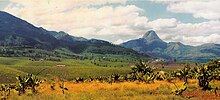
ボツワナ共和国は、驚異的な経済成長を達
成し、社会的政情的にも安定し、豊富なレ
アメタル鉱脈が発見され、中国に代わるレ
アメタル供給国としても注目されているが
ボツワナ経済は、その輸出総額の80%と国
家収入の50%を鉱山資源が占め不安定な国
際貿易に依存するリスクを抱える。そこで
ボツワナ政府は、国家の社会経済構造の多
様化を切望している。またボツワナ国民の
大部分は、農村部において肉牛の放牧や穀
物生産に従事し、雇用状況は安定していな
い。これら農村部における新規産業の振興
策も兼ねて、バイオ燃料生産、特にヤトロ
フアヘの関心が高まっている。
2007年にボツワナ資源省エネルギー局は、
ヤトロファのバイオデイーゼル燃料生産の
将来性が高いと結論付け、09年には今後10
年以内に国内ディーゼル油消費量の約10%
に当たる年間5,000万でのバイオデイーゼ
ル生産を達成する政府プランが公開された。
2004年よリボツワナ農務省農業研究部と、
カラハリ砂漠の野生植物資源に関する共同
研究を続けてきたが、社会ニーズの高まり
を受け研究開発を開始。

また、ボッヮナ国内のヤトロファ生産には、
①現地の乾燥冷害気候に適応したヤトロフ
ァ優良品種の選抜および育種が重要である
②この優良品種の確立においては、ボッヮ
ナの自国生物資源であるヤトロファ固有種
を利用することが有効と、③現地の乾燥冷
害気候に適応した農法の開発が必須である
こと、④ 改良された農法や優良ヤトロフ
ァ品種を、国内の農園や農家に提供する普
及システムを構築する必要がある。

これらの構想に基づいた共同研究がすでに
始動し、ヤトロファの栽培と育種に関する
技術体系が確立しているとは言い難く、乾
燥地での栽培法の確立に失敗し事業撤退す
る例も多く、実際には、栽培が容易な赤道
に近い多雨地帯での栽培が進んでいるのが
現状である。ヤトロファ研究開発の重要な
方向性は、乾燥地での生産効率をいかに向
上させるかである。これまでのアフリカに
おける経済活動は、コーヒー等のモノカル
チャーゃ、鉱物資源の輸出に依存する面が
大きく、アフリカ諸国における内需拡大に
は寄与しにくい面があったが、ヤトロファ
をはじめとするバイオ燃料開発では、高エ
ネルギーの油脂搾汁残汁等を利用した発電
や、バイオマスを利用した有機肥料の生産
など、デイーゼル油そのものの生産にとど
まらず、多面的な産業振興の可能性を内包
することを特徴とする。
尚、バイオ燃料として、Croton megalocarpus
は、肥料や灌水の要求量が低いバイオデイ
ーゼル植物として注目されている。

















