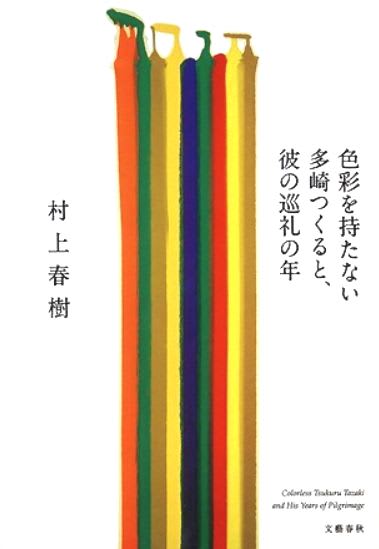今日はクーラーの修理に来るというので朝から落ち着かない。シャープの関連業者が家に来て一時
間ほど点検をしていたが、彼女のルーパーが作動しないというクレームの原因は結局のところ分か
らずじまいで帰って行った。やはり、一旦は自分自身で確認しておけば二度手間に済まずにおれた
ものをと少し悔いたが、彼女はわたしの腰をおもんばかってのことが反省点だ。そんなことで終始
落ち着かない一日となる。クーラー修理点検が終わってから、先日のブログの『ダイズとニンニク』
のフォローとして、昨日出された「豆腐ハンバーガー」が気になり、その創作料理について考察し
てみた。
調べてみてわかったことは、“Tofu Hanbuger” としてすでにグローバル化していることだった。市
販品としては、紀文の「豆腐と鶏のハンバーグ」「ひじき入り豆腐と鶏のハンバーグ」「豆腐と鶏
のデミグラスハンバーグ」「豆腐と鶏のたまとろハンバーグ」が販売されている。なお、「豆腐と
鶏のたまとろハンバーグ」は電子レンジでの加熱は禁止している。玉子が水蒸気による破裂を避け
るためだと考えられるが、予め水蒸気(空気)を逃がす微細孔を加工しておけばよい話しだが、コ
ストとリスクの再評価で解決できるだろう。
 Tofu Burgers
Tofu Burgers
 Grilled Lemon-Basil Tofu Burgers
Grilled Lemon-Basil Tofu Burgers
豆腐だけでなく、おからハンバーグもある。そして、魚肉ハンバーグも日本には、はんぺん、さ
つま揚などとして定着している。なぁ~~~んだ。それだけではない、豆腐素麺風が同じく紀文か
ら販売済みだ(下図/右)。なぁ~~~んだ。それじゃ、粉体化技術で、野菜ポリフェノールパウ
ダーとして、麺やバーガーに練り込めばもうこれはわたしの出番はないじゃないか。後は、ご当地
風にアレンジすれば世界を席巻してしまう。後は実行のみ、起業化のみということで話が終わって
しまう。

「フタに乾燥剤が内蔵された保存容器」(マルワ株式会社)がテレビで消火されていたが、電子レンジを使え
ば乾燥剤を捨てずに長期に使えるということだ。時代は確実に変わっている。
ところで、昼からは、ビールがきれたということで、白の金麦とヴォッカとスパーリング酒を買い
に出かけ、夕食前に、オイルサーディンをつまみに、ウイリキンソンのヴォッカ・ストレートをシ
ョット・グラスで飲んでいると空気清浄機の汚染センサ表示が赤くなる(汚れていることを表示)
ことを発見。ビールでは反応なしだったが、怖ろしやヴォッカとそのアルコール度を再確認した
次第。
食事のあと二人は渋谷まで歩いた。春も終わりに近い気持ちの良い夜で、大きな黄色の月が
霧に包まれていた。空気の中に漠然とした湿り気があった。彼女のワンピースの裾が風に吹か
れ、彼の隣で流れるように美しく揺れた。つくるは歩きながら、その衣服の内側にある肉体を
思い浮かべた。その肉体をもう一度抱くことを考えた。考えているうちにペニスが硬くなって
いく感覚があった。自分か感じているそのような欲望にとくに問題があるとは思えない。それ
は健康な成人男性として、自然な感情であり欲求だった。でもあるいはその根幹には、彼女が
指摘するように何か筋の通らない、歪んだものが含まれているのかもしれない、それは彼には
うまく判断できないことだっかに意識と無意識の境目について考えれば考えるほど、自分とい
うものがわからなくなった。
つくるはしばらく迷った末に、決心して切り出した。「この前に僕が言ったことで、ひとつ
訂正しておかなくちゃならないことがあるんだ」
沙羅は歩きながら興味深そうにつくるの顔を見た。「どんなこと?」
「これまで何人かの女性と交際した。どれもうまく実を結ばなかったけれど、それにはいろん
な事情もある。僕のせいばかりじゃないって言った」
「よく覚えている」
「僕はこの十年ほどの間に、三人か四人の女性とつきあった、どの場合もわりに長く真剣に。
遊びのつもりじゃなかった。そしてそれがうまくいかなかったのは、どの場合も主に僕のせい
だったと思う。彼女たちに何か問題があったわけじゃない]
「あなたの側にどんな問題があったの?」
「もちろんそれぞれに問題の傾向は少しずつ違っている」とつくるは言った。「でもひとつ具
通して言えるのは、僕が彼女たちの誰にも、本当に真剣には心を惹かれていなかったというこ
とだ。もちろん彼女たちのことが好きだったし、一緒にけっこう楽しい時を過ごした。良い思
い出はたくさん残っている。しかし自分を失ってしまうほど激しく相手を求めたことはなかっ
た」
沙羅は少し黙った。それから言った。「つまりあなたは十年間にわたって、それほど真剣に
は心を惹かれなかった女の人だちと、わりに長く真剣につきあっていたということ?」
「そういうことになると思う」
「私にはそれは、あまり理屈にかなったことに思えないんだけど」
「君の言うとおりだ」
「それはあなたの側に、結婚したくないとか、自由を束縛されたくないとか、そういう気持ち
があったからかしら?」
つくるは首を振った。「いや、結婚や束縛を恐れる気持ちはとくにないと思う。僕はむしろ
安定を求める性格だから]
「それでもあなたには常に精神的な抑制が働いていたのね?」
「働いていたかもしれない」
「だから心を全開にしなくて済む女性としか交際しなかった」
つくるは言った。「誰かを真剣に愛するようになり、必要とするようになり、そのあげくあ
る日突然、何の前置きもなくその相手がどこかに姿を消して、一人であとに取り残されること
を僕は怯えていたのかもしれない」
「だからあなたはいつも意識的にせよ無意識的にせよ、相手とのあいだに適当な距離を置くよ
うにしていた。あるいは適当な距離を置くことのできる女性を選んでいた。自分か傷つかずに
済むように。そういうこと?」
つくるは黙っていた。その沈黙は同意を意味していた。ただ同時に、問題の本質がそれだけ
ではないこともつくるにはわかっていた。
「そして私との間にもやはり同じことが起こるかもしれない]
「いや、そうは思わないな。君の場介はこれまでとは違うんだ。これは本当のことだよ。僕は
君に対して心を開きたいと思っている。心からそう思っている,だからこそこういう話もして
いるんだ」
沙羅は言った。[ねえ、私にもっと会いたい?」
「もちろん。もっと君と会っていたい」
[私もできることなら、あなたとこれからも会っていたいと思う]と沙羅は言った。「あなた
は良い人だと思うし、本来偽るところのない人だと思うから」
「ありがとう」とつくるは言った。
「だから四人の名前を私に教えて。あとのことはあなたが自分で決めればいい。いろんなこと
が明らかになった時点で、やはりその人たちと公いたくないと思うのなら、会わなければいい。
それはあくまであなた自身の問題だから。でもそのこととは別に、私は個人的にその人たちに
興味があるの。その四人についてもっとよく知りたいの。あなたの背中に今でも張り付いてい
る人たちのことを」
多時つくるは部屋に帰ると、机の抽牛から占い手帳を出し、住所録のページを開き、四人の
姓名と当時の住所と電話番けをラップトップの画面に正確にタイプした。
赤松慶(あかまつけい)
青海悦夫(おうみよしお)
白根柚木(しらねゆずき)
黒埜恵理(くろのえり)
画面に並んだ四人の名前をいろんな思いと共に眺めていると、既に通過したはずの時間が、
彼の周囲に立ち込めてくる気配があった。その過去の時間が、今ここに流れている現実の時間
に、音もなく混入し始めていた。ドアの僅かな隙間から、煙が部屋に忍び込んでくるみたいに。
それは匂いを持たない、無色の煙だった。でもある時点で彼はふと現実に戻り、ラップトップ
のキーをクリックし、メールを沙羅のアドレスに送った。それが送信されたことを確認し、コ
ンピュータの電源を落とした。そして時間が再び現実の位相に復していくのを待った。
「私は個人的にその人たちに興味があるの。その四人についてもっとよく知りたいの,あなた
の背中に今でも張り付いている人たちのことを」
沙羅の言っていることはおそらく正しい。つくるはベッドに横になってそう思った。その四
人は今でもまだ彼の背中に張り付いている。おそらくは沙羅が考えている以上にぴったりと。
ミスター・レッド
ミスター・ブルー
ミス・ホワイト
ミス・ブラック
第7章
父親が若い時に九州の山中の温泉で出会った、緑川というジャズ・ピアニストについての不
思議な話を灰田が語った夜、奇妙なことがいくつか起こった。
多時つくるは暗闇の中ではっと目を覚ました。彼を起こしたのはこつんという小さな乾いた
音だった。小石が窓ガラスにぶつかるような音だ。あるいは空耳だったかもしれない。確かな
ことはわからない。枕元の電気時計で時刻を見ようとしたが、首が曲がらなかった。首だけで
はなく、身体全体が動かなくなっている。蜂れているというのではない。ただ身体に力を入れ
ようと思っても、それができない。意識と筋肉がひとつに繋がらないのだ。
部屋は闇に包まれていた。つくるは明るいところで眠るのが苦手で、寝る時にはいつも厚い
カーテンをぴたりと引いて部屋を暗くする。だから外光は入ってこない。それでも自分以外の
誰かが室内にいることが気配でわかる。誰かが闇の中に潜んで、彼の姿を見つめている。擬態
する動物のように息を殺し、匂いを消し、色を変え、闇に身を沈めている。でもそれが灰田で
あることがつくるにはなぜかわかった。
ミスター・グレイ。
灰色は白と黒を混ぜて作り出される。そして濃さを変え、様々な段階の闇の中に容易に溶け
込むことができる。
灰田は暗い部屋の隅に立ち、ベッドに仰向けに寝たつくるをただじっと見下ろしていた。ま
るで彫像のふりをするパントマイムの芸人のように、彼は長い時間筋肉ひとつ動かさなかった。
そこで辛うじて動きを見せていたのはおそらくは彼の長い睫だけだ。それは奇妙な対照だった。
灰田が自らの意図でほぼ完璧に静止している一方、つくるは自らの意図に反して体を動かすこ
とができない。何かを言わなくては、とつくるは思った。何かを口にして、この幻しい均衡を
突き崩す必要がある。しかし声は出なかった。唇を動かすことも、舌を動かすこともできない,
喉から洩れ出てくるのは無音の乾いた息だけだ。
灰田はこの部屋で何をしているのだろう? なぜそこに立ち、それほど深くつくるを凝視し
ているのだろう?
これは夢ではない、とつくるは思う。夢にしてはすべてが克明にすぎる。でもそこに立って
いるのが本物の沃田なのかどうか、つくるには判断がつかなかった。本物の灰田は、その現実
の肉体は、隣室のソファの上でぐっすり眠っており、ここにいるのはそこから離脱してやって
きた灰田の分身のようなものなのではないか。そういう気がした。
しかしつくるはそれを不穏なもの、邪なものとしては感じなかった。何かあるにせよ、灰田
が自分に対して良からざることをするはずはない--そういう確信に近いものがつくるにはあ
った。それは初めて彼に出会ったときから一貫して感じていたことだった。いわば本能的に。
アカも確かに頭が切れたが、彼の頭の良さはどちらかといえば実際的であり、場合によって
功利的な側面を持ち介わせていた。それに比べて灰田の頭の良さはより純粋であり、原理的だ
った。自己完結的ですらあった。二人で場を共にしながら、灰田が今何を考えているのか、把
握できなくなることが時折あった。相手の頭の中で何かが盛んに進行しているらしいが、その
何かがどういう種類のものなのか、つくるには見当がつかない。そういう時にはもちろん戸惑
いを感じたし、自分一人あとに取り残されたような気持ちにもなった。しかしそんな場合でも、
彼がその年下の友人に対して不安や苛立ちを感じることはまずなかった。相手の頭の回転の速
度と、活動領域の広さが、自分のそれとはレベルが違っているだけなのだ。つくるはそう思っ
て、相手のペースについていくことをあきらめた。
灰田の脳内にはおそらく、彼の思考スピードに合わせてこしらえられた高速サーキットのよ
うなものがあり、彼は時々そこで本来のギアを使った走行を一定時間こなさなくてはならない
のだろう。そうしないと--つくるの凡庸なスピードにつきあってローギア走行を続けている
と--彼の思考システムは過熱し、微妙な狂いを見せ始めるのかもしれない。そんな印象があ
った。しばらくすると沃田はそのサーキットから降りて、何ごともなかったように穏やかな笑
みを浮かべ、つくるのいる場所に戻ってきた。そして速度を緩め、またつくるの思考のペース
に合わせてくれた。
どれくらい長くその濃密な凝視が続いたのだろう。つくるには時間の長短が判別できなかっ
た。灰田は真夜中の闇に静止し、無言のうちにつくるを見つめていた。灰田には何か語りかけ
たいことがあるようだった。どうしても伝えなくてはならないメッセージを彼は拍えている。
しかし何らかの理由があって、そのメッセージを現実の言葉に転換することができない。それ
がその年下の聡明な友人を、いつになく苛立たせているのだ。
つくるはベッドに横たわりながら、先刻聞いた緑川の話をふと思い起こした。死を目前に控
えた--少なくとも本人はそう王張する--緑川が中学校の音楽室でピアノを弾いたとき、楽
器の上に置かれた布の袋の中には何が入っていたのか? その謎が明かされないまま阪田の話
は終わっていた。つくるにはその袋の中身が気になってならなかった。誰かが彼にその袋の意
味を敦えてくれるべきなのだ。なぜ緑川はその袋をピアノの上に大事そうに置いたのか? そ
れはその物語の重要なポイントになっているはずだ。
しかしその答えが与えられることはなかった。長い沈黙の末に灰田は--あるいは灰田の分
身は--密やかにそこを去って行った。最後に彼の浅い吐息を耳にしたような気がしたが、定
かではない。線香の煙が宙に吸い込まれていくように灰田の気配が薄らいで消え、気がついた
ときつくるは一人で暗い部屋に取り残されていた。相変わらず身体は動かない。意識と筋肉を
結ぶケーブルは外されたままだ。結点のボルトは抜け落ちたままだ。
どこまでが現実なのだろう、とつくるは思った。これは夢ではない。幻影でもない。現実で
あるに違いない。しかしそこには現実の持つべき重みがない。
ミスター・グレイ。
それからつくるはもう一度眠りに落ちたのだろう。やがて披は夢の中に目を覚ました。いや、
正確にはそれを夢と呼ぶことはできないかもしれない。そこにあるのは、すべての夢の特質を
具えた現実だった。それは特殊な時刻に、特殊な場所に解き放たれた想像力だけが立ち上げる
ことのできる、異なった現実の相だった。
彼女たちは生まれたままの姿でベッドの中にいた。そして彼の両脇にぴたりと寄り添ってい
た。シロとクロ。彼女たちは十六歳か十七歳だった。彼女たちはなぜか常に十六歳か十七歳な
のだ。二人の乳房と太腿は、彼の身体に押しつけられていた。二人の肌のそれぞれの滑らかさ
と温もりを、つくるは鮮やかに感じとることができた。そして彼女たちの指と舌先は無討のま
ま、彼の身体を貪るようにまさぐった。彼もまた全裸だった。
それはつくるが求めている状況ではなかったし、彼が想像したい情景でもなかった。それは
そのように安易に彼にもたらされてはならないはずのものごとだった。しかし彼の意思に反し
て、そのイメージはますます鮮明に、感触はますます生々しく具体的なものになっていった。
女たちの指先は優しく絹く、繊細だった。四つの手と、二十の指先。それらは闇から生まれ
た視覚を持たない滑らかな生き物たちのように、つくるの全身を隈無く徘徊し、刺激した。そ
こには彼がこれまで感じたことのない激しい心の震えがあったご長いあいだ暮らしていた家屋
に、実は秘密の小部屋が存在していたことを教えられたような気持ちだった。心臓がケトルド
ラムのように小刻みに乾いた音を立てた。手足はまだすっかり棟れたままだ。指一本持ちにげ
ることができない。

女たちの肉体がつくるの全身にしなやかにまとわりつき、絡んだ。クロの乳房は豊満で柔ら
かかった。シロの、それは小ぶりだったが、乳首は丸い小石みたいに硬くなっていた。どちら
の陰毛も雨林のように湿っていた。彼女たちの息づかいが、彼自身の息づかいともつれ合って
ひとつになった。遠くからやってきた潮流が、暗い海の底で人知れず重なり合うように。
長い執拗な愛撫のあとで、彼女たちのうちの一人のヴァギナの中に彼は入っていた。相手は
シロたった。彼女はつくるの上にまたがり、彼の硬く直立した性器を手にとって、手際よく自
分の中に導いた。それはまるで真空に吸い込まれるように、何の抵抗もなく彼女の中に入った。
それを少し落ち着かせ、息を整えてから、彼女は複雑な図形を宙に描くようにゆっくり上半身
を回転させ、腰をくねらせた?長いまっすぐな黒髪が、鞭を振るうように彼の頭上でしなやか
に揺れかこ普段のシロからは考えられない大胆な動きだ。
しかしシロにとってもクロにとっても、それはきわめて当然なものごとの流れであるようだ
った。考慮する余地もないことだ。彼女たちにはためらいの気配はまったく見えなかった。愛
撫をするのは二人一緒だが、彼が挿入する相手はシロなのだ。なぜシロなんだろう、とつくる
は深い混乱の中で考えを巡らせた。なぜシロでなくてはならないのだろう? 彼女たちはあく
まで均等であるべきなのに。二人でひとつの存在であるべきなのに。
その先を考えるだけの余裕はなかった.、彼女の動きはだんだん速く、大きくなっていった、
そして気がついた時には、彼はシロの中に激しく射精していた。挿入から射精までの時間は短
かった。短すぎる、とつくるは思った。あまりに短すぎる。いや、それとも正しい時間の感覚
が失われているのだろうか。いずれにせよその衝動を押しとどめることは不可能だっかこまる
で頭Lから落ちかかる大波のように、予告もなくそれはやってきた。
しかし射精を実際に受け止めたのは、シロではなく、なぜか灰田たった。気がついたとき女
たちはもう姿を消し、阪田がそこにいた。射精の瞬間、彼は素早く身をかがめてつくるのペニ
スを□に含み、シーツを汚さないように、吐き出される精液を受けた。射精は激しく、精液の
量はずいぶん多かった。沃田は何度にもわたる射精を辛抱強く引き受け、一段落したところで、
あとをきれいに舌で猷めて取った。彼はそういう作業に手慣れているようだった。すくなくと
もつくるにはそう感じられた。それから阪田は静かにベッドを出て洗面所に行った。蛇口から
水を出す音がしばらく続いた。たぶん目をゆすいでいるのだろう。
射精したあとも、つくるの勃起は収まらなかった。シロの温かく湿った性器の感触はまだ生
々しくそこに残っていた。まるで現実の性行為を体験した直後のように。夢と想像との境目が、
想像とリアリティーの境目がまだうまく見きわめられない。
つくるは暗闇の中に言葉を探した。特定の誰かに向けられる言葉ではない。ただそこにある
無言の、無名の隙間を埋めるために、正しい言葉をひとつでも見つけなくてはならない。洗面
所から沃田が戻ってくる前に、しかしそれは見つからない。その間ずっと彼の頭にはシンプル
なひとつのメロディーが繰り返し流れていた。それがリストの『ル・マル・デユ・ペイ』の主
題であることに思い当たったのは、あとになってからだった、巡礼の年、第一年、スイス。
田園の風景が人の心に喚起する憂僻。
それから暴力的なまでに深い眠りが彼を包み込んだ。
目が覚めたのは朝の八時前たった。
起きてまず、自分が上着の中に射精していないかを確かめた。そんな性夢を見たときには、
必ず射精のあとが残っている,しかしそれはなかった。つくるにはわけがわからなかった。自
分は確かに夢の中で-少なくとも現実の世界ではない場所で-射精をしたのだ。とても激しく。
その感覚はまだ身体にはっきり残っている,。大量の現実の精液が放出されたはずだった。し
かし痕跡はない。
それから披は灰田が□でその射精を受けたことを思い出した。
彼は目を閉じ、顔を軽く歪めた。それは実際に起こったことなのだろうか? いや、そんな
はずはない。すべてはおれの意識の暗い内側で起こったことだ。どう考えても。それでは、あ
の精液はいったいどこに放出されたのだろう? それもまた意識の奥深くに消えてしまったの
か?
つくるは混乱した心を抱えたままベッドを出て、パジャマ姿で台所に行ったで灰田は既に服
を着替え、ソファに横になって分厚い本を読んでいた。彼はその本に意識を集中し、別の世界
に心を移しているように見えた。しかしつくるが顔を見せるとすぐに本を閉じ、明るい笑みを
浮かべ、台所でコーヒーとオムレツとトーストを用意した。新鮮なコーヒーの香りがした。夜
と昼とを隔てる香りだ。二人はテーブルをはさみ、小さな音で音楽を聴きながら朝食をとった。
灰田はいつものように、濃く焼いたトーストに薄く蜂蜜を塗って食べた。
灰田は食卓では、新しくどこかで見つけてきたコーヒ豆の味について、その焙煎の質の良さ
についてひとしきり意見を述べただけで、あとは一人で何かを考えていた。たぶんそれまで読
んでいた本の内容について思考を巡らせていたのだろう。架空の一点に焦点を結んだ一対の瞳
が、そのことを告げていた。きれいに透きとおってはいるものの、その奥には何もうかがえな
い。彼が抽象的な命題について思考するときに見せる目だ。それはいつも樹本の隙問から見え
る山中の泉をつくるに思い出させた。
灰田の様子には普段と違うところは見受けられなかった。いつもの日曜日の朝と変わりない。
空は淡く曇っていたが、光は柔らかかった。話をするとき、彼はまっすぐつくるの目を見て話
した。そこには何の含みもなかった。たぶん現実には何も起こらなかったのだろう。あれはや
はり意識の内側で生み出された妄想だったのだ。つくるはそう思った。そしてそのことを恥じ
ると同時に、激しい困惑に襲われた。彼はこれまで何度も、シロとクロが登場する同じような
性夢を体験していた。その夢は彼の意思とは関わりなくほぼ定期的にやってきて、彼を射精に
導いた。しかしこれほど一貫して生々しくリアルなものは初めてだった。そして何よりもそこ
に灰田が加わっていたことがつくるを混乱させた。しかしつくるはそれ以上その問題を追及し
ないことにした。どれだけ深く考えても解答は得られそうにない。彼はその疑問を「未決」と
いう名札のついた抽斗のひとつに入れ、後日の検証にまわすことにした。彼の中にはそんな抽
牛がいくつもあり、多くの疑問がそこに置き去りにされている。
そのあとつくると灰田は大学のプールに行き、一緒に三十分泳いだ。日曜の朝のプールは人
影がまばらで、好きなペースで心ゆくまで泳ぐことができた。つくるは必要な筋肉を的確に動
かすことに意識を集中した、背筋、腸腰筋、腹筋。ブレスとキックについてはとくに考える必
要はない。いったんリズムが生まれれば、あとは無意識の動きになる。いつも灰田が先を泳ぎ、
つくるがそれについていった。灰田の柔らかなキックが小さな白い泡をリズミカルに水中につ
くり出す光景を、つくるは無心に眺めていた。その光景は彼に常に軽い意識の麻痺状態をもた
らした。
シャワーを浴び、ロッカールームで着替えたあと、灰田の目は先刻の透徹した光を失い、普
段の物静かな目に戻っていた。たっぷり身体を動かしたことで、つくるの中にあった混乱もど
うやら収まっていた。二人は体育館を出て、図書館まで並んで歩いた。その間彼らはほとんど
口をきかなかったが、それはとりたてて珍しいことではなかった。これから図書館で少し調べ
ものをしたい、と灰田は言った、それもとくに珍しいことではない。灰田は回書館で「調べも
の」をするのが好きだった。それはおおむね「しばらく一人になりたい」ということを意味し
ていた。「家に帰って洗濯をするよ」とつくるは言った。
図書館の前まで来ると、二人は軽く手を振って別れた、
それからしばらく灰田からは連絡がなかった。プールでも大学の構内でも、灰田の姿を見か
けることはなかった。つくるは灰田と知り合う以前のように、一人で黙々と食事をとり、プー
ルに行って一人で泳ぎ、講義に出てノートを取り、外国語の単語や構文を機械的に記憶すると
いう生活を送った。静かで孤独な生活だった。時間は彼のまわりを淡々と、ほとんど痕跡すら
残さず過ぎ去っていった。ときどき『巡礼の年』のレコードをターンテーブルに載せ、耳を傾
けた。
一週間ばかり音沙汰がなかったあとで、灰田はもうおれには会わないことに決めたのかもし
れない、とつくるは思った。それはあり得ないことではなかった。彼は前おきもなく、理由も
告げず、どこかに去って行ったのだ。かつて故郷の街であの四人がそうしたのと同じように。
その年ドの友人が自分から離れていったのは、あの夜におれが体験した生々しい性夢のせい
かもしれない、とつくるは思った。灰田は何らかのルートを通じて、おれの意識の中で行われ
たことの一部始終を察知し、それに不快感を持ったのかもしれない。あるいは腹を立てたのか
もしれない。
いや、そんなことがあるわけはない。それはつくるの意識から外に出るはずのないものごと
だ。その内容を沢田が知る筋道はどこにもないはずだ。それでもつくるには、自分の意識の奥
底にあるいくつかの歪んだ要素を、その年下の友人の明晰な目が鋭く見通しているようにも思
えた。そう考えると自分が恥ずかしくてならなかった。
いずれにせよ、灰田の存在が消えてしまうと、その友人が自分にとってどれほど大事な意味
を持っていたか、日々の生活をどれほど色彩豊かなものに変えてくれていたか、つくるはあら
ためて実感した。沃田と交わした様々な会話や、彼の特徴のある軽やかな笑い声が懐かしく思
い出された。彼の好きな音楽や、ときどき読み上げてくれる本や、彼の解説する世間の事象や、
その独特のユーモアや、的確な引用や、彼のこしらえてくれる食事、作ってくれるコーヒー。
灰田があとに残していった空白を、彼は日常生活のいたるところに見出すことになった。
そのような彼が与えてくれたものに対して、こちらから灰田にいったい何を与えることがで
きただろう、とつくるは考えないわけにはいかなかった。おれはその友人の中にいったい何を
残せただろう?
おれは結局のところ、一人ぼっちになるように運命づけられているのかもしれない。つくる
はそう思わずにはいられなかった。人々はみんな彼のもとにやってきて、やがて去っていく。
彼らはつくるの中に何かを求めるのだが、それがうまく見つからず、あるいは見つかっても気
に入らず、あきらめて(あるいは失望し、腹を包てて)立ち去っていくようだ。彼らはある日、
出し抜けに姿を消してしまう。説明もなく、まともな別れの挨拶さえなく。温かい血の通って
いる。まだ静かに脈を打っている絆を、鋭い無音の大蛇ですっぱり断ち切るみたいに。
自分の中には根本的に、何かしら人をがっかりさせるものがあるに違いない。色彩を欠いた
多崎つくる、と彼は声に出して言った、結局のところ、人に向けて差し出せるものを、おれは
何ひとつ持ち合わせていないのだろう。いや、そんなことを言えば、自分自身に向けて差し出
せるものだって持ち合わせていないかもしれない。
しかし図書館の前で別れてから十日目の朝に、灰田は大学のプールにひょっこり姿を見せた。
つくるが何度目かのターンをしようとしたとき、壁に触れた右手の甲を誰かがとんとんと軽く
指で叩いた。顔をLげると、そこに水着姿の灰田がしゃがみ込んでいた。黒いゴーグルが額に
あげられ、□もとにはいつもの心地よさそうな微笑みが浮かんでいた。二人は久しぶりに顔を
合わせても、とくに言葉を交わすでもなく、小さく肯きあっただけで、あとは普段と同じよう
に、同じレーンで一緒に長い距離を泳いだ。柔らかな筋肉の動きと、穏やかで規則正しいキッ
クのリズムが、水中で二人の間に交わされる唯一のコミユニケーションだった。そこには言葉
は不要だった。
「しばらく秋田に帰っていました」。プールから上がり、シャワーを浴びたあと、タオルで髪
を拭きながら灰田は目を開いた。「急だったんですが、やむを得ない家庭の事情があったもの
で」
つくるは曖昧な返事をして、肯いた。学期の真ん中で十日も学校を留守にするのは、灰田と
してはとても珍しいことだ。彼もまたつくると同じように、よほどのことがなければ講義を休
まなかった。だからおそらく大事な用件であったに違いない。しかし帰郷の目的について、彼
は自分からはそれ以上何も語らなかったし、つくるもあえて尋ねなかった。ともあれその年下
の友人が何ごともなく戻ってきたことで、つくるは胸のどこかにつかえていた空気の重いかた
まりのようなものを、なんとかうまく外に吐き出すことができた。胸のつかえが取れたような
感触があった。彼はつくるを見かぎって姿を消したわけではなかったのだ。
PP.107-125
村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』