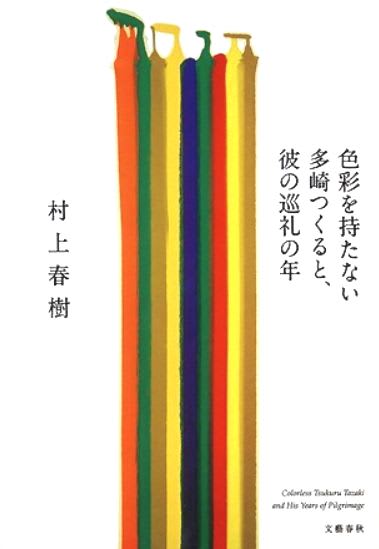【樹冠都市構想】
樹冠都市構想という、まちづくり未来図があるという。動植物の生態・構造を模倣した未来都市と
いう。バイオミミクリーとは生物摸倣とも表し、勤植物の生態や構造を分析し模倣することで、よ
りサステナブルな新しい技術を生み出すこころみだと。そのバイオミミクリーの技術を駆使した未
来の都市の構想、それが「樹冠都市」なのだ。この未来都市は、緑に覆われている。自然を征服する
べき対象と見るのではなく、人と他の種が同じ価値を持つというディープ・エコロジーの考え方も
反映させ、都市と森林が融合している。
人々が居住するのは、高さ二百メートル、地上63階の超高層住宅。アスパラガスにも見えるこの住
宅の建築材には、鉄筋コンクリートの数倍の強度を持つアワビの殻から生まれた新素材が使われ、
この住居は、地上から七階までが吹き抜けになっている。これは、アフリカのサバンナに生息する白
蟻の巣の構造を模したものだという。この白蟻の巣は土の上に盛り上がった巨大な塚のようになっ
ているのだが、内部は吹き抜けで、地下の湿った冷気を利用した気化熱で叫の中の温度を調整してい
る。その結結果、昼間50℃にも達し、夜はゼロ℃になる過酷な環境ににありながら、巣の中は30℃
前後に保たれる。さらに、チムニー効果と土の通気性で、巣の中は常に空気が循環している。アス
パラガス住居は、この構造を取り入れて、電気のいらない空調、換気システムを実現。また、年間
を通して安定した温度に保たれている地表に近い地下にチューブを通し、森と住居を繋ぐことで、夏
は涼しく、冬は暖かい空気を住居に送り込んでいる。
この住居の1フロアの住民数は約50人。フロアの各地に井戸端スペースが設けられていて、住民同
士の交流の場になっている。樹冠都市では、人間活動による環境負荷を減らすために、人間が占有
する地表面積をなるべく小さくなるよう設計されていて、例えば単身者用の小住宅は2メートル四方
と小ぶりなつくりだが、その分、井戸端スペースに人が集まる。シェアハウスのようなイメージだ。
藤森照信工学院大学教授によるこのような記事を読んでいたら、映画「スターウォーズ エピソード
1/ファントム・メナス」やジョージルーカスを思いだし、本棚にあった「スターウォーズ エピソード
1/ファントム・メナス」(ソニーマガジンズ)を取りページをめくりながら、チューイングガムを噛むように、“柔
軟で自由な発想時代”を懐かし思い出していた。

【スターウォーズ エピソード1/ファントム・メナス】

マルチ・トルーブ・トランスポート「大型兵員輸送車=MTT」
MTTのコンセプト・デザイン・モデル:ルーカスは巨大で、蒸気機関車を思わせ、ホパー移動し、
沼だろうが何だろうが、お構いなしに突き進んでいくような乗り物を要求していた。そこで、ダク・
チャンは衛角艦を思わせるデザインを揚いたその後、いかにも蒸気機関車らしく、かつリポルパー
拳銃の回転弾装を洗練させたようなデサインを試し、最終的に「おでこが高い位置にあり、回転砲
という「牙」を持った動物--今回は象なのたか ペースのデザインになった。ルーカスはこのデ
ザインを気に入り、タク・チャンはこれを多少洗練させて完ぼバージコンに仕上げたという。
すべてのデザインは
デザインのためのものであってはならない
ジョージ・ルーカス

「彼があなたに話したのはそれだけ?」と沙羅が尋ねた。
「とても短いミニマルな会話だった。これ以上正確に再現のしようもないよ」とつくるは言っ
た。
二人はバーの小さなテーブルをはさんで話をしていた。
「そのあと彼と、あるいは他の三人の誰かと、そのことについて話をする機会はあった?」と
沙羅は尋ねた。
つくるは首を振った。「いや、それ以来誰とも何も話していない」
沙羅は目を細めてつくるの顔を見た。物理的に理屈の通らない風景を検証するみたいに。
「まったく誰とも?」誰とも会ってもいないし、話してもいない」
沙羅は言った。「どうして自分がそのグループから突然放り出されなくてはならなかったの
か、その理由を知りたいとは思わなかったの?」
「どう言えばいいんだろう、そのときの僕には、何もかもがどうでもよくなってしまったんだ。
鼻先でぴしゃりとドアが閉められ、もう中に入れてもらえなくなった。その理由も教えてもら
えなかった。でももしそれがみんなの求めていることなら、それで仕方ないじゃないかと思っ
た」
「よくわからないな」と沙羅は本当によくわからないように言った。「それは誤解がもとで起
こったことかもしれないじゃない。だってあなたの方には思い当たる節がまるでなかったんで
しょう? そういうのを残念だとは思わなかったの? つまらないずれ違いが原因で、大事な
友だちをなくしてしまったかもしれないことを。努力すれば修正できたかもしれない誤解を修
正しなかったことを」
つくるは小さく首を振った。「明くる日の朝、家族には適当な理由をつけ、そのまま新幹線
に乗って東京に帰った。何はともあれそれ以上一日も名古屋に留まりたくなかった。それ以外
のことは考えられなかった」
「もし私があなただったらそこに留まって、納得がいくまで原因を突き止めるけどな」と沙羅
は言った。
「僕はそこまで強くなかったんだ」とつくるは言った。
「真相を知りたいとは思わなかったの?」
つくるはテーブルの上に置いた自分の両手を眺めながら注意深く言葉を選んだ。「その原因
を追及して、そこでどんな事実が明るみに出されるのか、それを目にするのがきっと怖かった
んだと思う。真相がどのようなものであれ、それが僕の款いになるとは思えなかった。どうし
てかはわからないけど、そういう確信のようなものがあったんだ」
「今でもその確信はあるの?」
「どうだろう」とつくるは言った。「でもそのときはあった」
「だから東京に戻って一人で部屋にこもり、目をつぶり、耳を塞いでいた」
「簡単にいえば」
沙羅は手を仲ばし、テーブルに置かれたつくるの手に重ねた。「かわいそうな多崎つくるく
ん」と彼女は言った。その柔らかな手のひらの感触が、彼の全身にゆっくり伝わっていった。
少しあとで彼女は手を難し、ワイングラスを口に運んだ。
「それ以来、名古屋には必要最低限しか帰っていない」とつくるは言った。「用事があって帰
郷しても、なるべく家から出ないようにしていたし、用事が終わればすぐに東京に戻った。母
と姉たちは心配して、何かあったのかとしつこく尋ねたけど、僕はいっさい説明をしなかった。
そんなことはとても口に出せない」
「その四人が今どこにいて、何をしているか、そういうことは知っている?」
「いや、何も知らないな。誰も敦えてくれなかったし、正直言って知りたいとも思わなかった
から」
彼女はグラスを回して赤ワインを揺らせ、その波紋をしばらく眺めていた。誰かの運勢でも
見るみたいに。それから□を開いた。
「それは私にはずいぶん不思議なことに思える。つまり、そのときの出来事はあなたの心に大
きなショックを与えたし、あなたの人生をある程度書き変えてしまった。そうよね?」
つくるは短く肯いた。「僕はそれが起こる以前とは、いろんな意味あいで、少し違う人間に
なってしまったと思う」
「たとえばどんな意味あいで?」
「たとえば、自分が他人にとって取るに足らない、つまらない人間だと感じることが多くなっ
たかもしれない。あるいは僕自身にとっても」
沙羅は彼の目をしばらくじっと見ていた。それから真剣な声で言った。「あなたは取るに足
らない人間でもないし、つまらない人間でもないと思う」
「ありがとう」とつくるは言った。そして自分のこめかみを指先でそっと押さえた。「でもそ
れは僕の頭の中の問題なんだ」
「まだよくわからないな」と沙羅は言った。「あなたの頭には、あるいは心には、それともそ
の両方には、まだそのときの傷が残っている。たぶんかなりはっきりと。なのに自分がなぜそ
んな目にあわされたのか、この十五年か十六年の間その理由を追及しようともしなかった」
「なにも真実を知りたくないというんじゃない。でも今となっては、そんなことは忘れ去って
しまった方がいいような気がするんだ。ずっと昔に起こったことだし、既に深いところに沈め
てしまったものだし」
沙羅は薄い唇をいったんまっすぐ結び、それから言った。「それはきっと危険なことよ」
「危険なこと」とつくるは言った。「どんな風に?」
「記憶をどこかにうまく隠せたとしても、深いところにしっかり沈めたとしても、それがもた
らした歴史を消すことはできない」。沙羅は彼の目をまっすぐ見て言った。「それだけは覚え
ておいた方がいいわ。歴史は消すことも、作りかえることもできないの。それはあなたという
存在を殺すのと同じだから」
「どうしてこんな話になってしまったんだろう?」、つくるは半ば自分自身に向けてそう言っ
た。むしろ明るい声で。「この話はこれまで誰にもしたことはなかったし、話すつもりもなか
ったんだけど」
沙羅は淡く微笑んだ。「誰かにその話をしちゃうことが必要だったからじゃないかしら。自
分で思っている以上に」
PP.35-40
村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』