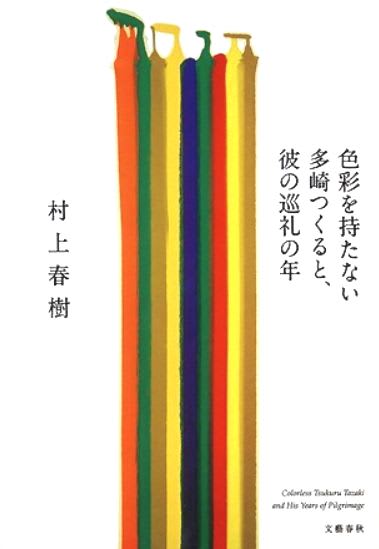【深志城情 その貳】



五月の終わり頃につくるは週末に繋げて休みを取り、三日間名古屋の実家に戻った。ちょう
ど父親の法事がその時期にあったので、帰郷するにはいろんな意味で都合がよかった。
父親が亡くなったあと、長姉の夫婦が母親とともにその広い家に住んでいたが、以前つくる
が使っていた部屋は、誰にも使われないまま取り置かれていたので、そこに寝泊まりすること
ができた。ベッドも机も本棚も、彼が高校生だったときのままになっていた。本棚には昔読ん
だ本が並んでいた。机の抽斗には文具やノートがまだ残っていた。
最初の日に寺での法要と親戚との会食を終え、家族との一通りの会話を済ませてしまうと、
翌日からは自由の身になった。つくるは最初にアオを訪問することにした。日曜日は普通の会
社は休みだが、自動車のショールームは営業している。誰に会うにせよアポイントメントはと
らず、行き当たりばったりで出かけて行く。それが前もって決めた方針だった。相手に心の準
備をさせず、その場でできるだけ率直な反応を引き出す。もしそこで会えなくても、あるいは
会うことを断られても、それはそれで仕方ない。その時は次の方法を考えればいい。
レクサスのショールームは名古屋城に近い静かな一画にあった。広々としたガラスのウィン
ドウの中には、スポーツクーペから四輪駆動車まで、色とりどりのレクサスの新車が晴れがま
しく並んでいた。中に入ると、新しいタイヤと合成樹脂と本革の匂いが混じり合った新車独特
の匂いがした。

つくるはレセプション・デスクに行って、そこに座った若い女性に話しかけた。彼女は髪を
上品に上にまとめ、ほっそりした白い首筋を表に出していた。デスクの花瓶にはダリアがピン
クと白の大きな花を咲かせていた。
「青海さんにお会いしたいのですが」と彼は言った。
彼女は明るく清潔なショールームに似合った穏やかな、整った微笑みを彼に向けた。唇が自
然な色に塗られ、歯並びが美しい。「はい。青海でございますね。失礼ですが、お客様のお名
前をいただけますでしょうか」
「多埼です」とつくるは言った。
「タサキ様。本日ご予約は承っておりますでしょうか?」
彼は名前の読み方の微妙な間違いをあえて指摘しなかった。その方がむしろ都合がいい。
「いや、予約はしていないんだけど」
「かしこまりました。少々お待ちいただけますでしょうか」。女性は電話の短縮番号を押して、
五秒ばかり待った。そして言った。「青海さん、タサキ様というお客様がこちらにお見えにな
っておられます。はい、そうです。タサキ様です」
相手が何を言ったのかは聞こえなかったが、彼女はそれに対して何度か短く相づちを打った。
そして最後に「はい、承知しました」と言った。
彼女は受話器を置き、つくるを見上げて言った。「タサキ様。青海はただ今所用があり、手
を離すことができません。まことに恐縮ですが、ここで今しばらくお待ちいただけますでしょ
うか? 十分とはかからないと本人は申しておりますが」
訓練された滑らかなしゃべり方だった。敬語の使い方も間違っていない。そして待たせるこ
とを本心から申し訳なく思っているように聞こえた。教育が行き届いている。あるいはそうい
うのは生来のものなのだろうか?

「いいですよ。べつに急いではいないから」とつくるは言った。
彼女はつくるをいかにも高価そうな黒い革張りのソファに案内した。巨大な観葉槙物の鉢が
あり、小さな音でアントニオ・カルロス・ジョビンの曲が流れていた。細長いガラスのテーブ
ルの上にはレクサスの豪華なカタログが並べられていた。
「コーヒーか紅茶か日本茶をお持ちできますが」
「じゃあ、コーヒーをください」とつくるは言った。

彼がレクサスの新しいセダンのカタログを眺めていると、コーヒーが運ばれてきた。クリー
ム色のマグカップにはレクサスのロゴが入っていた。つくるは彼女に礼を言って、それを飲ん
だ。美味いコーヒーだった。香りが新鮮で、温度もちょうどいい。
スーツを着て、革靴を履いてきて正解だったようだとつくるは思った。レクサスを買いに来
る人間が普通どんな服装をしているのか、つくるには見当もつかない。しかしポロシャツにジ
ーンズ、スニーカーという格好では軽く見られるかもしれない。家を出る前にふとそう思って、
念のためにスーツに着替え、ネクタイを締めてきた。
十五分ほど待っている間につくるは、販売されているレクサスの車種をすべて覚えてしまっ
た。そこでわかったのは、レクサスの車には「カローラ」や「クラウン」といった名称がつい
ていないので、車種は番号で覚えるしかないということだった。メルセデスやBMWと同じだ。
あるいはブラームスの交響曲と同じだ。
やがて背の高い男が、ショールームを横切ってやってきた。横幅もある。でも大きな体躯の
わりに身のこなしは機敏だ。歩幅は大きく、自分が比較的急いで空間を移動していることをま
わりにそれとなく示唆している。それは間違いなくアオたった。遠くから見ても、昔と印象は
ほとんど変わりない。身体がひとまわり大きくなっただけだ。家族が増えて家屋が増築される
みたいに。つくるはカタログをテーブルに戻し、ソファから立ち上がって彼を迎えた。
「お待たせいたしまして、申し訳ありませんでした。青海です」
アオはつくるの前に立ち、軽く頭を下げた。その大きな身体はしわひとつないスーツに包ま
れていた。青とグレーが混じった、軽い生地の上品なスーツだ。体型からしてきっとオーダー
メイドだろう。淡いグレーのシャツに、濃いグレーのネクタイ。隙のない着こなしだ。学生時
代の彼からは考えられない。しかし髪だけは相変わらず短い。ラグビー選手の髪型だ。そして
やはりよく日焼けしている。
それからつくるを見るアオの顔つきが少しだけ変化した。目に微かな戸惑いの色が浮かんだ。
彼はつくるの顔に覚えのある何かを読み取ったようだった。しかしそれが何であるかがうまく
思い出せない。彼は笑顔を浮かべ、言葉を呑み込んだまま、つくるが何かを口にするのを待っ
ていた。
「久しぶりだな」とつくるは言った。
その声を聞いて、アオの顔を覆っていた淡い疑念のようなものが急に晴れた。声だけは変わ
っていない。
「つくるか」と彼は目を細めて言った。
つくるは肯いた。「仕事場に突然押しかけて悪かった。でもそれがいちばんいいような気が
したんだ」
アオは肩で大きく息を吸い込み、ゆっくり吐き出した。それからつくるの全身を点検するよ
うに眺めた。上から下に徐々に視線を落とし、また上に戻した。
「ずいぶん見かけが変わったな」と彼は感心したように言った。「通りですれ違っても、まず
気がつかないだろう」
「そちらはぜんぜん変わらないみたいだ」
アオは大きな口を少し斜めに曲げた。「いや。体重は増えた。腹も出てきた。速く走れなく
なった。最近は月いちの接待ゴルフしかやってないからな」
しばしの沈黙があった。
「なあ、ここに車を買いに来たわけじゃないよな?」とアオは確かめるように言った。
「車を買いに来たわけじゃない。悪いけど。できれば二人で話をしたいんだ。短い時間でもか
まわない」
アオは少し顔をしかめた。どうすればいいものか、彼は迷っていた。昔から、思っているこ
とがそのまま顔に出てしまう性格だ。
「今日はかなり予定が詰まっているんだ。外回りもあるし、午後はミーティングに出ることに
なっている」
「都合のいい時間を指定してくれればいい。そちらに合わせる。今回はそのために名古屋に来
たんだ」
アオは頭の中でスケジュールを洗い直しか。そして壁の時計に目をやった。時計の針は十一
時半を指していた。彼は鼻の頭を指でごしごしこすってから、心を定めたように言った。「わ
かった。おれは十二時に昼休みをとる。三十分くらいなら話ができるだろう。ここを出て左に
しばらく歩いたところにスターバックスがある。そこで待っていてくれ」

十二時五分前にアオはスターバックスに現れた。
「ここはうるさい。飲み物を買ってどこか静かなところに行こう」とアオは言った。そして自
分のためにカプチーノとスコーンを買った。つくるはミネラル・ウオーターのボトルを買った。
それから二人は歩いて近所にある公園に行った。そこで空いているベンチを見つけて並んで座
った。
空は薄く曇って、青空はどこにも見えなかったが、雨の降り出しそうな気配はなかった。風
もない。緑の葉を豊かにつけたヤナギの枝は、地面すれすれまで垂れ下がり、深く考えごとを
しているみたいにぴくりとも動かなかった。時折小さな鳥がやってきてその枝に不安定にとま
り、すぐにあきらめて飛び立った。枝がかき乱された心のように僅かに揺れ、やがてまた静ま
った。
「話の途中で携帯電話が鳴り出すかもしれないけど、そいつは勘弁してくれ。いくつか仕事の
用件があってな」とアオは言った。
「かまわない。忙しいことはわかっている」
「携帯ってのは便利だから不便だ」とアオは言った。「それでおまえ、結婚しているのか?」
「いや。まだ一人だよ」
「おれは六年前に結婚して、子供が一人いる。三歳の男の子だ。もう一人は今かみさんの腹の
中に入っていて、着実に大きくなりつつある。九月に生まれる予定だ。女の子だと聞いてい
る」
つくるは肯いた。「人生は順調に運んでいる」
「順調かどうかはともかく、少なくとも着実に前には進んでいる。言い換えれば、後戻りはで
きなくなっている」、アオはそう言って笑った。「おまえの方はどうなんだ?」
「とくに悪いことは起こっていない」、つくるは財布から名刺を取り出して、アオに渡した。
アオはそれを手に取り、声に出して読んだ。
「***鉄道株式会社。施設部建築課」
「主に駅をつくったり、維持したりする仕事だよ」とつくるは言った。
「おまえは昔から駅が好きだったものな」とアオは感心したように言った。そしてカプチーノ
を一口鉄んだ。「結局、好きなことを仕事にできたわけだ」
「勤め人だから、好きなことばかりはやっていられないけどね。つまらないことはたくさんあ
る」
「それはどこだって同じだ。人に使われている限り、つまらんことはいっぱいあるさ」とアオ
は言った。そしてつまらないことの実例をいくつか思い出したみたいに、何度か小さく首を振
った。
「レクサスは売れているのか?」
「悪くない。ここは名古屋だからな。もともとトヨタの地元だ。放っておいてもトヨタ車は売
れる。ただし、おれたちの今回の相手は日産やホンダじゃない。目標は今までメルセデスやB
MWといった海外のプレミアム・カーに乗ってきた層を、レクサスのオーナーに変えることだ。
そのためにトヨタはフラッグシップ・ブランドを立ち上げたんだ。時間はかかるかもしれない
けど、きっとうまくいく」 「負けるという選択肢は、おれたちにはない」
アオは一瞬奇妙な顔をしたが、すぐに相好を崩した。「ラグビーの試合のあれか。変なこと
をよく覚えているんだな」
「士気を鼓舞するのがうまかった」
「ああ、試合にはよく負けたけどな。でも実際の話、ビジネスはそれなりに順調に進んでいる。
もちろん世の中の景気はあまり良くないが、それでも金を持っている人間はしっかり全を持っ
ている。不思議なくらいな」
つくるは黙って肯いた。アオは続けた。
「おれ自身ずっとレクサスに乗っている。優れた車だ。静かだし、故障もない。テストコース
を運転したときに時速二百キロを出してみたが、ハンドルはぴくりともぶれなかった。ブレー
キもタフだ。たいしたもんだよ。自分で気に入っているものを人に勧めるのは、いいものだ。
いくら目がうまくても、自分で納得のいかないものを人に売りつけることはできないよ」
つくるはそれに同意した。
アオはつくるの顔を正面から見た。「なあ、おれの話し方って車のセールスマンみたいか?」
「いや、そうは思わないよ」とつくるは言った。アオが自分の考えを正直に話していることは
理解できた。しかしそれはそれとして、高校時代にはそんな話し方をしなかったことも、また
確かたった。
「おまえ、車は運転するのか?」とアオは尋ねた。
運転はするけど、車は持っていない。東京に位んでいれば、電車とバスとタクシーでだいた
いは事足りるし、普段の足には自転車を使っている。どうしても必要があれば、そのときはレ
ンタカーを時間単位で借りる。そういうところは名古屋とは違う」
「そうだな、その方が気楽だし、金もかからない」とアオは言った。そして小さくため息をつ
いた。「車なんてなきゃないでいいんだ。それで、どうだ、東京での暮らしは気に入っている
のか?」
「仕事もあるし、もうけっこう長く住んでいるから上地柄にもなんとなく馴れた。ほかにとく
に行くところもない。それだけだよ。かくべつ気に入っているわけじゃない」
二人はそれからしばらく黙り込んでいた。二匹のボーダーコリーを連れた中年の女性が前を
通り過ぎた。何人かのジョガーが、城の方に向かって走っていった。
「話があるって言ったよな」とアオは遠くにいる誰かに向かって語りかけるように言った。
「大学二年生の夏休みに名古屋に帰ってきて、君と電話で話をした」とつくるは切り出した。
「そのとき、もう僕とは会いたくないし、これからいっさい電話もかけてほしくないと言われ
た。そしてそれは君たち四人の総意だと言われた。それは覚えているか?」
「もちろん覚えている」
「その理由が知りたいんだ」とつくるは言った。
「急に今になってか?」とアオは少しびっくりしたように言った。
「ああ、今になってだよ。そのときにはどうしてもこの質問ができなかった。出し抜けにそん
なことを言われたショックが大きすぎたし、それと同時に、自分がそれほどきっぱり拒絶され
る理由を教えられるのが怖かったということもある。それを知らされたら、ひょっとしてもう
立ち直れないんじゃないかという気がした。だから何も事情を知らないまま、すべてを忘れて
しまおうとした。時間が経てば心に受けた傷も癒えるだろうと思った」

アオはスコーンを小さくちぎって口に入れた。それをゆっくり喘み、カプチーノで喉の奥に
流し込んだ。つくるは話し続けた。
「それから十六年が経った。しかしそのときの傷はまだ僕の心に残っているみたいだ。そして
どうやらまだ血を流し続けているらしい。このあいだ、ちょっとした出来事があって、それに
気づかされた。僕にとってはけっこう大きな意味を持つ出来事だったんだ。だからこうして名
古屋まで君に会いに来た。突然で、迷惑だったかもしれないけど」
アオは重く垂れ下がったヤナギの枝をしばらく眺めていた。やがて口を開いた。「その理由
として、おまえに思い当たることはないのか?」
「十六年、理由を考え続けてきたよ。でもいまだに見当がつかない」
アオは困惑したように目を細め、鼻の頭を指でこすった。それが何かを深く考える時の彼の
癖だった。「あの時おれがそう言うと、おまえは『わかった』と言ってそのまま電話を切った。
とくに抗議もしなかった。話を深く追及もしなかった。だからおれとしては当然ながら、おま
えにはそれについて、自分でも何か思い当たるところがあるんだろうと解釈した」
「本当に深く心が傷ついたときには、言葉なんて出てこないものだよ」とつくるは言った。
アオはそれについて何も言わず、スコーンをちぎって、その塊を鳩のいる方に投げた。鳩た
ちがあっという間に群がった。それは彼が習慣的に行っている行為のように見えた。たぶん昼
休みに一人でよくここに来て、鳩に昼食を分け与えているのだろう。
「それで、いったい何か理由だったんだ?」とつくるは尋ねた。
「本当におまえは何も知らないのか?」
「ああ、本当に何も知らない」
そのとき携帯電話の陽気な着信メロディーが鳴り出した。アオは携帯電話をスーツのポケッ
トから取りだし、スクリーンで相手の名前をちらりと確かめてから、無表情にキーを押し、そ
のままポケットに戻した。その着信メロディーにはどこかで聞き覚えがあった。ずっと昔のポ
ップソング、たぶん生まれる前に流行った曲だ。何度か耳にしたことがあるが、曲名までは思
い出せない。
「もし何か用事があるのなら、先に済ませてくれてかまわないよ」とつくるは言った。
アオは首を振った。「いや、いいんだ。そんなに大事な用件じゃない。あとでも間に合う」
つくるはミネラル・ウォーターをプラスティックのボトルから一口飲み、喉の奥に潤いを与
えた。「どうして僕はあのとき、グループから追放されなくてはならなかったんだろう?」
アオはひとしきり考えを巡らせていた。それから言った。「おまえの方に思い当たる節がま
ったくないというのは、どう言えばいいんだろう、それはつまり、おまえはシロと性的な関係
を持たなかったということなのか?」
つくるの唇はとりとめのない形をつくった。「性的な関係? まさか」
「ンロはおまえにレイプされたと言った」とアオは言いにくそうに言った。「無理やりに性的
な関係を持たされたと」
つくるは何かを言おうとしたが、言葉は出てこなかった。いま水を飲んだばかりなのに、喉
の奥が痛いほど乾いていた。
アオは言った。「おまえがそんなことをするなんて、おれにはとても信じられなかった。ほ
かの二人も同じだったと思う。クロにしても、アカにしてもな。おまえはどう考えても、人の
いやがることを無理強いするタイプじゃない。とりわけ暴力をふるってそうするようなタイプ
じゃない。それはよくわかっていた。でもシロはどこまでも真剣だったし、思い詰めていた。
おまえには表の顔と裏の顔があるんだとシロは言った。表の顔からは想像もつかないような裏
の顔があるんだと。そう言われると、おれたちは何も言えなかった」
つくるはしばらく唇を噛んでいた。それから言った。「どんな風に僕にレイプされたか、シ
ロは説明したのか?」
「ああ、説明してくれたよ。かなりリアルに細部までな。できればそういうことは耳にしたく
なかった。実際のところ、その話を聞いているのはおれとしてもとてもつらかったよ。つらか
ったし、悲しかった。いや、心が傷つけられたという方が近いかもしれない。とにかく彼女は
ひどく感情的になっていた。身体が震えて、形相が変わるくらい激しい怒りにとらわれていた。
シロが言うには、誰だか有名な外国人ピアニストのコンサートがあって、それを聴きに東京ま
で一人で出かけ、そのときおまえの自由が丘のマンションに泊めてもらった。ホテルに泊まる
と両親には言って、宿泊代を浮かせたわけさ。男女二人きりで夜を過ごすとはいえ、相手がお
まえだからと安心していたんだが、夜中に力尽くで犯された。抵抗はしたが、身体が痺れてい
うことをきかなかった。寝る前に少しお酒を飲んだけど、そのときに何加薬を混ぜられたかも
しれない。そういう話だった」
つくるは首を振った。「泊まるもなにも、シロが東京のうちに来たことなんてコ院もないよ」
アオは広い肩をわずかにすぼめた。苦いものを口に入れてしまったような顔をして脇を向い
た。そして言った。「おれとしては、シロの言うことをそのまま信じるしかなかった。自分は
処女だったと彼女は言った。無理にそれを強要され、激しい痛みと出血があったと言った。あ
の内気なシロが、おれたちにわざわざそんな生々しい作り話をしなくちゃならない理由も思い
つけなかった」
つくるはアオの横顔に向かって言った。「でもそれはそれとして、どうしてまず僕に直接確
加めな加ったんだ? 釈明の機会くらい与えてくれてもよかったんじゃないのか。欠席裁判み
たいなかたちじゃなく」
アオはため息をついた。「たしかにおまえの言うとおりだよ。今にして思えばな。おれたち
はまず冷静になって、何はともあれおまえの言い分を聞くべきだった。でもそのときはそれが
できなかった。とてもそういう雰囲気じゃなかった。シロはひどく興奮して、取り乱していた。
そのままでは何か起こるかわ加らな加った。だからおれたちはまず彼女をなだめ、その混乱を
鎮めなくちゃならなかったんだ。おれたちにしても百パーセント、シロの言い分を信じたわけ
じゃない。正直な話、ちょっと変だと思うところもなくはなかった。でもそれがまるっきりの
フィクションとは思えなかった。彼女がそこまではっきり言うからには、そこにはある程度の
真実は含まれているはずだ。そう思った」
「だからとりあえず僕を切った」
「なあ、つくる、おれたちだって、やはりショックを受けてとても混乱していたんだ。傷つい
てもいた。誰を信じればいいのかもわからなかった。そういう中でまずクロがシロの側に立っ
た。彼女はシロの要求どおり、おまえをいったん切ることを求めた。言い訳をするんじゃない
が、アカとおれは勢いに押されてというか、それに従うかたちになった」
つくるはため息をついて言った。「信じてくれるかどうかはともかく、僕はもちろんシロを
レイブしかことはないし、彼女と性的な関係を持ったこともない。それに近いことをした覚え
もない」
アオは肯いたが、何も言わなかった。何を信じるにせよ、信じないにせよ、それからあまり
に長い時間が経ちすぎている。つくるはそう思った。ほかの三人にとっても、つくる自身にと
っても。
もう一度アオの携帯電話の着信メロディーが鳴った。アオは相手の名前をチェックし、つく
るに向かって言った。
「すまない。ちょっと外してもいいか?」「もちろん」とつくるは言った。
アオは携帯電話を持ってベンチから立ち上がり、少し離れたところで話をした。その身のこ
なしや表情から顧客との商談であるらしいことがわかった。
つくるは突然、その着信メロディーの曲名を思い出した。エルヴィス・プレスリーの『ラス
ヴェガス万歳!』だ。しかしそれはどう考えても、レクサスの辣腕セールスマンが着信メロデ
ィーとするのに相応しい音楽とは思えなかった。いろんなものごとがそれぞれ少しずつ現実昧
を欠いていた。
やがてアオが戻ってきて、ベンチの彼の隣に再び腰を下ろした。
「悪かったな」と彼は言った。「用件は済んだよ」
つくるは腕時計を見た。約束の三十分はそろそろ終わりに近づいていた。
つくるは言った。「なぜシロはそんなでたらめな話をしたんだろう? そしてなぜその相手
は僕でなくちやならなかったんだろう?」
「さあな、おれにはわからん」とアオは言った。そして力なく何度か首を振った。「おまえに
は悪いけど、それがいったいどういうことだったのか、その時も今も、おれには皆目わからな
いんだ」
「クロがもっと詳しい事情を知っているんじゃないかな」とアオは言った。「おれはそのとき、
なんとなくそういう印象を持った。おれたちには知らされていない事実が何かあるんじゃない
かって。わかるだろう。そういうことについては、女同士の方がもっと腹を割って率直に話す
ものだ」
「クロは今フィンランドに住んでいる」とつくるは言った。
「知ってるよ。たまに絵葉書をくれる」とアオは言った。
それから二人はまた黙り込んだ。制服姿の女子高校生が三人、グループで公園を横切ってい
った。短いスカートの裾を元気に振り、大きな声で笑いながら、二人の座ったベンチの前を通
り過ぎていく彼女たちは、まだほんの子供のように見えた。白いソックスに黒のローファー。
表情がまだ幼い。自分たちもついこのあいだまで、そのような年齢だったのだと思うと、ずい
ぶん不思議な気がした。
「なあ、つくる、おまえはずいぶん見かけが変わったよな」とアオが言った。
「もう十六年も会っていないんだ。それは変わるさ」
「いや、歳月だけのことじゃない。最初はおまえだとは、まるでわからなかったよ。もちろん
よく見ればわかるんだけどな。なんていうか、痩せて精悍な感じになった。頬がこけて、目が
深く鋭くなった。昔はもっと丸みのある、おっとりした風貌だった」
それが死について、自分を消滅させることについて、半年近く真剣に思い詰めた結果だとは、
そしてそれらの日々が自分の心身を大きく作り変えてしまったのだとは、つくるには言い出せ
なかった。そんなことを打ち明けても、そこにあったぎりぎりの心情は半分も伝わらないだろ
う。それくらいならまったく何も言わない方がいい。つくるは黙って、相手の話の続きを待っ
ていた。
PP.151-168
村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』



庭先に花咲くきせつがやってきた。彼女が作業準備中の僕の手をつかみ、「ねぇ、ねぇ、大事に
育ててきたレモンに蕾がついたのよ!」とそう叫びながら、現場に連れて行きゆびさす。「ほら」
と。「ジャマンアイリスも花が咲いたのよ」とゆびさしながら、写メールしている。庭には鉢植
えのブラッドオレンジの小さな果実がついていて、「オレンジとレモンが実れば、庭先のサラダ
として組み合わせることができるね」と言おうとしたが、秘するが花?と飲み込む。これからが
楽しみだ。