都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「コーカサスの虜」 ロシア・ソビエト映画祭2006 7/16
2006-07-21 / 映画
東京国立近代美術館フィルムセンター(中央区京橋3-7-6)
「コーカサスの虜」
(1995年/ロシア・カザフスタン/セルゲイ・ボドロフ監督)
ロシア・ソビエト映画祭2006(ロシア文化フェスティバル2006 IN JAPAN)
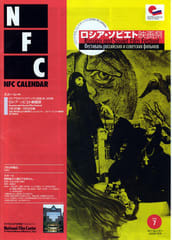
有楽町朝日ホールで「異国の肌」を見た後は、京橋の近代美術館フィルムセンターへ向かい、ロシア・ソビエト映画祭の「コーカサスの虜」を鑑賞しました。トルストイの小説を原作に、現代のチェチェン問題へ鋭く切り込んだ作品です。国家及び地域間の戦争や対立というシステムの中へ投げ込まれた人間が、どのように生きざるを得ないのかということを、コーカサス地方の大自然を背景にして淡々と、しかし重い課題を投げつけながら描いています。佳作でした。
ロシア人とチェチェン人という対立項がなければ、そして彼らが戦争中でなければ、決してワーニャやサーシャらとチェチェンの村人たちはいがみ合うことがなかったのでしょう。もちろん、ワーニャらが捕虜にされている間も、ジーナはともかく、その父であり、またこの捕虜計画の立案者でもあるアブドゥルにも、ワーニャらに個人的な憎しみがあるわけではありません。あくまでも戦争といった、大きな対立の中に憎悪が生まれてしまう。アブドゥルが最後のシーンでワーニャにした行為は、まさに人が人として本来なし得る優しさの表れです。しかしまたそのすぐ後に訪れるロシア軍の無慈悲な行動は、逆に軍隊として、そして戦争として当たり前の行為に過ぎないのでしょう。それにしても惨たらしい。ここには、戦争を語る際のキーワードに有りがちな、善と悪や、勝者と敗者もありません。あるのは、ただこの対立の中で翻弄される、ごく普通の感情を持った人間たちだけでした。

ワーニャ役のセルゲイ・ボドロフ(監督の息子だそうです。)の素朴な心情表現はもとより、いかにも職業軍人風の雰囲気でありながら、随所に人としての温かみを見せるサーシャ役のメンシコフの演技はとても心に残りました。ワーニャとサーシャは、同じロシア軍に所属しながらもいがみ合っている。それが徐々に捕虜生活の中で生まれた連帯感によって結びつけられます。しかしそれもつかの間の出来事に過ぎなかった。結局、彼らは永遠の別れを告げることなります。サーシャの結末は実に悲しいものです。しかし彼はその後にもワーニャを導いていく。サーシャが、彼らを見張ったムラットを簡単に殺めてしまうのもまた戦争であり、その報いとして受けるサーシャの最期もまた戦争の一コマである。ハリウッドばりの金のかかった派手なアクションもなく、むしろロシア民謡にのった簡潔で素朴なシーンばかりが続きますが、それが余計に彼らを取り巻く巨大な戦争の恐ろしさを伝えてきます。
それにしてもこの戦争は複雑です。アブドゥルは捕虜交換のため、ロシア軍司令官へ直接交渉するのにも驚かされますが、なんとワーニャの母とも面会します。絡み合った糸のような彼らの関係。チェチェン問題を単純化出来ない要因が垣間見られるようでした。
 「コーカサスの虜/オレグ・メンシコフ」
「コーカサスの虜/オレグ・メンシコフ」
ポドロフ監督の、「戦争を始めることは簡単だが、終わらせることは難しい。人を愛することより、殺すことの方が簡単なのだ。」という言葉が非常に重みを持って響いてくる作品です。DVDでも発売されていますが、これは是非おすすめしたいと思います。
「コーカサスの虜」
(1995年/ロシア・カザフスタン/セルゲイ・ボドロフ監督)
ロシア・ソビエト映画祭2006(ロシア文化フェスティバル2006 IN JAPAN)
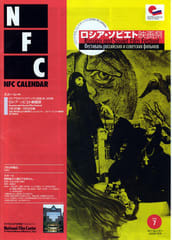
有楽町朝日ホールで「異国の肌」を見た後は、京橋の近代美術館フィルムセンターへ向かい、ロシア・ソビエト映画祭の「コーカサスの虜」を鑑賞しました。トルストイの小説を原作に、現代のチェチェン問題へ鋭く切り込んだ作品です。国家及び地域間の戦争や対立というシステムの中へ投げ込まれた人間が、どのように生きざるを得ないのかということを、コーカサス地方の大自然を背景にして淡々と、しかし重い課題を投げつけながら描いています。佳作でした。
ロシア人とチェチェン人という対立項がなければ、そして彼らが戦争中でなければ、決してワーニャやサーシャらとチェチェンの村人たちはいがみ合うことがなかったのでしょう。もちろん、ワーニャらが捕虜にされている間も、ジーナはともかく、その父であり、またこの捕虜計画の立案者でもあるアブドゥルにも、ワーニャらに個人的な憎しみがあるわけではありません。あくまでも戦争といった、大きな対立の中に憎悪が生まれてしまう。アブドゥルが最後のシーンでワーニャにした行為は、まさに人が人として本来なし得る優しさの表れです。しかしまたそのすぐ後に訪れるロシア軍の無慈悲な行動は、逆に軍隊として、そして戦争として当たり前の行為に過ぎないのでしょう。それにしても惨たらしい。ここには、戦争を語る際のキーワードに有りがちな、善と悪や、勝者と敗者もありません。あるのは、ただこの対立の中で翻弄される、ごく普通の感情を持った人間たちだけでした。

ワーニャ役のセルゲイ・ボドロフ(監督の息子だそうです。)の素朴な心情表現はもとより、いかにも職業軍人風の雰囲気でありながら、随所に人としての温かみを見せるサーシャ役のメンシコフの演技はとても心に残りました。ワーニャとサーシャは、同じロシア軍に所属しながらもいがみ合っている。それが徐々に捕虜生活の中で生まれた連帯感によって結びつけられます。しかしそれもつかの間の出来事に過ぎなかった。結局、彼らは永遠の別れを告げることなります。サーシャの結末は実に悲しいものです。しかし彼はその後にもワーニャを導いていく。サーシャが、彼らを見張ったムラットを簡単に殺めてしまうのもまた戦争であり、その報いとして受けるサーシャの最期もまた戦争の一コマである。ハリウッドばりの金のかかった派手なアクションもなく、むしろロシア民謡にのった簡潔で素朴なシーンばかりが続きますが、それが余計に彼らを取り巻く巨大な戦争の恐ろしさを伝えてきます。
それにしてもこの戦争は複雑です。アブドゥルは捕虜交換のため、ロシア軍司令官へ直接交渉するのにも驚かされますが、なんとワーニャの母とも面会します。絡み合った糸のような彼らの関係。チェチェン問題を単純化出来ない要因が垣間見られるようでした。
 「コーカサスの虜/オレグ・メンシコフ」
「コーカサスの虜/オレグ・メンシコフ」ポドロフ監督の、「戦争を始めることは簡単だが、終わらせることは難しい。人を愛することより、殺すことの方が簡単なのだ。」という言葉が非常に重みを持って響いてくる作品です。DVDでも発売されていますが、これは是非おすすめしたいと思います。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )










