都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「安岡亜蘭展 -kasane- 」 四季彩舎 4/16
四季彩舎(中央区京橋2-11-9 西堀11番地ビル2F)
「安岡亜蘭展 -kasane- 」
4/10-19
京橋のギャラリー四季彩舎で開催されている、若手作家安岡亜蘭の個展です。シャープなデザインによる日本画テイストの動物画。それが色取り取りに並んでいます。アクリルガッシュの美しい絵具の質感もまた必見です。

まるでまんじゅうのような形に閉じ込められた、どこか生々しくボリューム感のあるうさぎ。左右対称になって突き出た耳と、バランスをとるかのように配された赤い果実。背景はまるで金箔を貼ったようです。そしてうさぎの体には、入れ墨のような赤系統のカラフルな紋様。そのイメージは和風です。細かい線による巧みな造形と鮮やかな色の配置、さらには日本画のような味わい。研ぎすまされたデザインの技に日本画風の質感が加わる。この作品の隣に展示されていた亀をモチーフにしたものも実に良かったのですが、狭い幾何学模様の領域へ切り絵のように収めた動物の姿は可愛らしく、またどこか滑稽です。
狆をモチーフにしたやや大きな作品にも惹かれました。狆のシャープな造形はもちろんのこと、画面に塗り込まれた真っ白なアクリルガッシュの質感がとても魅力的です。また金や青、それに白をまぶしてグラデーションを描いたような、同じくアクリルガッシュの美しい質感が映えた作品にも惹かれました。斬新なデザインと日本画の伝統。それが色、形の両面で融合しています。
「展力 Recommend & Review」掲載の展覧会です。19日まで開催されています。
「安岡亜蘭展 -kasane- 」
4/10-19
京橋のギャラリー四季彩舎で開催されている、若手作家安岡亜蘭の個展です。シャープなデザインによる日本画テイストの動物画。それが色取り取りに並んでいます。アクリルガッシュの美しい絵具の質感もまた必見です。

まるでまんじゅうのような形に閉じ込められた、どこか生々しくボリューム感のあるうさぎ。左右対称になって突き出た耳と、バランスをとるかのように配された赤い果実。背景はまるで金箔を貼ったようです。そしてうさぎの体には、入れ墨のような赤系統のカラフルな紋様。そのイメージは和風です。細かい線による巧みな造形と鮮やかな色の配置、さらには日本画のような味わい。研ぎすまされたデザインの技に日本画風の質感が加わる。この作品の隣に展示されていた亀をモチーフにしたものも実に良かったのですが、狭い幾何学模様の領域へ切り絵のように収めた動物の姿は可愛らしく、またどこか滑稽です。
狆をモチーフにしたやや大きな作品にも惹かれました。狆のシャープな造形はもちろんのこと、画面に塗り込まれた真っ白なアクリルガッシュの質感がとても魅力的です。また金や青、それに白をまぶしてグラデーションを描いたような、同じくアクリルガッシュの美しい質感が映えた作品にも惹かれました。斬新なデザインと日本画の伝統。それが色、形の両面で融合しています。
「展力 Recommend & Review」掲載の展覧会です。19日まで開催されています。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
コシノヒロコ「襲(かさね)」展 大丸ミュージアム・東京 4/15
大丸ミュージアム・東京(千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店12階)
「コシノヒロコ『襲かさね』展 -具象・色象- 」
4/13-21
大丸ミュージアム(12階)へは、大抵エレベーターで下から直接向かうのですが、フロアに降りた途端、いつもとは随分異なった雰囲気に驚かされました。スタイリッシュな黒に包まれたミュージアム入口と、何やら聴こえてくるヒーリング系の音楽。服飾デザイナーとしても有名なコシノヒロコによる、着物をテーマとした展覧会です。

一言に今回の企画を表すと、「コシノヒロコがデザインした着物を展示する展覧会。」と言えるのかと思いますが、それだけで終らないところがこの展覧会の非常に重要なポイントです。コシノヒロコのデザインした着物の図柄を、京都の織物商誉田屋源兵衛が仕立てた上に、会場設営は建築家の隈研吾が担当している。コシノヒロコのデザインを中核にした三名のアーティストの業。それが見事にコラボレーションしています。単に着物を展示するだけにとどまらない、まさに現代アートのようなインスタレーション。それがあの手狭な大丸ミュージアムにて美しく展開されているのです。会場を見るだけでも十分に価値があります。


展示構成は「苔庭」風と言うことで、まさに和のテイストを思わせる仕掛けが随所になされています。暗がりの空間からスポットライトで浮かび上がるコシノヒロコデザインの着物。そして空間いっぱいに垂れ下がる帯の数々。どれも見応え十分でした。一部、着物に合わせて展示されていた書のような平面作品はあまり面白いと思えなかったのですが、具象から抽象、または書か墨絵、さらにはまるで油彩画のようなデザインまで、多種多様な着物の響宴は、それが元来持っていたイメージを吹き飛ぶような斬新さすら持ち合わせています。大きな蓮の花が入ったものや、奥に展示されていたまるで風景画のような図柄、さらにはシンプルな魚をいくつか象ったものから、蔦や葉の絡み合う日本画風の作品まで、まさに選り取り見取りの状態です。きっとそれぞれに一番好きな着物が見つかるかと思います。(ここにアップした画像は色が良くありません。実際とは大きく異なります。)


会期が非常に短いのが難点ですが、私のような着物の知識がない全くの素人でも楽しめる内容です。21日、金曜日までの開催です。(午後7時半まで入場可能です。最終日は午後4時半まで。)
「コシノヒロコ『襲かさね』展 -具象・色象- 」
4/13-21
大丸ミュージアム(12階)へは、大抵エレベーターで下から直接向かうのですが、フロアに降りた途端、いつもとは随分異なった雰囲気に驚かされました。スタイリッシュな黒に包まれたミュージアム入口と、何やら聴こえてくるヒーリング系の音楽。服飾デザイナーとしても有名なコシノヒロコによる、着物をテーマとした展覧会です。

一言に今回の企画を表すと、「コシノヒロコがデザインした着物を展示する展覧会。」と言えるのかと思いますが、それだけで終らないところがこの展覧会の非常に重要なポイントです。コシノヒロコのデザインした着物の図柄を、京都の織物商誉田屋源兵衛が仕立てた上に、会場設営は建築家の隈研吾が担当している。コシノヒロコのデザインを中核にした三名のアーティストの業。それが見事にコラボレーションしています。単に着物を展示するだけにとどまらない、まさに現代アートのようなインスタレーション。それがあの手狭な大丸ミュージアムにて美しく展開されているのです。会場を見るだけでも十分に価値があります。


展示構成は「苔庭」風と言うことで、まさに和のテイストを思わせる仕掛けが随所になされています。暗がりの空間からスポットライトで浮かび上がるコシノヒロコデザインの着物。そして空間いっぱいに垂れ下がる帯の数々。どれも見応え十分でした。一部、着物に合わせて展示されていた書のような平面作品はあまり面白いと思えなかったのですが、具象から抽象、または書か墨絵、さらにはまるで油彩画のようなデザインまで、多種多様な着物の響宴は、それが元来持っていたイメージを吹き飛ぶような斬新さすら持ち合わせています。大きな蓮の花が入ったものや、奥に展示されていたまるで風景画のような図柄、さらにはシンプルな魚をいくつか象ったものから、蔦や葉の絡み合う日本画風の作品まで、まさに選り取り見取りの状態です。きっとそれぞれに一番好きな着物が見つかるかと思います。(ここにアップした画像は色が良くありません。実際とは大きく異なります。)


会期が非常に短いのが難点ですが、私のような着物の知識がない全くの素人でも楽しめる内容です。21日、金曜日までの開催です。(午後7時半まで入場可能です。最終日は午後4時半まで。)
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「プラド美術館展」 東京都美術館 その1 4/8
東京都美術館(台東区上野公園8-36)
「プラド美術館展 -スペインの誇り 巨匠たちの殿堂- 」
3/25-6/30
エル・グレコ、ベラスケス、ティツィアーノ、ファン・ダイク、ゴヤ。ヨーロッパ絵画史を飾った錚々たるビックネームが、今、上野に集まっています。じっくりと見れば数時間はかかるとも言えそうな、非常に見応えのある展覧会です。

展示点数は約80点ほどとそれほど多くはありませんが、ともかくどの作品も非常に優れたものばかりなので、惹かれた作品を挙げていくとキリがありません。元々大好きだったエル・グレコに惹かれつつ、ベラスケスの描写力に驚嘆し、さらには思いがけないほどに美しいムリーリョに魅入っている。気がつくとあれもこれもと名画へ入り浸っていた自分がいました。一回の鑑賞では全ての作品を味わい尽くせない。と言うことで今回のエントリでは、展覧会の前半部分、つまり第1章「スペイン絵画の黄金時代」と第2章「16、17世紀イタリア絵画」に限って感想を書いていきたいと思います。(第3章以降は、後日もう一回鑑賞する予定なのでその際に書きます。)

まず出迎えてくれたのはエル・グレコの4点でした。その中ではやはり「十字架を抱くキリスト」(1597/1607年頃)が一推しの作品でしょうか。輝く赤と青い衣に身を纏ったイエス。両手で抱えている十字架よりも、この衣の方が重厚な質感を見せています。そして彼の真っ白な手。細くサラッと伸びた指と爪はとても男性のものとは思えません。また両目はハッキリと天を捉えています。瞳の中にて、白く輝く一筋の光。そこには十字架を背負いつつも希望を見出すイエスの意思が感じられます。まるでイエスを包み込む柔らかいマントのような美しい背景も魅力的でした。

ベラスケスは5点展示されています。ここで挙げたいのは「道化ディエゴ・デ・アセド、"エル・プリモ"」(1635-44年頃)です。まるで哲学者のように思慮深い表情をしている一人の道化。この人物の描写にも惹かれますが、まずは彼が手にしている巨大な書籍に目が奪われます。手前に置かれているのはペン入れでしょうか。分厚い書籍をめくりながら何かを執筆している。そんなイメージも湧いてきます。また彼の纏う、まるで喪服のような衣装。非常に重厚な味わいです。自分で着たのではなく誰かに着せられた。彼がどこか人形のように見えてくるのは、この服の奇妙な質感によるのかもしれません。

第1章では、未知の画家ながらも思いがけないほどに魅力的な作品に出会えました。それはバルトロメ・エステバン・ムリーリョです。上にアップした作品は、その中でも特に目立っていた「エル・エスコリアルの無原罪の御宿り」(1660-1665年頃)。大きな瞳とくっきりとした鼻筋。まずは否応無しにその端正な顔立ちへと目がいってしまいます。白と青のハッキリとした衣装のコントラスト、そしてまさに後光のように美しく照っている背後の描写。天使たちが朧げに集ってさらに彼女を引き立てている。また胸の前で合わせている両手も必見です。ここだけ絵から飛び出してきそうな存在感を見せています。(他の部分は靄がかかったように霞んでいます。)心打たれる作品とはまさにこのようなものを言うのでしょうか。彼女の祈りがひしひしと伝わってくる作品でした。

第2章では、パンフレットにも掲載されている作品、テッツィアーノの「アモールと音楽にくつろぐヴィーナス」(1555年頃)がとても印象的です。当たり前の話ではありますが、この作品の実物の質感はパンフレットの印刷物と全く異なっています。印刷物ではヴィーナスの質感が荒く、肌には老いすら感じさせる部分がありますが、実物にそのようなことは全くありません。やや紅潮した顔、豊満な腕と体、そしてだらりと伸ばした両足。その全てが細かいタッチにて生き生きと描かれています。そしてベットに広げられた高貴な紫色のシーツ。折り目にあたった光が美しく反射しています。また、端に施された細かい刺繍はまるで電飾のように輝いていました。ヴィーナスの耳に光るピアスの立体的な描写とともに、彼女の美しさを引き出す演出が随所に凝らされています。
第2章の最後を飾るのは、この展覧会でも一際力強い作品、ジョルダーノの「サムソンとライオン」(1695-1696年頃)です。(作品画像と解説は「Megurigami Nikki」のNikkiさんのブログをご参照下さい。)後景を吹き飛ばすほどに大きく、また威圧的に描かれたサムソンの姿。隆々とした肉体と神々しいマスクはその主題からして当然かもしれませんが、ライオンの口を素手で切り裂く様子はともかく目に焼き付きます。なす術もないライオンはただサムソンの前に横たわるだけ。しかしよく見ると、サムソンに負けないほどに太く逞しいライオンの足が画面の前方へ突き出していることが分かります。力と力のぶつかり合い。陽を受けて白く輝くサムソンと、まるで地獄からの使者(本来は聖人の象徴であるようですが。)のような闇を纏ったライオン。そのコントラストも見事でした。
この先は、フランドルやオランダのバロック絵画が展示された第3章へと続きますが、その感想は次回見た際にまた書きたいと思います。東京都美術館の展示室があまりにも手狭に見えてしまうほどの大作ぞろい。確かに名画揃いの展覧会です。6月末までの開催です。
*関連エントリ
「プラド美術館展」 東京都美術館 その2 5/14
「プラド美術館展 -スペインの誇り 巨匠たちの殿堂- 」
3/25-6/30
エル・グレコ、ベラスケス、ティツィアーノ、ファン・ダイク、ゴヤ。ヨーロッパ絵画史を飾った錚々たるビックネームが、今、上野に集まっています。じっくりと見れば数時間はかかるとも言えそうな、非常に見応えのある展覧会です。

展示点数は約80点ほどとそれほど多くはありませんが、ともかくどの作品も非常に優れたものばかりなので、惹かれた作品を挙げていくとキリがありません。元々大好きだったエル・グレコに惹かれつつ、ベラスケスの描写力に驚嘆し、さらには思いがけないほどに美しいムリーリョに魅入っている。気がつくとあれもこれもと名画へ入り浸っていた自分がいました。一回の鑑賞では全ての作品を味わい尽くせない。と言うことで今回のエントリでは、展覧会の前半部分、つまり第1章「スペイン絵画の黄金時代」と第2章「16、17世紀イタリア絵画」に限って感想を書いていきたいと思います。(第3章以降は、後日もう一回鑑賞する予定なのでその際に書きます。)

まず出迎えてくれたのはエル・グレコの4点でした。その中ではやはり「十字架を抱くキリスト」(1597/1607年頃)が一推しの作品でしょうか。輝く赤と青い衣に身を纏ったイエス。両手で抱えている十字架よりも、この衣の方が重厚な質感を見せています。そして彼の真っ白な手。細くサラッと伸びた指と爪はとても男性のものとは思えません。また両目はハッキリと天を捉えています。瞳の中にて、白く輝く一筋の光。そこには十字架を背負いつつも希望を見出すイエスの意思が感じられます。まるでイエスを包み込む柔らかいマントのような美しい背景も魅力的でした。

ベラスケスは5点展示されています。ここで挙げたいのは「道化ディエゴ・デ・アセド、"エル・プリモ"」(1635-44年頃)です。まるで哲学者のように思慮深い表情をしている一人の道化。この人物の描写にも惹かれますが、まずは彼が手にしている巨大な書籍に目が奪われます。手前に置かれているのはペン入れでしょうか。分厚い書籍をめくりながら何かを執筆している。そんなイメージも湧いてきます。また彼の纏う、まるで喪服のような衣装。非常に重厚な味わいです。自分で着たのではなく誰かに着せられた。彼がどこか人形のように見えてくるのは、この服の奇妙な質感によるのかもしれません。

第1章では、未知の画家ながらも思いがけないほどに魅力的な作品に出会えました。それはバルトロメ・エステバン・ムリーリョです。上にアップした作品は、その中でも特に目立っていた「エル・エスコリアルの無原罪の御宿り」(1660-1665年頃)。大きな瞳とくっきりとした鼻筋。まずは否応無しにその端正な顔立ちへと目がいってしまいます。白と青のハッキリとした衣装のコントラスト、そしてまさに後光のように美しく照っている背後の描写。天使たちが朧げに集ってさらに彼女を引き立てている。また胸の前で合わせている両手も必見です。ここだけ絵から飛び出してきそうな存在感を見せています。(他の部分は靄がかかったように霞んでいます。)心打たれる作品とはまさにこのようなものを言うのでしょうか。彼女の祈りがひしひしと伝わってくる作品でした。

第2章では、パンフレットにも掲載されている作品、テッツィアーノの「アモールと音楽にくつろぐヴィーナス」(1555年頃)がとても印象的です。当たり前の話ではありますが、この作品の実物の質感はパンフレットの印刷物と全く異なっています。印刷物ではヴィーナスの質感が荒く、肌には老いすら感じさせる部分がありますが、実物にそのようなことは全くありません。やや紅潮した顔、豊満な腕と体、そしてだらりと伸ばした両足。その全てが細かいタッチにて生き生きと描かれています。そしてベットに広げられた高貴な紫色のシーツ。折り目にあたった光が美しく反射しています。また、端に施された細かい刺繍はまるで電飾のように輝いていました。ヴィーナスの耳に光るピアスの立体的な描写とともに、彼女の美しさを引き出す演出が随所に凝らされています。
第2章の最後を飾るのは、この展覧会でも一際力強い作品、ジョルダーノの「サムソンとライオン」(1695-1696年頃)です。(作品画像と解説は「Megurigami Nikki」のNikkiさんのブログをご参照下さい。)後景を吹き飛ばすほどに大きく、また威圧的に描かれたサムソンの姿。隆々とした肉体と神々しいマスクはその主題からして当然かもしれませんが、ライオンの口を素手で切り裂く様子はともかく目に焼き付きます。なす術もないライオンはただサムソンの前に横たわるだけ。しかしよく見ると、サムソンに負けないほどに太く逞しいライオンの足が画面の前方へ突き出していることが分かります。力と力のぶつかり合い。陽を受けて白く輝くサムソンと、まるで地獄からの使者(本来は聖人の象徴であるようですが。)のような闇を纏ったライオン。そのコントラストも見事でした。
この先は、フランドルやオランダのバロック絵画が展示された第3章へと続きますが、その感想は次回見た際にまた書きたいと思います。東京都美術館の展示室があまりにも手狭に見えてしまうほどの大作ぞろい。確かに名画揃いの展覧会です。6月末までの開催です。
*関連エントリ
「プラド美術館展」 東京都美術館 その2 5/14
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第1期」 三の丸尚蔵館 4/9
宮内庁三の丸尚蔵館(千代田区千代田1-1 皇居東御苑内 大手門側)
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第1期」
3/25-4/23
伊藤若冲の代表作「動植綵絵」全30幅が、6幅ずつ、5回に分けて、皇居東御苑内の三の丸尚蔵館にて公開されています。若冲ファン必見の展覧会です。
今回出品されていた「動植綵絵」は、展示順に並べると以下の通りです。修復が施された後だからか、ともかくこれでもかと言うほどに彩色が鮮やかでした。ジッと見つめていると目がクラクラしてきます。

「芍薬群蝶図」(作品番号2-1)
ひらひらと舞い降りて来た色とりどりの蝶と、地面から湧き上がって来たような紅白、それにピンクの芍薬(しゃくやく)。蝶がどれも見事に描かれているのはもちろんのこと、芍薬の花びらの透き通った味わいが絶品です。また、蝶よりも芍薬の描写の方が、不思議と生き生きしているように見えます。まるで蝶を食べようとする食虫植物のような芍薬。爛れた花びらに、ざわめく茎と枝。特に後者の生々しさは、草花にないはずの意思すら感じさせます。あたかも動物の手足のようになって、蝶を捕まえようと頑張っているのでしょうか。

「老松白鶏図」(作品番号2-11)
白く輝く二羽の鶏。鷹のように鋭い嘴と目を持っています。大輪の花のように咲き誇る背景の松はやや荒く見えましたが、砂金をまぶしたような黄金色が交じり合う鶏の羽は実に見事です。画面右上の真っ赤な陽と鶏は喧嘩をしているのでしょうか。鶏冠が、煌煌と照る陽の赤みに負けないほどに赤らんでいます。また、鶏の目がしっかりと陽を見据えている様子も構図に緊張感を与えます。思わずこの鶏の視線を追っかけてしまいました。

「南天雄鶏図」(作品番号2-14)
今回出品されていたものの中で一番インパクトのある作品です。どっしりと構える一羽の真っ黒な雄鶏。ともかくこの鶏冠には驚かされます。小さな白い点がたくさん配されている。大きく見開いた目と、牙を剥いているように鋭い嘴、そしてこの爬虫類の皮膚のようにグロテスクな鶏冠。もはや鶏とは思えないような堂々とした勇姿を、大見得を切るかのようにさらけ出しています。肉食恐竜が咆哮する姿。ぶら下がる南天は彼の餌でしょうか。これから襲いかかって引きちぎろうとしているようにも見えました。また、それを横取りするかのように南天を摘む小鳥の存在も見逃せません。ここに若冲ならではの心憎い演出が感じられます。

「雪中錦鶏図」(作品番号2-19)
主役の錦鶏の立場を奪うほどの存在感を見せているのは、画面全体にまるで垂れているように塗られた雪の描写です。それにしてもこれをどう雪と見れば良いのでしょうか。ネバネバとしている砂糖か、飴を溶かしたものが打ちまけられている。まさかこの構図で口の中に甘さを感じるとは思いませんでした。そしてこの作品で最も美しいのは、中央左下にある花が登場する部分です。ここでは砂糖が片栗粉のような質感へと変化し、上からパラパラとまぶされています。そして群がるどこかセクシーな花々。まるで少女漫画のワンカットのようです。ここでも始めの「芍薬群蝶図」の芍薬のように、鶏の生気を超えた存在感を見せつけていました。

「牡丹小禽図」(作品番号2-22)
画面を所狭しと支配する牡丹と、可愛らしいつがいの小鳥。ここでも小鳥は牡丹に飲まれてしまっています。それにしてもこの作品のうるささは一体どこに由来するのでしょう。それぞれの牡丹がスピーカーとなってがなり合っている。今にも牡丹から発せられた音声がやかましく聞こえてきそうです。画面に良いアクセントを与えている深い青がなければやや息苦しいかもしれません。(画像では良く分かりませんが、深いエメラルドグリーンが配されていました。)

「芦雁図」(作品番号2-26)
真っ逆さまになった一羽の大きな雁。彩色のせいか、羽の質感がややベタッとして、胴体がやや平面的に見えてきますが、その分、雁の重量感、まるで鉄の塊のような重たさを感じることが出来ます。驚いたようにパクッと開いた口。まるで「アレレ~」とでも言っているかのような慌てぶりです。それにしても雁は一体何を間違えたのでしょう。すぐ真下にはひび割れた氷の水面が広がっています。自ら身を投げているとしか思えない構図。枯れ枝にネバネバとまとわりつく雪の質感もまた奇異でした。
さて若冲ばかり触れてしまいましたが、展覧会自体は近世(江戸期)の花鳥画にスポットを当てた企画です。と言うことで、当然ながら若冲以外にもいくつか見応えのある作品が展示されています。その中では、屏風に簾を巧みにはめ込んだ狩野常信の「糸桜図屏風」がとても印象に残りました。可愛らしいピンク色の小さな桜。それが屏風と簾の両方へ連なるように描かれています。簾の上にも仄かなピンク色の顔料がたっぷりとのって美しく映えている。また簾の部分に奥行き感が見て取れるのも興味深いところでした。
初めにこの展覧会の予定を見知った際に、「動植綵絵」を6幅ずつとは言わずにまとめて見せて欲しいとも思いましたが、6幅だけでも目がクラクラするほどです。まとめて見たらそれこそ卒倒してしまうかもしれません。(また尚蔵館の展示スペースが非常に狭く、30幅全てを並べること自体が無理かとも思います。)会期は9月までですが、その間に後4回展示替えがあります。(もちろん「動植綵絵」の他の作品も入れ替わります。)皇居東御苑の散歩も兼ねながら、じっくりと楽しんでいきたい展覧会です。
会期:3/25-9/10
第1期3/25-4/23 第2期4/29-5/28 第3期6/3-7/2 第4期7/8-8/6 第5期8/12-9/10
*毎週月、金曜日、もしくは展示替え期間はお休みです。また入館時間が16時までなのでご注意下さい。ちなみに観覧料は無料です!
*関連エントリ
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第2期」 5/22
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第1期」
3/25-4/23
伊藤若冲の代表作「動植綵絵」全30幅が、6幅ずつ、5回に分けて、皇居東御苑内の三の丸尚蔵館にて公開されています。若冲ファン必見の展覧会です。
今回出品されていた「動植綵絵」は、展示順に並べると以下の通りです。修復が施された後だからか、ともかくこれでもかと言うほどに彩色が鮮やかでした。ジッと見つめていると目がクラクラしてきます。

「芍薬群蝶図」(作品番号2-1)
ひらひらと舞い降りて来た色とりどりの蝶と、地面から湧き上がって来たような紅白、それにピンクの芍薬(しゃくやく)。蝶がどれも見事に描かれているのはもちろんのこと、芍薬の花びらの透き通った味わいが絶品です。また、蝶よりも芍薬の描写の方が、不思議と生き生きしているように見えます。まるで蝶を食べようとする食虫植物のような芍薬。爛れた花びらに、ざわめく茎と枝。特に後者の生々しさは、草花にないはずの意思すら感じさせます。あたかも動物の手足のようになって、蝶を捕まえようと頑張っているのでしょうか。

「老松白鶏図」(作品番号2-11)
白く輝く二羽の鶏。鷹のように鋭い嘴と目を持っています。大輪の花のように咲き誇る背景の松はやや荒く見えましたが、砂金をまぶしたような黄金色が交じり合う鶏の羽は実に見事です。画面右上の真っ赤な陽と鶏は喧嘩をしているのでしょうか。鶏冠が、煌煌と照る陽の赤みに負けないほどに赤らんでいます。また、鶏の目がしっかりと陽を見据えている様子も構図に緊張感を与えます。思わずこの鶏の視線を追っかけてしまいました。

「南天雄鶏図」(作品番号2-14)
今回出品されていたものの中で一番インパクトのある作品です。どっしりと構える一羽の真っ黒な雄鶏。ともかくこの鶏冠には驚かされます。小さな白い点がたくさん配されている。大きく見開いた目と、牙を剥いているように鋭い嘴、そしてこの爬虫類の皮膚のようにグロテスクな鶏冠。もはや鶏とは思えないような堂々とした勇姿を、大見得を切るかのようにさらけ出しています。肉食恐竜が咆哮する姿。ぶら下がる南天は彼の餌でしょうか。これから襲いかかって引きちぎろうとしているようにも見えました。また、それを横取りするかのように南天を摘む小鳥の存在も見逃せません。ここに若冲ならではの心憎い演出が感じられます。

「雪中錦鶏図」(作品番号2-19)
主役の錦鶏の立場を奪うほどの存在感を見せているのは、画面全体にまるで垂れているように塗られた雪の描写です。それにしてもこれをどう雪と見れば良いのでしょうか。ネバネバとしている砂糖か、飴を溶かしたものが打ちまけられている。まさかこの構図で口の中に甘さを感じるとは思いませんでした。そしてこの作品で最も美しいのは、中央左下にある花が登場する部分です。ここでは砂糖が片栗粉のような質感へと変化し、上からパラパラとまぶされています。そして群がるどこかセクシーな花々。まるで少女漫画のワンカットのようです。ここでも始めの「芍薬群蝶図」の芍薬のように、鶏の生気を超えた存在感を見せつけていました。

「牡丹小禽図」(作品番号2-22)
画面を所狭しと支配する牡丹と、可愛らしいつがいの小鳥。ここでも小鳥は牡丹に飲まれてしまっています。それにしてもこの作品のうるささは一体どこに由来するのでしょう。それぞれの牡丹がスピーカーとなってがなり合っている。今にも牡丹から発せられた音声がやかましく聞こえてきそうです。画面に良いアクセントを与えている深い青がなければやや息苦しいかもしれません。(画像では良く分かりませんが、深いエメラルドグリーンが配されていました。)

「芦雁図」(作品番号2-26)
真っ逆さまになった一羽の大きな雁。彩色のせいか、羽の質感がややベタッとして、胴体がやや平面的に見えてきますが、その分、雁の重量感、まるで鉄の塊のような重たさを感じることが出来ます。驚いたようにパクッと開いた口。まるで「アレレ~」とでも言っているかのような慌てぶりです。それにしても雁は一体何を間違えたのでしょう。すぐ真下にはひび割れた氷の水面が広がっています。自ら身を投げているとしか思えない構図。枯れ枝にネバネバとまとわりつく雪の質感もまた奇異でした。
さて若冲ばかり触れてしまいましたが、展覧会自体は近世(江戸期)の花鳥画にスポットを当てた企画です。と言うことで、当然ながら若冲以外にもいくつか見応えのある作品が展示されています。その中では、屏風に簾を巧みにはめ込んだ狩野常信の「糸桜図屏風」がとても印象に残りました。可愛らしいピンク色の小さな桜。それが屏風と簾の両方へ連なるように描かれています。簾の上にも仄かなピンク色の顔料がたっぷりとのって美しく映えている。また簾の部分に奥行き感が見て取れるのも興味深いところでした。
初めにこの展覧会の予定を見知った際に、「動植綵絵」を6幅ずつとは言わずにまとめて見せて欲しいとも思いましたが、6幅だけでも目がクラクラするほどです。まとめて見たらそれこそ卒倒してしまうかもしれません。(また尚蔵館の展示スペースが非常に狭く、30幅全てを並べること自体が無理かとも思います。)会期は9月までですが、その間に後4回展示替えがあります。(もちろん「動植綵絵」の他の作品も入れ替わります。)皇居東御苑の散歩も兼ねながら、じっくりと楽しんでいきたい展覧会です。
会期:3/25-9/10
第1期3/25-4/23 第2期4/29-5/28 第3期6/3-7/2 第4期7/8-8/6 第5期8/12-9/10
*毎週月、金曜日、もしくは展示替え期間はお休みです。また入館時間が16時までなのでご注意下さい。ちなみに観覧料は無料です!
*関連エントリ
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第2期」 5/22
コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )
「第25回損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館 4/9
損保ジャパン東郷青児美術館(新宿区西新宿1-26-1 42階)
「第25回損保ジャパン美術財団 選抜奨励展 -選ばれた新進画家たち- 」
3/16-4/13
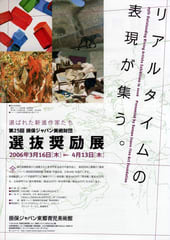
東京都美術館などで頻繁に開催されている公募展を見ることはまずありませんが、そこから選ばれた作家が一堂に会する展覧会となると少し気になります。と言うことで、全国36の公募展、もしくは推薦委員の推挙によって選ばれた作家たちの集う「損保ジャパン美術財団選抜奨励展」へ行ってきました。第25回を数える歴史ある展覧会とのことですが、出向いたのは今回が初めてです。

展示作品は平面が62点と、隔年で集められる立体作品が18点の計80点。さすがにどれも力の入った作品ばかりという印象を受けましたが、ズバリ、私の一推し作品は安冨洋貴の「僕に至る隔たり」(2005)です。どこか古びた団地かアパートの前で、仲良く対になって並んでいる二つのビニール傘。縦に並ぶ大小二つのガラス窓からは、一日を終えた後のくたびれた生活感が漂う電灯の明かりがもれている。地面はコンクリートによって塗り固められているのでしょうか。雨が染み込んで所々に溜まっています。そしてそれが窓の明かりを反射させて、傘自身をも映り込ませている。光と闇、または硬質の壁面や地面と、柔らかく透明なビニール傘の対比。それがモノトーンの美しい味わいによって巧みに表現されています。地味な構図であるのに、遠目から見ても非常に映える作品。そして何よりも驚かされるのが、この作品が油彩画ではなく鉛筆画だということです。恋人同士のように寄り添う傘の存在感がジワジワと伝わってくる。絵の前からなかなか離れられませんでした。
もう一点、画面の質感で非常に興味深かったのは、中山智介の「寡黙と饒舌の間から」(2005)です。このタイトルはあまり好きになれないのですが、ともかく油彩と岩絵具を織り交ぜた画面上の質感が面白い。闇に包まれた廃屋か神社。それが煌煌と輝く真っ赤な絵具に包まれている。木が激しく燃える音が聞こえてきます。そして黒い闇と、全体を覆う白い絵具の飛沫。パネルの表面には和紙が張られています。ゴワゴワとした、まるで石画のような質感も印象的です。
あまり惹かれた作品があったのも事実ですが、今挙げた二点のような美しい作品に出会えたのは大きな喜びでした。今後は毎年チェックしたいと思います。明日までの開催です。
「第25回損保ジャパン美術財団 選抜奨励展 -選ばれた新進画家たち- 」
3/16-4/13
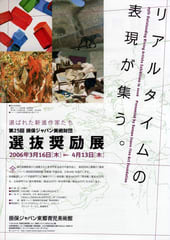
東京都美術館などで頻繁に開催されている公募展を見ることはまずありませんが、そこから選ばれた作家が一堂に会する展覧会となると少し気になります。と言うことで、全国36の公募展、もしくは推薦委員の推挙によって選ばれた作家たちの集う「損保ジャパン美術財団選抜奨励展」へ行ってきました。第25回を数える歴史ある展覧会とのことですが、出向いたのは今回が初めてです。

展示作品は平面が62点と、隔年で集められる立体作品が18点の計80点。さすがにどれも力の入った作品ばかりという印象を受けましたが、ズバリ、私の一推し作品は安冨洋貴の「僕に至る隔たり」(2005)です。どこか古びた団地かアパートの前で、仲良く対になって並んでいる二つのビニール傘。縦に並ぶ大小二つのガラス窓からは、一日を終えた後のくたびれた生活感が漂う電灯の明かりがもれている。地面はコンクリートによって塗り固められているのでしょうか。雨が染み込んで所々に溜まっています。そしてそれが窓の明かりを反射させて、傘自身をも映り込ませている。光と闇、または硬質の壁面や地面と、柔らかく透明なビニール傘の対比。それがモノトーンの美しい味わいによって巧みに表現されています。地味な構図であるのに、遠目から見ても非常に映える作品。そして何よりも驚かされるのが、この作品が油彩画ではなく鉛筆画だということです。恋人同士のように寄り添う傘の存在感がジワジワと伝わってくる。絵の前からなかなか離れられませんでした。
もう一点、画面の質感で非常に興味深かったのは、中山智介の「寡黙と饒舌の間から」(2005)です。このタイトルはあまり好きになれないのですが、ともかく油彩と岩絵具を織り交ぜた画面上の質感が面白い。闇に包まれた廃屋か神社。それが煌煌と輝く真っ赤な絵具に包まれている。木が激しく燃える音が聞こえてきます。そして黒い闇と、全体を覆う白い絵具の飛沫。パネルの表面には和紙が張られています。ゴワゴワとした、まるで石画のような質感も印象的です。
あまり惹かれた作品があったのも事実ですが、今挙げた二点のような美しい作品に出会えたのは大きな喜びでした。今後は毎年チェックしたいと思います。明日までの開催です。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
新国立劇場 「カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師」 4/9
新国立劇場 2005/2006シーズン
マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/レオンカヴァッロ「道化師」
指揮 ファビオ・ルイージ
演出 グリシャ・アサガロフ
合唱 新国立劇場合唱団
管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団
キャスト
「カヴァレリア・ルスティカーナ」
サントゥッツァ ガブリエーレ・シュナウト
ローラ 山下牧子
トゥリッドゥ アルベルト・クピード
アルフィオ 小林由樹
ルチア 三輪陽子
「道化師」
カニオ クリスティアン・フランツ
ネッダ 大村博美
トニオ 河野克典
ペッペ 樋口達哉
シルヴィオ 星野淳
児童合唱 世田谷ジュニア合唱団
2006/4/9 15:00~ 新国立劇場オペラ劇場 4階
これほどまでに劇場の音が変わるとは思いませんでした。ファビオ・ルイージが格の違いを見せつけた「カヴァレリア&道化師」です。ともかくルイージの指揮が素晴らしいの一言に尽きます。

私が新国立劇場へ通い出したのはここ数年のことですが、あまりにも美しい音楽に、初めてこの劇場にて涙を流しました。ともかくカヴァレリアの出だしの一音からして、これまでの新国立劇場の、また東フィルの音ではないと思ってしまうほどに素晴らしい。シルクの肌触りのようにしっとりとした弦と、ふくよかで、また爽やかな木管の調べ。金管こそやや残念な部分がありましたが、それでも驚くほどレンジが広い。自然体で、全く無理のない呼吸感。心情を静かに吐露するようなシーンから、合唱が入り交じって賑やかになる箇所まで、ともかく決して重くなることがなく、美感を損なわないで、軽快に劇を進めていく。もちろん音楽は全く遅滞しません。ヴェリズモの甘美でかつ、ドラマティクな管弦楽。それをこの劇場に教えるかのように手堅く、それでいて無理強いすることなく聴かせてくれる。これまでに噂には聞き、またCDでもそれなりに楽しませてくれたルイージですが、まさかここまで力のある指揮者とは思いませんでした。いつも何かと捻くれて文句を言ってしまうこの私も、ただこの音楽の前には聞き惚れるしかありません。新国立劇場でこれ以上の音楽を望むことはもう無理ではないか、そう少し寂しくも思ってしまうほどに素晴らしかった音楽。もう今回ばかりは盲目的に絶賛させていただきます。ファビオ・ルイージ、あなたは新国立劇場をこの公演だけでも変えました。スゴ過ぎます!
そんなルイージの至芸をより堪能出来たのは、特にカヴァレリアの音楽だったと思います。元々このオペラには実に美しい音楽が付いていますが、定番の間奏曲を初めとして、ともかくどこを切り取っても音楽が停滞しません。静かに木管が消えていく前奏曲の儚い音楽と、群衆のノリの良い軽快なワルツのリズム、そしてサントゥッツアが登場し、一気に沈みこんでくるラルゴのチェロ。ともかく冒頭のこれだけのシーンが、ルイージの軽快な指揮に引っ張られて、非常にスムーズに、そしてひたすら美しく奏でられていくのです。また時折煽り立てるようにテンポを早くしながらも、アリアの部分ではピッタリと歌手の呼吸感に合わせます。絶叫一辺倒のシュナウトと軽妙なクピードの組み合わせという奇妙なキャスティングにも決して迷うことがない。愛と憎しみの交じり合った彼ら彼女らの二重唱も、ルイージならではのスリリングなリズム感で巧みにリードしていきます。そして一転しての静謐な間奏曲。東フィルの弦がここで最高潮に達しました。春の高原に立って心地良い風を受けている。このホールで音がそんな感覚で聴こえて来たのは初めてです。これがイタリアオペラのリズム、そして響きなのでしょうか。
音楽は決してベタつきません。音符と音符の間のつなぎに清々しい空気が取り込まれて、全体としての音が塊にならずに、やわらかいスポンジ状になってホールをかき回す。消えてしまいそうなピアニッシモから、驚天動地のフォルテッシモまで、全てしっかりと最後まで音が抜けきっている。パリアッチでのやや錯綜とした音楽も、楽々と裁いていとも簡単にクライマックスへ持って行ってしまいます。劇中劇から憎しみの果ての殺人へ。ルイージは音楽における力の抜きどころを全て心得ているのでしょうか。合唱の絡んだネッダの芝居のシーンでは、音楽に半ば穴を空けるかのように抑え気味に響かせて、カニオの「もう道化師じゃない」あたりから一気に加速し、音楽に厚みを持たせていく。そうすることで劇の核心がハッキリと音楽上で示されます。劇のカタストロフィへの道程。それを伴奏だけで感じ取れたのは最近の新国立劇場では記憶にない。これには感動を取り越して半ば驚いてしまうほどでした。もう言葉もありません。
さてルイージばかり長々と書いてしまいましたが、キャストでは、やや役柄に違和感もあるカニオのフランツがさすがの歌唱でした。ともかくフランツは喜怒哀楽の表現を歌にのせるのが実に上手いと思います。道化師の身を嘆いて泣き崩れる「衣装をつけろ」のアリアと、ラストでのネッダやシルヴィオへの憎しみ。それがあの柔らかい声にのせられて巧みに対比されている。たんに声を張り上げないで、時に強烈な巻き舌で畳み掛けるように歌い、また凄んでいくその様子は、聴く者をグッと劇へ引き込む力があります。声量でホールを圧倒するだけで終らないその芸達者な表現力。他のキャストをゆうに超えていました。その他では、シルヴィオの星野淳やペッぺの樋口達哉が印象に残りました。逆に残念だったのはネッダの大村博美です。私にはやや違和感がありました。また、カヴァのシュナウトとクピードは思いっきり好き嫌いが分かれそうな歌唱です。クピードは務めを果たしていたとは思いますが、シュナウトはやはり別の役で聴きたかったと思います。
新国立劇場のイタリアオペラの公演にて非常に感動した指揮と言うと、最近ではマクベスを指揮したフリッツアぐらいしか思いつかないのですが、それを余裕で上回るルイージの指揮には心底酔わせていただきました。とにかく一にルイージ、二にルイージです。私にとってはこの上ない喜びの時間を過ごすことが出来ました。マエストロルイージ、どうもありがとう!
マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/レオンカヴァッロ「道化師」
指揮 ファビオ・ルイージ
演出 グリシャ・アサガロフ
合唱 新国立劇場合唱団
管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団
キャスト
「カヴァレリア・ルスティカーナ」
サントゥッツァ ガブリエーレ・シュナウト
ローラ 山下牧子
トゥリッドゥ アルベルト・クピード
アルフィオ 小林由樹
ルチア 三輪陽子
「道化師」
カニオ クリスティアン・フランツ
ネッダ 大村博美
トニオ 河野克典
ペッペ 樋口達哉
シルヴィオ 星野淳
児童合唱 世田谷ジュニア合唱団
2006/4/9 15:00~ 新国立劇場オペラ劇場 4階
これほどまでに劇場の音が変わるとは思いませんでした。ファビオ・ルイージが格の違いを見せつけた「カヴァレリア&道化師」です。ともかくルイージの指揮が素晴らしいの一言に尽きます。

私が新国立劇場へ通い出したのはここ数年のことですが、あまりにも美しい音楽に、初めてこの劇場にて涙を流しました。ともかくカヴァレリアの出だしの一音からして、これまでの新国立劇場の、また東フィルの音ではないと思ってしまうほどに素晴らしい。シルクの肌触りのようにしっとりとした弦と、ふくよかで、また爽やかな木管の調べ。金管こそやや残念な部分がありましたが、それでも驚くほどレンジが広い。自然体で、全く無理のない呼吸感。心情を静かに吐露するようなシーンから、合唱が入り交じって賑やかになる箇所まで、ともかく決して重くなることがなく、美感を損なわないで、軽快に劇を進めていく。もちろん音楽は全く遅滞しません。ヴェリズモの甘美でかつ、ドラマティクな管弦楽。それをこの劇場に教えるかのように手堅く、それでいて無理強いすることなく聴かせてくれる。これまでに噂には聞き、またCDでもそれなりに楽しませてくれたルイージですが、まさかここまで力のある指揮者とは思いませんでした。いつも何かと捻くれて文句を言ってしまうこの私も、ただこの音楽の前には聞き惚れるしかありません。新国立劇場でこれ以上の音楽を望むことはもう無理ではないか、そう少し寂しくも思ってしまうほどに素晴らしかった音楽。もう今回ばかりは盲目的に絶賛させていただきます。ファビオ・ルイージ、あなたは新国立劇場をこの公演だけでも変えました。スゴ過ぎます!
そんなルイージの至芸をより堪能出来たのは、特にカヴァレリアの音楽だったと思います。元々このオペラには実に美しい音楽が付いていますが、定番の間奏曲を初めとして、ともかくどこを切り取っても音楽が停滞しません。静かに木管が消えていく前奏曲の儚い音楽と、群衆のノリの良い軽快なワルツのリズム、そしてサントゥッツアが登場し、一気に沈みこんでくるラルゴのチェロ。ともかく冒頭のこれだけのシーンが、ルイージの軽快な指揮に引っ張られて、非常にスムーズに、そしてひたすら美しく奏でられていくのです。また時折煽り立てるようにテンポを早くしながらも、アリアの部分ではピッタリと歌手の呼吸感に合わせます。絶叫一辺倒のシュナウトと軽妙なクピードの組み合わせという奇妙なキャスティングにも決して迷うことがない。愛と憎しみの交じり合った彼ら彼女らの二重唱も、ルイージならではのスリリングなリズム感で巧みにリードしていきます。そして一転しての静謐な間奏曲。東フィルの弦がここで最高潮に達しました。春の高原に立って心地良い風を受けている。このホールで音がそんな感覚で聴こえて来たのは初めてです。これがイタリアオペラのリズム、そして響きなのでしょうか。
音楽は決してベタつきません。音符と音符の間のつなぎに清々しい空気が取り込まれて、全体としての音が塊にならずに、やわらかいスポンジ状になってホールをかき回す。消えてしまいそうなピアニッシモから、驚天動地のフォルテッシモまで、全てしっかりと最後まで音が抜けきっている。パリアッチでのやや錯綜とした音楽も、楽々と裁いていとも簡単にクライマックスへ持って行ってしまいます。劇中劇から憎しみの果ての殺人へ。ルイージは音楽における力の抜きどころを全て心得ているのでしょうか。合唱の絡んだネッダの芝居のシーンでは、音楽に半ば穴を空けるかのように抑え気味に響かせて、カニオの「もう道化師じゃない」あたりから一気に加速し、音楽に厚みを持たせていく。そうすることで劇の核心がハッキリと音楽上で示されます。劇のカタストロフィへの道程。それを伴奏だけで感じ取れたのは最近の新国立劇場では記憶にない。これには感動を取り越して半ば驚いてしまうほどでした。もう言葉もありません。
さてルイージばかり長々と書いてしまいましたが、キャストでは、やや役柄に違和感もあるカニオのフランツがさすがの歌唱でした。ともかくフランツは喜怒哀楽の表現を歌にのせるのが実に上手いと思います。道化師の身を嘆いて泣き崩れる「衣装をつけろ」のアリアと、ラストでのネッダやシルヴィオへの憎しみ。それがあの柔らかい声にのせられて巧みに対比されている。たんに声を張り上げないで、時に強烈な巻き舌で畳み掛けるように歌い、また凄んでいくその様子は、聴く者をグッと劇へ引き込む力があります。声量でホールを圧倒するだけで終らないその芸達者な表現力。他のキャストをゆうに超えていました。その他では、シルヴィオの星野淳やペッぺの樋口達哉が印象に残りました。逆に残念だったのはネッダの大村博美です。私にはやや違和感がありました。また、カヴァのシュナウトとクピードは思いっきり好き嫌いが分かれそうな歌唱です。クピードは務めを果たしていたとは思いますが、シュナウトはやはり別の役で聴きたかったと思います。
新国立劇場のイタリアオペラの公演にて非常に感動した指揮と言うと、最近ではマクベスを指揮したフリッツアぐらいしか思いつかないのですが、それを余裕で上回るルイージの指揮には心底酔わせていただきました。とにかく一にルイージ、二にルイージです。私にとってはこの上ない喜びの時間を過ごすことが出来ました。マエストロルイージ、どうもありがとう!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
今年の「熱狂の日音楽祭」のチケットは如何に?
ゴールデンウィークに東京国際フォーラムで開催予定のクラシック音楽の祭典、「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」(熱狂の日音楽祭)がいよいよ三週間後に迫ってきました。今年のテーマ作曲家は、もちろんメモリアルイヤーのモーツァルト。(厳密には「モーツァルトと仲間たち」ですが。)非常に話題性が高く、またメディア等への露出も多いせいか、昨年よりもチケットの売れ行きが断然良いようです。直前まであまり盛り上がりを見せなかった昨年とはかなり様相が異なっています。チケット争奪戦はなかなかシビアです。

今ぴあでチケットの発売状況を確認してみても、座席数が5000席以上という巨大なAホールの公演を除けば、軒並み完売と言ってもおかしくないほどチケットが残っていません。来日の少ない人気演奏家の公演などはもちろんのこと、同じ大ホールを使った公演でも、当然ながらAよりもCホールへ人気が集中して、そちらのチケットが購入しにくい状況になっています。そして室内楽や器楽曲関係の公演も完売続出。残席のあるものの方が少ないと言えるほどです。また、つい先日も完売公演の二次発売が行われましたが、やはり人気の公演はものの数十分(?)で売り切れました。私も無精なので、その二次発売でチケットを今更ながら少し購入したのですが、まさかこれほどの状態とは思いもよりませんでした。(フレンズ会員になっておいてこの有様です…。)
ただし当然ながら、前売が完売した公演でもまだチャンスがないわけではありません。それは、気軽にぶらりと立ち寄って音楽を楽しむという、「熱狂の日」のコンセプトに基づいて一定数確保される当日券です。座席数の内、どの程度の割合で当日券が出るのかは分かりませんが、少なくとも殆どの公演で発売されるはず。今の段階では「当日券を狙って人気公演を。」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。
それにしても当日券と聞いてすぐに思い出されるのが、昨年の「熱狂の日」における当日券販売の不手際ぶりです。チケットブースが少ないからなのか、発券に手間取り過ぎたのか、当日券売場はどこも大混雑。あげくの果てには、会場近くのぴあでは券が購入出来たのに、会場ブースでは混み過ぎて買えなかったという話も耳にしました。今年は絶対そのようなことがないよう、是非ともお願いしたいです。
私は連続して音楽を聴けるような集中力がないものなので、一日だけ出向いてコルボの「レクイエム」や、ベルリン古楽アカデミーのディヴェルティメントなどを楽しもうかと思っています。最後にチケットですが、現段階ではぴあやイープラスよりも楽天チケットの方が若干余裕があるようです。「熱狂の日」をご予定の方でまだチケットを購入されていらっしゃらない方は、一度ご確認なされることをおすすめします。
訂正:当日券は、前売り券の完売した公演は発売されないようです。ご注意下さい。(公式サイト、前売状況。)
*関連リンク
熱狂の日音楽祭
ぴあ
楽天チケット
イープラス
*関連エントリ
「『ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006』、ついに開幕!」(2006/4/30)
「『熱狂の日音楽祭』のあとは『ぶらあぼ』で!」(2006/5/4)
「モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 『熱狂の日音楽祭2006』」(2006/5/5)

今ぴあでチケットの発売状況を確認してみても、座席数が5000席以上という巨大なAホールの公演を除けば、軒並み完売と言ってもおかしくないほどチケットが残っていません。来日の少ない人気演奏家の公演などはもちろんのこと、同じ大ホールを使った公演でも、当然ながらAよりもCホールへ人気が集中して、そちらのチケットが購入しにくい状況になっています。そして室内楽や器楽曲関係の公演も完売続出。残席のあるものの方が少ないと言えるほどです。また、つい先日も完売公演の二次発売が行われましたが、やはり人気の公演はものの数十分(?)で売り切れました。私も無精なので、その二次発売でチケットを今更ながら少し購入したのですが、まさかこれほどの状態とは思いもよりませんでした。(フレンズ会員になっておいてこの有様です…。)
ただし当然ながら、前売が完売した公演でもまだチャンスがないわけではありません。それは、気軽にぶらりと立ち寄って音楽を楽しむという、「熱狂の日」のコンセプトに基づいて一定数確保される当日券です。座席数の内、どの程度の割合で当日券が出るのかは分かりませんが、少なくとも殆どの公演で発売されるはず。今の段階では「当日券を狙って人気公演を。」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。
それにしても当日券と聞いてすぐに思い出されるのが、昨年の「熱狂の日」における当日券販売の不手際ぶりです。チケットブースが少ないからなのか、発券に手間取り過ぎたのか、当日券売場はどこも大混雑。あげくの果てには、会場近くのぴあでは券が購入出来たのに、会場ブースでは混み過ぎて買えなかったという話も耳にしました。今年は絶対そのようなことがないよう、是非ともお願いしたいです。
私は連続して音楽を聴けるような集中力がないものなので、一日だけ出向いてコルボの「レクイエム」や、ベルリン古楽アカデミーのディヴェルティメントなどを楽しもうかと思っています。最後にチケットですが、現段階ではぴあやイープラスよりも楽天チケットの方が若干余裕があるようです。「熱狂の日」をご予定の方でまだチケットを購入されていらっしゃらない方は、一度ご確認なされることをおすすめします。
訂正:当日券は、前売り券の完売した公演は発売されないようです。ご注意下さい。(公式サイト、前売状況。)
*関連リンク
熱狂の日音楽祭
ぴあ
楽天チケット
イープラス
*関連エントリ
「『ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006』、ついに開幕!」(2006/4/30)
「『熱狂の日音楽祭』のあとは『ぶらあぼ』で!」(2006/5/4)
「モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 『熱狂の日音楽祭2006』」(2006/5/5)
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
「宇治山哲平展」 東京都庭園美術館 4/2
東京都庭園美術館(港区白金台5-21-9)
「宇治山哲平展 -絵に遊ぶ、絵に憩う- 」
2/4-4/9
二月から東京都庭園美術館で開催されている宇治山哲平の回顧展です。先日ようやく見に行くことが出来ました。

旧朝香宮邸の東京都庭園美術館は、展示作品を美しく映えさせるような趣きのある建物ですが、今回の宇治山展においても作品をより美しいものに仕立て上げていました。色とりどりの三角や四角形の踊った抽象世界が、どっしりとしたアール・デコ様式の室内へ溶け込んでいく。まとまって見ることで浮かび上がってくる宇治山の魅力が、アール・デコという借景によってさらに高まっています。建物と作品が相互に良い方向へ作用し合った、とても贅沢な展覧会です。


宇治山の作品を見ると、まずどうしてもその独特な形象へ目が向いてしまいますが、一番注視すべき点は形ではなく、作品の驚くべき質感にあると思います。画像やパンフレットでは全く分からないのが残念ですが、彼の魅力の半分以上は作品表面の見事な質感に由来しているかもしれません。幾何学的に区切られているデザイン的な画風が、その質感によって工芸的な、まるで古代の壁画のような趣をたたえてくる。そこに宇治山の醍醐味があるようです。
その質感の秘密は、ズバリ、キャンバスに使われた油彩にありました。パッと見ただけでは、油彩が使用されているとは分からないザラザラとしたキャンバスの表面。砂かざらめがまかれたような表面に象られている三角形や丸。それがキャンバスにペタッと張り付いている。ザラメの中身は、水晶など鉱石の粉末を混ぜて生み出された油彩絵具です。それをペインティングナイフで、パンにバターを塗り込むようにしてキャンバスにのせていく。それが画肌に、どこか壁画のような質感を生み出すようです。彼のこの技法には、当時「工芸的過ぎる。」という批判も浴びせられたそうですが、この絵具がなければ宇治山の魅力は半減するとさえ思います。(さらにごく普通に油彩をキャンバスに塗り込んだ部分との対比もまた面白い。)ともかく実物に接してそのざらめの感触を味わって欲しい。そう言いたくなるほどに魅惑的な、また意外性のある質感です。

展示は宇治山の画業史が分かるように構成されていました。絵画における形の変化と、絵具の質感の違い。それが時間的にどう変わっていくのか。最終的にはカラフルで鮮やかなタペストリーのような祝祭的な抽象画へと落ち着きましたが、私としてはその一つ前の段階の、やや構成に余白の多い、形に揺らぎのある作品の方が美しく見えました。また彼が抽象画にたどり着くまでに描いた版画作品や、いわゆる具象画もいくつか展示されています。(宇治山は版画作家としてスタートしたようです。)そちらの素朴な風情もまた必見です。

最後の展示室であるウィンターガーデンには、クラシックファンにとっては思いがけない作品が紹介されていました。それはサントリーホールのホワイエに展示されている「響」(1986年)です。ちょうど正面玄関の頭上に、横20メートルあまりに配された大理石の丸や四角。(ちなみにこの大理石は宇治山自身が一点ずつ見定めたものだそうです。)当然ながら大理石なので、キャンバス作品にある独特の質感は楽しめませんが、全体的にやや静的な味わいのある宇治山の作品の中でも、この「響」はどこか音楽的に感じられます。大理石がそれこそ音符となって響き合っている。ポリフォニックなバロックの調べ。バッハのチェンバロ協奏曲が浮かんできました。足早とホール内へ入る前に、暫し上を眺めながら宇治山の作品に見入るのも良いかもしれません。二階部分の手すりから眺めれば上手く一望出来そうです。それにしてもまさかあのように身近な場所(?)に彼の作品があるとは知りませんでした。迂闊です。今度しっかりと確認してきます。
最後に、宇治山の印象的な言葉を紹介します。
「私の絵画は具象的な描写ではないが、自然の全てが画因である。太陽、石、山脈、風、凍土、動植物など、あらゆる自然のリズムや形象を、極めて単純な記号のような原形にまで抽象して生気を蘇らせたいと希っている。」(美について想う 1962)
お庭の桜を見ながら、どっぷりとアール・デコに浸って宇治山の静かなリズムに身を任せる休日。明日までの開催です。
「宇治山哲平展 -絵に遊ぶ、絵に憩う- 」
2/4-4/9
二月から東京都庭園美術館で開催されている宇治山哲平の回顧展です。先日ようやく見に行くことが出来ました。

旧朝香宮邸の東京都庭園美術館は、展示作品を美しく映えさせるような趣きのある建物ですが、今回の宇治山展においても作品をより美しいものに仕立て上げていました。色とりどりの三角や四角形の踊った抽象世界が、どっしりとしたアール・デコ様式の室内へ溶け込んでいく。まとまって見ることで浮かび上がってくる宇治山の魅力が、アール・デコという借景によってさらに高まっています。建物と作品が相互に良い方向へ作用し合った、とても贅沢な展覧会です。


宇治山の作品を見ると、まずどうしてもその独特な形象へ目が向いてしまいますが、一番注視すべき点は形ではなく、作品の驚くべき質感にあると思います。画像やパンフレットでは全く分からないのが残念ですが、彼の魅力の半分以上は作品表面の見事な質感に由来しているかもしれません。幾何学的に区切られているデザイン的な画風が、その質感によって工芸的な、まるで古代の壁画のような趣をたたえてくる。そこに宇治山の醍醐味があるようです。
その質感の秘密は、ズバリ、キャンバスに使われた油彩にありました。パッと見ただけでは、油彩が使用されているとは分からないザラザラとしたキャンバスの表面。砂かざらめがまかれたような表面に象られている三角形や丸。それがキャンバスにペタッと張り付いている。ザラメの中身は、水晶など鉱石の粉末を混ぜて生み出された油彩絵具です。それをペインティングナイフで、パンにバターを塗り込むようにしてキャンバスにのせていく。それが画肌に、どこか壁画のような質感を生み出すようです。彼のこの技法には、当時「工芸的過ぎる。」という批判も浴びせられたそうですが、この絵具がなければ宇治山の魅力は半減するとさえ思います。(さらにごく普通に油彩をキャンバスに塗り込んだ部分との対比もまた面白い。)ともかく実物に接してそのざらめの感触を味わって欲しい。そう言いたくなるほどに魅惑的な、また意外性のある質感です。

展示は宇治山の画業史が分かるように構成されていました。絵画における形の変化と、絵具の質感の違い。それが時間的にどう変わっていくのか。最終的にはカラフルで鮮やかなタペストリーのような祝祭的な抽象画へと落ち着きましたが、私としてはその一つ前の段階の、やや構成に余白の多い、形に揺らぎのある作品の方が美しく見えました。また彼が抽象画にたどり着くまでに描いた版画作品や、いわゆる具象画もいくつか展示されています。(宇治山は版画作家としてスタートしたようです。)そちらの素朴な風情もまた必見です。

最後の展示室であるウィンターガーデンには、クラシックファンにとっては思いがけない作品が紹介されていました。それはサントリーホールのホワイエに展示されている「響」(1986年)です。ちょうど正面玄関の頭上に、横20メートルあまりに配された大理石の丸や四角。(ちなみにこの大理石は宇治山自身が一点ずつ見定めたものだそうです。)当然ながら大理石なので、キャンバス作品にある独特の質感は楽しめませんが、全体的にやや静的な味わいのある宇治山の作品の中でも、この「響」はどこか音楽的に感じられます。大理石がそれこそ音符となって響き合っている。ポリフォニックなバロックの調べ。バッハのチェンバロ協奏曲が浮かんできました。足早とホール内へ入る前に、暫し上を眺めながら宇治山の作品に見入るのも良いかもしれません。二階部分の手すりから眺めれば上手く一望出来そうです。それにしてもまさかあのように身近な場所(?)に彼の作品があるとは知りませんでした。迂闊です。今度しっかりと確認してきます。
最後に、宇治山の印象的な言葉を紹介します。
「私の絵画は具象的な描写ではないが、自然の全てが画因である。太陽、石、山脈、風、凍土、動植物など、あらゆる自然のリズムや形象を、極めて単純な記号のような原形にまで抽象して生気を蘇らせたいと希っている。」(美について想う 1962)
お庭の桜を見ながら、どっぷりとアール・デコに浸って宇治山の静かなリズムに身を任せる休日。明日までの開催です。
コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )
「ロダンとカリエール 特別鑑賞会 講演会」 国立西洋美術館 4/4
国立西洋美術館
「ロダンとカリエール 特別鑑賞会 講演会」
4/4 18:00~
先日「弐代目・青い日記帳」のTakさんのご好意によって参加させていただいた、毎日新聞社主催の特別鑑賞会で行われた講演会です。講師は美術館主任研究員の大屋美那氏。約30分ほどの時間で、展覧会の主旨や、二人の芸術家の類似点ついて簡単に触れていく内容でした。
「ロダンとカリエール展 特別鑑賞会 講演会」
国立西洋美術館講堂
講師 大屋美那(美術館主任研究員)
ロダンとカリエール展について
・ロダン(彫刻の巨匠・大家)とカリエール(知名度に欠ける画家)
→ともに外光を発見した印象派のグループに属するが、もっと人の内面的な要素に関心があった。
=象徴主義
↓
二人の親交。そこから二人の芸術性を結びつけていく
カリエールの意外性に注目し、また既存のロダン像(「カレーの市民」や「考える人」のイメージ)に楔を打ち込む。
二人の類似点(形の上だけではない、思想上の)を示していく。
ロダンとカリエールの関係とは -第一章と第二章において-
第一章「ロダン像とカリエール像」
・ロダンとカリエールの人物を紹介する。
カリエールの描いたロダンと、ロダンの制作したカリエールのデスマスクを並べて展示。


・二人の出会いは1880年頃
ロダン=職人
カリエール=ワインラベルなどを手がけるリトグラフの制作者。
→パリ・セーブルの陶磁器製作所にて知り合う。
・家族的な親交
作品を交換し合う。特にロダンは最後までカリエールの作品を手放さなかった。
第二章「ロダンとカリエールの直接の交流」
・アトリエを再現した会場
展示作品はともに二人のアトリエから出て来たもの。
互いにどう影響し合ったのかを考えていく。
・1900年のロダン展
パリ万博に合わせて開催された。
生前では最大の回顧展。(「地獄の門」が公開。)
展覧会のポスターはカリエールが制作。
 (ポスターの一部)
(ポスターの一部)
・カリエールの母子像とロダンのイース(トルソ)
母性愛(カリエール)と濃密な性愛表現(ロダン)の対比
ロダンには絡み合うような男女愛を象った作品が多い。
一方のカリエールはヌード作品が多いもの、母性愛を表現したものが多い。


・二人に共通のモチーフ
芸術家にインスピレーションを与えるミューズ
芸術家に舞い降りるミューズ
画家とモデル
モデルに触れる画家(モデルの存在を手で確認。彫刻を制作するかのよう。)
内なる生命を見出す=形に魂を与える=象徴主義的

以上です。
この後は三章以降の展示についてもお話になる予定だったのかと思いますが、おそらく時間切れでしょうか、ちょっと中途半端な所でまとまってしまいました。今回の講演の核心は、やはり二人の類似点、特に最後で触れた「芸術家とミューズ」または「画家とモデル」のモチーフの行です。そこからロダンとカリエールの「思想上」の類似点も考えて欲しい。そんな企画者側のメッセージを感じる内容でした。
さて初めにも触れましたが、この日は毎日新聞社の特別鑑賞会ということで、西洋美術館の「ロダンとカリエール展」を、閉館後ののんびりとした雰囲気の中でたっぷりと堪能させていただきました。あともう一度だけ出向く予定なので、この日の講演会を踏まえた上での展覧会の感想を、拙いですがまた後日にアップしたいと思います。
*関連エントリ
「ロダンとカリエール」展感想 3/19
「ロダン、カリエールと同時代の文化、社会」(講演会) 4/15
「ロダンとカリエール 特別鑑賞会 講演会」
4/4 18:00~
先日「弐代目・青い日記帳」のTakさんのご好意によって参加させていただいた、毎日新聞社主催の特別鑑賞会で行われた講演会です。講師は美術館主任研究員の大屋美那氏。約30分ほどの時間で、展覧会の主旨や、二人の芸術家の類似点ついて簡単に触れていく内容でした。
「ロダンとカリエール展 特別鑑賞会 講演会」
国立西洋美術館講堂
講師 大屋美那(美術館主任研究員)
ロダンとカリエール展について
・ロダン(彫刻の巨匠・大家)とカリエール(知名度に欠ける画家)
→ともに外光を発見した印象派のグループに属するが、もっと人の内面的な要素に関心があった。
=象徴主義
↓
二人の親交。そこから二人の芸術性を結びつけていく
カリエールの意外性に注目し、また既存のロダン像(「カレーの市民」や「考える人」のイメージ)に楔を打ち込む。
二人の類似点(形の上だけではない、思想上の)を示していく。
ロダンとカリエールの関係とは -第一章と第二章において-
第一章「ロダン像とカリエール像」
・ロダンとカリエールの人物を紹介する。
カリエールの描いたロダンと、ロダンの制作したカリエールのデスマスクを並べて展示。


・二人の出会いは1880年頃
ロダン=職人
カリエール=ワインラベルなどを手がけるリトグラフの制作者。
→パリ・セーブルの陶磁器製作所にて知り合う。
・家族的な親交
作品を交換し合う。特にロダンは最後までカリエールの作品を手放さなかった。
第二章「ロダンとカリエールの直接の交流」
・アトリエを再現した会場
展示作品はともに二人のアトリエから出て来たもの。
互いにどう影響し合ったのかを考えていく。
・1900年のロダン展
パリ万博に合わせて開催された。
生前では最大の回顧展。(「地獄の門」が公開。)
展覧会のポスターはカリエールが制作。
 (ポスターの一部)
(ポスターの一部)・カリエールの母子像とロダンのイース(トルソ)
母性愛(カリエール)と濃密な性愛表現(ロダン)の対比
ロダンには絡み合うような男女愛を象った作品が多い。
一方のカリエールはヌード作品が多いもの、母性愛を表現したものが多い。


・二人に共通のモチーフ
芸術家にインスピレーションを与えるミューズ
芸術家に舞い降りるミューズ
画家とモデル
モデルに触れる画家(モデルの存在を手で確認。彫刻を制作するかのよう。)
内なる生命を見出す=形に魂を与える=象徴主義的

以上です。
この後は三章以降の展示についてもお話になる予定だったのかと思いますが、おそらく時間切れでしょうか、ちょっと中途半端な所でまとまってしまいました。今回の講演の核心は、やはり二人の類似点、特に最後で触れた「芸術家とミューズ」または「画家とモデル」のモチーフの行です。そこからロダンとカリエールの「思想上」の類似点も考えて欲しい。そんな企画者側のメッセージを感じる内容でした。
さて初めにも触れましたが、この日は毎日新聞社の特別鑑賞会ということで、西洋美術館の「ロダンとカリエール展」を、閉館後ののんびりとした雰囲気の中でたっぷりと堪能させていただきました。あともう一度だけ出向く予定なので、この日の講演会を踏まえた上での展覧会の感想を、拙いですがまた後日にアップしたいと思います。
*関連エントリ
「ロダンとカリエール」展感想 3/19
「ロダン、カリエールと同時代の文化、社会」(講演会) 4/15
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「戸谷成雄 『ミニマルバロック』」 シュウゴアーツ 4/1
シュウゴアーツ(江東区清澄1-3-2 5F)
「戸谷成雄 『ミニマルバロック』」
3/18-4/28
「ミニマルバロック」と名付けられた戸谷成雄の新作展覧会です。戸谷と言えば、まずは刻み込みで覆われた木の柱を思い出しますが、今回はそれを含めた木の塊の作品が数点展示されています。戸谷の創作の今に触れられる展覧会でした。

まずは展示室正面の壁面に展示されている彫刻作品「双影根2 黄河」(2006)です。木彫と言っても、戸谷の作品はチェーンソーによって切り刻んだ痕跡を見せるもの。まるで襞のような削り跡が、生々しく群生するかのように寄り添っています。そして木棺のように整然と象られた白箱。それが襞に対峙するかのように連続している。素材に組み合わされたアクリルと灰は、木から生気を奪うのでしょうか。生々しい襞の形には見合わないような静謐な質感が漂っています。その味わいもまた見事でした。
「双影根」の前に展示されている球形の作品「双影塊」(2006)も見応えがあります。ゴツゴツと荒々しく刻まれた木の球。ここには「双影根」における襞のような紋様はあまりありません。特に上部の造形は非常に直線的。まるで高層ビルが林立しているかのように象られています。とある惑星の、知的生命体が滅亡した後の都市の廃墟。そんなイメージも浮かんできました。
球体にて生命の痕跡を表現したのが「双影塊」とするなら、それをまさに大地のように横へと広げたのが、入口付近の床へ直に置かれている「三影体」(2006)でしょう。神の業によって刻まれた山々と渓谷。「双影根」で見せた襞がさらに広がりを見せながら横たわっている。視点を落として作品を見ていくと、今にもその大地に吸い込まれてしまいそうになります。龍や炎のようにも見える襞が、こうして地に這わすことで全く異なった造形に見えてくるのも興味深いところです。
奥の小部屋にはお馴染みの木柱の作品「斜影柱」(2006)や、あまり他では見かけないようなドローイングも展示されています。そちらも必見です。
今月28日までの開催です。今回出向いた清澄のギャラリーの中では最も見応えがありました。おすすめします。
「戸谷成雄 『ミニマルバロック』」
3/18-4/28
「ミニマルバロック」と名付けられた戸谷成雄の新作展覧会です。戸谷と言えば、まずは刻み込みで覆われた木の柱を思い出しますが、今回はそれを含めた木の塊の作品が数点展示されています。戸谷の創作の今に触れられる展覧会でした。

まずは展示室正面の壁面に展示されている彫刻作品「双影根2 黄河」(2006)です。木彫と言っても、戸谷の作品はチェーンソーによって切り刻んだ痕跡を見せるもの。まるで襞のような削り跡が、生々しく群生するかのように寄り添っています。そして木棺のように整然と象られた白箱。それが襞に対峙するかのように連続している。素材に組み合わされたアクリルと灰は、木から生気を奪うのでしょうか。生々しい襞の形には見合わないような静謐な質感が漂っています。その味わいもまた見事でした。
「双影根」の前に展示されている球形の作品「双影塊」(2006)も見応えがあります。ゴツゴツと荒々しく刻まれた木の球。ここには「双影根」における襞のような紋様はあまりありません。特に上部の造形は非常に直線的。まるで高層ビルが林立しているかのように象られています。とある惑星の、知的生命体が滅亡した後の都市の廃墟。そんなイメージも浮かんできました。
球体にて生命の痕跡を表現したのが「双影塊」とするなら、それをまさに大地のように横へと広げたのが、入口付近の床へ直に置かれている「三影体」(2006)でしょう。神の業によって刻まれた山々と渓谷。「双影根」で見せた襞がさらに広がりを見せながら横たわっている。視点を落として作品を見ていくと、今にもその大地に吸い込まれてしまいそうになります。龍や炎のようにも見える襞が、こうして地に這わすことで全く異なった造形に見えてくるのも興味深いところです。
奥の小部屋にはお馴染みの木柱の作品「斜影柱」(2006)や、あまり他では見かけないようなドローイングも展示されています。そちらも必見です。
今月28日までの開催です。今回出向いた清澄のギャラリーの中では最も見応えがありました。おすすめします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「鶏の塩そぼろ飯と翡翠麺」 Cafe 茶洒 kanetanaka 4/2
「Cafe 茶洒 kanetanaka」
東京都庭園美術館
鶏の塩そぼろ飯と翡翠麺
つい先日、東京都庭園美術館にオープン(3/24)したばかりの新しいカフェ「茶酒」です。宇治山哲平展へ行った折に、早速利用してみました。


料亭「金田中」の手がけるレストランと言うことで、メニューは当然ながら和食です。翡翠麺と丼もののセットをメインに、甘味までを幅広く提供します。唯一のコースメニューの「サーシャの定食」のお値段は3500円。私の感覚では美術館ランチとしてはやや高い印象も受けますが、ミニサイズのお茶碗でご飯や麺を出す「ひとくち飯と時季のごはん」と「ひとくち飯と翡翠麺」のセットは、1000円から1700円弱前後です。これなら手軽に楽しむことが出来ます。

この日注文したのは「鶏の塩そぼろ飯と翡翠麺」。それにコーヒーを付けてみました。可愛らしい丸いお盆に、ご飯、一口サイズの翡翠麺、それにミニ茶碗蒸しが所狭しと並びます。
どれもお味は上々。量は決して多いとは言えないので、お腹いっぱいになるかかどうかは難しいところですが、この際美味しいものであれば量の如何は問いません。この値段でこのお味なら私は納得。塩味がほんのり口に広がる鴨、ご飯の甘みを引き出す控えめな鶏そぼろ、お出汁のよくきいた関東風(?)の茶碗蒸し。お庭の桜を眺めながらゆっくりといただきました。

食後にはコーヒーを楽しみます。赤いお茶碗にて運ばれてきました。深煎りの、それでいながら後味の良い、喉越しの爽やかなコーヒーです。こちらは250円程度だったでしょうか。甘味も提供するお店なので、和菓子や抹茶なども色々と取り揃えてあります。次回はそちらも楽しんでみたいです。
「茶酒」にリニューアルされる前、確かここは「カフェ庭園」というイタリアンのレストランだったと思うのですが、そちらも美術館併設レストランとしてはなかなか水準の高い店でした。そしてこの「茶酒」もまた美味しい。どうやら私は、この美術館のレストランと相性が良いようです。
庭園美術館のレストランは美術館入口外にあるので、当然ながら入場券がなくとも利用出来ます。テラス席もあるので、これからの季節にはぴったりでしょう。また一つ楽しみなレストランが増えました。おすすめします。
(今回はデジカメを持って行くのを忘れたので、画像は全て携帯カメラで撮影したものです。いつも以上に見苦しく拙い写真をお許し下さい…。)
東京都庭園美術館
鶏の塩そぼろ飯と翡翠麺
つい先日、東京都庭園美術館にオープン(3/24)したばかりの新しいカフェ「茶酒」です。宇治山哲平展へ行った折に、早速利用してみました。


料亭「金田中」の手がけるレストランと言うことで、メニューは当然ながら和食です。翡翠麺と丼もののセットをメインに、甘味までを幅広く提供します。唯一のコースメニューの「サーシャの定食」のお値段は3500円。私の感覚では美術館ランチとしてはやや高い印象も受けますが、ミニサイズのお茶碗でご飯や麺を出す「ひとくち飯と時季のごはん」と「ひとくち飯と翡翠麺」のセットは、1000円から1700円弱前後です。これなら手軽に楽しむことが出来ます。

この日注文したのは「鶏の塩そぼろ飯と翡翠麺」。それにコーヒーを付けてみました。可愛らしい丸いお盆に、ご飯、一口サイズの翡翠麺、それにミニ茶碗蒸しが所狭しと並びます。
どれもお味は上々。量は決して多いとは言えないので、お腹いっぱいになるかかどうかは難しいところですが、この際美味しいものであれば量の如何は問いません。この値段でこのお味なら私は納得。塩味がほんのり口に広がる鴨、ご飯の甘みを引き出す控えめな鶏そぼろ、お出汁のよくきいた関東風(?)の茶碗蒸し。お庭の桜を眺めながらゆっくりといただきました。

食後にはコーヒーを楽しみます。赤いお茶碗にて運ばれてきました。深煎りの、それでいながら後味の良い、喉越しの爽やかなコーヒーです。こちらは250円程度だったでしょうか。甘味も提供するお店なので、和菓子や抹茶なども色々と取り揃えてあります。次回はそちらも楽しんでみたいです。
「茶酒」にリニューアルされる前、確かここは「カフェ庭園」というイタリアンのレストランだったと思うのですが、そちらも美術館併設レストランとしてはなかなか水準の高い店でした。そしてこの「茶酒」もまた美味しい。どうやら私は、この美術館のレストランと相性が良いようです。
庭園美術館のレストランは美術館入口外にあるので、当然ながら入場券がなくとも利用出来ます。テラス席もあるので、これからの季節にはぴったりでしょう。また一つ楽しみなレストランが増えました。おすすめします。
(今回はデジカメを持って行くのを忘れたので、画像は全て携帯カメラで撮影したものです。いつも以上に見苦しく拙い写真をお許し下さい…。)
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
「塚田守展 -妖怪 SPECTER- 」 小山登美夫ギャラリー 4/1
小山登美夫ギャラリー(江東区清澄1-3-2 7F)
「塚田守展 -妖怪 SPECTER- 」
3/18-4/8
熱帯で咲くカラフルな花々か、それともSF映画に出てくるような異星人の仮面か、はたまた不気味な髑髏なのか。何とも鮮やかで、また奇妙な8点の写真。小山登美夫ギャラリーで開催中の、塚田守の個展です。

底抜けに明るいブルー、または太陽のように眩しいオレンジ、そしてレモンイエロー。一見、何が写っているのかすら分からないような写真からは、まずその鮮やかな色だけが目に飛び込んできます。そしてよく不可思議な形に目を近づけてみると、その花びらのようなモチーフが、髑髏や仮面としてこちらに微笑んでいるようにも見えてくる。そこでSPECTER、つまりタイトルの「妖怪」や「恐ろしいもの」、さらには「不安のもと」という意味が浮かんできます。この色であの形はあまりにもアンバランスです。
仮面の奥には、こちらをジッと覗き込む目が確かに存在していました。そしてそれらに囲まれた時、妖怪たちに自分が見られているという感覚が沸いてくる。何でもこれらの作品は、カメラに仮面を被せて制作されたものとのことですが、ともかくもあまり頻繁には近づきたくはないものの、少し背筋をゾッとさせるような、そう言う意味での魅力がある作品です。
同時開催中の、まるでインクや砂を打ちまけたような「大野智史 acid garden」展もなかなか凄まじいインスタレーションですが、そちらと合わせて見ても面白い展覧会かと思いました。8日までの開催です。
「塚田守展 -妖怪 SPECTER- 」
3/18-4/8
熱帯で咲くカラフルな花々か、それともSF映画に出てくるような異星人の仮面か、はたまた不気味な髑髏なのか。何とも鮮やかで、また奇妙な8点の写真。小山登美夫ギャラリーで開催中の、塚田守の個展です。

底抜けに明るいブルー、または太陽のように眩しいオレンジ、そしてレモンイエロー。一見、何が写っているのかすら分からないような写真からは、まずその鮮やかな色だけが目に飛び込んできます。そしてよく不可思議な形に目を近づけてみると、その花びらのようなモチーフが、髑髏や仮面としてこちらに微笑んでいるようにも見えてくる。そこでSPECTER、つまりタイトルの「妖怪」や「恐ろしいもの」、さらには「不安のもと」という意味が浮かんできます。この色であの形はあまりにもアンバランスです。
仮面の奥には、こちらをジッと覗き込む目が確かに存在していました。そしてそれらに囲まれた時、妖怪たちに自分が見られているという感覚が沸いてくる。何でもこれらの作品は、カメラに仮面を被せて制作されたものとのことですが、ともかくもあまり頻繁には近づきたくはないものの、少し背筋をゾッとさせるような、そう言う意味での魅力がある作品です。
同時開催中の、まるでインクや砂を打ちまけたような「大野智史 acid garden」展もなかなか凄まじいインスタレーションですが、そちらと合わせて見ても面白い展覧会かと思いました。8日までの開催です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「村瀬恭子展」 タカ・イシイギャラリー 4/1
タカ・イシイギャラリー(江東区清澄1-3-2 5F)
「村瀬恭子展 -月と森とシダの下のかたつむり- 」
3/18-4/15
清澄のギャラリービル5階、タカ・イシイギャラリーで開催されている村瀬恭子の個展です。タイトルは「月と森とシダの下のかたつむり」。何やら詩的で美しいイメージの浮かぶ表題ですが、作品自体もなかなか見応えがありました。知らない間にスッと引き込まれるような、ソフトタッチの油彩画です。

描かれているのは少女でしょうか。真っ白な裸体をさらけ出しながら、静かに目を閉じたり、また背中を向けたりして立っています。彼女はどこにいるのでしょう。深い森の奥、それとも透き通った湖の底。美しく長い髪は、まるで冷たい風か透き通った水にあたって靡いているようです。そして緑やオレンジ色の大きな蝶。これは彼女を守る妖精かもしれません。
線はブルブルと震えるように引かれていて、また油彩絵具は限りなく瑞々しく、透明感に溢れています。色は至る所で滲み出して、他の色とも交わっている。全体が少女を核にした一つの幻影のようでもあります。無垢な少女。包まれた安心感。さらには水の中に浸った心地良さ。そんな言葉も浮かんできました。
もしかしたら彼女は、まだ母親のお腹の中にいる胎児なのかもしれません。大きな母性に守られた一人の無垢な生命。まだ汚れを知らない、母の愛を信じきって育つこども。殻に閉じこもって安心しきっているかたつむりのような魂。童心へと帰るような、優しい気持ちにさせられる作品です。
今月15日までの開催です。
「村瀬恭子展 -月と森とシダの下のかたつむり- 」
3/18-4/15
清澄のギャラリービル5階、タカ・イシイギャラリーで開催されている村瀬恭子の個展です。タイトルは「月と森とシダの下のかたつむり」。何やら詩的で美しいイメージの浮かぶ表題ですが、作品自体もなかなか見応えがありました。知らない間にスッと引き込まれるような、ソフトタッチの油彩画です。

描かれているのは少女でしょうか。真っ白な裸体をさらけ出しながら、静かに目を閉じたり、また背中を向けたりして立っています。彼女はどこにいるのでしょう。深い森の奥、それとも透き通った湖の底。美しく長い髪は、まるで冷たい風か透き通った水にあたって靡いているようです。そして緑やオレンジ色の大きな蝶。これは彼女を守る妖精かもしれません。
線はブルブルと震えるように引かれていて、また油彩絵具は限りなく瑞々しく、透明感に溢れています。色は至る所で滲み出して、他の色とも交わっている。全体が少女を核にした一つの幻影のようでもあります。無垢な少女。包まれた安心感。さらには水の中に浸った心地良さ。そんな言葉も浮かんできました。
もしかしたら彼女は、まだ母親のお腹の中にいる胎児なのかもしれません。大きな母性に守られた一人の無垢な生命。まだ汚れを知らない、母の愛を信じきって育つこども。殻に閉じこもって安心しきっているかたつむりのような魂。童心へと帰るような、優しい気持ちにさせられる作品です。
今月15日までの開催です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
4月の予定と3月の記録
4月の予定
展覧会
「宇治山哲平展」 東京都庭園美術館(4/9まで)
「グンナール・アスプルンド建築展」 松下電工汐留ミュージアム(4/16まで)
「私のいる場所 - 新進作家展Vol.4」 東京都写真美術館(4/23まで)
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第1期」 三の丸尚蔵館(4/23まで)
「藤田嗣治展」 東京国立近代美術館(5/21まで)
「プラド美術館展」 東京都美術館(6/30まで)
コンサート
「新国立劇場2005/2006シーズン」 マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/レオンカヴァッロ「道化師」 4/5-11
「東京都交響楽団第625回定期Aシリーズ」 ブルックナー「交響曲第9番」他 4/17
「東京二期会オペラ劇場」 モーツァルト「皇帝ティートの慈悲」 4/22
「NHK交響楽団第1568回定期Aプロ」 モーツァルト「交響曲第41番」他 4/29-30
3月の記録(リンクは私の感想です。)
展覧会
4日 「フランス近代絵画展」 三越日本橋ギャラリー
4日 「MOTアニュアル2006/転換期の作法/MOTコレクション」 東京都現代美術館
18日 「Emerging Artist Support Program 2005 vol.5」 トーキョーワンダーサイト
18日 「桜さくらサクラ・2006」 山種美術館
19日 「ロダンとカリエール展」 国立西洋美術館
21日 「アートと話す/収蔵品展020/project N 24 小林浩」 東京オペラシティアートギャラリー
25日 「VOCA展 2006」 上野の森美術館
25日 「TEAM04+05 鬼頭健吾+田幡浩一」 トーキョーワンダーサイト渋谷
25日 「スイス・スピリッツ」 Bukamura ザ・ミュージアム
ギャラリー
4日 「小林正人『ヌード』」 シュウゴアーツ
4日 「菅木志雄展」 小山登美夫ギャラリー
5日 「life/art'05 part4 中村政人」 資生堂ギャラリー
9日 「菅木志雄個展 『空気の流路』」 東京画廊
12日 「life/art'05 part5 須田悦弘」 資生堂ギャラリー
12日 「藤原靖子 個展『-LOGUE』」 現代美術研究所
25日 「ヘレン・ファン・ミーネ展」 ギャラリー小柳
25日 「宮島達男展 『FRAGILE』」 SCAI
コンサート
21日 「新国立劇場2005/2006シーズン」 ヴェルディ「運命の力」/井上道義
映画
11日 「Divine Intervention」 アラブ映画祭2006/国際交流基金フォーラム
3月は「ロダン展」に「MOTアニュアル展」、それに楽しみにしていた宮島の個展などが特に印象に残りました。ちなみに、先月予定していた森美術館の「東京-ベルリン展」は実際に出向きましたが、体調不良気味だったせいか殆ど印象に残りませんでした。と言うことで感想はパスします。(ボリュームだけはスゴかったような…。)
今月は藤田、若冲、それにティートなどが特に楽しみです。藤田はかなり混雑しているという話も聞きますので、出来れば平日に行きたいと思います。
それでは今月もどうぞ宜しくお願い致します。
展覧会
「宇治山哲平展」 東京都庭園美術館(4/9まで)
「グンナール・アスプルンド建築展」 松下電工汐留ミュージアム(4/16まで)
「私のいる場所 - 新進作家展Vol.4」 東京都写真美術館(4/23まで)
「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第1期」 三の丸尚蔵館(4/23まで)
「藤田嗣治展」 東京国立近代美術館(5/21まで)
「プラド美術館展」 東京都美術館(6/30まで)
コンサート
「新国立劇場2005/2006シーズン」 マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」/レオンカヴァッロ「道化師」 4/5-11
「東京都交響楽団第625回定期Aシリーズ」 ブルックナー「交響曲第9番」他 4/17
「東京二期会オペラ劇場」 モーツァルト「皇帝ティートの慈悲」 4/22
「NHK交響楽団第1568回定期Aプロ」 モーツァルト「交響曲第41番」他 4/29-30
3月の記録(リンクは私の感想です。)
展覧会
4日 「フランス近代絵画展」 三越日本橋ギャラリー
4日 「MOTアニュアル2006/転換期の作法/MOTコレクション」 東京都現代美術館
18日 「Emerging Artist Support Program 2005 vol.5」 トーキョーワンダーサイト
18日 「桜さくらサクラ・2006」 山種美術館
19日 「ロダンとカリエール展」 国立西洋美術館
21日 「アートと話す/収蔵品展020/project N 24 小林浩」 東京オペラシティアートギャラリー
25日 「VOCA展 2006」 上野の森美術館
25日 「TEAM04+05 鬼頭健吾+田幡浩一」 トーキョーワンダーサイト渋谷
25日 「スイス・スピリッツ」 Bukamura ザ・ミュージアム
ギャラリー
4日 「小林正人『ヌード』」 シュウゴアーツ
4日 「菅木志雄展」 小山登美夫ギャラリー
5日 「life/art'05 part4 中村政人」 資生堂ギャラリー
9日 「菅木志雄個展 『空気の流路』」 東京画廊
12日 「life/art'05 part5 須田悦弘」 資生堂ギャラリー
12日 「藤原靖子 個展『-LOGUE』」 現代美術研究所
25日 「ヘレン・ファン・ミーネ展」 ギャラリー小柳
25日 「宮島達男展 『FRAGILE』」 SCAI
コンサート
21日 「新国立劇場2005/2006シーズン」 ヴェルディ「運命の力」/井上道義
映画
11日 「Divine Intervention」 アラブ映画祭2006/国際交流基金フォーラム
3月は「ロダン展」に「MOTアニュアル展」、それに楽しみにしていた宮島の個展などが特に印象に残りました。ちなみに、先月予定していた森美術館の「東京-ベルリン展」は実際に出向きましたが、体調不良気味だったせいか殆ど印象に残りませんでした。と言うことで感想はパスします。(ボリュームだけはスゴかったような…。)
今月は藤田、若冲、それにティートなどが特に楽しみです。藤田はかなり混雑しているという話も聞きますので、出来れば平日に行きたいと思います。
それでは今月もどうぞ宜しくお願い致します。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |









