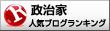こんにちは石井伸之です。本日も昨日に引き続き防災士資格取得のために、講習を受けてきました。本日の講習も、トリビアの泉の「へえ、へえ」があったら何度も叩きたくなるくらいの様々な事を聞くことができ、知っているようで知らないと言う事が分かりました。
午前中は近年の自然災害に学ぶということで、どうやら近年、自然災害が多発してその規模が大きくなっているのは、地球全体の温暖化にあるのではないかという推測が現実味を帯びてきており、その実例として、今から6500年前の縄文時代は、現代より平均気温が2℃高かったそうです。それが6500年かけて下がったというように自然にまかせると隕石落下とかの特別なケースを除くと、この程度の温度変化なのですが、現代の人為的な化石燃料の使用やフロンガス、メタンガスにより赤外線が宇宙空間に放出しにくい状況では、65年で2℃上昇していくそうです。つまり、地球にとっては初めて経験するするスピードで、温暖化が継続しているので、これからどのような気象の変化がどのようなスピードで我々にもたらされるか想像がつかないということです。ちなみに、現在の予測では、2100年には平均気温が5.6℃上昇し、海水面は最大88cm上昇するそうです。国立市は海抜60m程度ありますので、すぐに影響が分からないかもしれませんが、全国に広がる綺麗な砂浜は相当数が海中に消えると予想され、0メートル地帯は今よりさらに堤防決壊への不安が高まります。
そして、話は地震の方に移りますが、平成17年7月23日午後4時46分に千葉県北西部を震源とするM6.0の地震があり、足立区で震度5強を観測したときに、エレベーターの停止が6万4千件、そのうち閉じ込められたのは78件あり、その中で、最新の地震があったときには付近の階に止まってドアが開くとうたわれているエレベーターが73件あったそうです。何故そうなったか調べた結果は、大きな揺れをエレベーター自身が、ドアが開いたと勘違いをして停止してしまったそうです。
次に午後の講義に移り、今度は都市防災と言うことで、話をききましたが、この講師に来ていただいた、目黒公郎(きみろう)先生の話は、テンポ良く様々なことについて大変内容の凝縮された話をしていただき、その全てが完全なるリアリスト(現実主義者)な立場から見た視点で話していただけたので、二コマ2時間が光陰矢のごとしに感じられました。
さて内容はと言うと、まずはパキスタン地震を例に上げ、その地域は組積造(簡単に言うと、石を積み上げた構造のことです)の建物ですので、大変地震に弱く、揺れを受けると瞬時に崩壊し、逃げる間もなく居住者の上に屋根や壁に使われている石材の下敷きになり、およそ八万人の方が犠牲になりました。そこで、お金も無く資材もないところで、どのような対策を提案したかと言うと、PPバンドというダンボールを梱包する幅15ミリくらいで厚さ0.5ミリくらいのビニールテープを積んである石に巻き付ける事により、十分に逃げる時間を稼ぐ事ができます。
そして、話は本題に入り、阪神大震災から学ぶこととなるのですが、6434名の犠牲者のうち5時46分の地震発生15分後にそのうちの92%が亡くなっており、いかに自宅の耐震性能が重要であるかわかります。やはり、昭和56年に新耐震基準が建築基準法に適用される以前の建物が危険であるということが分かります。犠牲者の年代別分布を見ると、高齢者が多いのですが、以外と20代前半の若者が、老朽化した下宿先で被害にあうケースも多かったそうです。
さらに、阪神大震災では地震初期に53件の火災が発生しましたが、倒壊した家屋から救出作業をしている間に、初期消火に手が回らず、火災が大きくなってしまったと言う一面があります。もちろん、倒壊した建物のどこに火種が隠れているかを見つけることは、なかなか難しいといっておりましたが、倒壊した建物は火災が発生し易いと言う一面があります。
そして、目黒先生は避難所の乾パンの賞味期限を心配するような議員は、単に一票が欲しいだけの議員だから、何も分かっていないことを指摘してほしいと言われました。要は、犠牲者には一票はないが、避難者には一票があるからだと言われており、それよりも本質的な既存不適格建物(新耐震基準基準適用前に建設された建物)を少しでも耐震補強する必要があり、その費用をまずは自助努力として個人がどれだけ出せるか、個人で難しければ、公的機関がどれだけ貸し出す事ができるかが重要であると言っておりました。こういった現実的な対応を取れれば、それだけ倒壊する建物が減少し、それによる火災の減少、焼け出されて仮設住宅を用意する数量も減り、一時的な避難生活ですぐに帰宅でき、それから通常の生活に戻るスピードに格段の差が出ると言われておりました。
さらに、被災地で被災者にインタビューをするシーンがあり、その中でアナウンサーは被災者に物資が足りてるかといった事を聞いておりますが、そんなことよりもっと重要なのは、今回亡くなった人の声は何だったのか調べる必要があります。死人に口なしということを、あまり良くないイメージで聞きますが、今回の災害を次に生かす為には、犠牲者と会話して死因を調べる事がなければ、犠牲者も浮かばれません。犠牲者の大半が家屋の倒壊であると分かっているのですから、既存不適格建物どうやって震度6に耐えられるように耐震補強するかということに、一番の論点をおくべきであると実感しました。
各自治体は大震災で一人の犠牲者を出さないように、できることをどれだけ行っているか、ある日突然やってくる大地震によって試される運命にあります。一市議会議員の力でどこまでできるか分かりませんが、一軒でも倒壊する建物を少なくできるように努力して行きます。今日の日記は大変長くなりましたが、最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。これから、明日の試験に向けて勉強しますので、そろそろ失礼します。写真は長女撮影の私の鞄です。
午前中は近年の自然災害に学ぶということで、どうやら近年、自然災害が多発してその規模が大きくなっているのは、地球全体の温暖化にあるのではないかという推測が現実味を帯びてきており、その実例として、今から6500年前の縄文時代は、現代より平均気温が2℃高かったそうです。それが6500年かけて下がったというように自然にまかせると隕石落下とかの特別なケースを除くと、この程度の温度変化なのですが、現代の人為的な化石燃料の使用やフロンガス、メタンガスにより赤外線が宇宙空間に放出しにくい状況では、65年で2℃上昇していくそうです。つまり、地球にとっては初めて経験するするスピードで、温暖化が継続しているので、これからどのような気象の変化がどのようなスピードで我々にもたらされるか想像がつかないということです。ちなみに、現在の予測では、2100年には平均気温が5.6℃上昇し、海水面は最大88cm上昇するそうです。国立市は海抜60m程度ありますので、すぐに影響が分からないかもしれませんが、全国に広がる綺麗な砂浜は相当数が海中に消えると予想され、0メートル地帯は今よりさらに堤防決壊への不安が高まります。
そして、話は地震の方に移りますが、平成17年7月23日午後4時46分に千葉県北西部を震源とするM6.0の地震があり、足立区で震度5強を観測したときに、エレベーターの停止が6万4千件、そのうち閉じ込められたのは78件あり、その中で、最新の地震があったときには付近の階に止まってドアが開くとうたわれているエレベーターが73件あったそうです。何故そうなったか調べた結果は、大きな揺れをエレベーター自身が、ドアが開いたと勘違いをして停止してしまったそうです。
次に午後の講義に移り、今度は都市防災と言うことで、話をききましたが、この講師に来ていただいた、目黒公郎(きみろう)先生の話は、テンポ良く様々なことについて大変内容の凝縮された話をしていただき、その全てが完全なるリアリスト(現実主義者)な立場から見た視点で話していただけたので、二コマ2時間が光陰矢のごとしに感じられました。
さて内容はと言うと、まずはパキスタン地震を例に上げ、その地域は組積造(簡単に言うと、石を積み上げた構造のことです)の建物ですので、大変地震に弱く、揺れを受けると瞬時に崩壊し、逃げる間もなく居住者の上に屋根や壁に使われている石材の下敷きになり、およそ八万人の方が犠牲になりました。そこで、お金も無く資材もないところで、どのような対策を提案したかと言うと、PPバンドというダンボールを梱包する幅15ミリくらいで厚さ0.5ミリくらいのビニールテープを積んである石に巻き付ける事により、十分に逃げる時間を稼ぐ事ができます。
そして、話は本題に入り、阪神大震災から学ぶこととなるのですが、6434名の犠牲者のうち5時46分の地震発生15分後にそのうちの92%が亡くなっており、いかに自宅の耐震性能が重要であるかわかります。やはり、昭和56年に新耐震基準が建築基準法に適用される以前の建物が危険であるということが分かります。犠牲者の年代別分布を見ると、高齢者が多いのですが、以外と20代前半の若者が、老朽化した下宿先で被害にあうケースも多かったそうです。
さらに、阪神大震災では地震初期に53件の火災が発生しましたが、倒壊した家屋から救出作業をしている間に、初期消火に手が回らず、火災が大きくなってしまったと言う一面があります。もちろん、倒壊した建物のどこに火種が隠れているかを見つけることは、なかなか難しいといっておりましたが、倒壊した建物は火災が発生し易いと言う一面があります。
そして、目黒先生は避難所の乾パンの賞味期限を心配するような議員は、単に一票が欲しいだけの議員だから、何も分かっていないことを指摘してほしいと言われました。要は、犠牲者には一票はないが、避難者には一票があるからだと言われており、それよりも本質的な既存不適格建物(新耐震基準基準適用前に建設された建物)を少しでも耐震補強する必要があり、その費用をまずは自助努力として個人がどれだけ出せるか、個人で難しければ、公的機関がどれだけ貸し出す事ができるかが重要であると言っておりました。こういった現実的な対応を取れれば、それだけ倒壊する建物が減少し、それによる火災の減少、焼け出されて仮設住宅を用意する数量も減り、一時的な避難生活ですぐに帰宅でき、それから通常の生活に戻るスピードに格段の差が出ると言われておりました。
さらに、被災地で被災者にインタビューをするシーンがあり、その中でアナウンサーは被災者に物資が足りてるかといった事を聞いておりますが、そんなことよりもっと重要なのは、今回亡くなった人の声は何だったのか調べる必要があります。死人に口なしということを、あまり良くないイメージで聞きますが、今回の災害を次に生かす為には、犠牲者と会話して死因を調べる事がなければ、犠牲者も浮かばれません。犠牲者の大半が家屋の倒壊であると分かっているのですから、既存不適格建物どうやって震度6に耐えられるように耐震補強するかということに、一番の論点をおくべきであると実感しました。
各自治体は大震災で一人の犠牲者を出さないように、できることをどれだけ行っているか、ある日突然やってくる大地震によって試される運命にあります。一市議会議員の力でどこまでできるか分かりませんが、一軒でも倒壊する建物を少なくできるように努力して行きます。今日の日記は大変長くなりましたが、最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。これから、明日の試験に向けて勉強しますので、そろそろ失礼します。写真は長女撮影の私の鞄です。