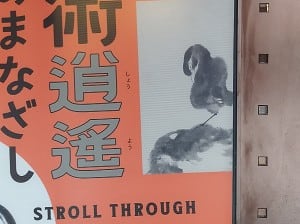〇泉屋博古館東京 リニューアルオープン記念展III『古美術逍遥-東洋へのまなざし』(2022年9月10日~10月23日)
リニューアルオープン展パート3では、京都・東山の泉屋博古館から当館を代表する中国絵画・日本絵画に加え、東京館の収蔵品からも茶道具や香道具など、数寄者の心を伝える作品を紹介する。待ってました!という感じである。
第1展示室(入って右手)は全て中国絵画で、徐渭『花卉雑画巻』に迎えられ(花の間にメザシみたいな小魚がいる)、すぐその次が八大山人の『安晩帖』だった。前期(9/10-10/1)が「叭々鳥図」と知って、飛んできたのである。にじむ薄墨で描かれたふわっふわの叭々鳥。足元の岩か何かも、やわかい斑猫の毛皮のようにも見える。私は2010年に京都の泉屋博古館で、2017年に東博で見て以来、三度目の鑑賞になる。いちばん好きなページを久しぶりに見ることができて嬉しかったけど、私の宿願は『安晩帖』22面を全部見ることだ。「2.瓶花図」「4.山水図」「6.魚図」「7.叭々鳥図」「10.蓮翡翠図」「12.冬瓜鼠図」の計6図制覇から、なかなか増えない。
次に石濤の『黄山八勝図冊』『黄山図巻』『廬山観瀑図』と、繊細な淡彩の作品が続く。私はこれらを京都の泉屋博古館で何度か見ているのだが、京都の明るい展示室で見た記憶と、東京の暗い(作品のみ照明で浮き立たせる)展示室だと、ちょっと色合いの印象が異なる気がした。華嵒『鵬挙図』は、最近見た中国ドラマの影響で「神鵰侠!」と叫びそうになって、にやにやした。
ホールの裏側を通る第2展示室には、高麗仏画の『水月観音像』が来ていた。全体に茶色に褪色してるけれど、ベールの透け感が美しく、左下の童子の愛らしさも見どころ。唐代の金銅舎利槨・棺や雲南大理国の銅造観音菩薩立像など、京都でおなじみの名品が多数来ており、宇宙人みたいな弥勒仏立像(北魏時代)に「56億7千万の微笑み」というキャプションがついていたのに笑ってしまった。
第3展示室は主に日本の古美術。上畳本三十六歌仙絵切「藤原兼輔」や佐竹本三十六歌仙絵切「源信明」に加え、伊藤若冲『海棠目白図』や呉春『蔬菜図巻』も大好きな作品。あまり京都で見た記憶のない蒔絵の工芸品が出ていたのは、東京館のコレクションなのだろうか。桃山時代の能面「白色尉」を収めた『畦道蒔絵平文面箱』のデザインがモダンで素敵だった。
第4展示室は、1つの展示ケースに文房四宝を取り合わせたり、書画と香炉・酒杯を取り合わせたり、工夫があって面白かった。
なお、第3展示室の『二条城行幸図屏風』(江戸時代、17世紀)は複製が玄関ホールに展示されている。こちらは、かなり近づいて鑑賞できるし、撮影も可。描かれた人々のファッションが気になる。同じ着物は二人といないのではないか(仕事中の武士のユニフォームは別)と思うくらい千差万別。大柄の文様は着ている人間の身体を意識しているが、スクリーントーンを貼るみたいな感覚で文様を描いているものもあって面白い。

モブシーン(大群衆)にケンカはつきもの。

入口横のパネルから『安晩帖』の叭々鳥ちゃん。私が明清絵画の深みにハマったのは、第一に泉屋博古館の住友春翠コレクションの影響である。このたび東京で展観してくれて、感謝しかない。