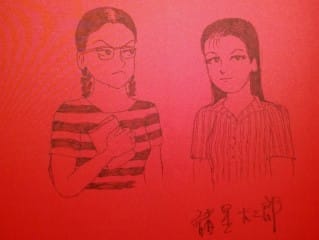〇九州国立博物館 特集展示・没後350年記念『明国からやって来た奇才仏師 范道生』(2021年7月17日~10月10日)
文化交流展示室に入ると、左横の第11室の入口を囲むように巨大な羅漢像の写真が飾り付けられていた。京都・萬福寺(万福寺)の羅怙羅(らごら)尊者像で、両手で自分の胸を左右に押し開き、中には仏の顔が見えている。その下をくぐり、あたかも羅怙羅尊者のお腹の中に入っていくような気持ちで展示室に入る。
范道生(1635-1670)は福建省泉州市安平生まれ。万治3年(1660)長崎に渡来し、福済寺と興福寺で仏像や道教神像を造った。その後、寛文3年(1663)、日本黄檗宗の開祖である隠元禅師に招かれて、萬福寺の仏像を造った。私は、長崎の唐寺も宇治の萬福寺も大好きなので、范道生の仏像は何度も見ている。しかし、こんなにたくさん、展示会場でじっくり見るのは初めてのことで、とても嬉しかった。しかも写真が撮り放題!
長崎・興福寺の三官大帝倚像。左から、水官、天官、地官である。長崎は、2009年、2010年、2018年のランタンフェスティバルに行って、唐寺巡りをしているのだが、あまり記憶に残っていない。図録の写真を見たら、媽祖堂(中央に媽祖・二侍女像、その前に順風耳・千里眼立像)の奥のほうに控えめに祀られているようだ。

同じく興福寺媽祖堂に安置されている関帝倚像。着衣(龍袍)の肩から腰まで、立体的な細い線で龍文や唐草文を施しており、照明が当たると、キラキラ輝く。泉州や厦門に伝わる漆線彫(チーセンティオ)という技法だと説明されていた。

興福寺本堂の韋駄天立像は、胸の前で剣を横たえるスタイル。図録の写真だと、輪になった細い天衣が翻って、頭部を囲んでいるが、保安上の理由か、展示会場ではそのパーツがなかった。金をベースに、赤や緑の彩色がよく残っている。下の写真で韋駄天像の左側に映っている白黒のパネルは、原爆で焼失した長崎・福済寺の護法堂の韋駄天像の写真(当時の絵葉書を拡大)で、興福寺のものより小柄な印象だが、スタイルはよく似ていた。

京都・萬福寺の十八羅漢のうち、羅怙羅尊者像。奇抜な造形に目を奪われるが、中心に視線を集めるような着衣の襞、繊細な唐草文も見どころである。この装飾文は、范道生が去った後、委託された京都仏師が担当したのだろうとのこと。

右側は、萬福寺祖師堂の達磨大師坐像。脱乾漆造である。衣も肌も真っ赤だが、もとはこの上に金箔が貼られており、全身が黄金色だったのではないかと思う。頭髪と髭は、白土と見られる別素材を型抜きして貼り付け、青色が塗られていたという。左側は、十八羅漢のひとり、半托迦尊者。鉢の中から出現する龍を𠮟りつけて(?)いるようで、迫力もあり、ユーモアも感じる。

展示には、范道生の仏画や書もあって面白かった。写真は黄檗山第二代住持となった木庵性瑫(もくあんしょうとう)の詩偈集『東来集』の刊本で、刻者(版木を彫った者)として范道生の名前がある。いろんな仕事をしていたんだな。

さて范道生は、広南国(現在のベトナム)にいる父親の古希を祝うため、いったん日本を離れたが、寛文10年(1670)6~8月頃、広南船の客人として再び長崎に来航した。萬福寺の梵像(本象)を彫造する約束があったようだ。しかし、新来唐人扱いとされ、滞留許可が下りなかった。へえ、当時、こういう制度があったことを初めて知った。萬福寺の木庵が道生を留め置くよう願い出たり、道生自身が以前日本に滞在したことがある旨を申し出たり、いろいろ交渉するのだが、長崎奉行は頑なで、幕府の回答は「道生が帰化するなら滞留差し支えなし」だった。なんだか、むかしから外国人労働者に冷たい国だったのだなあ、と思って悲しくなる。
道生は9月から吐血を患っており、11月2日に死去し、長崎の崇福寺の裏山に葬られた。36年の短い生涯だったというが、残された仕事の素晴らしさに感嘆する。日本に来てくれてありがとうございます。次回、長崎に行ったら、必ず范道生のお墓にお参りしてこよう。そして、中国の泉州にはいつか行きたい。
このほかの文化交流展示もゆっくり楽しんだ。東京や京都の国立博物館に比べて、先史時代の比重が大きいのが特色だと思う。装飾古墳や石人、興味深い。それから「丸くなった地球」のエリアでは、九州を基盤とした西洋・中国・朝鮮との交流だけでなく、蝦夷地・アイヌ関係の資料もあって面白かった。九博でエトピリカの絵を見るとは思わなかった。あと、『鉄砲玉鋳型蒔絵棚』(江戸時代、17世紀)の奇抜さにも驚いた。