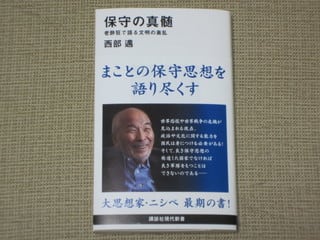西部邁 2017年 講談社現代新書
先月のとある休日に、あてもなく書店を見て歩ってたら、新書の棚に表紙向けてある西部さんの本があった。
最後の書って、でっかい帯の表紙にあるから、そうかあ西部さんもご高齢だろうから引退するのかなあ、なんて気になって手に取ったのは偶然。
そしたら、翌朝のこと、西部さんの訃報に出くわしたのには驚いた。え? 川に飛び込んで、自殺?
報道に触れて気がついて、よく見たら、表紙の文字「最期の」だったよ、死を決意してた? あっても不思議ぢゃないけど。
西部さんの存在を知ったのはいつのことだろう、元号が変わったころだったかな、はっきりおぼえてはいない。
テレビで他の多くのひとがワーワーとウケ狙ってるように怒鳴り合うような討論番組で、いちばんまともなこと言ってるひとだなあと思ったことはある。
いまとなってはしかたない、のこされたものを読むことにしよう。
本書は、例によって西部さんの看板であるような「保守」をタイトルにしてるんだけど、サブタイトルの「老酔狂で語る文明の紊乱」のほうが、なんとなく中身に近いのではと思う。
紊乱なんて言葉は、もちろん知らなかったんだけどね。
>紊乱とは「文がもつれた糸のように乱れる」状態を指す(p.13)
だそうだけど。何が乱れてるって現代の日本っつーか日本人、そのことへの嘆きというか呆れもまじえた指摘が中心といえるのでは。
ときどき、このことは前にも書いたんだけど何の反応もなかった、みたいなチクッとしたフレーズが入るのは、めずらしく老人っぽさみたいの感じさせられちゃうけど。
>しかし問題なのは、その適応の果てに日本文化の喪失という深刻な事態が訪れることについてどう評価するかということにほかならない。その適応の結果についていささかでも懐疑しておいたならば、適応の規模と速度は弱まったかもしれないが、日本国家の独立性と自発性はその分だけ保持されたに違いない。その意味で適応主義は自己喪失のための早道なのである。(p.33)
みたいなのは、日本の戦後(っていうか明治維新後くらいからか)をマジに見てきたひとだから言えることなのではっていう気がする。
あと、言葉を大事にするひとだけあって、いたるところ言葉の意味由来、本来含まれる概念、類似語とのちがいとかへの言及が多い。横文字多くて、私なんかは読めないし書けないし困ってしまうくらい。
モダンってのは、近代とか最近の時代ぢゃなくて、モデルとモードの類似語なんだから「模型の流行する時代」で「模流」とでもすべきであった言葉だなんていう。
もちろん、言葉あれこれいうだけぢゃなくて、
>模流化のどこが問題なのか。それは、数ある模流の可能性のうちでいずれを選択するかに当たって、「歴史の英知」としての伝統が一向に省みられない点である。トラディション(伝統)はカスタム(慣習)と同じではない。物事を選択するに当たって最初に参照すべき規準、それが伝統である。(p.38)
みたいにちゃんと保守の思想の話になる。
思想というか、文明論みたいなことだけぢゃなくて、政治や経済の具体的なことにも数々の評をくだしてるんだけど、なかでも、
>こうした経緯を振り返ると平成期の日本人にあって「討論の絶滅」が進行したのだといわざるをえない。歴史のもたらした平衡感覚としての伝統を今の状況にあっていかに具体化するか、そのためには討論がなければならない。それなのに、我が列島人はステレオタイプ(紋切り型)の標語を薄っぺらな自由民主時点から取り出すだけのことで、実質的には「言葉なき騒動」だけをこの平成時代に刻印した。(p.165)
ってあたりが、いまの日本の問題を指摘してるとこぢゃないかと私は思う。
ちなみに、最終節では、「自裁死」の覚悟というか意志を、おもいっきりはっきりと表明している。
亡くなってしまったあとで読んだからかもしれないが、とても痛々しい。
大きな章立ては以下のとおり。
第一章 文明に霜が下り雪が降るとき
第二章 民主主義は白魔術
第三章 貨幣は「戦さの女神」
第四章 「シジフォス」の営みは国家においてこそ
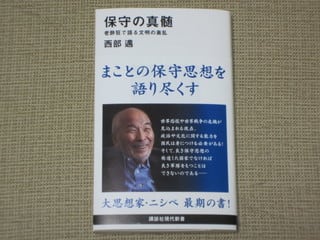
先月のとある休日に、あてもなく書店を見て歩ってたら、新書の棚に表紙向けてある西部さんの本があった。
最後の書って、でっかい帯の表紙にあるから、そうかあ西部さんもご高齢だろうから引退するのかなあ、なんて気になって手に取ったのは偶然。
そしたら、翌朝のこと、西部さんの訃報に出くわしたのには驚いた。え? 川に飛び込んで、自殺?
報道に触れて気がついて、よく見たら、表紙の文字「最期の」だったよ、死を決意してた? あっても不思議ぢゃないけど。
西部さんの存在を知ったのはいつのことだろう、元号が変わったころだったかな、はっきりおぼえてはいない。
テレビで他の多くのひとがワーワーとウケ狙ってるように怒鳴り合うような討論番組で、いちばんまともなこと言ってるひとだなあと思ったことはある。
いまとなってはしかたない、のこされたものを読むことにしよう。
本書は、例によって西部さんの看板であるような「保守」をタイトルにしてるんだけど、サブタイトルの「老酔狂で語る文明の紊乱」のほうが、なんとなく中身に近いのではと思う。
紊乱なんて言葉は、もちろん知らなかったんだけどね。
>紊乱とは「文がもつれた糸のように乱れる」状態を指す(p.13)
だそうだけど。何が乱れてるって現代の日本っつーか日本人、そのことへの嘆きというか呆れもまじえた指摘が中心といえるのでは。
ときどき、このことは前にも書いたんだけど何の反応もなかった、みたいなチクッとしたフレーズが入るのは、めずらしく老人っぽさみたいの感じさせられちゃうけど。
>しかし問題なのは、その適応の果てに日本文化の喪失という深刻な事態が訪れることについてどう評価するかということにほかならない。その適応の結果についていささかでも懐疑しておいたならば、適応の規模と速度は弱まったかもしれないが、日本国家の独立性と自発性はその分だけ保持されたに違いない。その意味で適応主義は自己喪失のための早道なのである。(p.33)
みたいなのは、日本の戦後(っていうか明治維新後くらいからか)をマジに見てきたひとだから言えることなのではっていう気がする。
あと、言葉を大事にするひとだけあって、いたるところ言葉の意味由来、本来含まれる概念、類似語とのちがいとかへの言及が多い。横文字多くて、私なんかは読めないし書けないし困ってしまうくらい。
モダンってのは、近代とか最近の時代ぢゃなくて、モデルとモードの類似語なんだから「模型の流行する時代」で「模流」とでもすべきであった言葉だなんていう。
もちろん、言葉あれこれいうだけぢゃなくて、
>模流化のどこが問題なのか。それは、数ある模流の可能性のうちでいずれを選択するかに当たって、「歴史の英知」としての伝統が一向に省みられない点である。トラディション(伝統)はカスタム(慣習)と同じではない。物事を選択するに当たって最初に参照すべき規準、それが伝統である。(p.38)
みたいにちゃんと保守の思想の話になる。
思想というか、文明論みたいなことだけぢゃなくて、政治や経済の具体的なことにも数々の評をくだしてるんだけど、なかでも、
>こうした経緯を振り返ると平成期の日本人にあって「討論の絶滅」が進行したのだといわざるをえない。歴史のもたらした平衡感覚としての伝統を今の状況にあっていかに具体化するか、そのためには討論がなければならない。それなのに、我が列島人はステレオタイプ(紋切り型)の標語を薄っぺらな自由民主時点から取り出すだけのことで、実質的には「言葉なき騒動」だけをこの平成時代に刻印した。(p.165)
ってあたりが、いまの日本の問題を指摘してるとこぢゃないかと私は思う。
ちなみに、最終節では、「自裁死」の覚悟というか意志を、おもいっきりはっきりと表明している。
亡くなってしまったあとで読んだからかもしれないが、とても痛々しい。
大きな章立ては以下のとおり。
第一章 文明に霜が下り雪が降るとき
第二章 民主主義は白魔術
第三章 貨幣は「戦さの女神」
第四章 「シジフォス」の営みは国家においてこそ