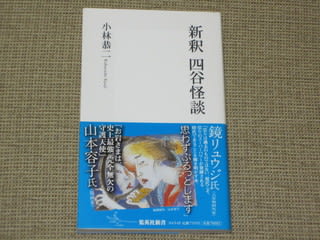小林恭二 2008年 集英社新書
『悪への招待状』『心中への招待状』に次ぐ、小林恭二の新書。
四谷怪談の主人公であるお岩さまに関する考察、何がお岩さまを強力な怨霊としたのか、その背負ってる怨念の対象は何なのかといったことを考えるのがテーマ。
著者得意の歌舞伎の筋書きをたどって、丁寧に四谷怪談の解説がなされていきます。
文化文政の時期の御家人は、非常に苦しい生活を強いられていて、そこの女性たちには(現実には苦しい家計を切り盛りしたといわれる)お岩さまが信仰の対象になったとか、そういう時代背景は、言われてみなけりゃ確かにわかりません。
「お岩さまの霊力の裏には困窮する御家人の内儀たちの怨嗟の声がある」ってことだそうです。
そして、お岩さまについては、ただただ単発にこの怪談のストーリーの登場人物ってんぢゃなくて、「日本におけるあらゆる怨霊、妖怪の伝統を一気に引き受けたような存在」「日本の歴史すべてから材料を得たサイボーグ」「極言すれば一種の装置であり、個人的感情を超越した存在」だってことを解き明かしてくれてます。
ふつうだったら、自分が亡き後に後妻になった女あたりにたたりそうなところを、ダイレクトに男を攻撃したりするとこが、それまでの日本の幽霊にはなかったところ、ってのも言われてみれば、ハタと目からうろこが落ちる。
ちなみに、幽霊ってのは、ボヤっとした存在(不在?)で、気の迷いのせいみたいなとこもあるけど、お岩さまは、喉笛にかみつくとか、物理的に攻撃をすることのできる存在・怪物ってことで、幽霊とは一線を画してるっつーか、違う存在だってことも解説されてる。
まあ、怪談を題材にして、書きようによっては、暗くて救いがなくなるんだけど、そこんとこらへんを、「子年の人間が怨霊になるたびに鼠が総動員されるとすれば、鼠だって忙しくてやりきれないでしょう」ってユーモアはさんだりとか、論陣を張ってる合間に「まだ話は終りではありません」とか一文を入れて呼吸を整えたりとか、そういう書き方がされてるんで、読んでて楽しい一冊ではあります。
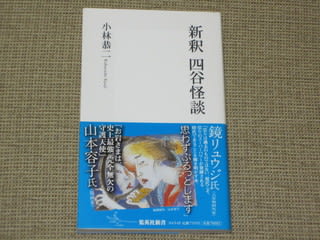
『悪への招待状』『心中への招待状』に次ぐ、小林恭二の新書。
四谷怪談の主人公であるお岩さまに関する考察、何がお岩さまを強力な怨霊としたのか、その背負ってる怨念の対象は何なのかといったことを考えるのがテーマ。
著者得意の歌舞伎の筋書きをたどって、丁寧に四谷怪談の解説がなされていきます。
文化文政の時期の御家人は、非常に苦しい生活を強いられていて、そこの女性たちには(現実には苦しい家計を切り盛りしたといわれる)お岩さまが信仰の対象になったとか、そういう時代背景は、言われてみなけりゃ確かにわかりません。
「お岩さまの霊力の裏には困窮する御家人の内儀たちの怨嗟の声がある」ってことだそうです。
そして、お岩さまについては、ただただ単発にこの怪談のストーリーの登場人物ってんぢゃなくて、「日本におけるあらゆる怨霊、妖怪の伝統を一気に引き受けたような存在」「日本の歴史すべてから材料を得たサイボーグ」「極言すれば一種の装置であり、個人的感情を超越した存在」だってことを解き明かしてくれてます。
ふつうだったら、自分が亡き後に後妻になった女あたりにたたりそうなところを、ダイレクトに男を攻撃したりするとこが、それまでの日本の幽霊にはなかったところ、ってのも言われてみれば、ハタと目からうろこが落ちる。
ちなみに、幽霊ってのは、ボヤっとした存在(不在?)で、気の迷いのせいみたいなとこもあるけど、お岩さまは、喉笛にかみつくとか、物理的に攻撃をすることのできる存在・怪物ってことで、幽霊とは一線を画してるっつーか、違う存在だってことも解説されてる。
まあ、怪談を題材にして、書きようによっては、暗くて救いがなくなるんだけど、そこんとこらへんを、「子年の人間が怨霊になるたびに鼠が総動員されるとすれば、鼠だって忙しくてやりきれないでしょう」ってユーモアはさんだりとか、論陣を張ってる合間に「まだ話は終りではありません」とか一文を入れて呼吸を整えたりとか、そういう書き方がされてるんで、読んでて楽しい一冊ではあります。