成田悠輔 2022年7月 SB新書
しまってある古いものを引っ張り出して読み返してみたり、古本を探してみては買ってきたりしてるばかりで、最近出たものを読むことは少ないんだが、めずらしく新しいものを読んでみた。
著者がテレビ番組に出てるのを何度かみて、なんかおもしろそうだなっつーか、なに書いてんだろうと興味もったもんで。
副題は、「選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる」。
政治学は専門ぢゃないらしいけど、民主主義って、ほかの制度よりいいような感じでとらえられてるみたいでいて、うまくいってないよね、ってあたりが問題意識になっている。
特に、
>では、なぜ選挙という雑なデータ処理装置がこれほど偉そうに民主主義の中核に鎮座しているのだろうか?(p.166)
ってとこを疑うのはおもしろい。
雑ってのは、限られた候補者のなかから誰かに一票を入れるだけの選択を突きつけられてるからで、たとえば、こいつの安全保障政策には賛成なんだけど経済政策にはまったく同意できないって候補者とか政党とかしかなかったら、自分の意思を反映することはできないよねえ、たしかに。
で、まあ、歴史的にいろいろあって成り立ってきて正当性がありそうだから続いてんだろうって見当はつけるんだが、ふつうはそこで、選挙制度をいじろうとか、政治家を監視して行動評価をしようとか、既存システムのなかで改善を考えるんだけど、そうぢゃない。
古代都市国家でもないし、王政を終わらせたばかりの時代でもないんだから、いま現在において、こっから民主主義をつくるとしたら、一人一票の代議制の選挙ぢゃないだろ、ってことになる。
そこで、でてくるのが「無意識データ民主主義」というもの。
政治的意思表示は選挙だけにしとくんぢゃなくて、実際にどうやるかは知らんけど、世の中にセンサーをはりめぐらして、人々が意識して発する意見にとどまらず、無意識のうちにのぞんでる意思や選好もデータとして集めちゃおうというもの。
(なんか想像力ない私からすると、防犯カメラ映像リレーしての犯罪捜査みたいに思えちゃう。)
で、集まったデータを利用して、とるべき政策を導き出すアルゴリズムをつくればいいでしょ、ということになる。
私が興味をもったのは、たとえばAIつかって問題解決のための政策を決定するってほうぢゃなくて、民意データを集めることによって目的を発見する、ってことのほう、なにが問題なのか、それを人々の無意識のなかから見つけ出すのは大事、現実世界では利益団体が自分たちだけの価値観のために議会に送り込む人物を担いでることが多いからね。
本書には、おもしろい表現の箇所はいっぱいあって、著者も、
>(略)この本の内容を再利用したい場合はジャンジャンやってしまってほしい。(略)切り抜くなりパクるなりリミックスするなり自由にしてほしい。(p.28)
とあるけど、新しく出たばかりのものについては、あんまり抜き書きたくさんしないようにしているので、目次だけ並べとく。
A.はじめに断言したいこと
B.要約
C.はじめに言い訳しておきたいこと
第1章 故障
〇□主義と□〇主義
もつれる二人三脚:民主主義というお荷物
ギャツビーの困惑、またはもう一つの失われた20年
感染したのは民主主義:人命も経済も
衆愚論の誘惑を超えて
21世紀の追憶
「劣化」の解剖学:扇動・憎悪・分断・閉鎖
失敗の本質
速度と政治21:ソーシャル・メディアによる変奏
「小選挙区は仕事すると票減りますよ」
デマゴーゴス・ナチス・SNS
偽善的リベラリズムと露悪的ポピュリズムのジェットコースター
そして資本主義が独走する
第2章 闘争
闘争・逃走・構想
シルバー民主主義の絶望と妄想の間で
政治家をいじる
政治家への長期成果報酬年金
ガバメント・ガバナンス(政府統治)
メディアをいじる
情報成分表示・コミュニケーション税
量への規制
質への規制
選挙をいじる
政治家への定年や年齢上限
有権者への定年や年齢上限
未来の声を聞く選挙
「選挙で決めれば、多数派が勝つに決まってるじゃないか」
「一括間接代議民主主義」の呪い
政治家・政党から争点・イシューへ
UI/UXをいじる
電子投票が子どもの健康を救う?
ネット投票の希望と絶望
実現(不)可能性の壁、そして選挙の病を選挙で治そうとする矛盾
第3章 逃走
隠喩としてのタックス・ヘイブン
デモクラシー・ヘイブンに向けて?
独立国家のレシピ1:ゼロから作る
独立国家のレシピ2:すでにあるものを乗っ取る
独立国家:多元性と競争性の極北としての
すべてを資本主義にする、または〇□主義の規制緩和
資本家専制主義?
逃走としての闘争
第4章 構想
選挙なしの民主主義に向けて
民主主義とはデータの変換である
入力側の解像度を上げる、入射角を変える
データとしての民意1:選挙の声を聞く
データとしての民意2:会議室の声を聞く
データとしての民意3:街角の声を聞く
万華鏡としての民意
歪み、ハック、そして民意データ・アンサンブル
アルゴリズムで民主主義を自動化する
エビデンスに基づく価値判断、エビデンスに基づく政策立案
データ・エビデンスの二つの顔
出力側:一括代議民主主義を超えて、人間も超えて
「しょせん選挙なんか、多数派のお祭りにすぎない」
闘争する構想
「一人一票」の新しい意味
無謬主義への抵抗としての乱宅アルゴリズム
アルゴリズムも差別するし偏見も持つ
選挙vs.民意データにズームイン
ウェブ直接民主主義から遠く離れて
不完全な萌芽
グローバル軍事意思決定OS
金融政策機械
マルサの女・税制アルゴリズム
萌芽の限界:自動価値判断とアルゴリズム透明性
無意識民主主義の来るべき開花
政治家不要論
政治家はネコとゴキブリになる
「民度」の超克、あるいは政治家も有権者も動物になる
政治家はコードになる
夢みがちな無意識民主主義
おわりに:異常を普通に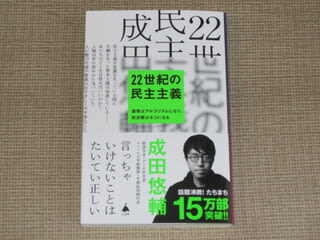
最新の画像[もっと見る]
-
 君子蘭
3日前
君子蘭
3日前
-
 君子蘭
3日前
君子蘭
3日前
-
 鳥の歌
6日前
鳥の歌
6日前
-
 100%孤独のグルメ!
2週間前
100%孤独のグルメ!
2週間前
-
 ファービアン
3週間前
ファービアン
3週間前
-
 サム・ホーソーンの事件簿V
4週間前
サム・ホーソーンの事件簿V
4週間前
-
 解体新著
1ヶ月前
解体新著
1ヶ月前
-
 錯覚の科学
1ヶ月前
錯覚の科学
1ヶ月前
-
 チャンドラー傑作集1
2ヶ月前
チャンドラー傑作集1
2ヶ月前
-
 「待った」をした頃
2ヶ月前
「待った」をした頃
2ヶ月前















