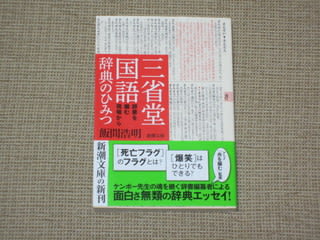山崎浩一 1992年 ちくま文庫版
去年のおわりに、キヨシローの『ロックで独立する方法』を読んでから、非常に気になってしまった山崎浩一さんのことが。
で、年明けころに古本屋で文庫を探して買ってみた、読んだのつい最近だけど。
エッセイというか評論というか、そういうのの集まり。
読んでるあいだから、あー八十年代だなー、という感じがしてきた、単行本の発行は一九八八年一一月というから昭和のおわりに向かうころか。
どこがどうというわけではないけど、八十年代後半には背伸びして小難しいことを読もうとしていた私には、やっぱあのころの時代の雰囲気がする。
>今の東京の街の面白さは、ハイテックなインテリジェント・ビルとローテックな路地裏が混在する、ミスマッチによって主に生まれていると思う。(p.54「都市のトータルコーディネーション」)
>近代的すなわち産業化社会的な遊びの大衆化と、経済のポスト産業化が、日本では同時に到来した。(略)「遊び」が社会によって奨励どころか強迫される時代に突入してしまったのである。(p.90「刺激装置のトートロジー」)
>消費者(つまりぼくたち全部)とは、このアンビバレントな志向の間を揺れ動く存在なのである――というのが異化と他己のジレンマ、すなわち《イカタコ合戦》である。(p.168「イカタコ合戦 差異化と同一化」)
>都市はあらゆる土着的なものを等価な情報=記号に変換してしまうシステムでもある。そこの住人は、だから土着から自由になった(あるいは疎外された)ニュートラルな情報環境の住人でしかない。(p.265「国際化時代のガイジンごっこ」)
とかとか、各章から適当にパッと見で抜き出してみたりしても、なんかこういうのが八十年代っぽいなあという感じがする、しない?
いま思うと、情報化社会とか高度消費社会とかいっても、中途半端な時代だったのかなあという気がする。
大まかな章立ては以下のとおり。
1 都市 medio-cosmos
2 刺激/退屈 pleasuredome
3 子供 child in time
4 消費 easy money
5 TV eye in the sky
6 政治 scritti-politti
7 知性 talking book
8 世代 blank generation

どうでもいいけど、
>この「世間を騒がせた罪」という名の罪は刑法のどこにも書かれてはいないものの、日本という国では最も大きな、そして便利な罪名だ。(略)
>彼らが犯した肝心の罪そのものは曖昧にされたまま、とにかく「世間を騒がせたこと」を詫びさえすればそれですむのだ。(略)
>そして、なんとそれだけで彼らは「世間」に許されてしまったりもするのだ。とても面白い法治国家だと思う。(p.248「去勢された反逆 校庭机文字事件」)
って一節は、とても気にいっている。
去年のおわりに、キヨシローの『ロックで独立する方法』を読んでから、非常に気になってしまった山崎浩一さんのことが。
で、年明けころに古本屋で文庫を探して買ってみた、読んだのつい最近だけど。
エッセイというか評論というか、そういうのの集まり。
読んでるあいだから、あー八十年代だなー、という感じがしてきた、単行本の発行は一九八八年一一月というから昭和のおわりに向かうころか。
どこがどうというわけではないけど、八十年代後半には背伸びして小難しいことを読もうとしていた私には、やっぱあのころの時代の雰囲気がする。
>今の東京の街の面白さは、ハイテックなインテリジェント・ビルとローテックな路地裏が混在する、ミスマッチによって主に生まれていると思う。(p.54「都市のトータルコーディネーション」)
>近代的すなわち産業化社会的な遊びの大衆化と、経済のポスト産業化が、日本では同時に到来した。(略)「遊び」が社会によって奨励どころか強迫される時代に突入してしまったのである。(p.90「刺激装置のトートロジー」)
>消費者(つまりぼくたち全部)とは、このアンビバレントな志向の間を揺れ動く存在なのである――というのが異化と他己のジレンマ、すなわち《イカタコ合戦》である。(p.168「イカタコ合戦 差異化と同一化」)
>都市はあらゆる土着的なものを等価な情報=記号に変換してしまうシステムでもある。そこの住人は、だから土着から自由になった(あるいは疎外された)ニュートラルな情報環境の住人でしかない。(p.265「国際化時代のガイジンごっこ」)
とかとか、各章から適当にパッと見で抜き出してみたりしても、なんかこういうのが八十年代っぽいなあという感じがする、しない?
いま思うと、情報化社会とか高度消費社会とかいっても、中途半端な時代だったのかなあという気がする。
大まかな章立ては以下のとおり。
1 都市 medio-cosmos
2 刺激/退屈 pleasuredome
3 子供 child in time
4 消費 easy money
5 TV eye in the sky
6 政治 scritti-politti
7 知性 talking book
8 世代 blank generation

どうでもいいけど、
>この「世間を騒がせた罪」という名の罪は刑法のどこにも書かれてはいないものの、日本という国では最も大きな、そして便利な罪名だ。(略)
>彼らが犯した肝心の罪そのものは曖昧にされたまま、とにかく「世間を騒がせたこと」を詫びさえすればそれですむのだ。(略)
>そして、なんとそれだけで彼らは「世間」に許されてしまったりもするのだ。とても面白い法治国家だと思う。(p.248「去勢された反逆 校庭机文字事件」)
って一節は、とても気にいっている。