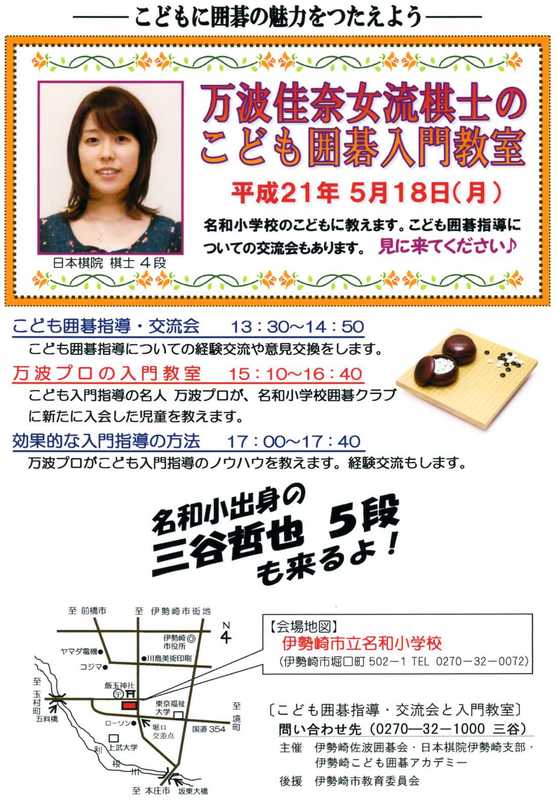私がいつも行く理髪店は自宅から100mほどの所にあり、1ヶ月~1ヶ月半の間隔で整髪してもらっています。
私がいつも行く理髪店は自宅から100mほどの所にあり、1ヶ月~1ヶ月半の間隔で整髪してもらっています。
マスターと奥さんの二人で営業していますが、10年ほど前は若い理容師がいました。低料金店舗の進出で従業員を抱えるのは苦しくなったのでしょうね。
料金は標準コースで3,600円。低料金の店に行けば半額以下でもできるようですが、雰囲気が変わるのがなんとなく鬱陶しいんですね。
あと新しい店を探すのが面倒というか、モノグサ気分もありますが・・・。
最初に行った頃はマスターがいろいろと話しかけてきて、地域のことなど世間話をしていました。
ところが途中から「フンフン」といい加減な受け答えになり、眠たそうな当方の気持ちを察したのか今では話しかけてきません。
夢うつつ気分の小一時間は、なによりのリラックス・タイムです。
◇ ◇
理髪店の客の中には話し好きなタイプもいます。プロ野球や健康の話題など、とり止めのない話が続きます。
マスターも相手をするためには、新聞やTVなどの情報チェックは欠かせませんね。
会話するには結構エネルギーも必要だと思うのですが、話し好きな人にとっては会話がストレス解消になるのかも知れません。
あと営業畑の人にとっては、世間話の組み立て方などは有用なスキルの一種なんでしょうね。
私の親は職人タイプで家でも必要なこと意外は喋らない方でした。
幸か不幸か、私もその血を受け継いでいるようです。