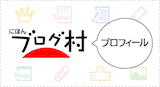昨日(15日)未明、軽井沢でスキーツアーバスの転落事故があり、大学生14人が亡くなるという大惨事となった。悲しみを言葉で言い表すことはできない。亡くなられた輝かしい将来のあった若者達のご冥福をお祈りし、ご家族にもお悔やみ申し上げます。

さて、今日・明日は大学入試センター試験、いよいよ今年の大学受験シーズンの幕開け。私の娘も朝早くから起きだして出かけていったが、会場がずいぶん遠いのでかわいそうだ。私が共通一次試験を受けたときは、都内に住んでいて会場は通っていた高校の近くでとても楽だった。楽すぎて点数が伸びなかったのかもしれないが、会場が自宅から遠いというのは気の毒だ。現役生はせめて、通っている学校の近くにしてくれたらいいのに。
まあ、地方に目を向けたら、それどころではないところもたくさんあるだろう。ずいぶん、不公平な話だ。

娘は奇しくもかつて私が描いていたと同じ夢を持っていて、その夢の実現の第一歩が今回の受験となる。
厳しい将来が待っていると思うが、私が果たせなかった夢をぜひ叶えてほしい。といっても、べつに私が薦めた道ではなく、たまたま一緒というだけで、娘の選択を純粋に応援するだけ。

センター試験は二日間。一日目の手応えにとらわれることなく、二日目も頑張ってほしい。
きっと勝って、志望校に受かってほしいと、普通の親として願う。
明日は、天気が崩れるようだが、受験生達にはベストの状態で受けて欲しいものだ。

合格祈願お菓子セットはお隣からの差し入れ