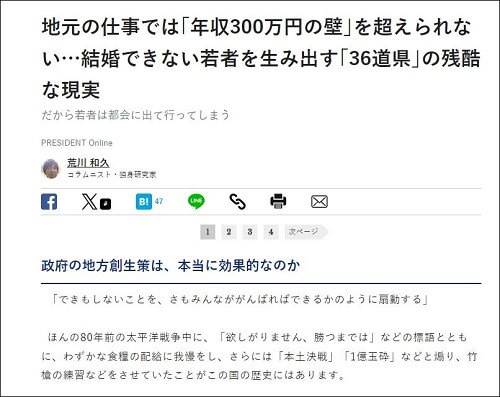
ネット記事サイトPresident Onlineにコラムニスト荒川和久さんの「地元の仕事では『年収300万円の壁』を超えられない…結婚できない若者を生み出す『36道県』の残酷な現実」という論考を読みました。 https://president.jp/articles/-/66797
副題は「だから若者は都会に出て行ってしまう」とあります。
論考の主題は、若者が地方からいなくなる問題です。
かつてコロナ禍が日本中を襲ったときに、リモートワークが流行し人と接する機会の多い東京から人口が流出したという報道がありました。
しかしそれは実は事の一面で、東京から人口は流出してはいませんでした。
相変わらず東京への一極集中は変わっておらず、一方で地方は一向に創生されてはいないのです。
ではどんな人たちが人口の移動に関わっているのか。
18歳で進学する大学を選別するとき、そして大学卒業の22歳時に就職先を目指して都会へ移動をするということが統計では示されています。
生まれ故郷の出生数と25歳時点居住地の増減率を著者の荒川さんが調べてみると、出生人口が生まれた時よりも増えているのは東京、東京圏の埼玉、千葉、神奈川、そして近畿圏、愛知、宮城、福岡、岡山の11都府県のみだったそうです。
つまり多くの若者が25歳段階で生まれ故郷を後にして都会を目指して移動しているという実態です。
著者の荒川さんはその理由として「若者は仕事のある都会へ移動する」と言います。
逆に言えば見放される地方は「仕事がなく稼げないところ」なのだと。
論考は、その結果としての「稼げない」ということは婚姻数の減少にも影響しています。
稼げる仕事を目指して都会へ出る若者は結婚もできますが、稼げない地方で暮らす者は結婚ができないという傾向がはっきりと見て取れます。
男性の結婚には「年収300万円の壁」があると言われていて、これを超えるか超えないかで既婚率が大きく変わることも指摘されています。
◆
著者は、国も自治体も手を打っていないわけではないが、地方に仕事を作り稼げるのは実際は難しく、さらには稼ぎ以上に若者を都会に誘う要素があるといいます。
それは「交流」ということで、人と出会うことで人は成長し、出会いを通じてその先に恋愛や結婚というステージにたどりつくのだと。
人が集まる場所だからこそ交流が可能になり、人がいないところには交流は生まれず、地方にはそこが圧倒的に不利に働くのだと。
著者の結論は、「未来を作るのは若者であり、若者が自分の可能性を確かめるために出ていくことを(止めるのではなく)むしろ応援してあげるべき」ではないか、地方創生の名の下に、若者に我慢や犠牲を強いることがあってはならないのではないか、というものです。
◆
非常に当を得た論考だとおもいます。
実は稼げる仕事と言う視点でも、地方に根差している仕事とは農林水産業という一次産業、建設業などの二次産業が中心ですが、都会では圧倒的にサービス産業としての三次産業が割合を高めています。
しかしこのようなサービス産業が成り立つのは都会という人(=需要家)がたくさんいるところだからです。
若者が人それぞれに興味を持つようなニッチな産業は人が多いからこそ成立します。
ネイルサービス、ペットのトリマー、エスニック料理専門店、不動産業などちょっと考えても、これらが人口と需要が不足する地方では成立しないことが想像できます。
地方が苦しいのは、これらの特殊な能力を身に着けてもそれだけで収入を得て暮らしてゆけるだけの需要が少なく食べていけないこと、もちろん機会が少ないことでより高度な技術を身に着けることができない、ということもあると思います。
地方では専門業が業としてなりたつだけの需要がなくなってくるということが問題です。
さて、そこでそれを支える発想の転換がなにかというお話です。
私はここで、「地方における多能工」と「分業型社会から参加型労働社会への転換」への可能性を論じたいと思います。
地方では専業が成り立ちにくい中で、一人ひとりが「それもできるけどこれもあれもできる」という多能工化することで、専業+軽サービス+軽労働の組み合わせで収入を得るという考え方です。
分業型社会は専業者によって経済活動を効率化しようという適応ですが、地方ではそれが成り立たないとすれば、専業を持ちつつ、地域の求めに応じた仕事/務めを果たし、それで収入を補えないか、と言う考えです。
腕は磨けないかもしれませんが、地域の少ないニーズに応えながら地域で重宝されながら暮らしてゆく。
そのためには、住民も公務員も皆が副業を認めるような機運も必要になるかもしれません。
公務員ですら地方では有用な地域の務めの担い手として、多能工で副業も可能にするような社会にならないものでしょうかねえ。















