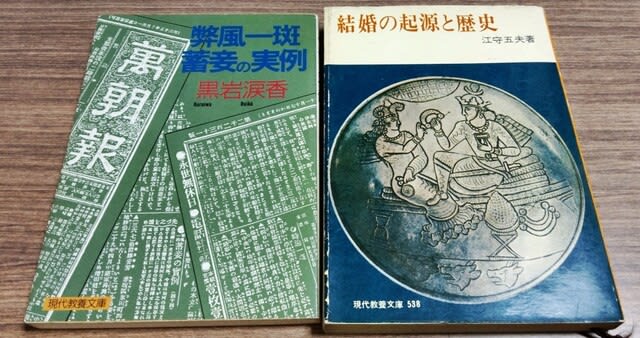
江守五夫著 『結婚の起源と歴史』(社会思想社、現代教養文庫、1965年)を読んだ。
ぼくが大学に入学した1969年ころは、ぼくのような(政治的にはノンポリに近い、少なくともノンセクトの)学生でも「読書会」に誘われて参加したことがあった。
当時はやっていた羽仁五郎の『都市の論理』(勁草書房、手元にない)や、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』(手元にあるのは岩波文庫版、昭和44年5月10日の第7刷。以下では「起源」)などがテキストだった。
残念ながら、良い指導者に恵まれず、いつの間にか立ち消えになってしまった。あるいは、ぼくが勝手にやめてしまったのかもしれない。
久しぶりに「起源」(岩波文庫)を開いてみると、第6章までは読んだ形跡があるが、第7章の初め(174頁)にリボンが挟んであって、ここで断念したようである。そして、巻末の訳者解説の中の「原始的集団の内部での生産力の発展、とくに牧畜や犂耕の導入が私有財産と父権的家族制家族の発生・強化を招き、これら相互間の貧富の差の拡大、階級対立の激化が国家を成立させるという、本書の基本的な論旨は・・・(今日でも)否定されそうにない」という文章に傍線が引いてある。・・・ということがこの本には書いてあるのだろう、ということで済ませることにしたのだと思う。
ちなみに、この解説によれば、わが国で最初に「起源」の全訳を出版したのは、何と有斐閣だったそうだ(内藤吉之助訳、1922年)。最近の同社の出版物を考えると、同社からエンゲルスが出ていたとは意外である。
結局「起源」は当時のぼくには難しすぎたことが中断の主な原因だったと思うが、「読書会」というのを初体験するうちに、ぼくは、やはり本は自分の関心に従って一人で読むものであり、ダメだったら途中で投げ出すことも許されるべきだ(積読(ツンドク)権?)と思うようになった。もしあのまま第7章以降を読んだ(字面を追った)としても得ることは少なかったと思う。
後に教師になってからも、クラスの全員で一つの本を読む(読ませる)という形式の授業は苦手だった。(かつてのぼくのように)その本に関心をもてない学生に気の毒でもある。さらに、「原典を読め」(解説書は読むな)という読書指導にも反対である。良い解説書は原典を理解できないままに読むよりはるかに優っていると思う。
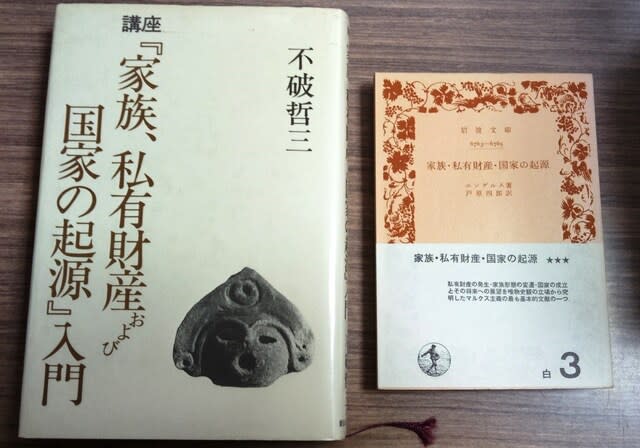
19歳の大学1年生の時に挫折したエンゲルス「起源」に書いてあることは、ずっと後に読んだ江守さんの本書『結婚の起源と歴史』や『愛の復権』(大月書店、1977年)、不破哲三『講座<家族、私有財産および国家の起源>入門』(新日本出版社、1983年)などを読んで、ようやく多少は分かった気になれた。
江守さんの『結婚の起源と歴史』は、エンゲルス「起源」以降の人類学の発展を、<原始社会=乱交制から文明社会=単婚制へ>という発展図式の再検討に絞って明快に整理してくれる。本文に関係する「未開民族」(現代では何と呼ぶのか分からいので、本書に従っておく)の人物や習俗の写真もふんだんに入っている。ここに登場する民族も今日ではほとんど「文明化」しているだろう。
原始社会や、執筆当時(1960年代ころ)の「未開社会」に残る(現代人から見ると)「奇習」と思われる性習俗を、当該部族や民族において何らかの必要から承認された「性的に接近する権利」として説明し、かえって単婚(=一夫一婦制)が貫徹されていると言われている文明社会において、売淫、夫の蓄妾、姦通など、いかに性が堕落しているかを指摘し、これまでは理想にすぎなかった「一夫一婦制」をいかに実現させるかが私たちの課題であると結んでいる。
今回再読して、腑に落ちたことが一つある。
最近はアメリカ諸州や西欧などの諸外国で同性婚(同性のカップル同士が結婚すること)を認める方向にあり、わが国でも認めるべきであるという主張が行われているが、ぼくは同性婚だけでなく、近親婚や複婚( polygamy。一夫多妻制、多夫多妻制(集団婚)など結婚の当事者が3人以上の婚姻)がなぜ議論の俎上にすら上らないのかを不思議に思い続けてきた。
同性婚の可否についてはこれだけ議論があるのに、近親婚(モンテスキュー『法の精神』はかなり広範囲に近親婚を認めていたが、本書では「性的に接近する権利」を承認する社会でも外婚制(近親婚回避)の掟は厳しく守られていると指摘している)や複婚についてはその可否や範囲をめぐってまったく議論がないのはなぜなのか。
近親婚や複婚に賛成するというのではなく、婚姻の自由に対するこれらの制限に関する議論すら行われないことへの疑問である。
そんなことを思うぼくの記憶の「古層」に江守さんの本書で知った文明社会以前の社会における「性的に接近する権利」による多数当事者間の性的関係が承認されていたことの説明が説得的だったことがあったのではないか、と今回再読して思ったのである。江守さんはそれを現代社会に再現させようなどとは言っておられないが。
なお、本書にはけっこう「文明批評」的なことも書いてあって、聖職者の性の堕落の箇所では、スチュワーデス殺し事件のベルメルシュ神父への言及があり(235頁。同事件については松本清張『黒い福音』というノンフィクション小説がある)、日本の売春汚職事件(昭和31年)をめぐって「赤線は社会の共同便所」(!)などと国会で放言した参議院議員の発言なども紹介されている(241頁)。ほかにも、イスラム国の首相の第2夫人になった日本人女性のこともどこかに書いてあった。
その他の箇所でも、資料を援用して主張を展開しながらも、時おり著者自身が顔をのぞかせることがある。とくに印象に残ったのは、ある写真のキャプションである。他では「寝宿の前の娘」(115頁)、「前掛けを織る女」(123頁)のように「娘」、「女」と中立的(没主観的)だったキャプションが、「ダヤーク族(ボルネオ)の美少女」だけは、なぜか「美」少女となっている(117頁)。このキャプションは著者の入れたものか、編集者が入れたものか分からないが、著者が嫌う文明社会の側による価値観の持ち込みではないか。確かにその写真の女性は「美少女」だと思うけれど(蛇足かな)。
※ 冒頭の写真左側は黒岩涙香『弊風一斑 蓄妾の実例』(社会思想社、現代教養文庫、1992年。原書は「萬朝報」1898年)の表紙。明治期の政治家、実業家、官僚、学者、お雇い外国人、その他市井の人も含め、いかに多くの男たちが妾を囲っていたかを実名を挙げて暴露している(計510名が登場する)。このような一夫多妻制的な状況では、複婚の可否など検討することすら憚られるであろう。
2020年10月20日 記















