
ディドロ『ブーガンヴィル航海記補遺』を読んだ。
森本和夫編『婚姻の原理--結婚を超えるための結婚論集』(現代思潮社、1977年改訂版)に収録されたもの。出典一覧には、浜田泰佑訳とだけあって、出版元、出版年が明記されていないが(290頁)、岩波文庫版か。
森本氏が本書を編集した意図は、本書のサブ・タイトルや、彼の『家庭無用論』にも示されていたように、最終的には家族の死滅、国家の死滅を目ざすマルクス主義の立場に至る結婚論の系譜をたどることにある。
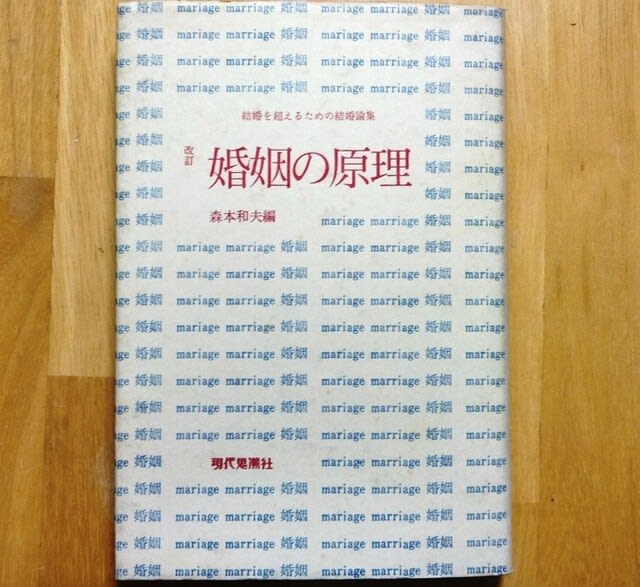
ディドロ(1713~84年)は高校の世界史で習った「百科全書」の編纂者として知られる(ディドロ、ダランベールと対で覚えた)フランス革命前の啓蒙思想家である。顔写真を載せたいと思って、息子の世界史教科書や参考書を調べたが出ていない。山川の『詳説世界史研究』に至ってはディドロの名前すら出ていない。
あれこれ探して、ようやく『新世紀ビジュアル大辞典』(学習研究社)に、彼の銅像の写真が載っているのを見つけた。一辺4センチ足らずの小さな写真のため、拡大したらぼやけてしまった。
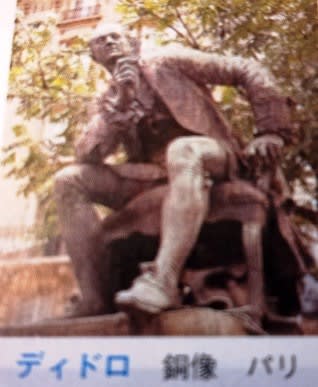
※だったのだが、2023年5月14日に下の写真に差し換えた。

下の写真はディドロ、ダランベールが編纂した百科全書の要約版である岩波文庫の『百科全書』(桑原武夫訳編)。
世界史の教科書や参考書に書いてある啓蒙思想の紹介には、本書『ブーガンヴィル航海記補遺』を読んでみると、ディドロの紹介としては疑問がわく記述もあるが、柴田三千雄他『新世界史B』(山川出版社)の、啓蒙思想は「ひろい範囲にまたがり、個人差も大きいが、・・・教会や神学の独善を激しく批判し」た、という共通点の指摘は大いに納得できる。
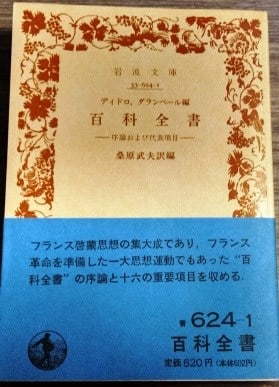
さて、ブーガンヴィルというのは18~19世紀に活躍した実在のフランス人である。法律家として出発しながら、後には探検家、航海家となり、アメリカ独立戦争にも従軍し、さらには数学の著書もあるという、フランス革命期の人物である。“ブーゲンビリア”という花は、彼にちなんで命名された植物だそうだ。
世界を一周した航海家としての彼は、『世界周航記』という本を出版している(邦訳は岩波書店刊)。しかし『ブーガンヴィル航海記補遺』の方は、この航海記に藉口して(?)、ディドロが自らのフランス文明批判を論じたものである(らしい。解説がないので不明だが)。
ブーガンヴィルの航海に同行したフランス人従軍牧師と、寄港先のタヒチで彼の接待役となったタヒチ人青年オルーとの対話という形をとっているが、実際は著者ディドロが対話形式で革命前フランスの宗教および性道徳を批判した内容となっている。
オルーが語るタヒチ人の習俗が本当に当時のタヒチの習俗を正しく語っているのか、ぼくには判断できない。ブーガンヴィルの『世界周航記』にそのような記述があるのかも、同書を見ていないのでわからない。
ただ、江守五夫『結婚の起源と歴史』(現代教養文庫)によれば、遠来の異人に対して部族の主人が性的なもてなし(婦女の提供)を行なう習俗は南太平洋の随所に残っていたようで、その性的なもてなしを拒むことは主人を侮辱し、主人に対して敵意を表明したものとして、場合によっては殺されることもあったという(江守157頁)。
ただし、江守氏の著書には「タヒチ」と明示して、そのような性的供応の習俗があったとは書いてないので、以下はすべてディドロが本書においてタヒチの習俗として紹介したままに記述している。なお[ ]内の見出しは便宜的にぼくがつけたもの。
[性的なもてなしについて] 従軍牧師の接待役となったタヒチ人オルーには妻と3人の娘があった。最初の夜、オルーは牧師に向かって、「一人寝はつらかろう」と言って、若い末娘を提供する。「私の宗教が、私の職分が・・・」といって固辞する牧師だったが、このもてなしを拒むことは末娘を侮辱することだと説得され、受け入れることになる。
自分の娘に性的接待をさせることは、うまくいけばオルー一家に子をもたらし、その子たちは労働力となり、場合によっては他部族への奴隷として提供することもできる。したがって、オルーにとって、娘たちを異人に提供することは、やって来たフランス人から税金を取り立てる意味があるという。
しかも同地にあっては、娘が結婚する際にすでに子持ちであることは、夫から歓迎されこそすれ、結婚の妨げになることはない。夫は喜んで子どもたちの父親になる。妻が結婚の時点で誰かほかの男性の子をはらんでいても構わない。
最終的に出航するまでの間に、牧師は、オルーの次女、長女、そして最後の夜にはオルーの妻とも一夜を共にし、性関係を結ぶことになる。
[結婚とは何か] オルーに言わせれば、生涯一人の相手とだけ契りを結ぶというフランスの結婚は自然の掟に反し、理性に反するものである。
オルーは、フランス人の夫は本当に結婚の間ほかの女性と関係をもたないのか、フランスの妻は夫以外の男と関係をもたないのか、と牧師に尋ねる。牧師は「残念ながら、実はそのような関係はありふれたことである」と答えざるを得ない(24頁)。
それでは、タヒチ人にとって結婚とは何かという牧師の問いに、オルーは「都合がよい限り、同じ小屋に住み、同じ寝床で一緒に寝ようという約束だ、都合が悪くなったら別れればよい」と答える。子どもたちはどうするのかという牧師の問いには、子どもは一家の財産であるのと同時に世間の財産でもある、子どもが増えることは部族にとってもよいことである、別れる夫婦双方で協議して分け合うのだ、と答える。
牧師は、この人たちには嫉妬という感情がないようだ、夫婦愛とか母性愛といった感情はないようだと独り言をいうが、かえって、オルーは、不義の子を捨てなければならないフランスの妻や、妻の産んだ子が本当に自分の子かと猜疑心に苛まれるフランスの夫を憐れむのである(25頁)。
[近親相姦について] 父と娘が同衾し、母が息子と同衾することを当然とするタヒチ人オルーに向かって近親相姦を批判する牧師に対して、オルーはこう反論する。
「もし神(このタヒチ人は万物の創造主を「(万物を作る)職人の親方」と呼んでいる)が最初にアダムとイヴを作ったとして、もし2人の間に女の子しか生まれず、しかもイヴが先に死んでしまったら、どうやってアダムは子孫をもうけることができたのか? もしアダムとイヴの間に男の子しか生まれず、しかもアダムが先に死んでしまったとしたら、どうやってイヴは子孫をもうけることができたのか」と問いかけて、近親相姦を当然のことのように言う(32頁)。
ぼくは聖書には疎いが、創世記には、アダムとイヴの子どもたちはどうやって3代目をもうけたと書いてあるのだろうか。この近親相姦の許容もディドロの見解であろうが、モンテスキュー『法の精神』もそうだったが、フランスの啓蒙思想家の近親相姦への許容的態度は、フランスのどのような文化、思想に由来するのだろうか。2人とも、大航海時代にヨーロッパにもたらされた世界各地の習俗に関する知見から、そのような見解に至ったのかもしれない。
[自然状態と自然法] ディドロが、オルーというタヒチ青年の口を通して語るタヒチの習俗と自然の掟は、実はディドロが理想とする自然状態と自然法を描いているようだ。
ディドロは、本来悪とされるものの他は何も法律や世論によって悪とされることのない、仕事や収穫は共同体でなされ、「所有権」の範囲はきわめて狭く、恋愛の情念は肉体的欲求に還元され、島全体が一つの家族のようであると、タヒチの習俗を要約する(40頁)。そして、くだんの従軍牧師は僧衣を投げ捨てて、残りの生涯をタヒチ人と共に過ごしたいと願ったであろうと想像する(同頁)。
タヒチ人こそが、文明国民よりも良き立法に近づいて、自然法を守った(42頁)。これに対して、ヨーロッパ人は、相矛盾する自然法と市民法と宗教法に服従させられることで、常にこれら3つの法典にかわるがわる違反せざるを得ない状態にある。もし、永遠の人間関係の上に道徳が樹立されるなら、自然法に従うことによって、他の2つの法律は必要なくなる(41頁)。
「貞節」(fidelite)とは、律儀な男と律儀な女の我慢くらべの難行苦行であり、「操」(constance)とは、一瞬の陶酔のためにめくらにされている身の程を知らない二人の子供の哀れな虚栄であり、「嫉妬」とは、われわれの間違った習俗の必然の結果である、ということになる(42~43頁)。そして、女性が男性の所有物となったときから、「羞恥」、「慎み」、「行儀」といった架空の美徳(すなわち悪徳)が生じたという(44頁)。
ヨーロッパ人は両性の間に柵を設け、両性が互いに誘い合って彼らに課せられた法律を犯そうとするのを防止しようとしたが、その柵はかえって彼らの想像を灼熱させ、欲望を刺激する(同頁)。ヨーロッパでは、人間の自然の衝動(=性衝動だろう)に従うことを悪徳とし、自然がわれわれに与えた偉大で、甘美で、無邪気な楽しみを堕落の源泉としてしまった(45頁)。
[再び結婚について] もっとも、ディドロは、「結婚」とは一個の雌が雄全体の中から一個の雄に限って許す選り好みである、一個の雄が雌全体の中から一個の雌に限って許す選り好みのことで、期間はともかく継続的な結合を生じさせ、個体を生殖することによって種族を永続させるものだから、結婚は自然なことだとも言う(42頁)。
この「選り好み」の手段が“galanterie”であるという。訳者は「いんぎん」(慇懃)という訳語を当てているが、辞書で調べると、“galanterie”には「①(女性に対する)慇懃さ、親切。丁重;色好み」とあり、「③[古語]色事、情事→aventure.」といった訳語があてられている。「いんぎん」ではないだろうが(もっともぼくは「慇懃」の正確な語義を知らない)、どれが適訳なのか。そもそも、この語に対応する日本語があるのか。
他方で、「汝の妻以外の女を知るべからず、汝の妹の夫となるべからず」という禁制を奇怪なものだというところを見ると(46頁)、ディドロは、結婚として、生殖を目的とした男女間の単婚を想定しているが、終身ではなく期間の定めのある有期の、しかも配偶者以外の異性との交渉(「文明国」の用語で言えば姦通、不貞)を許容し、近親者同士の結婚も認めるという、緩やかな条件の結婚制度を想定しているようだ。
男性の専制は女性を所有権の対象とし、習俗と慣例は婚姻関係に条件を負わせすぎ、市民法は婚姻を無限の形式的手続きに従属させ、子どもの出生は国家の富の増大をもたらすはずなのに実際には家庭の貧困の増大を招いている(46頁)。
われわれは自然や幸福から何と遠いところにいるのだろう、とディドロは嘆く。
ディドロがタヒチの習俗に仮託して語った上記のような自然法、結婚観を、編者の森本氏も家庭無用論、家族の廃絶への系譜の出発点と考え、このオムニバス形式の『婚姻の原理』という結婚論集の筆頭に置いたのであろう。
ブーガンヴィルのタヒチに関する知見から前近代ヨーロッパの家族、婚姻を批判したディドロの態度は、モルガン『古代社会』で得た知見から家族の死滅を説くエンゲルスを思わせ、あるいは、台湾原住民の習俗に依拠して明治民法の改正を提案した岡松参太郎を思わせるものがある。
※ ただし、訳者浜田泰佑氏の解説に引用されたアンリ・ルフェーブルによれば、ディドロはタヒチの性道徳と対比してヨーロッパの(カトリックの)性道徳を批判し、「自然に帰るか? 法律に従うか?」と問いかけ、「不条理な法律を攻撃するのだ」と言いながら、最終的には「さしあたっては(悪法でも)法律に従うのだ」とあいまいな結論に終わっていると批判されている(岩波文庫159頁)。
2021年4月6日 記









