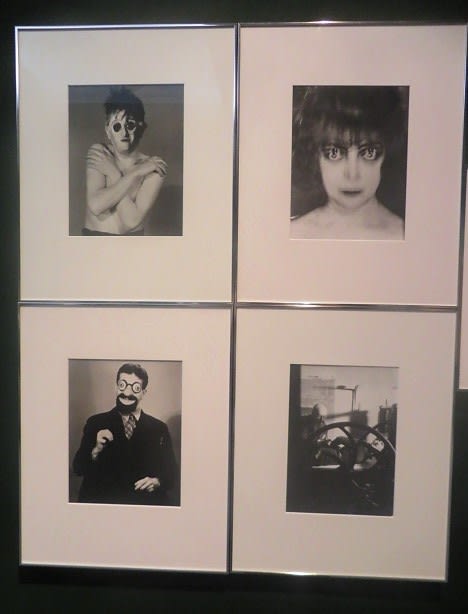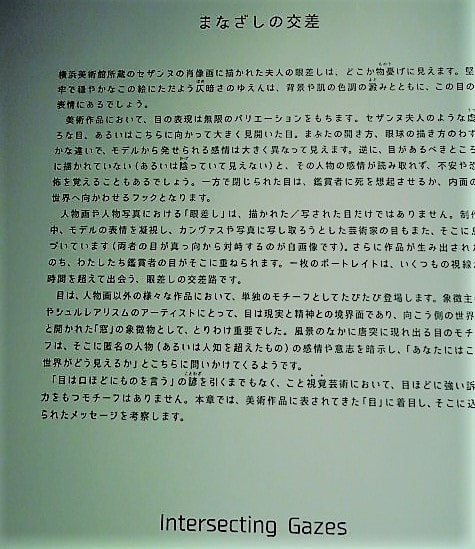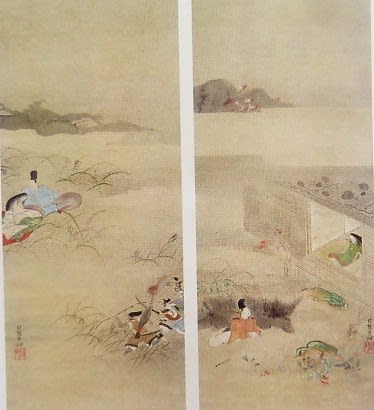こんにちわ。京都夏の旅シリーズです。
天竜寺のあと、大覚寺の蓮も考えたが、あまりの暑さに、あまり歩かないで済む嵐電に乗り、広隆寺に出掛けた。ここは蓮見が目的ではなく、言わずと知れた国宝第一号の弥勒菩薩さまにお会いするため。気まま生活に入って十数年になるが、その間、3回も拝観しているから、ぼくのお気に入りの仏像さんのひとつと言ってよい。
霊宝室に安置されているが、暗い照明と、奥まったところにおられるので、弥勒菩薩さまのはっきりした表情はわからない。だからいつもカタログの写真も併せて見る。

ドイツの哲学者カール・ヤスパースが、今まで、世界中のいろいろな人間存在の最高に完成されたという彫刻を見てきたが、この広隆寺の弥勒像に敵うものはものはないと絶賛している。
(正面から)
この霊宝館では、弥勒菩薩さまが突出した人気だが、お隣りの弥勒菩薩(泣き弥勒)も国宝だし、対面の3メートルもある不空羂索観音、十一面千手観音像、そして、入口から左手の壁には十二神将がずらりと並ぶが、これらもすべて国宝である。さらに、重要文化財の寄木造の千手観音(藤原期)、聖徳太子16歳像(鎌倉期)など、飛鳥、天平、貞観、藤原、鎌倉それぞれの時代を代表するような仏像が並んでいる。国宝が20点、重要文化財48点というからすごい。
泣き弥勒
不空羂索観音
十一面千手観音像
千手観音坐像
不動明王坐像
聖徳太子孝養像
推古11年(603年)に、この地に住む秦河勝が聖徳太子から賜った弥勒菩薩を本尊として広隆寺を創建した。山科最古のお寺。明治維新後の廃仏毀釈で、広隆寺は荒れ果て、弥勒菩薩もかなり傷んだが、明治中期に修復され現在に至っている。
秦河勝ご夫妻神像
山門の仁王様
上宮王院太子殿(本堂)


霊宝殿の前庭には蓮の花は見られなかったが、弥勒菩薩さまのようにうつくしい桔梗が咲いていた。


(京都夏の旅#4)