9月だというのに毎日暑い日がつづき、
夕立も降らなくなってしまいました。
鉢植えはもちろん、庭の木々たちも水をやらないと、葉がしおれ気味でぐったりした様子。
一通り水をやるのに1時間くらいかかるので、最近は忙しくては一日おき。
イチジクの産地の愛知県で、イチジクの収穫期を迎えたというニュースをやっていたので、
水遣りついでに、わが家のイチジク・バナーネの様子を見に行きました。
数日見ないうちに、色づいているのが3個。
よく見ると、どれも鳥につつかれています。

とはいえ、初物なので、もったいないので食べることにしました。
3個のイチジクを小さく切って、バナーネの生ハムまきです。

生ハムの塩分と、イチジクの甘味がマッチして美味。
鶏ムネニクと舞茸があったので、炊き込みご飯をしようと炊飯器にセットして、
「炊き込みご飯」を選んだのですが「炊飯」を押すのを忘れていました。
1時間ほどしてから、ともちゃんに「つやつや保温になってるよ」と言われて、
あっと気がついたら、水分がなくなっていました。
きょうきょ、蒸し器で蒸して「とり釜飯」風に。

おこげはないけど、これはこれでおいしい。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
毎日新聞の「記者の目:離婚と親子のかかわり」を書いている
反橋希美記者の記事がおもしろいので紹介します。
最後まで読んでくださってありがとう
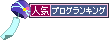
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

夕立も降らなくなってしまいました。
鉢植えはもちろん、庭の木々たちも水をやらないと、葉がしおれ気味でぐったりした様子。
一通り水をやるのに1時間くらいかかるので、最近は忙しくては一日おき。
イチジクの産地の愛知県で、イチジクの収穫期を迎えたというニュースをやっていたので、
水遣りついでに、わが家のイチジク・バナーネの様子を見に行きました。
数日見ないうちに、色づいているのが3個。
よく見ると、どれも鳥につつかれています。

とはいえ、初物なので、もったいないので食べることにしました。
3個のイチジクを小さく切って、バナーネの生ハムまきです。

生ハムの塩分と、イチジクの甘味がマッチして美味。
鶏ムネニクと舞茸があったので、炊き込みご飯をしようと炊飯器にセットして、
「炊き込みご飯」を選んだのですが「炊飯」を押すのを忘れていました。
1時間ほどしてから、ともちゃんに「つやつや保温になってるよ」と言われて、
あっと気がついたら、水分がなくなっていました。
きょうきょ、蒸し器で蒸して「とり釜飯」風に。

おこげはないけど、これはこれでおいしい。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
毎日新聞の「記者の目:離婚と親子のかかわり」を書いている
反橋希美記者の記事がおもしろいので紹介します。
 記者の目:離婚と親子のかかわり=反橋希美(大阪学芸部) 記者の目:離婚と親子のかかわり=反橋希美(大阪学芸部)毎日新聞 2010年8月31日 離婚すると夫婦は他人。では親子は--。離婚後に離れて住む親と子のかかわりを考える企画「親子が別れる時~離婚を考える」を5月、本紙くらしナビ面に連載し「離婚しても親子は親子」と必ずしも言えない現状を報告した。離婚後の子どもの心と体を育てるのは養育費と、離れて住む親と会う面会交流。親権者さえ決めれば離婚できる現在の協議離婚制度から、この二つを取り決めてから離婚する仕組みに改めるべきだ。 ◇別居親との面会は子の権利 この問題に関心を持ったきっかけは自分の離婚だった。当時、私が親権を持った長男は3歳、長女は8カ月。子を元夫に会わせるには私が連れて行かねばならない。元夫と顔を合わせるのは気まずいが「親子の交流は必要」と考え、離婚時に養育費と併せ面会についても話し合った。だが周囲は、上の世代ほど「なぜ会わせるの」と困惑した。 国が5年ごとに実施するひとり親世帯の調査で、養育費の支払率は約2割(06年)。極めて厳しい数字だが、同調査で面会交流は実施状況すら把握されていない。「離婚=縁切り」というイエ制度からの離婚観がいまだに根強いことを肌で感じた。 ◇違う価値観知りたくましく育つ 父母の一方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係および直接の接触を維持する権利を尊重する--。日本が94年に批准した子どもの権利条約の文言だ。欧米では80年代ごろから離婚の増加とともに子どもの福祉を重視する潮流が生じ、離婚後も両親が子の養育にかかわる「共同親権」が広がった。子どもは普段は一方の親と暮らすが、隔週2泊3日程度、別居親と過ごす。 日本は一方しか親権を持てない単独親権制だ。面会交流は近年、裁判や調停で広く認められるようになってきたが「子が嫌がっている」と親権者が強く拒否すれば、却下されることも少なくない。書類の親権者欄にチェックを入れるだけで協議離婚が成立する現行制度で、面会交流を取り決めている人は少ない。 面会交流が広がらない一番の要因は、子が別れた親に会う意義を見いだせないと考える人が多いからではないか。 私は、多くの場合、親子の交流は意味があると思う。幼いころに親の離婚を経験した男性(39)は祖母に「母は死んだ」と育てられた。成長し祖母との閉鎖的な関係に悩んでいた時、母の生存が分かり、離婚理由を聞いたことが生きる力を取り戻すきっかけになった。「テレビの再会番組みたいな劇的な感動はない。でも何かふに落ちた」という男性の言葉が印象的だった。 離婚家庭の子どもたちが交流し助け合うグループの運営にかかわる東京国際大の小田切紀子教授(臨床心理学)は「一概には言えない」としつつ「別居親と交流がある子は同居親といい関係が築ける傾向がある」と話す。両方の親の価値観に接すると、同居親と過度に依存し合ったり、逆に反発が集中しにくくなる。 親子の面会を援助する家庭問題情報センター(東京)の山口恵美子さんは「あんな父親でも会わせる意味はあるの」と相談してくる母親に「あなたは完ぺきな親?」と問う。山あり谷ありの面会を経て、たくましく育つ子たちを見てきた経験から「反面教師でも、親を知ることが自我形成につながる」と確信しているという。私も同意見だ。 ◇「共同親権」の原則化は疑問 では共同親権を導入すべきか。私は選択肢としてならよいが、原則化には賛成できない。理由は「会わせられない」人の存在だ。離婚原因に家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)や精神的虐待を挙げる人は少なくない。今でも調停や裁判で面会を命じられてもうまくいかないケースが多々ある。欧米のように、安全な面会援助施設や、離婚前後の両親の相談に乗る機関の整備が先決だ。 当面の手立てとして参考になるのが、離婚観が近い韓国だ。養育費支払いと面会の方法を取り決めた計画書を裁判所に提出しなければ離婚できない。離婚時に作成した書類で養育費取り立ての強制執行もできる。08年以降に法が改正された結果だが、現地の専門家は「親たちの意識が変わってきた」という。 韓国方式の導入にはそれなりの公費投入が必要だが、効果はある。離婚後、何年も紛争が続くほど対立が激しい夫婦は全体から見れば少数で、一時の感情で交流のきっかけを失っている人たちも相当数いる。前述した施設や機関の整備を進め、「養育費と面会交流は子の当然の権利」との認識が広まれば、スムーズに交流できる人も多いはずだ。親が離婚する子どもは年間24万人。本気で取り組むときだ。 毎日新聞 2010年8月31日 |
| 親子が別れる時:離婚を考える 韓国の制度改革 養育費、面会…家裁が確認 毎日新聞 2010年8月4日 ◇「子の利益」を重視/両親への教育、指導も 離婚後の親子のかかわり方をめぐって欧米を中心に制度改革が進む中、韓国でも08年6月に協議離婚制度の改正法が施行された。養育費の支払いや面会交流についての協議書を家庭裁判所に提出しなければ離婚できないのが大きな特徴だ。「離婚=縁切り」という伝統的な離婚観は日本と同じ韓国で、なぜ改正が実現したのか。研究者や現地の家裁調査官に背景を聞いた。【反橋希美】 法改正の柱は次の3点だ。 (1)離婚時、夫婦は離婚に関する説明会に参加し、子どもに与える影響などを学ぶ (2)軽率な離婚防止のため、養育する子がいる場合は、(1)の説明会から3カ月を経なければ離婚できない(熟慮期間の設置) (3)親権者や面会交流の方法を記した協議書を家庭裁判所に提出する 親権は単独でも父母共同でも持てるが、日本と同様、母親が持つケースが大半という。 韓国家族法に詳しい山梨学院大の金亮完(キムヤンワン)准教授は「97年の通貨危機による不況で、離婚後、双方の親から引き取られない子どもたちが増え、社会問題になった」と法改正の背景を説明する。政府機関が06年に行った調査では、離婚家庭の8割が養育費の支払いを受けておらず、定期的に面会交流をする家庭はわずか1割。離婚が増える中、子どもに与える影響への懸念も要因になった。 家裁に提出する養育の協議書には、養育費の支払口座や、面会交流の日程、面会する場所まで書き込む欄がある。源泉徴収票の添付も義務付けられており、養育費の額が所得とかけ離れていないかどうか確認される。昨年からは離婚時の作成書類を使って、養育費を払わない親からの取り立てを強制執行できるようにもなった。 * 日本ではいまだに養育費や面会方法を取り決めずに離婚することができる。「子どもの福祉に反する」などの批判がある一方で、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害女性を擁護する立場からは「暴力から逃げるために一刻も早く離婚したい人もいる」と、韓国のような改正に反対する声がある。 同じような反発は韓国内でもあった。このため改正法にはDVなどの場合は熟慮期間を免除してすぐに離婚できる規定が設けられている。ソウル家庭法院(家裁)の調査官、宋賢鐘(ソンヒョンジョン)さんは「子どものことを決めずに離婚できる弊害のほうが問題視された」と説明する。 法改正後の変化について、宋さんは「元配偶者に子どもと面会させたがらなかった親が、家裁の教育を受け、面会をさせるようになるケースが現れている」と話す。 ソウル家庭法院では今年1月から、対立が激しい両親の意思疎通を助ける「養育手帳」も配布している。面会時に気を付けてほしいこと、相談事などを書き、面会の際に子に持たせる。また、子どもの意見を聞く重要性が認識されるようになり、聞き取り方などを解説した「意見聴取指針書」も作られ、全国の裁判所で使われているという。 * こうした韓国の制度は日本でも採用できるのだろうか。金さんは「子どもの利益を考える観点から、現状の日本の制度は早急に再検討すべきだ。韓国と同じ制度を導入するのであれば、協議書のチェックなどの事務作業が増えるため、家裁の処理能力をより充実させる必要があるだろう」と話している。」 (毎日新聞 2010年8月4日) |
| 父子家庭にも児童扶養手当 2010年8月31日 読売新聞 8月から児童扶養手当が父子家庭にも支給されるようになりました。そもそもどんな制度? 非正規就労の増加に対応 児童扶養手当は、離婚や死別などにより、1人で子どもを育てなければならなくなった親に支給される。1962年から始まった国の制度で、仕事と育児を1人でこなしていくのは負担がかかるため、経済的に支援する仕組みだ。 住んでいる市町村に申請すると、一定の所得以下の親に月4万1720円~9850円が支給される。2人目の子どもには5000円、3人目以降は1人につき3000円の加算。例えば親子2人世帯なら年収365万円未満で受給資格が生じ、130万円未満で最大額が支給される。 手当を受け取れるのはこれまで、母子家庭や祖父母が子育てをするケースなどに限られていた。父子家庭が外れていたのは、「男性は正社員で働くことが多く、収入も多い」とみられたためだ。しかし、民主党政権が児童扶養手当法を見直し、8月から父子家庭も支給対象に加えられた。 その背景には、男性の間にも不安定な非正規雇用が広がっていることがある。正社員だったとしても、保育園の送迎や家事、転勤などとの両立に苦しんで、非正規へ転じるケースもあるだろう。 厚生労働省の2006年度の調査では、働いて得られる年収が300万円未満の父子家庭は37%。母子家庭なら88%に上っており、それより低いとはいうものの、多くの父子家庭が家計のやりくりに苦しんでいる様子がわかる。 厚労省のまとめでは09年に、母子家庭約120万世帯のうち約97万世帯に手当が支給されている。父子家庭は約20万世帯で、半数の10万世帯が支給対象になる見込みだ。 離婚の増加で手当の受給者は増えている。就業を促すとともに財政支出を減らすため、02年の法改正で、受給期間が5年を超えれば手当が半減されるようになった。働いても収入が少なかったり、病気や障害などで働けないことを証明したりすれば減額されないものの、受給者の反発は強く、厚労省では、減額制度の見直しも検討している。これまでに約4000人が手当を減額されている。 ひとり親家庭に対しては経済的な面だけにとどまらず、就労や住宅の確保、教育、育児など様々な支援が求められている。(小山孝) (2010年8月31日 読売新聞) |
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね



















