けさは肘関節を粉砕骨折した人に付き添って病院へ。
来週、腫れが引くのを待って入院・手術することになりました。
その帰りに、マーサ岐阜店にある自然食レストラン「 豆乃畑 」に行ってきました。


ビュッフェ形式で、手作りのお豆腐(白と黒ゴマ)や豆腐料理がおいしいです。
デザートもヘルシー。
おなかがいっぱいになりました。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨年秋から今年の春にかけて、毎日新聞の「くらしナビ」で、
性同一性障害や性分化疾患のことをテーマにした
「境界を生きる」という連載があり、わたしももブログにアップしました。
性同一性障害:「思い尊重を」/境界を生きる 性分化疾患(毎日新聞(2010-02-14)
今日の「記者の目」は、その連載を書いた、丹野恒一記者が、
「性別の『多様な形』を認めよう」という記事を書いていらっしゃいます。
朝日新聞は、「スポーツ界の性別問題」として、
「性分化疾患(DSD)」のことを取り上げていました。
明日は豊田市美術館へ、
上野千鶴子さんと森村泰昌さんとの対談を聴きに行きます。
最後まで読んでくださってありがとう
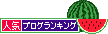
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

来週、腫れが引くのを待って入院・手術することになりました。
その帰りに、マーサ岐阜店にある自然食レストラン「 豆乃畑 」に行ってきました。


ビュッフェ形式で、手作りのお豆腐(白と黒ゴマ)や豆腐料理がおいしいです。
デザートもヘルシー。
おなかがいっぱいになりました。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨年秋から今年の春にかけて、毎日新聞の「くらしナビ」で、
性同一性障害や性分化疾患のことをテーマにした
「境界を生きる」という連載があり、わたしももブログにアップしました。
性同一性障害:「思い尊重を」/境界を生きる 性分化疾患(毎日新聞(2010-02-14)
今日の「記者の目」は、その連載を書いた、丹野恒一記者が、
「性別の『多様な形』を認めよう」という記事を書いていらっしゃいます。
 記者の目:性分化疾患と性同一性障害=丹野恒一 記者の目:性分化疾患と性同一性障害=丹野恒一毎日新聞 2010年9月3日 「男の子か女の子か、どちらにしますか」。子が生まれた直後、医師にそんな決断を迫られたら、どう答えることができるのだろう。 染色体やホルモンの異常が原因で外見からは性別が判断しづらい赤ちゃんが数千人に1人の割合で生まれている。その事実を知ったのは2年余り前だった。我が子3人の出産に立ち会った私は、子どもの性別は出産前から決まっていて、誕生した時には確かめるだけだと思い込んでいた。だが幸せに包まれるはずの瞬間に医師の一言で目の前が真っ暗になり、親族や知人からの祝福の電話にも出られない親たちがいる。しかも医療関係者の知識が不十分だと、適切な検査もなく性別が決められてしまうことさえある。 ◇自分は男?女?苦しんで自死も 性別は染色体の型がXXかXYかで決まると考えられがちだが、性器や性腺(卵巣・精巣)が女性か男性かで一致していなかったり、染色体もXだけだったり、XXYといった型で生まれてくる子どもがいる。成長後も、男女どちらにもはっきり属することができない体と感覚に苦しむことが少なくない。 こうした子どもはずっと前から生まれていたにもかかわらず、社会の偏見の中で本人や親は隠し続け、医療界もメディアもタブー視してきた。日本小児内分泌学会はこれまで使われてきた「半陰陽」や「両性具有」という言葉に蔑視(べっし)するような響きがあるとして「性分化疾患」に統一したが、それもわずか1年前のことだ。 私は当事者や家族を一人一人訪ね、昨秋からくらしナビ面で連載「境界を生きる」を執筆している。長く声を上げられなかった人の話を聞いていくにつれ、自分の中にあった「性別」というものに対する固定観念は崩れていった。 性分化疾患を持って生まれてきた子どもたちは、いつ自分の疾患を知るべきなのか。それだけでも難しい問題だ。何も知らず男の子として育ち、ある日突然に初潮が来たり、女の子として育って成長後に卵巣や子宮がないと知ることがある。恋をする年齢になり、事実を知った直後に自ら命を絶った大学生もいた。 性別の境界にいるのは彼らだけではない。体の性別がはっきりしていても、心と一致せず苦しむ性同一性障害は、1000人に1人の割合ともいわれる。男女別の生活を強いられる学校に通えなくなったり、誰にも打ち明けられず自傷行為を繰り返す子どもたちもいる。 連載をこう評した家族がいた。「取材に応じられるのは壁を乗り越えられた人たちだけ。声を上げられない人が大勢いる」。取材を申し込んだところ、こう断られたこともある。「あなたのお子さんが同じような状況のとき、知る必要のない人たちにまで知ってほしいと思いますか。世の中には知らなくていいことだってあるんです」。心も体もほぼ女性なのに、ホルモンの異常で外性器が男性化してしまう疾患の子の母親だった。 ◇自分らしく生きたいだけ 他にも耳を離れない言葉がある。心は女性なのに体が男性で苦しむ18歳の学生を取材した時のことだ。安全性を無視して個人輸入した女性ホルモン剤を服用しているが、外見の変化は期待ほどでないという。「今の姿のままで女性として生き始めても、性的倒錯者としか思われない」。自分らしく生きたいだけなのに、なぜ自らをそんなふうに表現しなければならないのか。返す言葉が見つからない私に、学生は痛々しい決意を示した。「それでも生き抜けるよう、強くなりたい」 連載にはこれまでに100通近い反響をいただいた。共感や体験に交じり、55歳の男性会社員から批判的な感想が届いた。「男に生まれた以上は男として生きるよう身に着けさせるべきだ」。理由は「手術で性別を変えても、母親にはなれないから」という。こうした考えもまだ根強いのだろう。 私自身は取材を通して、性別の境界を生きる人々は決して特別な存在ではないと思うようになった。性には多様な形があり、体の性別があいまいなこともあれば、心の性別が体と逆になることもあり、好きな性が異性であったり同性であったりもする。私を含む多数の人は、その数限りない組み合わせの中から、たまたま典型的な形でそろっただけの存在なのだ。 「知らなくていいことがある」「性的倒錯者とみられてしまう」。家族や子どもたちにそう思わせているものは何なのだろう。人間は男女に二分される。そんな常識を問い直す先に訪れるのは無秩序か、それとも誰もが生きやすい社会か。私は後者だと信じたい。(生活報道部) 毎日新聞 2010年9月3日 |
朝日新聞は、「スポーツ界の性別問題」として、
「性分化疾患(DSD)」のことを取り上げていました。
| 性別問題、急ピッチで指針づくり 「セメンヤ疑惑」契機1/2 2010年8月24日 朝日新聞 男性か女性か。そんな単純な二分法が通用しない。どう対処すべきか――。性別疑惑に揺れた末、約11カ月のブランクを経て競技に復帰した陸上女子のキャスター・セメンヤ(19)=南アフリカ=は、実は古くからあるスポーツ界の性別問題に改めて目を向けさせた。 ◇ 国際オリンピック委員会(IOC)と国際陸連(IAAF)は1月、米マイアミで2日間の専門家会議を開いた。テーマは「性分化疾患(DSD)」。生まれつき、性染色体や性器、性腺などが男性か女性かで統一されず、性があいまいな状態をいう。 米紙などの報道によると、IOCのリュンクビスト医事委員長は「特定のケースは議論しなかった」と話した。しかし、昨夏のベルリン世界選手権女子800メートルで優勝し、筋肉質の体形や顔立ちなどから「男性ではないか」と世界中で話題になったセメンヤの登場が、こうした動きの引き金になったことは間違いない。会議では、性別が問題になる選手を扱う専門の医療センターを世界数カ所につくることなどが検討された。医事委員長は診断や検査だけでなく、ホルモン療法や手術をする可能性を示した。 IAAFはIOCとの合同会議以降、7回もの協議を重ね、DSDの選手の扱いに関するルールづくりを急いでいる。原案はほぼ完成。11月の理事会で承認、来年1月からの発効を目指す。 ◇ 日本陸連の医事委員を務める埼玉医大産婦人科の難波聡講師は、今までの情報から推測して、セメンヤもDSDである可能性が高いと考える。IAAFは検査の詳細を一切公表していないが「人権保護の面から当然。DSDなら彼女は患者であり、プライバシーを侵害されたという面では被害者でもある」。 DSDのスポーツ選手が競技を続ける場合、問題になるのが男性ホルモンの量だ。 例えば、DSDの一種「アンドロゲン(男性ホルモン)不応症」。体内には卵巣でなく精巣があり、男性ホルモンのテストステロンが分泌されるが、ホルモンとしてうまく働かない症状だ。テストステロンは細胞内にある受容体と結合してはじめて効果を表すが、その受容体が機能しないと男性化が進まない。 まったく受容体が機能しない「完全型」なら競技で有利さはないが、一部が機能する「部分型」だとほかの女性に比べて筋肉増強作用が強く、有利になってしまう。難波講師は「過去には、精巣を摘出する手術をして競技に復帰した選手もいる」と話す。 セメンヤの場合も、長いブランクの理由として、性別検査のほかにホルモン療法や手術が実施されたのではないかという情報も流れている。しかし、セメンヤ本人もセメ・コーチも「その質問には一切答えない」と口をつぐむ。 性別問題、急ピッチで指針づくり 「セメンヤ疑惑」契機2/2 ◇ あるスポーツ医学関係者によると、性別が問題になりそうな選手が現れたときは「国際舞台に出る前に、各国内で対処する」という了解があるという。 南ア陸連は世界選手権に派遣する前、ドーピング検査と偽ってセメンヤに性別検査をしていた。が、そのまま出場させた。もし、その時点で派遣を見合わせていれば、少なくとも、セメンヤが世界中の好奇の目にさらされることはなかっただろう。 1年前に疑惑が浮上して以降、IAAFから競技会への参加自粛を要請された。その間、性別検査と同時に代理人の弁護士とIAAFとの協議が続き、7月にIAAFは「出場を認める」と発表した。 22日には、ベルリンでの国際競技会に出場し、1分59秒90で優勝した。1年前の記録よりはまだ4秒以上遅いが、復帰後初の1分台。「ここまでの道は簡単ではなかった。過去のことでなく、未来について話したい」(AP)と話すセメンヤの表情に少しずつ明るさが戻っている。(酒瀬川亮介) ■過去にあった性別問題の例 ・1930年代に五輪でメダル2個を獲得したポーランドの短距離選手が引退後に強盗事件に巻き込まれ、撃たれて死亡。検視すると男性器があり、性染色体も男性と女性の両型をもっていた。 ・1960年代、旧ソ連の投てき選手として五輪で複数のメダルを手にし、計26個の世界記録をつくった姉妹に性別疑惑が。国際試合に性別検査が導入されると、表舞台から姿を消した。 ・2006年ドーハ・アジア大会陸上女子800メートルで銀メダルだったインド選手に性別疑惑。検査の結果、男性が偽って出場していたことがわかり失格。 ◇ 《性別検査》五輪では、1960年代半ばから90年代後半まで全女子選手を対象に性別検査を実施していた。口内の粘膜から性染色体を採り「XY」型なら男性、「XX」型なら女性と判定する。ところが、実際には「XXY」や、「XY」「XX」の両方が存在するなど様々な型がある。 96年アトランタ大会では、女子選手3300人あまりのうち8人に男性型のY染色体があった。が、結果的にDSDと判断されて出場が認められた。この検査だけで出場の可否を決められないこともあり、廃止に。現在は問題が起きた時に個別対応している。 |
明日は豊田市美術館へ、
上野千鶴子さんと森村泰昌さんとの対談を聴きに行きます。
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね



















