12月4日の朝日新聞社説は、シリーズ「政治を鍛える」。
今回は、「自治―『自分たちで決める』が原点だ」でズバリ「市民自治」がテーマ。
ずっーと前から私たちが言ったり実践してきたことが、
社説で取り上げられる時代になったんだ、と感慨深いです(笑)。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
同じ日の朝日新聞の書評欄に、上野さんの記事、
現代思想12月号増刊号の「総特集 上野千鶴子」が載っていました。
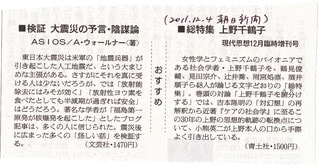
この日、名古屋に行っていて上野さんの話を聞いて帰ったら、
上野さんから、「総特集 上野千鶴子」が届いていました。
岐阜の本屋を探しても見つからなかった、とツイッターでつぶやいたので、
送ってくださったのでしょう。
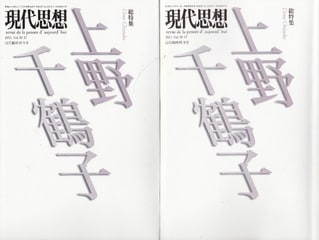
その後入手できたので、二さつになりました。
名古屋に行ったとき、高島屋の三省堂で、
上野さんと古市さんの共著『上野先生、勝手に死なれちゃ困ります』と、
信田さよ子さんの『さよなら、お母さん 墓守娘が決断する時』を見つけて買いました。


どちらも読みやすく、おもしろい本です。
オマケ。
上野さんの講演の記事です。
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

今回は、「自治―『自分たちで決める』が原点だ」でズバリ「市民自治」がテーマ。
ずっーと前から私たちが言ったり実践してきたことが、
社説で取り上げられる時代になったんだ、と感慨深いです(笑)。
 社説:政治を鍛える 自治―「自分たちで決める」が原点だ 社説:政治を鍛える 自治―「自分たちで決める」が原点だ 2011年12月4日(日)付 朝日新聞 きょう、岩手県大槌町は復興のひとつの節目を迎える。 町内の10地区が、それぞれ2カ月かけて検討してきた復興計画の素案を持ち寄る。前町長をはじめ、住民の1割近い1300人余りが犠牲になった町が、再起へまた一歩を踏み出す。 高さ14.5メートルの防潮堤を築くのか。もっと低くして、盛り土の上に住宅を建てるのか。コンサルタント会社が地区ごとに描いた複数の復興計画のたたき台を、隔週末に地元の体育館などで、数十人から時には100人を超える住民が、図面を囲んで車座になって議論してきた。 町の原案に住民の同意を求める手法ではなく、町民に決めてもらう。そのため、町職員は発言せず、大学教授ら第三者が進行役を務めた。 住民主導にこだわったのは、8月に選ばれた碇川(いかりがわ)豊町長だ。 「まずは住んでいる人たちに議論してもらうのが基本。それが自治ということ」 役場機能を失い、復興に出遅れた町が行き着いたのが、拙速を避け「自分たちで決める」という自治の原点だった。 ■新しい参加のかたち いま、各地にさまざまな住民参加が広がりつつある。 地方議会を傍聴する住民が、議員の仕事ぶりを「通信簿」や「白書」で評価する動きが、仙台市や神奈川県川崎市、相模原市、千葉県佐倉市、兵庫県尼崎市などで盛んだ。 無作為に選ばれた住民が地域の課題を話し合い、役所に進言する「市民討議会」も増えている。NPO法人「市民討議会推進ネットワーク」によると、ことしは東京都町田市や愛知県豊山町をはじめ、全国55カ所で、市役所跡地の利用法や子育て政策などを議論してきた。 ただ、こんな元気な住民の活動は、1800近い自治体全体からみれば、まだまだ少数だ。ほとんどの市区町村では「役所頼み」「議会任せ」という「自治の丸投げ」が当たり前だ。 中学生までの医療費を無料にする自治体が現れるなど、住民負担の地域差は広がっている。 国民健康保険料でみれば、1人あたりの年額の最高は北海道猿払村の13万円余、最低は沖縄県伊平屋村の約3万円、ざっと4.3倍の開きがある。 医療や介護の受益と負担をどう考えるのか。いつとも知れぬ大地震にどう備えるのか。 住民が傍観者でいるわけにはいかない問題が山積している。 ■議会を変えよう 4年に一度の選挙で知事や市町村長、議員を選ぶ。それだけで私たちは主権者といえるのだろうか。もっと、役所や議会との距離を縮めよう。 まずは議会だ。落選したときを考えれば、一般の勤め人は出にくい。だから自営業など一部の職種の議員が居並び、住民構成とかけ離れた議会になる。住民は関心を抱かず、不信感を募らせる悪循環に陥っている。 会議を夜に開くなどの工夫はもちろん、職場の仕事と議員活動を両立できる休職制度や、議員が議席を持ったまま首長選や国会に挑める制度などの仕組みを整えよう。 いまの議会には予算の提案権はなく、修正にも制約がある。住民に認められている条例制定などの直接請求では、地方税は対象にできない。 こうした地方自治法の規定が、議会や住民を「自治体の財政」に関する議論から遠ざけているとの指摘がある。法改正を検討してもいいだろう。 有権者の間口も広げよう。 「選挙制度」でも提言したが、若者に地域のことを考えてもらうため、地方選挙権は16歳から認める。永住外国人にも地方選挙の投票権を与えよう。「日本国籍をとればいい」という反対論も根強いが、地域の一員として暮らす人々を排除しないことで、多様な意見が行き交い自治が豊かになる。 ■もっと住民に聞こう 住民投票制度も進化させる。投票ごとテーマごとに条例をつくるのでなく、あらかじめルールを決め、一定数の請求があれば実施する常設型を増やそう。全国で40余りの自治体が導入しており、岩手県奥州市、愛知県高浜市などでは永住外国人にも投票権を与えている。 また、首長と議会が対立したら、住民投票で決着をはかるのも一案だ。名古屋市のように首長と議会の激しい対立にエネルギーを費やすより、その両方を選んだ住民の判断に委ねるという発想だ。 自治の議論では、大阪都構想や道州制といった自治体の枠組みの議論が華やかに取り上げられがちだ。だが、もっと地道に地方分権を進め、足元を見つめ直すことで、住民自治を強めることが出発点になる。 できる限り、みずから参加して、考え、判断して、決めて、その責任も負う。そんな自治へのかかわりが、私たち自身の「政治」を鍛える。 |
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
同じ日の朝日新聞の書評欄に、上野さんの記事、
現代思想12月号増刊号の「総特集 上野千鶴子」が載っていました。
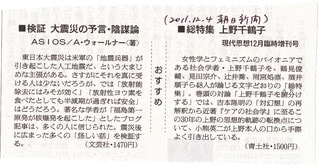
この日、名古屋に行っていて上野さんの話を聞いて帰ったら、
上野さんから、「総特集 上野千鶴子」が届いていました。
岐阜の本屋を探しても見つからなかった、とツイッターでつぶやいたので、
送ってくださったのでしょう。
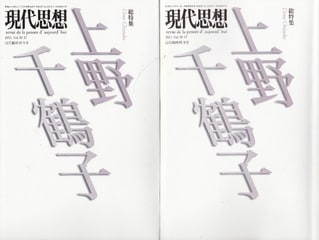
その後入手できたので、二さつになりました。
名古屋に行ったとき、高島屋の三省堂で、
上野さんと古市さんの共著『上野先生、勝手に死なれちゃ困ります』と、
信田さよ子さんの『さよなら、お母さん 墓守娘が決断する時』を見つけて買いました。


どちらも読みやすく、おもしろい本です。
| 『上野先生、勝手に死なれちゃ困ります 僕らの介護不安に答えてください 』 上野千鶴子/著 古市憲寿/著 光文社新書 ベストセラー『おひとりさまの老後』を残して、この春、東大を退職した上野千鶴子・東大元教授。帯の名文句「これで安心して死ねるかしら」に対して、残された教え子・古市憲寿が待ったをかける。親の老いや介護に不安を覚え始めた若者世代は、いくら親が勝手に死ねると思っていても、いざとなったら関与せずにはすまない。さらに少子高齢化社会で、団塊世代による負の遺産を手渡されると感じている子世代の先行きは、この上なく不透明。だとすれば、僕たちが今からできる心構えを、教えてほしい――と。これに対し、「あなたたちの不安を分節しましょう。それは親世代の介護の不安なの? それとも自分たち世代の将来の不安なの?」と切り返す上野。話は介護の実際的な問題へのアドバイスから、親子関係の分析、世代間格差の問題、共同体や運動の可能性etc.へと突き進む。30歳以上歳の離れた2人の社会学者の対話をきっかけに、若者の将来、この国の「老後」を考える試み。 目次 上野先生、勝手に死なないでください!(古市から上野先生への手紙) この本の読み方 第1章 何が不安なのか、わからない、という不安 第2章 介護という未知のゾーンへの不安 第3章 介護保険って何? 第4章 それより自分たちのこれからのほうが不安だった 第5章 少子化で先細りという不安 第6章 若者に不安がない、という不安 第7章 不安を見つめ、弱さを認めることからはじまる 古市くんへ(あとがきに代えて 上野からの返信) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ さよなら、お母さん 墓守娘が決断する時 信田さよ子著 春秋社 心の中での決別から関係断絶まで。『母が重くて…』の反響から生まれた難問解決の実践書! ベストセラー『母が重くてたまらない』から3年。その後の社会状況と震災後の様相を視野にいれた、今最も必要とされる問題解決の書。本気で一歩を踏み出したい墓守娘のために、より具体的な提言を試みる。娘でもあり、母親でもある(あるいはこれから母になる)読者にも届く一冊。 |
オマケ。
上野さんの講演の記事です。
| 上野さんが講演・「不惑のフェミニズム」 2011.12.5(草加市) とーよみ-NET 草加市立中央公民館で11月23日、NPO法人ウイメンズ・アクション・ネットワーク理事長で、女性学、ジェンダー研究のパイオニアとして知られている上野千鶴子さんによる「不惑のフェミニズム~弱いものが弱いままで生きられる社会づくりに向けて~」と題した講演会が行われた。主催は草加市と特定非営利活動法人みんなのまち草の根ネットの会。 この催しは、男女が互いに尊重し合い、共に持っている力を発揮し、生き生きと暮らせる社会を目指し、同市が毎年開催している「男女共同参画フォーラム」。今回は、法務省の地域人権啓発活動活性化事業の一つともなっている。 上野さんは、1970年のウーマン・リブ運動を萌芽とするフェミニズムの歴史を語るとともに、フェミニズムは女性解放の思想と行動であり、女性学とはリンカーンの言葉を借り「女の女による女のための学問研究」という。この女性学は、これまで男性が関心を持たず、しかも価値がないものとみなしてきた家事、出産、育児、生理などの女性の日常生活における疑問点や問題点を女性の目と言葉で語る。この、私のことは私が一番知っているから私に聞いて、は当事者研究へとなり、女性だけではなく障害者、がん患者、高齢者といった当事者(=弱者)にも目が向けられていく。 上野さんは、「フェミニズムは強い女の自己主張ではなく、弱者で何が悪いのか、弱いから繋がり支え合う社会を作り上げよう、と進めてきている」と結んだ。 また第2部として上野さんと、外国人の支援をしているNPO法人リビング・イン・ジャパンの簗瀬裕美子代表、学童保育を運営しているNPO法人草加・元気っ子クラブ小池奈津夫代表、草加市食生活改善推進員協議会岡田紀子代表が、それぞれの活動や問題点を意見交換した。上野さんは「皆さん活動していて楽しいでしょう。楽しいから続けられる」と語りかける。さらに「こうしたお金に換えることができない活動も楽しいものだということを若者に伝え、次につなげてほしい」と後継者の育成をお願いした。 講演会に訪れた同市住吉の嶋根重雄さん(67)は「上野さんと考え方が同じなのですんなりと話が入った。できればこうした大切な話は録音を認めてくれれば、もっと多くの人に広げられるのだが・・・」と話した。 |
最後まで読んでくださってありがとう


 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね



















