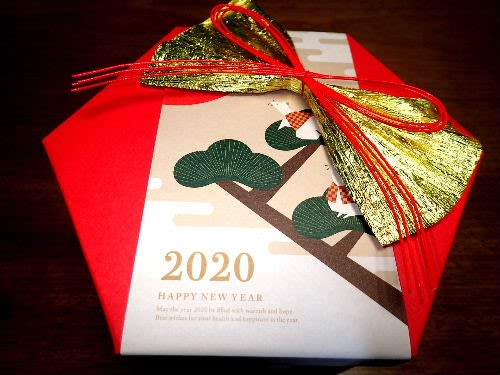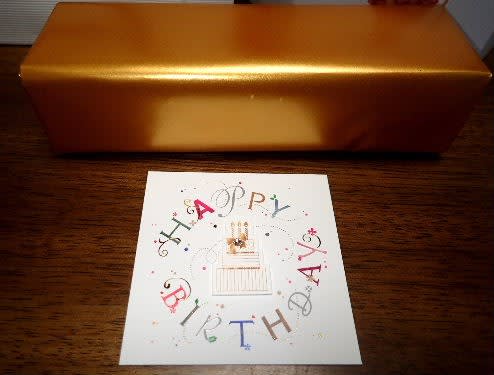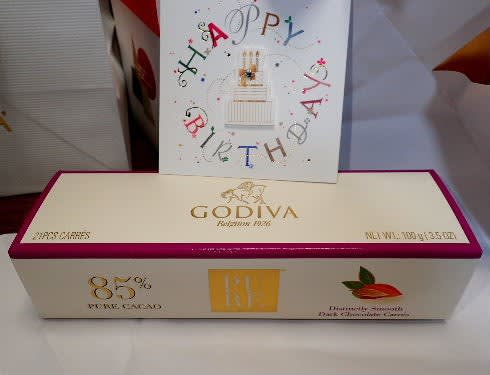2020年初の満月が、1月11日(土)未明ということを、
昨夜の10時ころに知って、
いそいでデジカメを手に外にできました。

夜空はとても明るくて、月には薄雲がかかっていたので、
輪のような光が月のまわりをつつんでいました。

幻想的なまんまるお月様を見てみてください。
1月の満月は“Wolf Moon(狼月)というそうです。

応援クリック してね
してね 


後半は、昨日の朝日新聞の記事、
「男女平等へ「一瞬の不都合の許容を」 ハヤカワ五味さん」を紹介します。
最後まで読んでくださってありがとう
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

昨夜の10時ころに知って、
いそいでデジカメを手に外にできました。

夜空はとても明るくて、月には薄雲がかかっていたので、
輪のような光が月のまわりをつつんでいました。

幻想的なまんまるお月様を見てみてください。
1月の満月は“Wolf Moon(狼月)というそうです。

応援クリック



後半は、昨日の朝日新聞の記事、
「男女平等へ「一瞬の不都合の許容を」 ハヤカワ五味さん」を紹介します。
| 男女平等へ「一瞬の不都合の許容を」 ハヤカワ五味さん 太田成美 2020年1月10日 朝日新聞 安倍晋三首相による長期政権は安定をもたらしたと言われる一方で、異論や変化を拒む空気も広がっている。「最長首相」の任期が迫る中、日本の政治は前に進めるのか。起業家のハヤカワ五味さん(24)に聞いた。 「自衛隊、唯一の策ではない」看護師が考える国際貢献 日本でもトランプ型広がる?言語学者に聞く政治家の言葉 歴史学者が見る安倍政権「江戸幕府より豊臣政権に近い」 ◇ 政治とビジネスって似ている部分がある。消費者が選挙権を持っているようなもので、買うこと自体がそのブランドを支持しているという表明になるから。 昨年立ち上げた生理用品のEC(ネット通販)サイトなどのプロジェクト「illuminate(イルミネート)」は、コソコソとレジに持って行くような花柄の派手なものではなく、シンプルでジェンダーレスなパッケージの生理用品など、今までになかった選択肢をつくりたいと始めた。 イルミネートには「照らす、啓蒙(けいもう)する」という意味がある。妊娠、出産や働き方……。女性が自ら選べるようになってきた。だからこそ、選択肢を増やし、選択肢があることに気付いてもらいたい。そしてタブー視されてきた生理を照らし、付随する課題を考えるきっかけにしたい、という思いを込めた。私は、世の中に価値観の変化を起こすのは、政治かビジネスのどちらかだと思っている。 前のパートナーと別れた理由は「選挙」。昨年7月の参院選では、選択的夫婦別姓も自民党とほかの政党の意見が割れて争点になったのに、パートナーが投票に行かなかったから。 法人の代表をしているので、結婚するにしても離婚するにしても、名字を変えるとめちゃくちゃ手続きが大変。パートナーも名字を変えたくないと言っていたから、じゃあ、夫婦別姓の議論に加わるべきだよね、「選挙に行こう」と言ったのに、行かなかった。自分たちの将来に対し、「無責任じゃないか」と。たかが一票だけど、それでしか世界は変わらない。 女性が選挙権を持ってから100年も経っていない。行使してやるぞ、と思う。 ジェンダーギャップ、「最下位目指しているのか」 政治の世界で女性を増やすためには、まずは形から入ってもいいのではないか。一定以上の議席を女性に割り当てる「クオータ制」を導入し、意識が追いつくのを待つことは合理的だ。最低限、25%とか30%を占めるようになれば、女性も安心して意見を発信できるようになる。 政党に、男女の候補者を均等にするよう求める候補者男女均等法もできたが、努力義務しかないなんて性善説が過ぎる。女性候補を擁立するようにインセンティブが働く設計が必要。私が男性だったら、当選できる確率が下がるから、ゲームのルールを変えようとは思わないので。いっそのこと、政党に制裁を科すことがあってもいいくらい。 過渡期なので、半分を女性議員にしようとした時、男性議員より能力が発揮できないこともあるだろう。これは、ある意味自然なこと。専業主婦になるのが当たり前とされていた世代では、女性が経験を積めない状況をつくってきたから。企業の取締役でも同じこと。なのに「能力が低いから登用できない」なんて。10年後には専業主婦が前提じゃないキャリアをつくってきた私たちの世代が中心になる。そんな一瞬の不都合を許容する土壌がないのは、おかしい。 先月発表された「男女格差(ジェンダーギャップ)報告書」で、日本は過去最低の121位。もう最下位を目指しているのかなとあきれた。昨年9月の内閣改造まで女性閣僚が1人。そんな政治分野の格差が足を引っ張ったそうだが、学校のクラスで女性が1人だけだったら、その子は超不安でしょう。クラスに3人だったとしてもマイノリティーだなと思う。なぜ違和感を持たないのか。 このニュースに、SNS上では「女性の意識が低いからでしょう」というコメントがあふれていたように見えた。格差を課題と意識しない限り、日本は下位を独走していくしかない。色紙に「下位独走なるか?!??」と書いたのは、皮肉。そうはなってほしくはないが。 男女平等って無理だよねという議論もあるが、一度不平等に気付いたら、もう平等だと思い込んでいた時代には戻れない。 先月、米サンフランシスコを訪れたら、トッププレーヤーの日本人女性がこぞって活躍していた。インターネットでどこでも仕事ができる時代。日本では女性というジェンダーを持ってビジネスをするのはしんどく、海外への人材流出は進むだろう。5年以内に変わらなかったら、私も海外に出ようと思う。国がトップダウンで動かないと、本当にやばい。 ◇ 選択的夫婦別姓認めるか? 手を挙げない首相 世界経済フォーラム(WEF)が先月17日に発表した各国の男女格差(ジェンダーギャップ)の報告書で、日本は調査対象の153カ国の中、過去最低の121位だった。政治、経済、教育、健康の4分野での格差を指数化しているが、昨年9月の内閣改造まで女性閣僚が1人だけだったことなど政治分野が足を引っ張り、順位を下げた。 3位の北欧フィンランドでは先月、女性のサンナ・マリン首相が就任。連立の5党の党首全てが女性で、新内閣の閣僚19人のうち女性は12人で対照的だ。 日本では2018年、男女の候補者を均等にするよう政党に求める候補者男女均等法が成立。施行後初の国政選挙となった昨年7月の参院選では、候補者の女性比率は28%だったが、自民党は15%、公明党は8%にとどまった。7党の党首らが参加した公示前日の党首討論会では、選択的夫婦別姓制度を「認めるか」と記者に問われ、安倍晋三首相はただ1人、手を挙げなかった。(太田成美) |
最後まで読んでくださってありがとう

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね