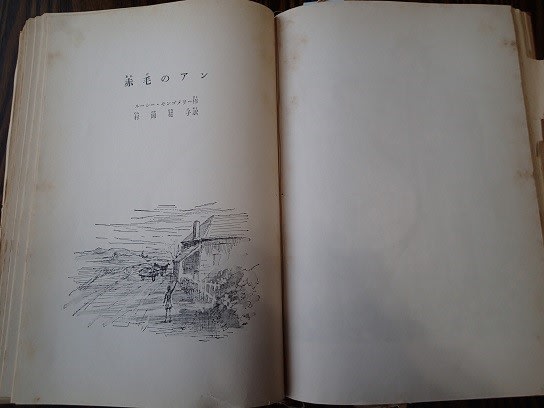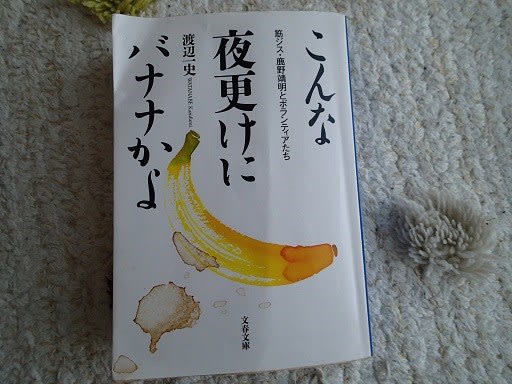雨で行くところもなく、暇つぶしに新聞を読んでいると、スポーツ欄によく判らぬ写真と記事。
写真は、トウモロコシの畑の間から野球選手が次々出てくる写真、記事は、映画「フィールド・オブ・ドリームス」のロケ地、トウモロコシ畑を野球場にした男の物語らしいが、ここで大リーグの後半のスタートの試合があったというもの。
ふと、記憶がよみがえった。
同居の次男が雨の日は家でゴロゴロしている暇なトーちゃんのために、使わなくなった古いプレーステーションと今のテレビをつなぎ、アマゾンの「プライムビデオ」で映画見たい放題にしてくれていて、愛用しいるが、どれを見ようかと、映画紹介の短文を見ていた時、トウモロコシ畑・声が聞こえたという一文があり、アクション映画がいいと、スルーしたことがある。
1989年封切りで評判になった映画らしい。
これは面白そうと、プライムビデオで探し出して、見てみる。
面白かった。
1919年のワールドシリーズで八百長の試合をしたというので、ホワイトソックスの選手が球界追放になり、その中の、スター選手、ジョー・ジャクソンが野球ファンの子供たちにはショックで嘘でしょうと、声が上がったという話は、小学生の頃読んだベーブルースの伝記で読んだことがある。
映画は主人公の中年の農夫が、トウモロコシ畑の中で、声を聞き、これをきっかけに、なけなしの貯金をはたいて、トウモロコシ畑を潰して、ナイター照明付きの野球場を作ってしまうと言うのが話の始まり。
もうなくなったはずの、ジョー・ジャクソンがまずこの野球場に現れ、球界追放になった8人の野球選手がこの球場で野球させてくれと、練習。
選手たちはトウモロコシの間から現れ消えていく、幽霊ではなく、球場内の区域で生身の人間のようにプレー。
見える人と見えない人があり、主人公とその奥さんと幼い娘には普通に見え、野球の練習を面白がって見ているという続き。
よく判らなかったが、打算で世渡りしている人には、野球選手が見えない感じ。
奥さんが良くできた人で、変わり者の旦那にgoサインを出すし、面白かったのは、娘の通う学校の父兄が、不道徳な本を図書館から排除しよう、その中にはアンネの日記もあったが、表現の自由、人権、アメリカの建国の精神等、機関銃のような啖呵を飛ばして、父兄会の空気を一変させる下りは拍手。
アメリカの国民スポーツの野球の変わらぬ価値を再認識させる下りもあり、新聞記事で紹介されたように大リーグの後半戦の開始試合にこの映画のロケ地の球場が選ばれたらしい。
映画の最後は、けんか別れして死別した父親が野球着姿で球場に現れて、主人公とキャッチボールをして、家族を紹介できたり、破産していた農場も野球好きの純真なアメリカ人が大挙押し寄せ、観覧料20ドルを払って、経済問題も解決したらしいという場面でお終い。
コロナ下の東京オリンピックに聖火リレーに王・長嶋の私ら団塊の世代のヒーローか現れたり、野球でも、JAPANがガチンコ勝負で優勝してと、気持ちが野球モードだったので、この映画はひきつけられた。
時期もお盆の時期で、ご先祖がこの世に戻ってくるといわれているタイミングと、この映画で亡くなったジョー・ジャクソン等往年の野球の名選手らが、よみがえるという筋書きが、共振するものがある。
毎年、お盆の暇なとき、見ると為になる映画と思ったことでした。
このタイミングで、この記事を書いた日経新聞のスポーツ記者、えらい。
記事は、冒頭、新聞記事をそのまま載せるのは問題だか、このブログを読んでくれるのは、北九州の少数の釣りバカオヤジなので、ご勘弁。
写真は、トウモロコシの畑の間から野球選手が次々出てくる写真、記事は、映画「フィールド・オブ・ドリームス」のロケ地、トウモロコシ畑を野球場にした男の物語らしいが、ここで大リーグの後半のスタートの試合があったというもの。
ふと、記憶がよみがえった。
同居の次男が雨の日は家でゴロゴロしている暇なトーちゃんのために、使わなくなった古いプレーステーションと今のテレビをつなぎ、アマゾンの「プライムビデオ」で映画見たい放題にしてくれていて、愛用しいるが、どれを見ようかと、映画紹介の短文を見ていた時、トウモロコシ畑・声が聞こえたという一文があり、アクション映画がいいと、スルーしたことがある。
1989年封切りで評判になった映画らしい。
これは面白そうと、プライムビデオで探し出して、見てみる。
面白かった。
1919年のワールドシリーズで八百長の試合をしたというので、ホワイトソックスの選手が球界追放になり、その中の、スター選手、ジョー・ジャクソンが野球ファンの子供たちにはショックで嘘でしょうと、声が上がったという話は、小学生の頃読んだベーブルースの伝記で読んだことがある。
映画は主人公の中年の農夫が、トウモロコシ畑の中で、声を聞き、これをきっかけに、なけなしの貯金をはたいて、トウモロコシ畑を潰して、ナイター照明付きの野球場を作ってしまうと言うのが話の始まり。
もうなくなったはずの、ジョー・ジャクソンがまずこの野球場に現れ、球界追放になった8人の野球選手がこの球場で野球させてくれと、練習。
選手たちはトウモロコシの間から現れ消えていく、幽霊ではなく、球場内の区域で生身の人間のようにプレー。
見える人と見えない人があり、主人公とその奥さんと幼い娘には普通に見え、野球の練習を面白がって見ているという続き。
よく判らなかったが、打算で世渡りしている人には、野球選手が見えない感じ。
奥さんが良くできた人で、変わり者の旦那にgoサインを出すし、面白かったのは、娘の通う学校の父兄が、不道徳な本を図書館から排除しよう、その中にはアンネの日記もあったが、表現の自由、人権、アメリカの建国の精神等、機関銃のような啖呵を飛ばして、父兄会の空気を一変させる下りは拍手。
アメリカの国民スポーツの野球の変わらぬ価値を再認識させる下りもあり、新聞記事で紹介されたように大リーグの後半戦の開始試合にこの映画のロケ地の球場が選ばれたらしい。
映画の最後は、けんか別れして死別した父親が野球着姿で球場に現れて、主人公とキャッチボールをして、家族を紹介できたり、破産していた農場も野球好きの純真なアメリカ人が大挙押し寄せ、観覧料20ドルを払って、経済問題も解決したらしいという場面でお終い。
コロナ下の東京オリンピックに聖火リレーに王・長嶋の私ら団塊の世代のヒーローか現れたり、野球でも、JAPANがガチンコ勝負で優勝してと、気持ちが野球モードだったので、この映画はひきつけられた。
時期もお盆の時期で、ご先祖がこの世に戻ってくるといわれているタイミングと、この映画で亡くなったジョー・ジャクソン等往年の野球の名選手らが、よみがえるという筋書きが、共振するものがある。
毎年、お盆の暇なとき、見ると為になる映画と思ったことでした。
このタイミングで、この記事を書いた日経新聞のスポーツ記者、えらい。
記事は、冒頭、新聞記事をそのまま載せるのは問題だか、このブログを読んでくれるのは、北九州の少数の釣りバカオヤジなので、ご勘弁。