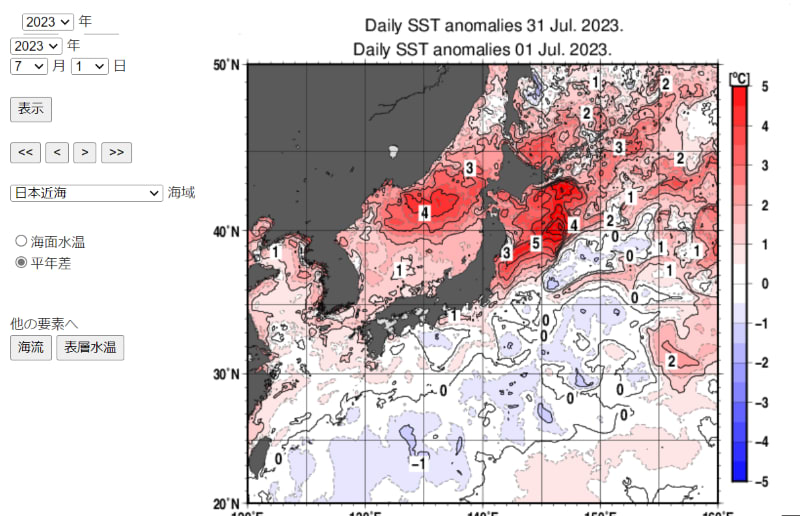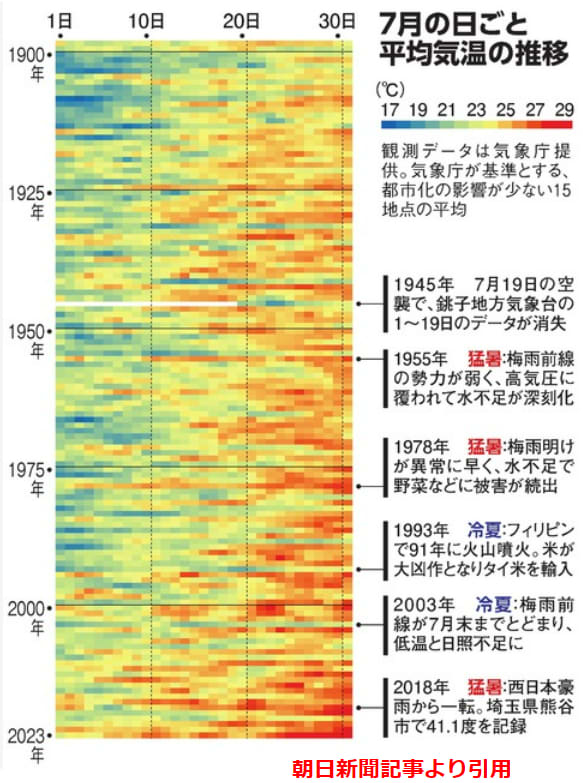昨日は、1日早く夏休みを取得して西吾妻山に登ってきました。吾妻連邦には一切経山と吾妻小富士しか登ったことが無く、日本百名山の西吾妻山は初めてとなります。昨日は湿った東風が吹きつけ積雲におおわれ天気は悪そうですが、太平洋高気圧が一時的に強まり雲は解消傾向と予想。雷雲の発生も無いと判断して予定通り福島県へ向かいました。8時40分過ぎにグランデコスキー場の駐車場に到着。ロープウエイを利用して9時過ぎに登山開始。西大巓へ向けての登山道はグチャグチャです。沢登りのような感じで、平坦な場所は水溜まり状態。足場を気にしながらの登山でした。尾根に出ると霧と暴風が吹き荒れる状態が昼前まで続きました。西吾妻山に着いた昼過ぎから上空に青空も見え始めて、急速に天気が回復。帰りの西大巓からは安達太良山や磐梯山、朝日連峰や遠く月山を遠望できました。西吾妻山付近の湿原や西大巓への登山道では高山植物が咲き乱れ、天気も回復して気持ち良いハイキングでした。

ロープウエイ乗り場の案内です。山頂の天気は晴れとなっていますが、標高1600mm以上は霧に包まれています。

ロープウエイを下りて登山開始。登山客はほとんどいない様子で、熊鈴を鳴らして歩きます。

しばらくは草原歩きが続きます。ヤマハハコの群生。

ヨツバヒヨドリの群生地が続きます。アサギマダラの姿も見かけました。帰りは天気も回復すると予想し、先を急ぎます。

笹の花

20分ほどで気持ちの良い草原歩きを終わり、標高1600m付近から樹林帯の中の本格的な登山道となります。水が流れて滑りやすいため、足元に気をつけながらゆっくりと登ります。奥白根山でもよく見かけるカニコウモリの花。

標高1800m付近から姿を見せたミヤマアキノキリンソウ。ここから山頂まで、登山道を黄色く彩っていました。

少し空が開けてきました。まだまだ霧の中の上りが続きます。

稜線に出ました。山頂が近いかな? 霧に加えて猛烈な風が吹きつけます。

ナンブタカネアザミが咲き始めています

イワイチョウ。ミツガシワ科の花です。

ツルリンドウかな? 季節的にまだ早い印象ですが。

ウメバチソウが開花

ミヤマコゴメグサ。初めて見る可憐な高山植物です。

暴風吹き荒れる中、標高1982mの西大巓に到着。霧のため視界はゼロ。帰りに期待しましょう。

暴風の中、西大巓の東斜面を下ります。クロヅルの群生とツリガネニンジン

再びウメバチソウ

霧と暴風の中、西吾妻山へ向けて登ります。

あちらこちらに咲く青い可憐な花はミヤマリンドウ

木道の分岐点。右側の西吾妻山方面へ向かいます。

咲き始めた白い大きな花はモミジカラマツ? 雰囲気が違うかな?

11時20分に標高2035mの西吾妻山山頂に到着。登山開始してから2時間20分で日本百名山の山頂に立つことができました。想定より早いペースです。山頂付近は高い木に覆われ視界はありません。えっ、ここが山頂という印象です。
少々拍子抜けしたので、少し先の天狗岩まで足を延ばし、湿原を歩いて戻ることにします。

緩やかな下りが続きます。サンカヨウの実。

湿原の木道を歩きます。

天狗岩に到着。山頂付近では風が収まっていましたが、標高2005mのこの付近は風の通り道で再び暴風に見舞われます。

山頂の祠は吾妻神社。上空は雲の動きが非常に早く、青空が見え隠れします。天気は回復傾向のようです。この付近は暴風で飛ばされそうなので、天狗岩の裏側で昼食休憩とします。

昼食を食べていると、流れ去る雲の間から山形県の平野部が見え隠れします。米沢あたりでしょうか。下界の山形県平野部はフェーン現象のため快晴。猛暑となっている様子です。

天狗岩から湿原を歩いて戻ります。左側の小高い丘が西吾妻山です。

湿原ではミヤマリンドウが満開

キソチドリ

正面はこれから向かう西大巓。霧と暴風に見舞われた往路とは雰囲気が全く異なり、風は強いものの爽快な湿原歩きが続きます。

西大巓へ続く登山道を見上げます

霧が晴れて、南側には磐梯山と猪苗代湖が姿を見せました。

足元に見慣れない花が咲いています。キンコウカかな?

再び東側を振り返ります。東吾妻山の右に安達太良山が姿を見せました。

安達太良山をズーム。左から箕輪山、鉄山、安達太良山、和尚山と連なります。

山頂が近づいてきました。斜面に咲くエゾシオガマ。

クロヅルの群生とツリガネニンジン

往路にも紹介したミヤマコゴメグサ。落ち着いて観察できました。

北東方向の霧が晴れて蔵王連山が見えています。

南側には磐梯山

足元の高山植物と周囲の眺望と楽しむうちに再び西大巓に到着

南側正面に磐梯山と猫魔ヶ岳。その手前には小野川湖(左)と桧原湖(右)を見下ろします。桧原湖の先の猫魔ヶ岳と雄国山の間には雄国沼が見えています。往路には味わえなかった絶景です。

櫛ヶ峰と磐梯山をズーム。磐梯山頂にはちょこっと雲がかかり、なかなか全容を見ることができません。

南東には箕輪山、鉄山、安達太良山と和尚山

山頂の西側から北側にかけて、樹木の間から東北の山を遠望できます。西側の飯豊山は積雲の中。

北側には朝日連峰から月山を遠望します。

朝日連峰をズーム。左から袖朝日岳、西朝日岳、大朝日岳、小朝日岳と連なります。

コンデジで袖朝日岳、西朝日岳、大朝日岳をさらに超ズーム。

朝日連峰の右には月山をうっすらと遠望します。左から湯殿山、姥ヶ岳、そして最高峰の月山。

北東の方角には蔵王連山を遠望
西大巓山頂から360度の遠望を満喫したので、麓へ向けて下ります。

しばらくは見晴らしの良い尾根を下ります。西吾妻山へ続く稜線を振り返ります。
樹林帯に入ってから標高差200mの間は、泥濘や滑りやすい沢下りが続き、気を抜けません。

樹林帯を抜けスキー場?の草原に出ると、視界が開けます。ヨツバヒヨドリの群生と磐梯山。

オヤマリンドウの蕾が膨らんでいました

ヨツバヒヨドリと安達太良山

ヨツバヒヨドリと磐梯山。朝登るときにはアサギマダラの姿を見かけましたが、下りでは全く姿を見かけません。アサギマダラは暑さが苦手なので休憩中なのでしょう。

14時過ぎにロープウエイ乗り場に到着。アサギマダラのモニュメント。

こちらのモニュメントの背後には磐梯山。
ロープウエイ山頂駅付近はアサギマダラの飛来地になっていて、アサギマダラの観察会が開催されています。こう暑いと、なかなか姿を見るのが難しいのではないでしょうか。

最後に、グランデコスキー場とトレッキングマップの案内を掲載しておきます。
初めて訪れた西吾妻山。前半は霧と暴風に見舞われましたが、後半は天気に恵まれました。メインの登山ルートは山形県の天元台からロープウエイとリフトで標高1800mまで上がり、中大巓から梵天岩経由で湿原を散策するコースのようです。紅葉の時期に訪れてみたいですが、天元台までは遠いな。。。友部のアパートから磐梯山やグランデコまでは2時間30分。天元台となると福島を経由するので3時間30分は見ておく必要があり日帰りではしんどそうです。