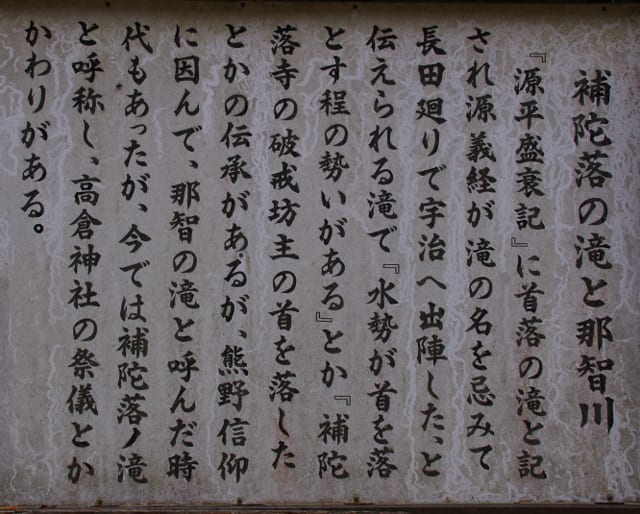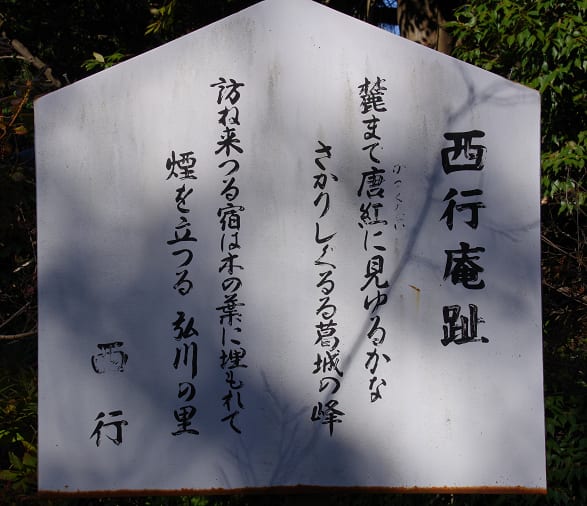.
もともとお酒に強い方ではなかった、仕事帰りに飲んで、電車に乗って眠ってしまい、終着駅迄行ったことは度々あった。

以前からメインは日本酒である、そして寒い時期はコレ
口当たりは甘口で美味しい、けど アルコール度 21%、いつも飲んでるコップ一杯 240CC で効いてくる
・・・ なので、ちょっと種類を変えようと

昨日 こんなのを買ってきました
アルコール度 5% の発泡酒で350CC と 500CC

こんなのも買ってきた
アルコール度 5% のチユーハイで 500CC
いずれも TOPVALU ブランドで、価格も他社のものより安い、味もまあまあで安物好きのワタクシに合っている
早速、 アルコール度 5% の発泡酒 350CC缶 2本 を昨日の夕食時に飲んでみました。
この価格でこの味、コストパフォーマンスは上々、上を向いたらキリがない
アルコール度 9% の 500CC缶にしようかな? と思ったが、ちょっときついかも?
5% の 350CC缶 2本程度がちょうどいい感じ、いい感じのほろ酔い状態になる

どれも大して変わらないようだが、チューハイならこれが一番 ウマイような気がします

アルコール飲料を飲んだ後には やっぱり甘いものです、この類のものの銘柄にこだわりはありません
もともとお酒に強い方ではなかった、仕事帰りに飲んで、電車に乗って眠ってしまい、終着駅迄行ったことは度々あった。

以前からメインは日本酒である、そして寒い時期はコレ
口当たりは甘口で美味しい、けど アルコール度 21%、いつも飲んでるコップ一杯 240CC で効いてくる
・・・ なので、ちょっと種類を変えようと

昨日 こんなのを買ってきました
アルコール度 5% の発泡酒で350CC と 500CC

こんなのも買ってきた
アルコール度 5% のチユーハイで 500CC
いずれも TOPVALU ブランドで、価格も他社のものより安い、味もまあまあで安物好きのワタクシに合っている
早速、 アルコール度 5% の発泡酒 350CC缶 2本 を昨日の夕食時に飲んでみました。
この価格でこの味、コストパフォーマンスは上々、上を向いたらキリがない
アルコール度 9% の 500CC缶にしようかな? と思ったが、ちょっときついかも?
5% の 350CC缶 2本程度がちょうどいい感じ、いい感じのほろ酔い状態になる

どれも大して変わらないようだが、チューハイならこれが一番 ウマイような気がします

アルコール飲料を飲んだ後には やっぱり甘いものです、この類のものの銘柄にこだわりはありません